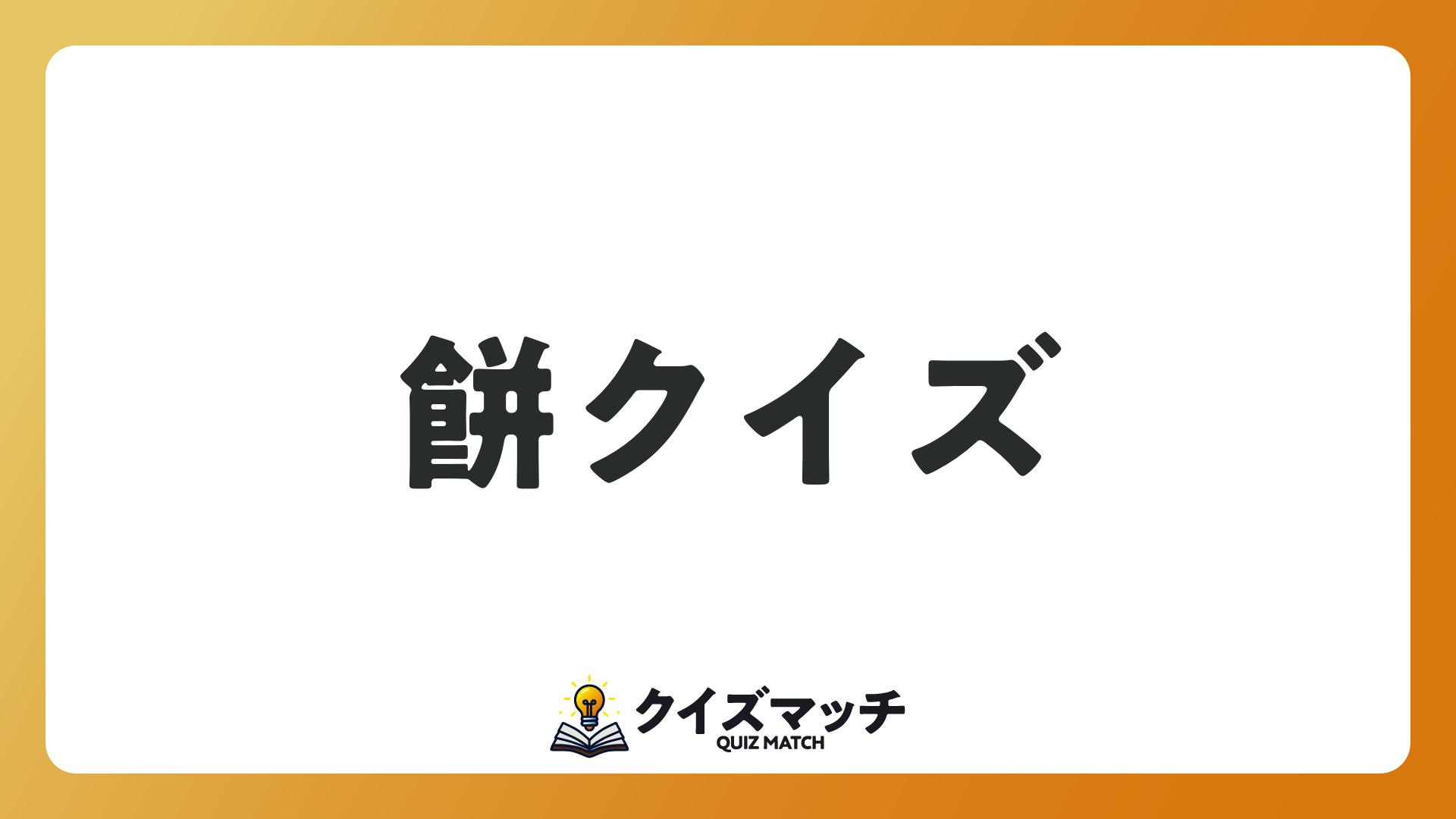餅つきは、蒸したもち米を臼に入れ、杵で交互につきながら粘りを引き出す日本の伝統行事であり、古くは神事とも結び付いてきました。力強くつく動作と合いの手で米粒を潰しつつ空気を抜く工程が独特で、家庭用の餅切り機で作る餅とは舌触りが大きく異なります。正月用の鏡餅や雑煮用の角餅を用意するため年末に行われることが多く、つき上がった餅は素早く丸めたり伸ばしたりして保存されます。現代では機械化が進むも、杵と臼による餅つきは地域の交流や子どもの体験学習として大切に守られています。この記事では、こうした餅に関する10問のクイズをお楽しみいただけます。
Q1 : 木の板や串に平たく伸ばした餅を味噌だれで香ばしく焼き上げる五平餅が郷土料理として特に知られている長野県の山間地域はどこか?
五平餅は中山道の宿場が並ぶ木曽路で山仕事や旅人の携行食として発達した料理で、つぶした米を平たく成形してクルミやゴマを混ぜた味噌だれを塗り炭火で焼く。焼く際に木曽ヒノキなど香りの良い材の板や串を使うため、木の香と味噌の香ばしさが一体となる。名称は御幣に似た形から御幣餅と呼ばれた説や、考案者とされる木曽義仲の家臣 五平 の名を取った説など複数あり、岐阜や愛知では円盤型や団子型などの派生形も見られる。木曽路の宿場町では今も道沿いに炭火で焼く店が軒を連ね、観光客の食べ歩き名物になっている。
Q2 : きな粉と砂糖をまぶして食べる安倍川餅の発祥地として最も知られるのは次のうちどこか?
安倍川餅は東海道を往来する旅人が安倍川の渡しで休憩した際に茶店で振る舞われたのが始まりとされる。つきたての餅を一口大にちぎり、砂糖を混ぜたきな粉をたっぷり絡めて食べる素朴な甘さが特徴で、当時貴重だった砂糖を用いたぜいたくさから名物として評判になった。浮世絵師の歌川広重や滑稽本の東海道中膝栗毛にも登場し、その名が全国に広まった。現在も静岡市内の老舗や駅売店で販売され、餡入りや抹茶味など派生品も生まれているが、本来の発祥地は安倍川流域の静岡市である。
Q3 : 正月に供えた鏡餅を割って食べる行事を何と呼ぶか?
鏡開きは松の内が明ける一月十一日頃に行われ、歳神への供物である鏡餅を木槌などで割り、雑煮や汁粉にして食べる行事である。刃物で切ると切腹を連想させ不吉とされたため、武家社会では割ることを開くと呼び縁起を担いだ。餅を食べることで一年間の無病息災や家内安全を祈願する信仰が背景にあり、茶道や祝宴で酒樽の蓋を割る儀式が同じ言葉で呼ばれるのもこの慣習が源流である。現代でも職場や学校で鏡開きをしてぜんざいをふるまう風景が各地で見られる。
Q4 : ロッテが発売するアイス入り大福 雪見だいふく が初めて全国販売された年はいつか?
雪見だいふくは冷たいアイスを柔らかな求肥で包む発想が斬新で、ロッテが一九八一年に全国発売した。当時アイスは夏のものという固定観念が強かったが、こたつに入りながら食べる冬アイスというキャッチコピーとテレビCMが話題を呼びヒット商品となった。求肥部分は冷凍下での硬化を防ぐため砂糖や水あめの配合を最適化し、表面にはでんぷん粉をまぶして手に付かない工夫が施されている。発売後はチョコやいちごなど期間限定フレーバーも数多く登場し、冬季以外も棚に並ぶロングセラーアイスへと成長した。
Q5 : 草餅やよもぎ餅に香り付けと緑色を与える原料植物として用いられるのはどれか?
草餅やよもぎ餅に使われるヨモギはキク科の多年草で、若芽にはシネオールやツヨンなどの精油成分が含まれ爽やかな香りとほろ苦さを与える。餅生地にゆでて刻んだヨモギを練り込むことで鮮やかな緑色が付くうえ、繊維による独特の歯切れも生まれる。古くから邪気払いの薬草とされ端午の節句や春の彼岸に食されてきた。抹茶は粉末茶、青のりは海藻、スギナは杉菜でありいずれも草餅の主要原料には用いられない。春先に摘んだ新芽を用いると香りが格段に良く、冷凍ストックで一年中楽しむ家庭も増えている。
Q6 : 農林水産省の統計で作付面積が最も多いもち米品種として知られるのはどれか?
ヒメノモチは秋田県で育成された品種で、倒伏しにくく収量が高いことから北海道から九州まで幅広く作付されている。農林水産省の令和元年産作付統計ではもち米品種のうち約三割を占め首位となった。炊飯時の吸水が安定していて搗き上げた餅はコシが強く、冷めても硬化しにくいため正月用の切り餅や和菓子、赤飯など多彩な用途に向く。また玄米外観が白いことから加工品の色調が良い点も評価されている。こがねもちやヒヨクモチも良食味だが、普及面積ではヒメノモチが頭一つ抜けている。
Q7 : 絹織物に由来する名を持つ銘菓 羽二重餅 が県下随一の土産として知られる都道府県はどこか?
羽二重餅は絹織物の羽二重のように滑らかで薄く重ねた生地を特徴とし、もち米に砂糖と水あめを練り込むことでとろける食感を生み出す福井県の銘菓である。明治三十八年に創製されたと伝わり、北陸線の開通と共に旅人の土産として人気が高まった。近年は柚子や抹茶味、焼き羽二重など派生商品も多く、東尋坊や永平寺など県内観光地の定番みやげとなっている。絹業が盛んだった福井の歴史を映す菓子として地元の学校では郷土学習にも取り上げられる。
Q8 : 杵と臼を使って餅米を打ちつぶしながらこね上げる伝統的な餅作りの方法を何という?
餅つきは、蒸したもち米を臼に入れ、杵で交互につきながら粘りを引き出す日本の伝統行事であり、古くは神事とも結び付いてきた。力強くつく動作と合いの手で米粒を潰しつつ空気を抜く工程が独特で、家庭用の餅切り機で作る餅とは舌触りが大きく異なる。正月用の鏡餅や雑煮用の角餅を用意するため年末に行われることが多く、つき上がった餅は素早く丸めたり伸ばしたりして保存する。現代では機械化が進むが、杵と臼による餅つきは地域の交流や子どもの体験学習として大切に守られている。
Q9 : お雑煮に入れる餅の形は地域により異なるが、丸餅を主に用いる地域はどこか?
お雑煮は正月に食べる汁物で、餅の形や味付けに強い地域差がある。関東では保存や炭火焼きに適した角餅を焼いて澄まし仕立ての汁に入れるのが一般的だが、関西では円満を意味する丸餅を焼かずに白味噌の汁で煮ることが多い。丸餅の文化は公家社会の伝統を色濃く残しており、材木の生産や薪文化の違いも形の分岐に影響したとされる。同じ日本の正月料理でも、餅の形を見れば食文化の背景や歴史的経緯が読み取れる点が興味深い。
Q10 : 三重県伊勢市の名物として知られ、こしあんを巻いた柔らかい餅が特徴の和菓子はどれか?
赤福餅は宝永四年創業の菓子舗が伊勢神宮参拝客向けに販売したことに始まり、三筋の波形に伸ばしたこし餡で柔らかい餅を包む姿が五十鈴川の清流を象徴する。保存料を用いないため賞味期限は短いが、出来たての滑らかさこそが魅力で、今も早朝から職人が手作業で成形する。夏はかき氷に赤福を添えた赤福氷、冬は赤福ぜんざいといった季節限定商品も人気で、伊勢参宮と結び付いた土産文化の象徴として全国に広く知られている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は餅クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は餅クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。