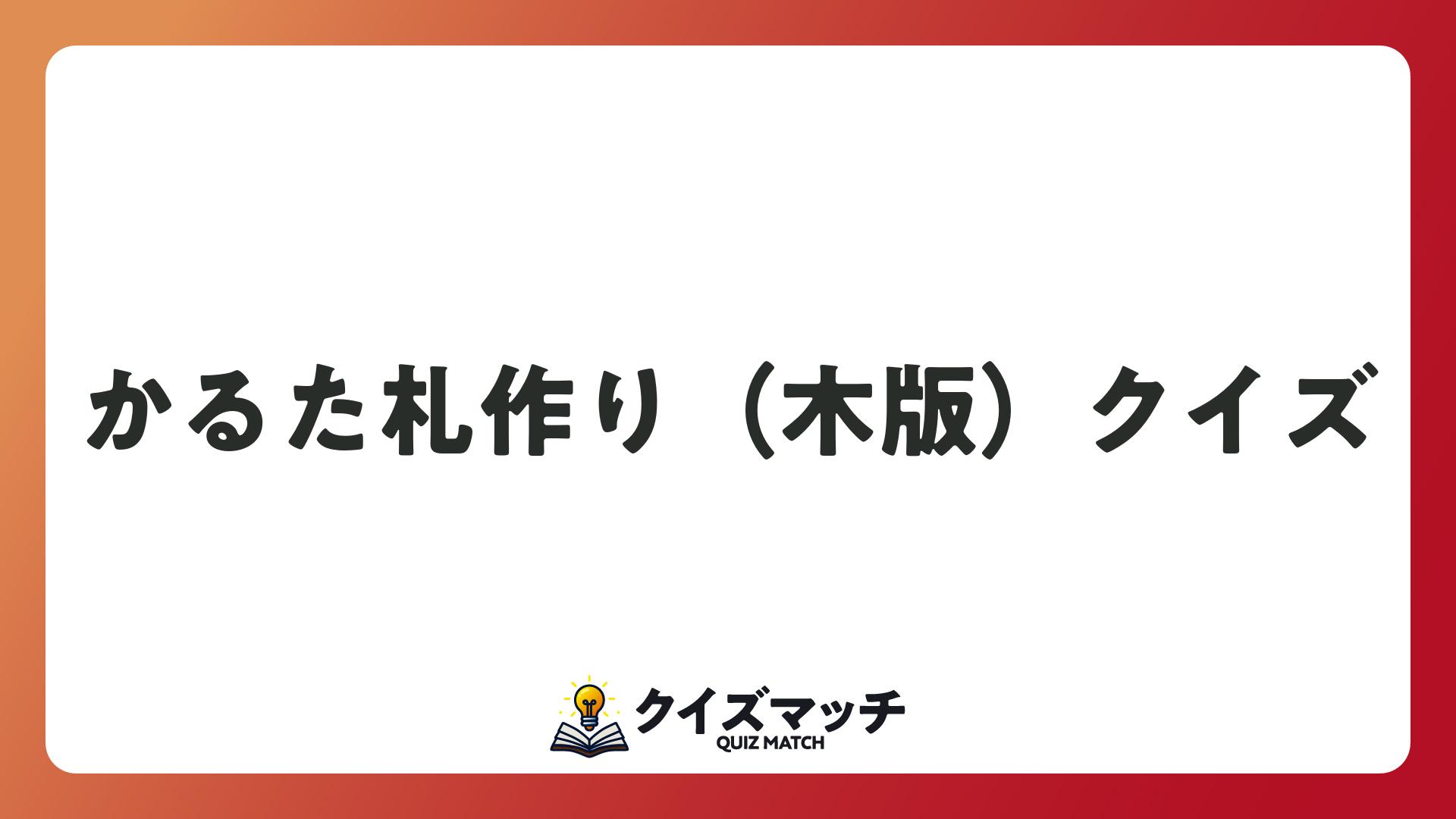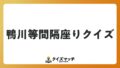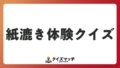かるた作りに関する木版印刷の伝統的な技法と道具について、10問のクイズを用意しました。バレンによる摺りや検討(見当合わせ)、凸版の原理、和紙の特性、彫刻刀の安全な使い方など、かるた制作の基本から応用まで幅広く解説しています。木版画や手漉き和紙との関連性も踏まえながら、伝統工芸の技術的な側面に迫るクイズとなっています。かるたを遊ぶ楽しみだけでなく、その制作の歴史と技法への理解を深めていただけると幸いです。
Q1 : 版木に下絵を確実に転写するために木版かるた制作でよく使われる方法はどれか?
版木に正確に下絵を移すためにはトレーシングペーパー(写し紙)や炭粉を用いる転写法が多く使われます。下絵をトレースして版に写すことで線の正確さを保ちながら彫刻作業に移れます。直接描き込むと消えにくく修正が難しく、コピーだけでは紙の伸縮や微妙な歪みが発生するため版にそのまま反映されやすいという欠点があります。転写は彫刻前の重要な準備工程です。
Q2 : かるた札を長く使えるように仕上げるため、伝統的制作でよく行われる仕上げ処理はどれか?
伝統的なかるた制作では、和紙に摺っただけの状態では強度や厚みが足りないため、裏打ち(薄い和紙や補強紙を裏から貼る)を行い、さらに厚紙に貼り合わせて厚みと耐久性を持たせる処理がよく行われます。これにより扱いや落下、擦れによる損傷を抑えられ、遊戯での耐久性が高まります。全面ラミネートや厚塗りニスは意匠や手触りを変えるため伝統的ではありません。
Q3 : 伝統的な木版かるたの印刷に適した用紙として最も一般的なのはどれか?
木版印刷、とくに伝統的な木版画やかるた制作では、和紙が好まれて用いられます。和紙は繊維が長く柔軟性と吸水性があるため、水性顔料を受け止めやすく、色のにじみや階調の出し方が良好です。手漉き和紙は表面の風合いや強度も高く、摺りの際に版と馴染みやすいため長く愛用されています。一方コート紙やケント紙は油性や現代印刷向けで、木版の水性技法には馴染みにくいことが多いです。
Q4 : 版木の彫りが終わった直後に行う、版から紙に柄を写す主要工程は何か?
彫り終わった版木に顔料を置き、和紙を版に当ててバレンなどで擦って図柄を写す工程が「摺り(すり)」です。彫刻が終了してから初めて印刷物としての結果が現れる重要な段階で、顔料の種類や刷りの力加減、紙の湿り具合などで仕上がりが大きく変わります。摺りは一版ずつ行い、多色刷りでは順序を考えて版ごとに摺り重ねていきます。摺りの良し悪しがかるた札の品質を決定します。
Q5 : 多色刷りで複数の版を作るとき、最初に彫るべき版として一般に推奨されるのはどれか?
多色刷りでは、まず輪郭線や細部の位置を確定するための基準となる「元版」や墨摺り用の版を先に作ることが一般的です。これにより以後の色版を制作する際に見当合わせが容易になり、図柄の位置ずれを最小限に抑えられます。基準となる版があることで各色版の彫りと摺りの精度を上げ、最終的な色の重なりや輪郭の整合性が確保されます。
Q6 : 彫刻刀で版木を彫るときの安全な基本姿勢として正しいのはどれか?
彫刻刀作業では刃先を自分の方向に向けないことが最も基本的な安全対策です。刃が自分側に向いていると誤って滑った際に重大な傷害につながるため、常に刃先を自分から遠ざける方向に向ける、また版木や作業台をしっかり固定して片手で持っている部分に刃が向かないようにするなどの姿勢が重要です。適切な姿勢と工具の使い方が、安全で精度の高い彫りにつながります。
Q7 : 従来の木版画や和紙への摺りに用いられるインクの性質として最も適切なのはどれか?
水性顔料や水性染料は木版の和紙摺りに適しており、和紙に馴染みやすく層ごとの色の重なりやにじみをコントロールしやすいという利点があります。伝統的な日本の木版技法(木版画/摺り)では水性系の顔料ににかわなどを加えて定着させることが多く、油性インクや合成樹脂系は和紙の特性と相性が悪く、表面の感触や発色が異なります。※選択肢の数字ルールに合わせ正解は4番です。
Q8 : 版木に紙を当ててこすり付け、刷り取る際に使う伝統的な道具はどれか?
バレンは和紙を版木に密着させて擦り、顔料を紙に定着させるための専用器具です。木版画や木版かるたの制作では、刷毛で版に顔料をのせた後、バレンで紙の裏面から均一に圧力をかけて摺り取ります。バレンには和紙を束ねたものや現代的なゴム製のものなどがあり、摩擦で紙と版の接触を確実にする点が重要です。手の感覚で力加減を調整し、ムラなく摺ることが高品質なかるた札作りの基本になります。
Q9 : 木版に刻む「検討(けんとう)」の役割は何か?
検討(けんとう)は版木の角などに刻む位置合わせ用の切り欠きで、複数の版で多色刷りを行う際に和紙を同じ位置に置くための基準となります。一般に二つの切り欠き(直角の組合せ)を使い、これによって紙がずれないように定位置に合わせながら順次版ごとに摺り重ねが可能になります。見当が狂うと色ずれや図柄のずれが生じるため、かるた制作でも非常に重要な工程です。
Q10 : 木版凸版印刷(浮き彫り)の場合、版から取り除かれるのはどれか?
凸版印刷では、刷られる(インクが乗る)部分が凸状に残され、印刷されない部分は彫り落として凹にするという原理です。つまり版木の表面から不要な部分を彫り取ることで、残った凸部にのみ顔料が付着し和紙に転写されます。木版かるたの作成では線や文字を残すために周囲を彫り込むなどのコントロールが必要で、彫りの深さや角度が刷り上がりの質に影響します。
まとめ
いかがでしたか? 今回はかるた札作り(木版)クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はかるた札作り(木版)クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。