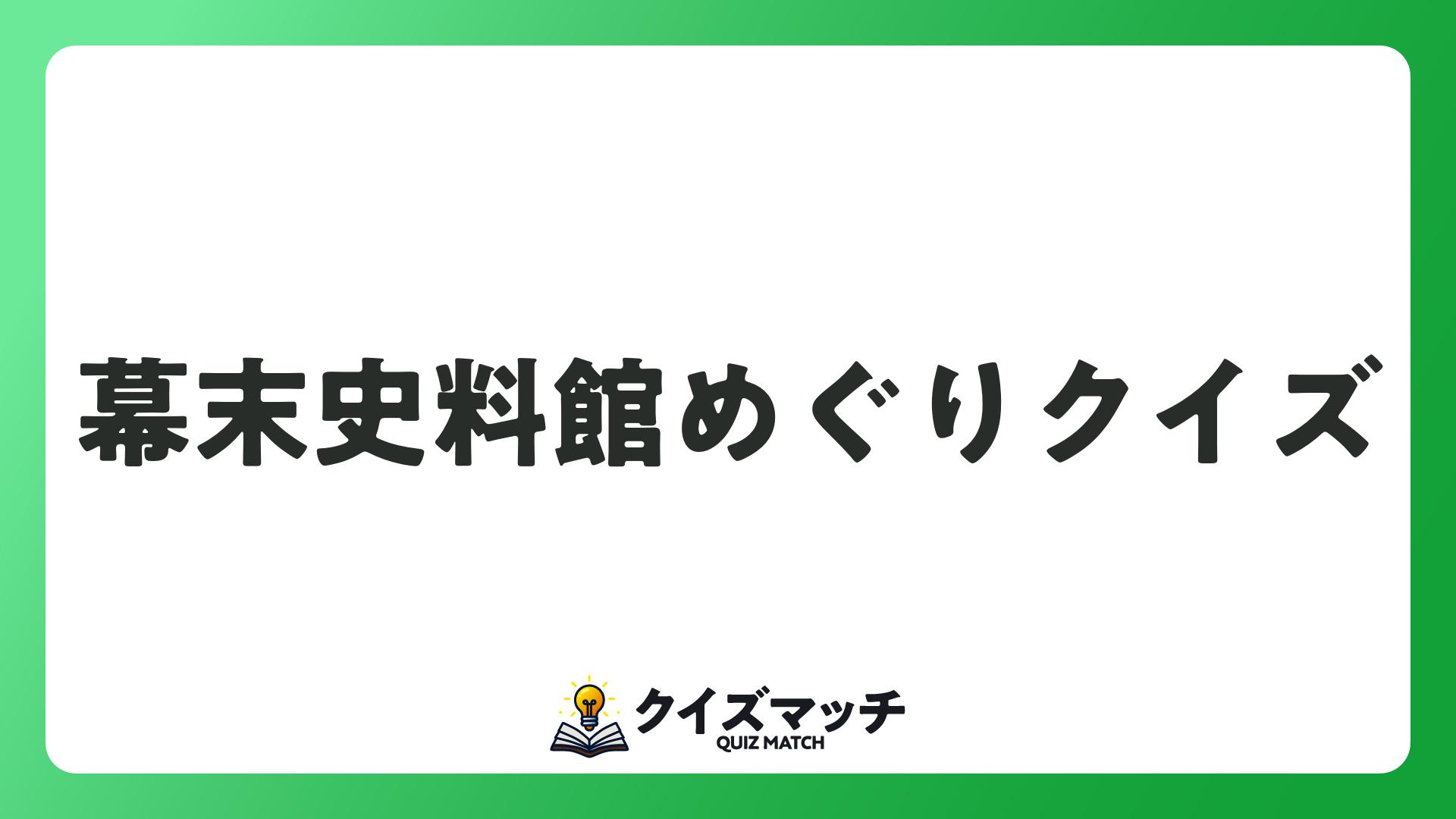幕末史料館めぐりクイズ
幕末期の重要な出来事や人物、政治変革の過程を知ることのできる幕末史料館。本記事では、そこに所蔵される資料に基づいた10問のクイズを紹介します。幕末の動乱を舞台にした政治駆け引きや武力衝突、明治維新への道のりについて、史料館が提供する貴重な手がかりを通じて理解を深めましょう。当時の人々の生の声や生活の記録に触れることで、近代日本史の起点となった幕末をより立体的に捉えることができるはずです。
Q1 : 西郷隆盛(西郷どん)はどの藩の出身で、明治維新で主要な役割を果たしたか?
西郷隆盛は薩摩藩(現在の鹿児島県)出身の武士で、討幕運動や明治維新において中心的な役割を果たしました。薩摩は当時、軍事力や藩政の独自性を有し、幕末の政治舞台で重要な存在でした。西郷は討幕後も新政府の要職を務めつつ、のちに不満を抱き西南戦争へと向かいます。史料館では西郷に関する書簡、肖像、藩政資料などが保存され、彼の思想や行動、薩摩藩内部の政治状況を学べます。
Q2 : 1867年の『大政奉還』が指すものは何か?
大政奉還は1867年に徳川慶喜が政権を朝廷に返上した出来事を指します。これは形式的には政権の返上であり、幕府が直接的な政治支配を行う体制を終わらせる一大措置でした。この決定により政治の正統性は天皇の下に回帰し、明治新政府樹立への道筋が固まりました。史料館では大政奉還に関する上申書や答申、慶喜や周辺人物の書簡などが展示され、その政治的背景と影響を詳細に解説しています。
Q3 : 1859年に横浜が開港した背景となった米国との条約は何と呼ばれるか?
1858年に締結された日米修好通商条約(通称ハリス条約)は、将来の開港と関税の取り決めなどを定めた条約で、これに基づき1859年に横浜などが開港しました。条約は幕府とアメリカ側の間で結ばれ、日本の開国と近代化を促す契機となりました。史料館では条約原本や幕府・外国公使の交渉記録、開港後の港町の写真や商業資料を通じて、国際関係の変化と地域社会への影響を学ぶことができます。
Q4 : 五箇条の御誓文(五箇条の誓文)が公布されたのは西暦何年か?
五箇条の御誓文は明治維新直後の1868年(明治元年)に発布され、新政府の基本方針を示した宣言です。天皇中心の新しい政治体制の理念として、広く公議を行うこと、身分制度の改革、知識の啓発などが掲げられました。この文書は近代日本の政治理念形成に大きく寄与し、各地の史料館ではその原文や訳注、当時の板挙や布告に関する資料を通じて、近代国家づくりの過程を説明しています。
Q5 : 薩長同盟(薩摩藩と長州藩の同盟)が結ばれたのはどの藩同士か?
薩長同盟は、幕末期に倒幕を目指す勢力同士である薩摩藩(現在の鹿児島県)と長州藩(現在の山口県)が協力関係を築いた同盟です。1866年に成立し、幕府打倒の運動を加速させる重要な転機となりました。薩摩は西南の雄で軍事力と経済力を持ち、長州は尊王攘夷を掲げて活動していたため、両藩の連携は明治維新へとつながる政治的・軍事的基盤を形成しました。多くの史料館や博物館では、この同盟に関する書簡や密談の記録、両藩の軍備・人事に関する資料が展示され、幕末の政治的駆け引きや連携の背景を知る手がかりを提供しています。
Q6 : マシュー・ペリーが日本に最初に来航した年は?
黒船で知られる米国のマシュー・ペリーは、江戸幕府に開国を迫るため1853年に浦賀に来航しました(嘉永6年)。この最初の来航が日本国内に大きな衝撃を与え、攘夷論と開国論の対立を深めることとなりました。翌年の1854年には日米和親条約が結ばれ、さらに1858年の日米修好通商条約(ハリス条約)へとつながり、横浜などの開港が実現します。幕末史料館ではペリー来航に関する報告書、船の図、和英のやり取りを記した記録などが展示され、当時の国際情勢や外交文書の重要性を学べます。
Q7 : 最後の征夷大将軍(最後の将軍)として知られる人物は誰か?
徳川慶喜(とくがわ よしのぶ)は幕末における最後の征夷大将軍であり、江戸幕府の将軍職を天皇に返上する「大政奉還」を1867年に行いました。これにより幕府の政治的支配は終焉を迎え、その後の明治新政府樹立へと道を開きました。慶喜の決断は国内の混乱を避け、比較的平和的に政権移行を進める意図があったと評価されます。幕末史料館では慶喜の公文書や辞表、関連する幕臣の記録などを通じて、大政奉還前後の政局や慶喜の立場を理解することができます。
Q8 : 江戸城の無血開城(実質的な引き渡し)を仲介し、江戸の混乱を避けた人物は誰か?
勝海舟は海軍を整備した幕臣で、江戸城無血開城において徳川慶喜側と新政府側の間で交渉を行い、江戸の大火や市民の被害を最小限に抑える形で城の引き渡しを仲介しました。1868年前後の江戸開城に向けた交渉は非常に緊迫していましたが、勝の交渉手腕と相手側の配慮により大きな流血を避けることができたとされています。史料館では勝海舟が残した書簡や交渉記録、海軍に関する資料などでこうした経緯を学べます。
Q9 : 戊辰戦争において、官軍が新政府側として幕府軍と衝突し最初の大きな戦闘となったのは何の戦いか?
鳥羽・伏見の戦い(1868年1月)は、戊辰戦争における初期の大規模な戦闘で、新政府側(薩摩・長州など)の軍と旧幕府軍が京都近辺で衝突しました。この戦いで新政府軍が勝利したことは、旧体制の軍事的優位を覆し、東日本へと戦線が拡大する契機となりました。史料館では戦場の地図、参戦者の書簡、軍令や兵站に関する文書などを通じて、戦闘の経過や兵士の日常、各藩の動向を知ることができます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は幕末史料館めぐりクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は幕末史料館めぐりクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。