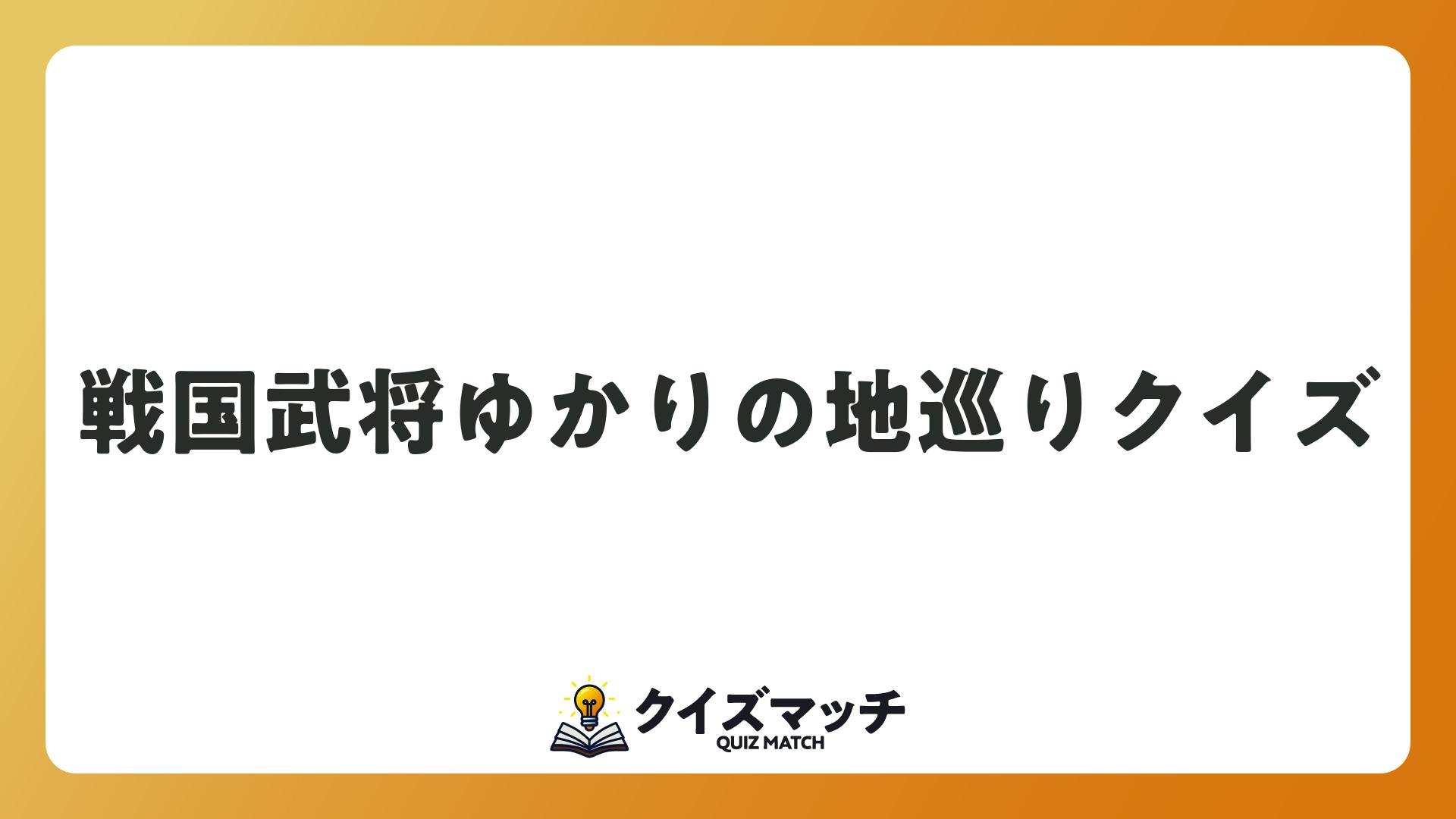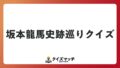戦国時代の歴史に彩られた地域を巡るクイズをお楽しみください。武将たちの足跡を辿る中で、織田信長や上杉謙信、武田信玄といった激動の時代を牽引した人物の活躍に迫ります。城郭や古戦場、神社仏閣など、豊かな歴史遺産を舞台に、戦国ならではの戦術や戦略、政治的な動きを体感できるはずです。知られざる逸話や史実に触れながら、戦国武将ゆかりの地を巡る、新たな発見に満ちたクイズの旅をお楽しみください。
Q1 : 真田信繁(幸村)が活躍したことで知られる、関東近辺での拠点といえば次のうちどれか? 安土城 浜松城 上田城 春日山城
上田城は真田氏の本拠で、現在の長野県上田市にあります。真田昌幸・信繁 father and son were active there; 特に第一次・第二次上田合戦(徳川勢との戦い)での防衛戦が有名で、少数の真田軍が大軍を翻弄した戦例として歴史に残ります。関ヶ原の合戦前後にも真田氏は重要な役割を果たし、上田城址や博物館では真田家に関する史料や遺構が保存され、真田信繁(幸村)ゆかりの地として知られています。
Q2 : 本能寺の変(1582年)で織田信長が明智光秀に討たれた寺院・事件の舞台はどこか? 名古屋市 江戸(東京) 大阪市 京都市
本能寺の変は天正10年(1582年)に京都で発生し、織田信長が宿泊していた本能寺が明智光秀の軍に襲われて討たれた事件です。本能寺は京都市中京区に所在し、事件後に信長の死は全国に大きな衝撃を与えました。現在の本能寺は戦後に復興されたもので、事件の跡地や関連史料は京都の史跡として研究・公開されています。本能寺の変は戦国時代の大きな転換点の一つと考えられています。
Q3 : 徳川家康を祭る日光東照宮の主たる祀り対象は誰か? 日光東照宮(徳川家康) 久能山東照宮(徳川家康の別祀) 東大寺(盧舎那仏) 平等院(阿弥陀如来)
日光東照宮は江戸幕府初代将軍・徳川家康を東照大権現として祀る社で、日光市にある代表的な霊廟です。家康の遺骸は久能山(静岡)に一時葬られた後、日光に改葬され、豪華な社殿や彫刻、装飾が施されました。日光東照宮は世界遺産にも登録され、家康を祭る神社として政治的・宗教的意味合いを持ち、参詣・観光の主要スポットになっています(久能山東照宮も家康を祀る別の場所として存在します)。
Q4 : 明智光秀が築いた城として知られ、後に廃城となった坂本城の所在地は現在のどこか? 京都市 大津市(坂本) 鹿児島市 長野市
坂本城は明智光秀が主に丹波や近江方面の拠点として築いた城で、当時の所在地は近江国の坂本(現在の滋賀県大津市坂本)です。築城後、光秀は天正10年の本能寺の変を経て変転の末、坂本の地も戦乱で影響を受け廃城になりました。現在は城跡や史跡、光秀に関する史料館や案内が整備されており、明智光秀ゆかりの地として観光・研究の対象になっています。}
Q5 : 織田信長と深く結びついた城として知られる、琵琶湖東岸の廃城はどれか? 安土城 大阪城 浜松城 甲府城
安土城は織田信長が天正4年(1576年)に築いた城で、近世城郭の先駆けとされる天守風の大規模な構造を持ちました。所在地は現在の滋賀県近江八幡市安土町で、豪華な造りや政治的拠点としての役割から信長の権力を象徴する存在でした。本能寺の変(1582年)後に廃城となり、遺構はほとんど残りませんが、発掘や資料により当時の規模や意匠が明らかになっています。安土城址は史跡として保存・展示され、信長ゆかりの代表的な史跡の一つです。
Q6 : 桶狭間の戦い(1560年)の戦場は、現在のどの市町村付近とされるか? 岐阜県大垣市付近 愛知県豊明市付近 長野県上田市付近 滋賀県大津市付近
桶狭間の戦いは1560年、今川義元が尾張に侵攻した際に織田信長が奇襲をかけて勝利した戦いで、その主要な戦闘地点は現在の愛知県豊明市と名古屋市緑区の境界付近とされています。史料や地形の比較からこの地域が特定され、桶狭間古戦場として記念碑や案内が整備されています。戦術的には少数の織田勢が奇襲で大軍を破った例として戦史上有名です。
Q7 : 春日山城や上杉氏と結びつき、越後国の拠点であった城は次のうちどれか? 武田信玄 徳川家康 上杉謙信 織田信長
春日山城は越後国(現在の新潟県上越市)に位置し、上杉謙信の本拠地として知られる山城です。山頂に本丸を置く典型的な背山城で、軍事的・政治的拠点として戦国期に整備されました。謙信は越後統治と対外的な戦いをここから指揮し、春日山城跡には堀切や石垣の一部、謙信に関する資料を展示する博物館などがあり、上杉氏の拠点として史跡価値が高い場所です。
Q8 : 川中島の戦い(上杉謙信と武田信玄の連続した合戦)が行われた地域は、当時のどの国に属していたか? 越後国(現在の新潟県) 尾張国(現在の愛知県) 駿河国(現在の静岡県) 信濃国(現在の長野県)
川中島の戦いは戦国期に複数回行われた合戦群で、主に信濃国(現在の長野県、特に長野市周辺)の川中島平野で行われました。上杉謙信(越後)と武田信玄(甲斐)の国境紛争が背景にあり、地形を生かした激戦が繰り返されました。代表的なのは天文・永禄年間の戦闘で、地名や武将の行動が史料に残され、信濃の戦場として史跡や合戦跡が知られています。
Q9 : 武田信玄の居館(躑躅ヶ崎館)があったのは次のうちどこか? 躑躅ヶ崎館(甲斐・甲府) 浜松城(遠江) 大阪城(畿内) 上田城(信濃)
躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)は武田氏の本拠で、甲斐国(現在の山梨県甲府市)にありました。戦国大名・武田信玄が政務と居住の中心とした館で、館の周囲には城郭的な防御施設や城下町が形成されました。近世の石垣天守を持つ城とは異なり、中世の館的構造ですが、武田氏の政治・軍事の中心地として史料にも多く登場します。現在は館跡や関連史跡が残り、武田信玄ゆかりの地として知られます。
Q10 : 長篠の戦い(1575年)に関連する設営や激戦が行われた城・地域はどこか? 大津市 新城(現在の愛知県新城市) 甲府市 米沢市
長篠の戦いは織田・徳川連合軍が武田勝頼の騎馬軍団を迎え撃った戦いで、戦場は現在の愛知県新城市(当時の設楽郡長篠附近)です。長篠城や鳶ヶ巣山など周辺の地形を利用した戦術と、鉄砲隊の運用が有名です。長篠・設楽原古戦場として史跡整備され、長篠城址や戦いに関する資料館があり、戦術史上重要な合戦として観光・学術の対象になっています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は戦国武将ゆかりの地巡りクイズをお送りしました。
今回は戦国武将ゆかりの地巡りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!