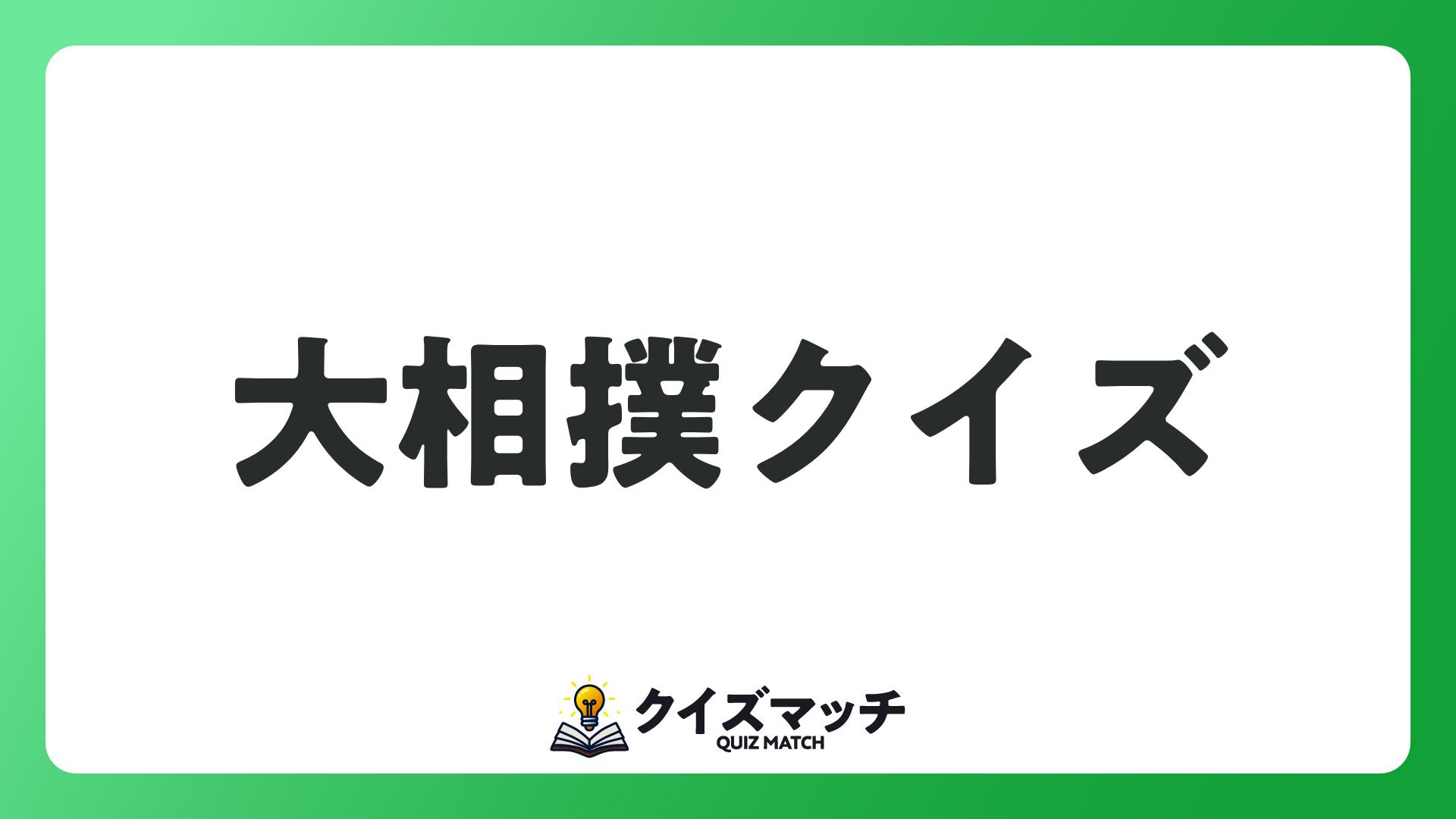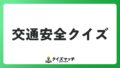大相撲は日本の伝統文化の一つで、長い歴史と独特の規則、伝統が存在します。その大相撲についてよく知っていただくために、本記事では大相撲のさまざまな側面をクイズ形式で取り上げています。横綱昇進条件、土俵の素材、行司の道具、番付表の役割など、大相撲ならではの特徴について学べる10問を用意しました。大相撲ファンはもちろん、初めて触れる方にも楽しんでいただけると思います。大相撲の魅力をぜひ感じ取ってください。
Q1 : 大相撲の勝利方法として認められないものはどれでしょうか?
大相撲の勝利方法には、様々な技が認められていますが、「控え手」は勝利方法として存在しません。控え手とは、取り組みの際にバックアップを行う手助けのことで、技とは異なります。技術としては認識されていないため、正式な勝利方法としてはカウントされません。他の選択肢は、すべて実際に存在する立派な技です。
Q2 : 力士が通常どおり土俵に上がる際に履くものは何ですか?
力士が普段土俵外で履く草履を土俵際までくると脱ぎ、土俵では素足の状態で取り組みを行います。草履は、力士が会場へ出入りする際に履くもので、日本伝統の履物となります。土俵場では、特に力士が足の裏で土俵の感触を感じることで力強さや安定感を向上させるために裸足という伝統が続けられています。
Q3 : 大相撲で6場所ある年間興行のひとつは、どこの開催でしょうか?
大相撲は年間6回の本場所があります。東京で初場所(1月)、春場所(3月)、名古屋場所(7月)、秋場所(9月)が開催されます。その他に5月と11月の場所がそれぞれ大阪と福岡で行われます。これにより、大相撲は全国で大々的に行われ、各地のファンに親しまれています。福岡場所は通常11月にイベントがあります。
Q4 : 大相撲で、取り組みに勝利した力士が受け取る賞金の名称は何でしょうか?
取り組みに勝利した力士が受け取る賞金は「懸賞金」と呼ばれます。懸賞金は、特に幕内上位の取組みで出され、スポンサーや企業が懸けられたお金を指します。懸賞金の数は取り組みごとに異なり、勝利者だけが受け取ることができます。この懸賞金は力士にとって大きなモチベーションの一つです。
Q5 : 大相撲の力士が引退した際、与えられる称号は何でしょうか?
力士が現役を引退した後、相撲協会の規定を満たすことで親方として活動することができます。親方とは、元力士が自分の部屋を持ち、弟子を育成したりする立場を指します。また、実績や貢献度によっては、審判や協会内部での仕事を持つこともありますが、まずは親方としての免許を取得する必要があります。
Q6 : 大相撲の中で、力士の立ち位置が決まる番付の種類は?
力士の地位や階級を示すのが番付表です。番付表は、重量地位に基づく力士の順位が書かれており、横綱、大関、関脇、小結、前頭、序二段以下とカテゴライズされます。番付表は、発行されるごとに公式に競技会が近づく証として認識され、力士たちにとって非常に重要なものです。
Q7 : 大相撲の行司が持つ、判定を示すための道具は何でしょうか?
行司は、取り組み中、軍配を使用して判定を示します。軍配とは、扇状の道具で、行司はこれを持って取り組みの開始と終了、勝ち負けを示します。軍配が下がるとタイムレースの合図で、上がると立ち会いの合図になります。行司の判定がまたされるため、非常に重要な役割を果たします。
Q8 : 大相撲の土俵は一般に何で作られているでしょうか?
大相撲の土俵は土で作られています。土俵は四角い舞台の中央に円形に盛り上げられ、粘土質の土が使用されます。これにより、土俵が滑りにくくなり、力士の踏ん張りやすさが向上します。土の上に砂がまかれ、取り組み終了後にそれが整えられることで、力士の動きがよくわかるように配慮されています。
Q9 : 大相撲での制限時間があるのはどの取り組み前でしょうか?
大相撲の取り組みでは、土俵上で仕切りと呼ばれる一連の動作があります。この仕切りには時間制限がありますが、実際の取り組みには制限時間はありません。幕内の取り組みではこの制限時間が4分とされており、これを過ぎると審判長が制限時間を伝え、速やかに立会いを促します。
Q10 : 横綱の昇進条件に関係している番付はどれでしょうか?
横綱に昇進するためには、通常、大関の地位での活躍が条件となります。ただし、必ずしも公式に明示された条件はありませんが、通常は大関で2場所連続優勝、またはそれに準じる成績が求められます。大関以外の地位からの昇進は非常に例外的であり、通常大相撲の昇進では取り上げられません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は大相撲クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は大相撲クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。