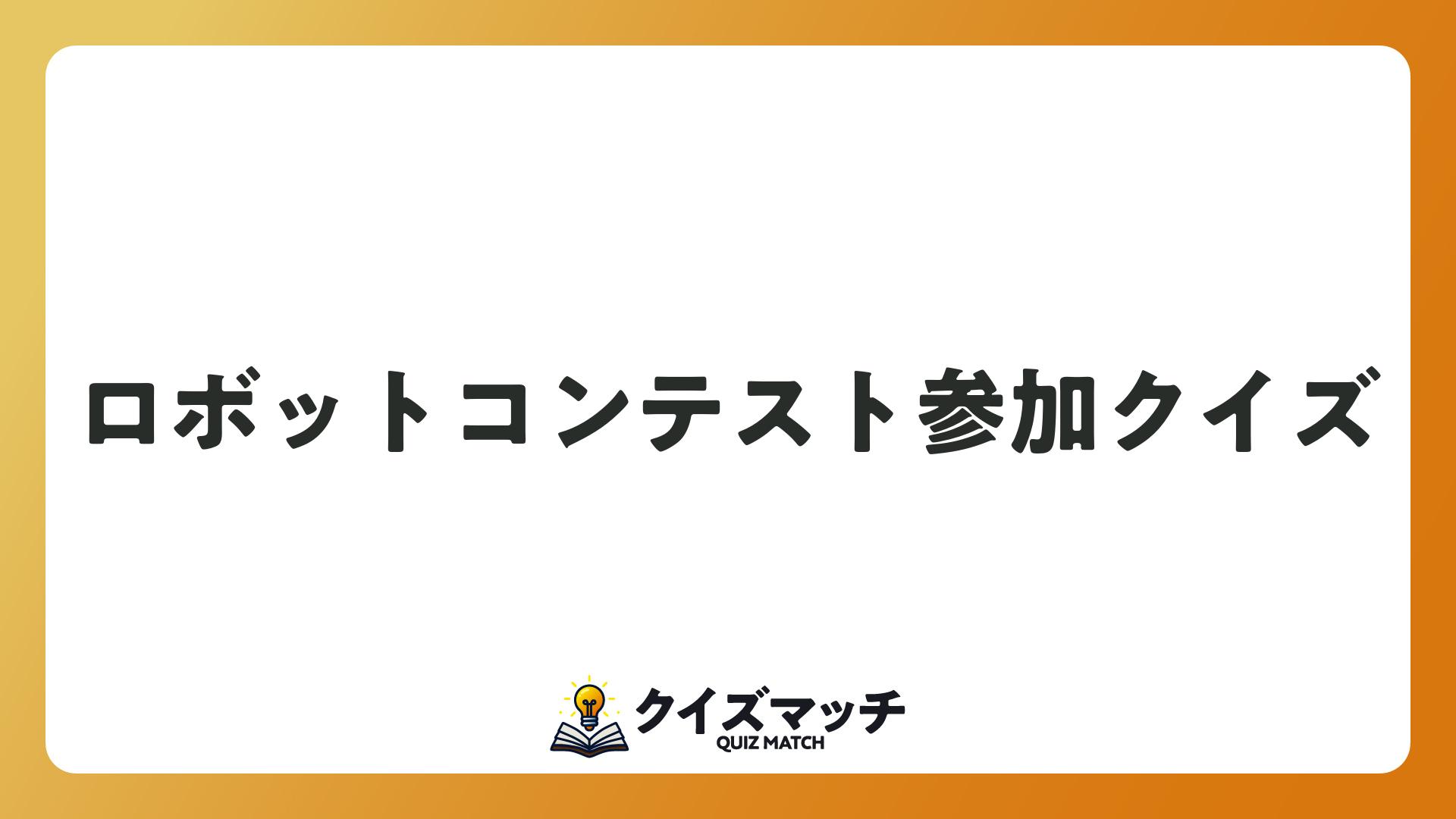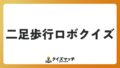ロボットコンテストを目指すみなさん、この記事では参加に向けて必要な基本知識を10問のクイズで紹介します。ラインセンサの原理から、PID制御、エンコーダの種類、差動駆動の操作方法、安全装置としての非常停止機能など、ロボットの設計と制御に欠かせないテクノロジーについて学べます。また、自己位置推定や地図作成のSLAM手法、バッテリーのCレート、カルマンフィルタの仮定など、先進的な自律移動技術の基礎も解説しています。ぜひ確認して、コンテストに向けた準備に役立ててください。
Q1 : 競技で使うセンサのうち、角分解能が高く長距離の測距が得意で地図作成や障害物検知に広く使われているのはどれか? 超音波センサ 赤外反射センサ カラーカメラ レーザ(LiDAR)センサ
LiDAR(Light Detection And Ranging)センサはレーザー光の反射を利用して高精度な距離と角度の情報を取得できるため、障害物検知や環境の高密度な点群取得、2D/3D地図作成に適しています。超音波や赤外は近距離や粗い測距に向き、カメラは視覚情報は豊富だが距離推定には追加処理やステレオ化が必要です。LiDARは精度・レンジ・角分解能の点で優れるためロボコンでも多用されます。
Q2 : 大会で要求される非常停止(E-stop)の機能として最も重要なのは次のうちどれか? 制御プログラムの実行を一時停止すること モーターやアクチュエータの駆動信号を即座に遮断して運動を停止させること 無線通信を遮断すること マイコンをリセットして再起動させること
E-stop(非常停止)は人や機器の安全を守るために即時に機械的運動を止めることが最優先です。具体的にはモーターやアクチュエータへの駆動電力や駆動信号を遮断して動力源を無効化し、機体の移動やアクチュエータ動作を速やかに停止させます。プログラムの一時停止や無線遮断、リセットは補助的手段であり、実際の危険除去には駆動系の遮断が不可欠です。
Q3 : 自律移動ロボットが未知環境で同時に自己位置推定と地図作成を行う技術を何というか? オドメトリ(死算) GPSによる位置推定 SLAM(Simultaneous Localization and Mapping) 単純閾値センサ制御
SLAMはセンサデータ(レーザ、カメラ、IMUなど)と運動モデルを用いて、ロボットが同時に自己の位置を推定しながら周囲の地図を構築する手法です。オドメトリは車輪速度から位置を推定するが累積誤差を修正できず、GPSは屋外限定で精度や観測条件に依存します。SLAMは観測の特徴量と自己位置推定を結合して誤差を補正し、未知環境での自律移動に有効です。
Q4 : リチウム系バッテリーの「Cレート(C)」が示す意味として正しいのはどれか? バッテリーの充放電可能回数を示す指標である 定格容量に対する充放電電流の倍率(例:1Cは1時間で容量を放電する電流) 電池内部抵抗の大きさを示す指標である バッテリーの重量(重量当たりの容量)を示す指標である
Cレートはバッテリーの定格容量に対する電流の倍率を示します。例えば容量が1000mAhの電池で1Cは1A、0.5Cは0.5A、2Cは2Aに相当し、1Cで放電すると理論的に1時間で放電が完了します。これにより充放電速度と発熱、寿命への影響を評価できます。Cレートは回数や内部抵抗、重量そのものを直接示すものではありません。
Q5 : カルマンフィルタ(基本形)が前提とする主な確率的仮定はどれか? 観測ノイズとプロセスノイズがポアソン分布であること ノイズは時間により相関が強い非線形過程であること ノイズがガウス分布であり、システムが線形であること ノイズが一様分布であり、システムは周期的であること
古典的な(線形)カルマンフィルタはシステムの状態遷移と観測が線形モデルで表現され、プロセスノイズと観測ノイズが平均ゼロのガウス(正規)分布であることを仮定します。この仮定の下で状態推定は最小二乗(最小分散)推定となり、閉形式で最適推定器が得られます。非線形や非ガウスの場合は拡張カルマンフィルタや粒子フィルタ等の手法が用いられます。
Q6 : 2次元平面で剛体の回転と並進を同時に表現するホモジニアス変換行列(同次変換)は何次の行列か? 2×2行列 3×3行列 4×4行列 6×6行列
2次元空間(SE(2))の同次変換は回転行列と並進ベクトルをまとめて扱うために3×3の行列で表現します。上段左が2×2回転成分、上段右が並進の2×1ベクトル、下段は[0 0 1]となり、一つの行列で回転・並進の合成や座標変換が容易になります。3次元の場合は4×4行列(SE(3))を用いるのが一般的です。
Q7 : ライントレース用の反射型フォトセンサが検出する主な情報は何か? 路面の色(カラー)を直接判別する 反射光の強弱(明るさ)の違いを検出する 磁場の強さを検出する 超音波の到達時間を測る
反射型フォトセンサは発光素子(通常は赤外LED)と受光素子(フォトトランジスタ等)を用い、路面やラインからの反射光の強さの差を電気信号として取り出します。色そのもののスペクトルを詳細に識別するのではなく、白や黒といった反射率の違いを利用してラインを検出します。磁場や超音波の測定とは原理が異なり、光の反射強度を基に閾値やアナログ値で位置ずれを検出して制御に利用するのが一般的です。
Q8 : PID制御で定常偏差(定常状態で残る誤差)を小さくする効果がある項はどれか? 比例(P)項 積分(I)項 微分(D)項 フィードフォワード項
PID制御において積分(I)項は過去の誤差を時間積分して制御量に反映することで、累積した誤差を打ち消し定常偏差をゼロに近づける役割を果たします。比例項は応答を大きくするが定常偏差を完全には無くせないことが多く、微分項は応答の振動抑制や予測的補正に寄与します。フィードフォワードは外乱補償に有効ですが、定常偏差の打ち消しは積分項が主になります。
Q9 : ロータリーエンコーダ(エンコーダ)のうち「クアドラチャエンコーダ」が通常持つ特徴はどれか? 単に回転パルスの総数だけを出力する 絶対角度を電源投入直後から示す 位相差により回転方向を判別できる 回転トルクを直接測定できる
クアドラチャ(矩形相)エンコーダはA相とB相という二つのパルス信号を90度位相差で出力します。この位相差により信号の先行・後行を判定して回転方向を識別でき、またエッジ検出で分解能を2倍または4倍に拡張できます。絶対エンコーダは別種で電源投入時から角度が分かりますが、クアドラチャは通常は相対位置計測に使われます。
Q10 : 差動(ディファレンシャル)駆動のロボットをその場で旋回(その場で回転)させるための車輪の動かし方として正しいのはどれか? 左右両輪を同じ方向に等速度で回す 片側の車輪だけをゆっくり回す 両輪を逆向きに異なる速度で回す 左右の車輪を逆方向に同じ速度で回す
差動駆動でその場回転(スピンターン)を実現するには、左右の車輪を互いに逆方向に同じ角速度で回転させます。このときロボットの中心はその場で回転し、並進成分が打ち消されます。片側のみや同方向回転ではその場回転にならず、異なる速度で逆向きに回すと回転速度は非対称になり中心がずれる可能性があるため一般的には等速で逆向きが用いられます。
まとめ
いかがでしたか? 今回はロボットコンテスト参加クイズをお送りしました。
今回はロボットコンテスト参加クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!