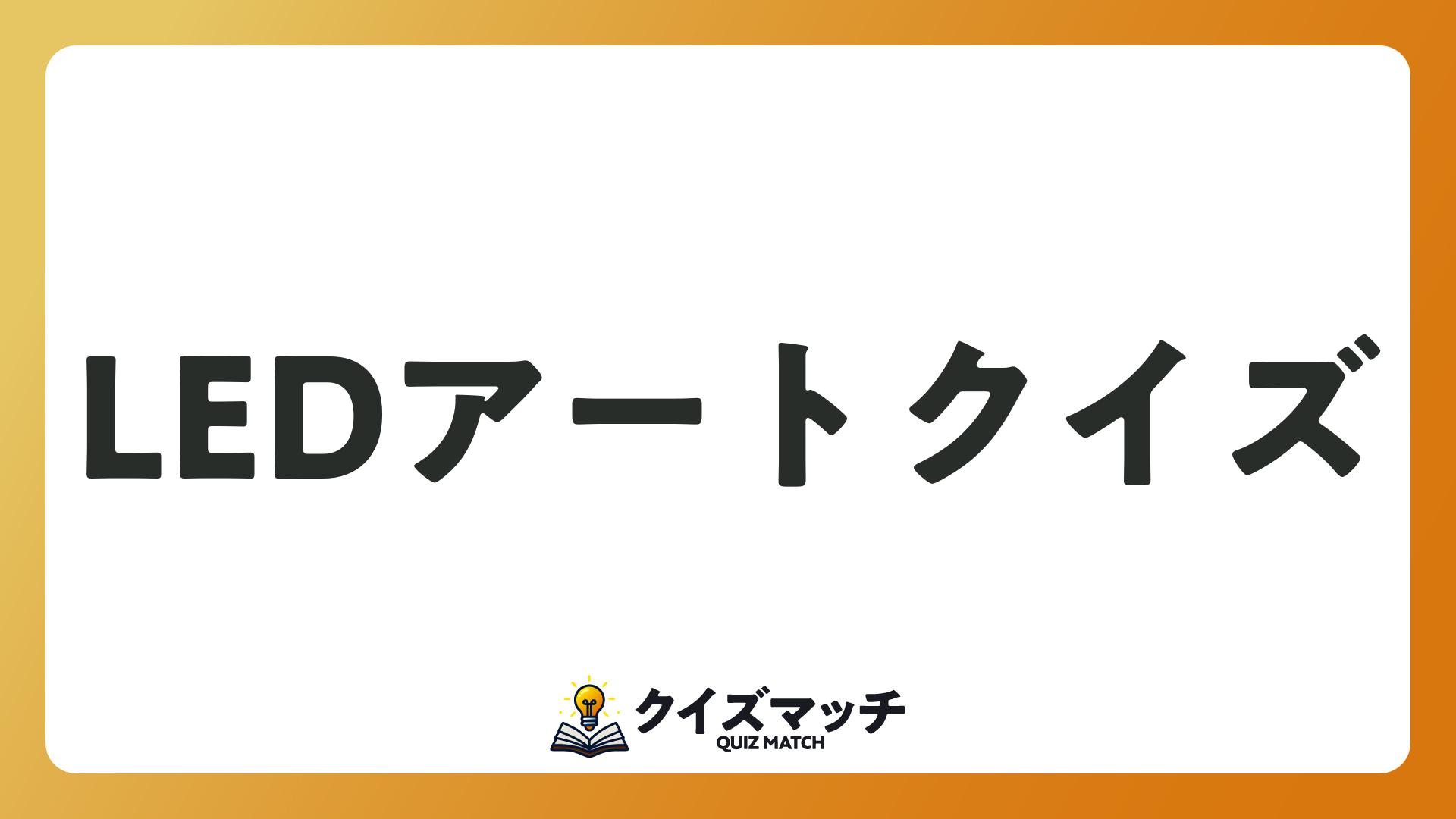LEDアートの世界へようこそ。この10問のクイズであなたのLED知識を試してみましょう。加法混色の不思議、PWMの仕組み、アドレス可能LEDの特性、DMXプロトコルの基本、電源設計の注意点など、LEDを使ったアート制作に必要な基礎知識が問われます。クイズを通して、LEDの物理特性や制御手法を理解し、より創造的な表現につなげていきましょう。光のアーティストを目指す方にぜひお楽しみいただきたい内容です。
Q1 : Wi-Fi接続で多数のLEDを遠隔制御し、性能やピン数が豊富でRMT/I2S等の精密なタイミング制御が行いやすいマイコンとして現在よく使われるものはどれか?
ESP32はWi-FiやBluetoothを内蔵し、クロックや割り込み、RMT(Remote Control)やI2Sなどのハードウェア機能を活用してアドレス可能LEDのタイミング生成や大量データの送信を比較的容易に行えるため、LEDアートの制御に広く使われています。性能が高くI/Oも豊富なので、多数のLEDやセンサ、ネットワーク連携を行う作品に適しています。
Q2 : 白色の見え方を示す色温度について、いわゆる「電球色(暖かい白)」に相当する代表的なケルビン値はどれか?
色温度はケルビン(K)で表され、低い値ほど赤みを帯びた暖かい光、高い値ほど青白い光に見えます。家庭用の電球色(暖色系)の代表値としては約2700K前後が一般的で、温かみのある落ち着いた雰囲気を演出します。5000Kや6500Kは昼光色や寒色系、3500Kはやや中間のニュートラル寄りといえます。LEDアートでは色温度の選択が作品の印象に大きく影響します。
Q3 : LEDアートでPWM(パルス幅変調)を利用する場合、PWMが主に制御しているものは何か?
PWM(Pulse Width Modulation)は一定周期のオン/オフの比率(デューティ比)を変えることで、LEDの平均的な出力を調整し、人間の目に対して明るさを変化させる手法です。電圧そのものを可変するのではなく、電源を高速で切り替えることで見かけ上の輝度を制御します。色温度や遅延を直接変えるものではなく、RGBそれぞれのチャネルでPWMを行うと色合いの調整も可能になります。
Q4 : WS2812Bのような一般的なアドレス可能LEDストリップの標準的な動作電圧はどれか?
WS2812Bをはじめとする多くの「NeoPixel」タイプのアドレス可能LEDは5Vで動作する設計になっています。データ線は5Vロジックに最適化されているため、3.3Vマイコンを使う場合はレベル変換が必要になることがあります。また、各LEDのフルホワイト時の最大消費電流は約60mA(R,G,B各20mA)になるため、電源容量と配線の電圧降下に注意する必要があります。
Q5 : WS2812系LEDでしばしば言及される「カラーオーダー(出力順)」として多く使われているのはどれか?
WS2812/WS2812B系のLEDではICの実装や製品によって異なりますが、GRB(Green-Red-Blue)の順でデータが配置されていることが多く、ライブラリや配列設計の際に注意が必要です。誤った色順で出力すると色がずれて表示されるため、対応するライブラリの設定や実機の仕様確認が重要です。APA102など他のICはRGB順など別の順を採ることもあります。
Q6 : LEDアートで人間の目にちらつきが見える主な原因として正しいものはどれか?
LEDのちらつき(フリッカー)は主にPWMや電源のオン/オフ周期が人間の視覚の閾値に近い場合に発生します。PWM周波数が低いと視覚的に点滅として認識されやすく、特に周辺視野では敏感になります。対策としてはPWM周波数を十分高くする、一定の直流成分を持たせる、電源を安定化するなどがあり、映像撮影時はカメラのシャッタースピード/フレームレートとも合わせる必要があります。
Q7 : LEDパネルやストリップでディフューザー(拡散板)を入れる主な目的は何か?
ディフューザーは個々のLEDの点光源性を和らげ、複数のLEDが発する光を混ぜて面光源のように見せるために使われます。これによりドット感(ピクセル感)を低減して滑らかなグラデーションや均一な面発光を実現できます。拡散材の種類や厚みでぼやけ具合やコントラストが変わるため、作品の意図に合わせて選定することが重要です。集光や色温度の変化、効率向上は主目的ではありません。
Q8 : DMX512を使ってRGB(各色独立制御)の灯具を個別に制御する場合、1台あたり通常何チャンネルを割り当てるか?
DMX512は512チャンネルを持つ照明制御プロトコルで、RGBの各色を独立に制御する従来型のフィクスチャでは、赤・緑・青の3チャンネルを占有することが一般的です。各チャンネルは0〜255の値を持ち、色と明るさを表現します。より複雑な機能(ディマー、ストロボ、色温度など)を持つ器具ではチャンネル数が増えますが、単純なRGBライトは3チャンネルが基本です。
Q9 : フルホワイト(R,G,Bすべて最大)で点灯したとき、一般的な1個のRGB LED(各色約20mA)が消費するおおよその電流はどれか?
標準的なRGB LEDでは各色が約20mA程度流れる設計が一般的で、赤+緑+青を同時に最大で点灯すると合計で約60mAの電流が流れます。アドレス可能LED(例:WS2812系)もフル白で1灯当たり約60mAになるのが目安です。多数のLEDを使用する際は電源容量と配線の許容電流を十分に見積もり、電圧降下や発熱にも注意を払う必要があります。
Q10 : RGB LEDの加法混色に関する問題:赤と緑を同時に最大輝度で点灯させると何色に見えるか?
LEDの色は加法混色で決まります。赤(Red)と緑(Green)を同時に同等の強さで点灯すると、人間の目には黄色に見えます。これは光の三原色(赤・緑・青)の加法混色の基本で、印刷の減法混色(シアン・マゼンタ・黄)とは原理が異なります。白はRGBすべてを同時に最大で点灯させたときに得られ、マゼンタやシアンは赤+青、緑+青など別の組み合わせで生じます。演出や色設計ではこの加法の性質を利用して多彩な表現が可能です。
まとめ
いかがでしたか? 今回はLEDアートクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はLEDアートクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。