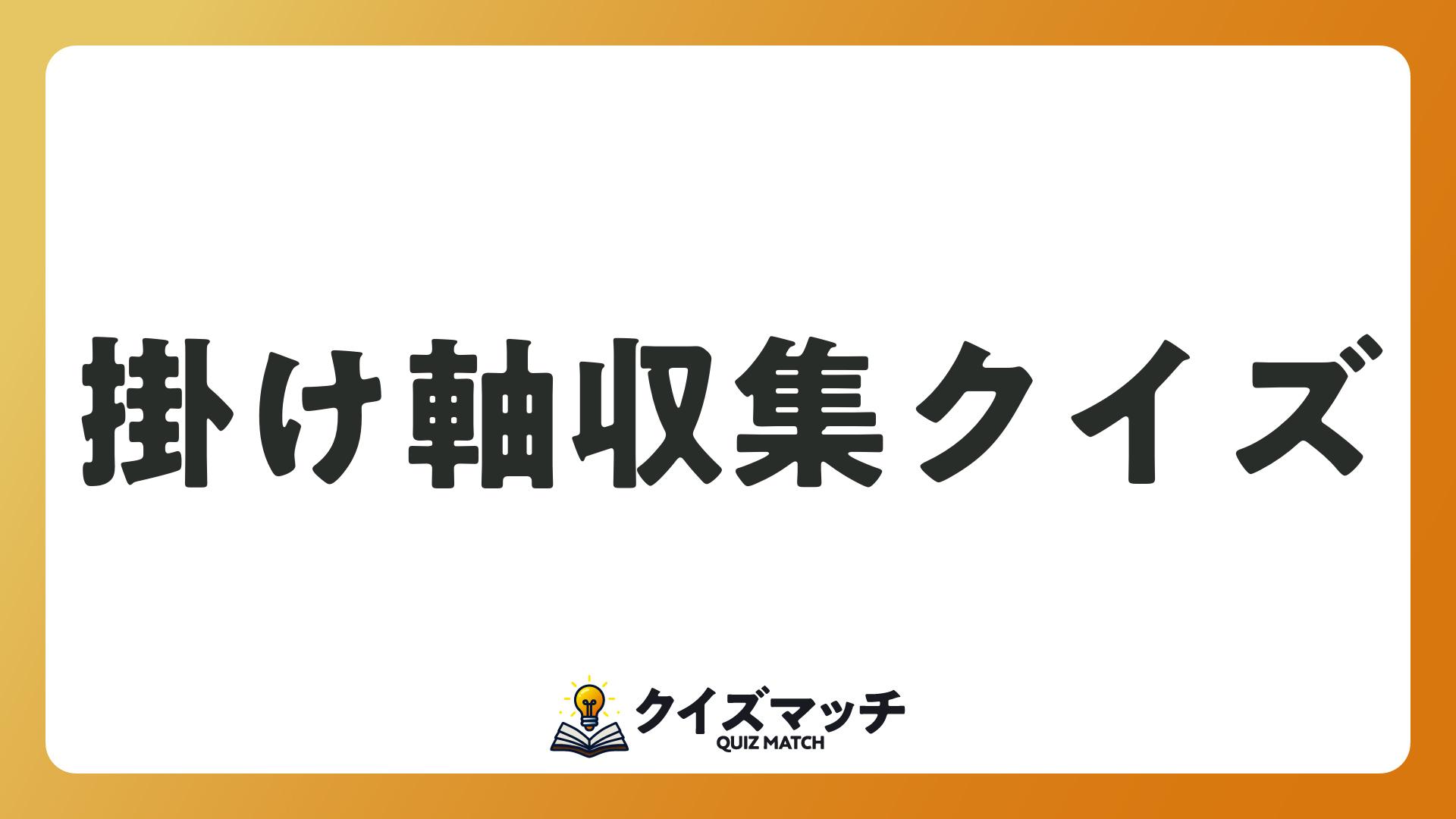掛け軸はその歴史と伝統、そして美意識が魅力の文化遺産です。本記事では、掛け軸コレクションを楽しむためのクイズをご紹介します。掛け軸の構造や材質、作家、鑑賞ポイントなど、コレクターとしての知識を深められる内容となっています。掛け軸の細部にまで注目すれば、その歴史に触れ、作品の価値を理解することができるでしょう。真の掛け軸愛好家になるためのヒントが詰まった、必見のクイズをお楽しみください。
Q1 : 金地に四季の草花を描くなど装飾性豊かで、光琳・抱一らが活躍した画派はどれ?
琳派は江戸初期の本阿弥光悦、俵屋宗達に始まり、尾形光琳、酒井抱一らが継承した装飾性豊かな絵画様式で、屏風だけでなく掛け軸の肉筆画も多く伝わる。金地や群青に花鳥草木を配置し、余白とリズムを活かした構図が特徴。光琳や抱一の掛け軸は状態が良ければ数千万円単位で取引され、近代の神坂雪佳など後継作家の作品も人気がある。縁起物の松竹梅図や季節を彩る草花図は床の間映えがよく、茶人の好みとしても定着している。
Q2 : 床の間上部に打ち付け、掛け軸の掛緒を引っ掛けるための金具は何と呼ばれる?
床の間の上部に打ち付け、掛け軸の掛緒を引っ掛ける金具が掛釘である。鉄製や真鍮製が一般的だが、茶室では目立たないよう黒漆仕上げのものが好まれる。打つ位置は地板からおよそ180センチ前後が標準で、作品の丈に合わせ微調整する。掛釘が不適切だと軸が前傾しシワや巻癖の原因となるほか、転落事故にもつながる。床の間を新設する場合、柱の芯材が堅木かどうか確認したうえで掛釘を固定することが望ましい。
Q3 : 禅宗で師から弟子へ法の継承を証明する文書で、掛け軸形式で残ることも多いものは?
印可状は禅宗において師匠が弟子に法を嗣ぐ証として授与する文書で、多くは巻物または掛け軸形式で残される。内容は血脈譜や法語、師名と花押が書かれ、弟子が修行の間持ち歩くこともあったため擦れや折れが多い。現存例は室町末期から江戸初期が多く、真正かどうかは墨跡の筆致、紙質、朱印の押し方で判定される。禅林墨蹟の分野では高位の僧の印可状は希少で、市場でも数百万円規模になることがある。
Q4 : 掛け軸を水平に寝かせ、引き出し式で多数収納できる桐材の専用家具を一般に何と呼ぶ?
掛け軸箪笥は薄型の引き出しを何段も備え、掛け軸や巻物を水平に収納できる専用家具で、桐材が用いられることが多い。桐は調湿性と防虫性に優れ、火災の際も内部の温度上昇を遅らせるため古美術品の保管に最適。引き出し底には軸盆と呼ばれる木枠や布包みを敷き、巻癖を防ぐため作品を軽く寝かせる。一本ずつ布袋に入れて番号を振れば出し入れも容易で、鑑賞会の準備が格段に早くなる。
Q5 : 掛け軸の本紙周囲をぐるりと囲む主布地を一般に何と呼ぶか?
掛け軸は本紙・一文字・中廻し・風帯・軸木など複数の部材で構成されるが、中廻しは本紙のすぐ外側をぐるりと囲む最も広い布地で、作品の雰囲気を調和させる重要な役割を担う。派手すぎる裂を使うと本紙を殺してしまうため、表具師は色味・文様・質感を慎重に選定する。修復時には中廻しだけを張り替えて印象を一新することもあり、収集家の評価ポイントとなる。
Q6 : 掛け軸の軸装で最も格式が高く、茶室でも改まった席に用いられる装いは次のうちどれ?
掛け軸の軸装には真・行・草の三体があり、仏画や格式ある場面に用いられるのが真である。真は天地に金襴の一文字を配し、中廻しも同系統の裂で統一するなど端正で重厚。茶道では床の間の格式や季節、招く客筋に応じて真行草を使い分けるが、最も改まった席では真が選ばれる。収集家も裂の選定や仕立ての丁寧さから真表具を高く評価し、保存状態が良いと価格が上がる。
Q7 : 風景版画「東海道五十三次」を制作し、肉筆掛け軸の花鳥画も人気が高い江戸後期の浮世絵師は誰か?
歌川広重は江戸後期の浮世絵師で、代表作東海道五十三次は風景版画として世界的に知られる。彼は版画のみならず肉筆画も手がけており、四季の花鳥や街道風景を描いた掛け軸作品は国内外のコレクターに人気が高い。版画に比べ一点物であるため希少価値が高く、保存状態や落款の有無によって価格が大きく変動する。柔らかな遠近法や叙情的な色彩は肉筆でも健在で、鑑賞の愉しみが深い。
Q8 : 湿気対策として掛け軸を収納する箱に一緒に入れられる吸湿材として最も一般的なのは?
掛け軸は絹や和紙でできているため湿気に弱く、カビやシミが発生すると修復費が高額になる。そこで保管箱内に入れるのがシリカゲル乾燥剤である。シリカゲルは多孔質で吸湿性が高く、一定以上の湿度になると水分を取り込んで結晶が色変するタイプもあり交換の目安になる。木箱や桐箱にシリカゲル包を同梱し、年に一度程度取り替えることで湿度を50%前後に保ち、作品を長期にわたり良好に保存できる。
Q9 : 掛け軸の上部から二本垂れ下がる細長い布片で、装飾的意味合いも強い部分を何と呼ぶ?
風帯は掛け軸上部に二本垂れ下がる細長い布片で、本来は巻き上げた際に外風から本紙を守る役目を果たしたため風帯と呼ばれる。現在では実用性より審美性が重視され、裂地や丈で全体のバランスを取る装飾的要素となっている。床の間に掛けた際にゆらりと揺れる姿が品格を添え、禅画や墨蹟では無地、花鳥画や琳派では文様入りなど作品の格と調和を考慮する。欠損や汚れの有無は評価にも直結する。
Q10 : 掛け軸の本紙裏に薄い和紙を貼り重ねて補強する表具の基本工程は?
裏打ちは本紙の裏から薄い和紙を糊で貼り重ね、強度を持たせると同時にシワや波打ちを矯正する表具の基本工程である。和紙は繊維が均一で中性に近いものが用いられ、糊には小麦澱粉を発酵させて作る生麩糊が使われる。適切な裏打ちが施されると本紙が呼吸しやすくなり、温湿度変化による伸縮にも耐える。逆に粗雑な裏打ちは変色や剥離を招き価値を損なうため、収集家は裏打ち紙の質や時代を細かく確認する。
まとめ
いかがでしたか? 今回は掛け軸収集クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は掛け軸収集クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。