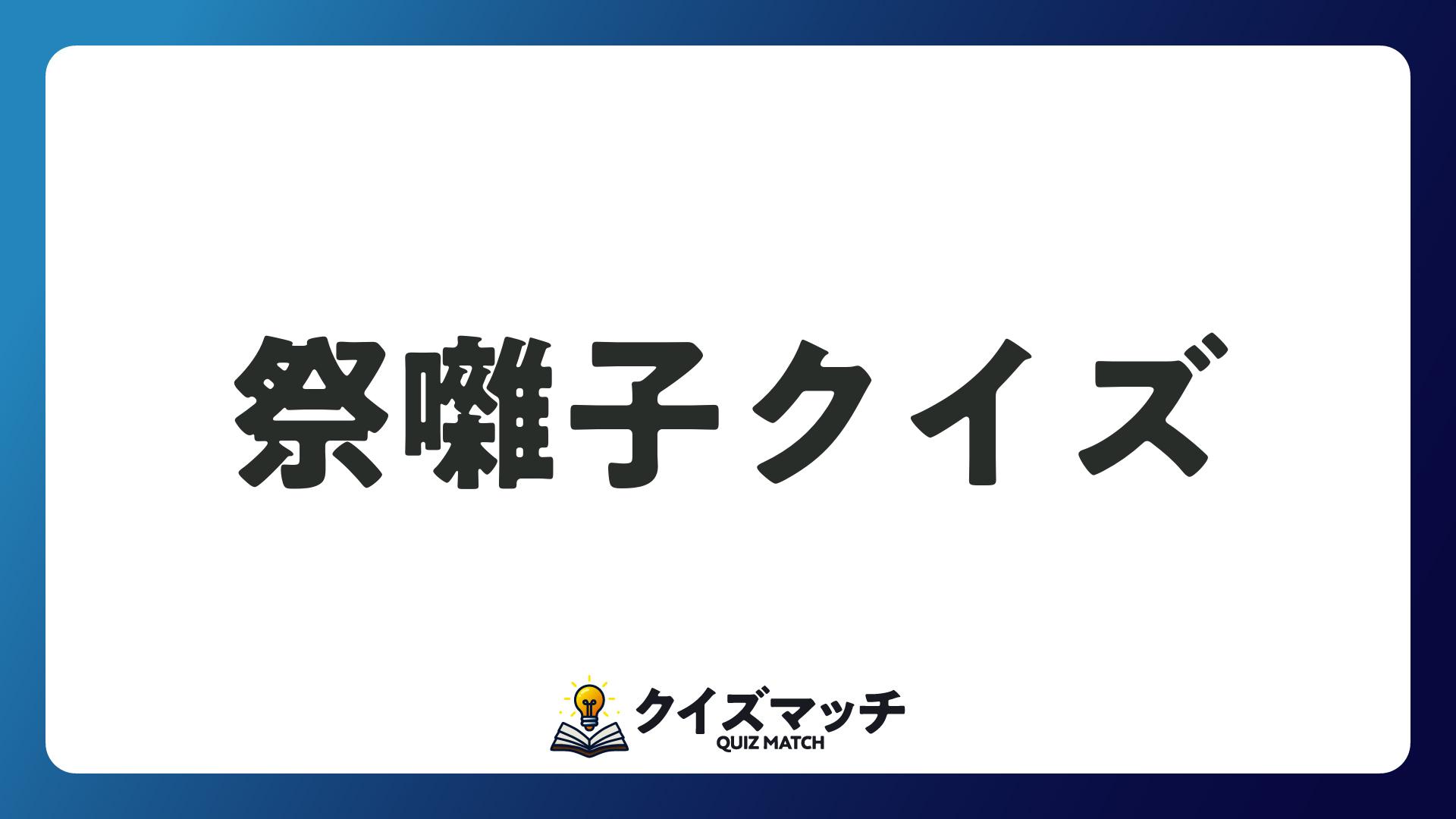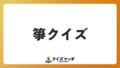江戸祭囃子の基本となる四人編成から、京都祇園祭の象徴的フレーズ、青森ねぶた祭の勇壮な囃子、阿波踊りの独特の鳴り物、諏訪大社御柱祭の木遣り囃子、そして関東三大囃子まで、日本各地に息づく祭りの伝統的な囃子楽について一挙にご紹介します。これらの祭囃子に特徴的な楽器や旋律、リズムなどを10問のクイズにまとめ、祭りの音楽の魅力に迫ります。祭りの祝祭性と地域性を体感できる、祭囃子の世界をお楽しみください。
Q1 : 阿波踊りの囃子で、鉦と太鼓に加えてリズムと旋律を兼ねる弦楽器として用いられるのはどれか?
徳島阿波踊りの鳴り物は、大太鼓・締太鼓・鉦・篠笛・三味線という編成が一般的で、テンポの速い二拍子に合わせて踊り手の足を誘います。三味線は旋律楽器でありながら、弾く強さやポジションを変えることで独特のパーカッシブな音も出せるため、打楽器と旋律の両面を支える存在です。特に男踊りでは低弦を強く弾いてリズムを強調し、女踊りでは高音のさえずりで優雅さを添えるなど表現の幅も広いです。拍子木やシンバルは鳴り物には含まれず、阿波踊りの基礎を成す弦楽器は三味線である点が重要です。
Q2 : 長野県諏訪大社の御柱祭で、里曳き行事中に演奏される囃子は太鼓と何の組み合わせが中心か?
御柱祭は七年に一度行われる勇壮な山出しと里曳きで知られ、巨大な柱を曳行する際に囃子方が演奏するのが木遣り囃子です。囃子は拍のはっきりした太鼓に対し、篠笛が甲高い旋律を重ねて進行の合図や気勢を高めます。里曳きでは狭い町中を通るため音の抜けが良い篠笛が適しており、尺八のような柔らかい音や津軽三味線の撥音は使われません。鳴子も舞踊用の鳴り物で御柱祭には一般的でなく、太鼓と篠笛のシンプルな編成が参加者の掛け声と一体化して祭りを盛り上げます。
Q3 : 祭囃子で使われる竹製の横笛で、孔が7〜8個あり民俗芸能で最も普及しているものはどれか?
篠笛は節を残した細い竹を用い、歌口を斜めに切った横笛で、民俗芸能から歌舞伎囃子、現代邦楽まで幅広く用いられます。能管や龍笛は雅楽や能の専門笛で音域が高く装飾音が多いのに対し、篠笛は素朴で親しみやすい音が特徴です。穴の数は6孔が古型ですが、現在は7孔や8孔が一般的で、半音域の拡大にも対応しています。祭囃子ではメロディー担当として欠かせず、地域によっては調子笛として複数本を持ち替え、山車のキーを合わせるなど機能も多彩です。
Q4 : 江戸囃子の代表的な四曲のうち、演奏の最後に置かれ別れの合図となる曲はどれか?
江戸囃子には山車が動く場面や踊りの場面に応じた定型曲があり、一般的な構成は宮昇殿(宮出し)、鎌倉(行列進行)、屋台(巡行盛り上げ)、四丁目(納め)の順で演奏されます。四丁目はテンポを次第に落としながらフィナーレを示すリズムが特徴で、鉦が締めの合図を出した後に太鼓が二打で終わることで演奏全体を完結させます。曲名は江戸時代の芝居小屋が多く集まった芝居町四丁目に由来し、終演後の余韻を想起させるため別れの曲と呼ばれるようになりました。
Q5 : 関東三大囃子に数えられるのは秩父屋台囃子、佐原囃子と、あと一つはどれか?
関東三大囃子は江戸時代から関東地方で発達した祭礼囃子の中でも特に規模と伝統が際立つ三系統を指し、秩父夜祭で演奏される秩父屋台囃子、千葉県香取市の佐原囃子、そして東京を中心に広がった江戸囃子が該当します。江戸囃子は神田祭や山王祭をはじめ都市部の山車文化に根付き、四人囃子の編成や多彩な曲目を整備した点で他地域の囃子に大きな影響を与えました。川越囃子は江戸囃子の流れをくむものの独立した三大囃子には含まれず、祇園囃子と津軽囃子はいずれも関東ではなく地域が異なるため選外となります。
Q6 : 祭囃子でしばしば耳にする擬音『ドドンガドン』の低音部分を担当する太鼓として最も一般的なのはどれか?
ドドンガドンは二拍三連の重厚なフレーズで、神輿が差し上がる瞬間や山車がカーブを切る場面などで高揚感を演出します。この擬音は実際には大太鼓の低いドンと締太鼓の高いガ、再び大太鼓のドンという組み合わせで作られ、中でも基礎となる低音を出すのが口径の大きな大太鼓です。胴が太く皮も厚いため豊かな残響を持ち、人波や屋台の歓声に埋もれず遠方まで拍を伝えます。締太鼓や桶胴太鼓は装飾的な刻みに使われ、鼓は主に能楽器で祭囃子ではほとんど用いられません。
Q7 : 祭囃子で用いられるヨナ抜き音階はどの音階の作り方を指すか?
日本の民謡や祭囃子、演歌などで使われるヨナ抜き音階は、ドレミファソラシドの七音からヨにあたる第4音ファとナにあたる第7音シを抜いた五音で構成されます。ファとシは半音進行を生む不安定な音なので、これを除くことで旋律がなだらかに流れ、裏拍の跳ねや装飾音とも親和性が高まります。祭囃子の笛旋律では同じ音を持続させながら装飾で色を付ける場合が多く、半音階の緊張が少ないヨナ抜きは簡潔で覚えやすいフレーズ作りに適しています。また、打楽器中心の賑やかな音場でも音が濁りにくいという利点があります。
Q8 : 江戸祭り囃子の基本となる4人編成は何と呼ばれるか?
江戸祭囃子は神田祭や山王祭で発展した屋台囃子の代表格で、大太鼓・締太鼓・鉦・篠笛の4人で組むのが標準です。このため編成そのものを示す名称として「四人囃子」という言葉が定着しました。笛が旋律、締太鼓が細かなリズム、大太鼓が低音の拍、鉦が合図とアクセントを受け持ち、4人が息を合わせて山車の進行や踊り手の動きを導きます。江戸期の町火消や氏子が担った屋台で培われ、現在も東京の神田祭や深川祭などで同じ人数構成が踏襲されています。
Q9 : 祇園祭で聞かれる祇園囃子の代表的な擬音「コンチキチン」を打ち出す打楽器はどれか?
祇園囃子は京都祇園祭の山鉾巡行を彩る音楽で、笛と太鼓類に加え高く澄んだ金属音を鳴らす鉦が独特のアクセントを生みます。祇園囃子の象徴的フレーズとされる擬音コンチキチンは、鉦をコン、締太鼓をチキ、再び鉦をチンと叩いて生じる連打の総称ですが、最も印象的な部分で響く金属音は鉦によるものです。鉦はひし形の台に吊るした銅鑼状の板を撥で打つため伸びのある音が遠くまで届き、祇園囃子の軽快さと華やかさを支えています。
Q10 : 青森ねぶた祭の囃子で勇壮なリズムを打ち出す大型太鼓は何と呼ばれるか?
青森ねぶた祭りの囃子は笛と太鼓、手振り鉦で構成され、囃子方はラッセラーの掛け声とともに隊列を先導します。その中心となるのが口径1メートル近い革を張った大太鼓で、低く重いドンという音が全体のテンポと迫力を決定します。締太鼓や手振り鉦が細かい刻みで装飾的リズムを付ける一方、大太鼓はゆったりとした二拍子基調の脈動を保ち、ねぶた本体と跳人の足取りを合わせる役目を担います。地域ごとに胴の装飾や担ぎ方が異なり、祭りの視覚的な見どころにもなっています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は祭囃子クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は祭囃子クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。