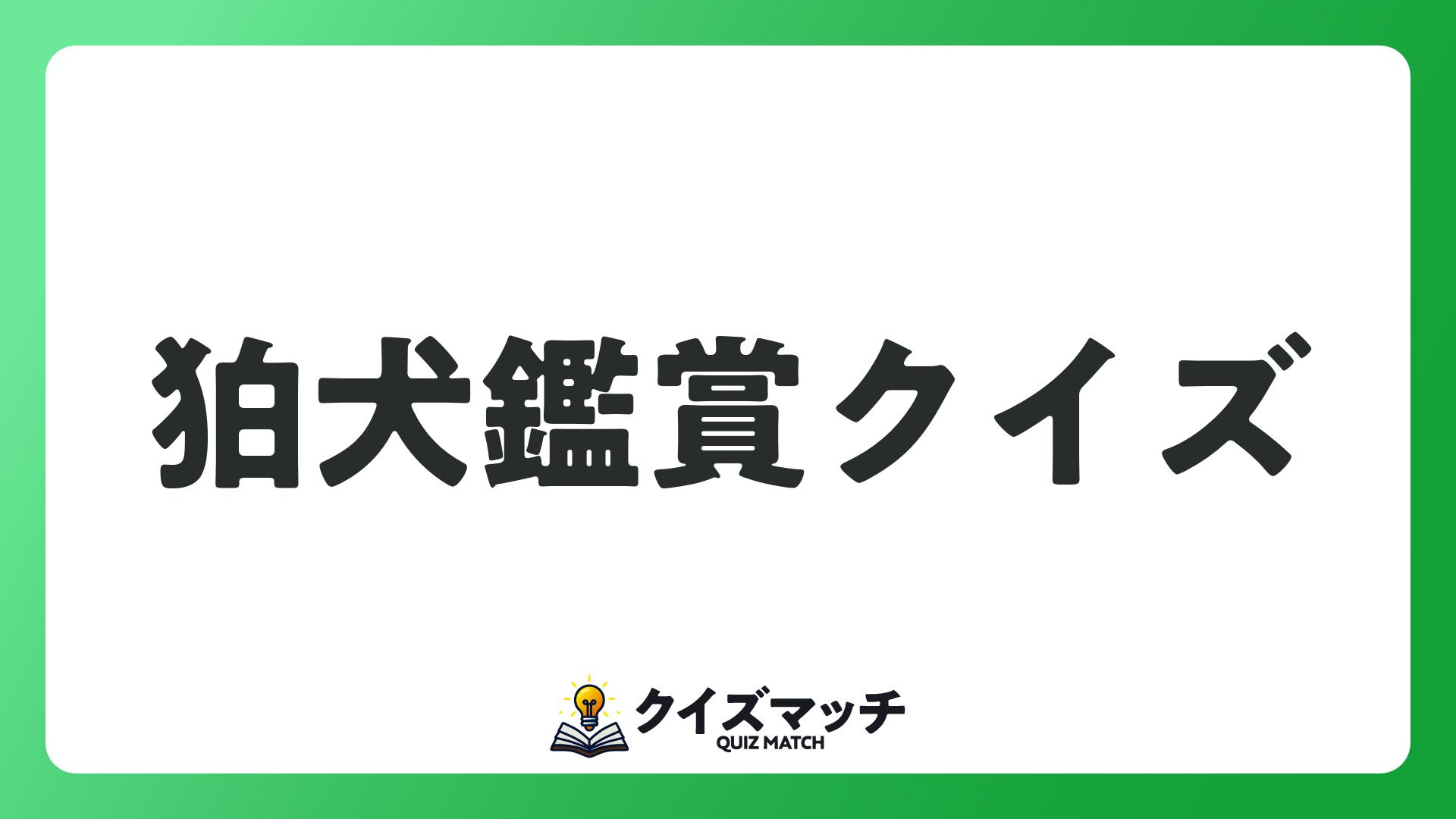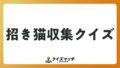日本の神社に立つ「狛犬」は、古来より参拝者を見守る存在として信仰されてきました。その魅力的な姿には、様々な象徴や由来が隠されています。本記事では、狛犬の基本構造や彫刻手法、配置の規則性など、専門家ならではの視点からクイズを10問ご用意しました。狛犬の細部に注目しながら、その歴史と信仰の世界をお楽しみください。狛犬を深く理解することで、神社参拝をより一層有意義なものにしていただければ幸いです。
Q1 : 狛犬を正面から観察したとき、胸と前脚の間に表現される球状の巻き毛の束は専門用語で何と呼ばれる?
毬毛は胸前で渦を巻く毛束を球状にまとめた装飾で、中国獅子の宝珠毛を祖形とする。鎌倉彫刻や江戸石造では大きく張り出すほど高級とされ、社寺の財力を示した。毬毛は力強さと富貴さを象徴し、彫技の見せ場にもなる。袖毛は前脚外側に垂れる毛、ひさし毛は額の房、たれ毛は首から下がる鬣で位置ごとに名称が異なる。毛束名称を覚えると造形の意図や石工の技量が読み取りやすく、鑑賞の深度が一段と増す。
Q2 : 本来、一対のうち角を持つ像を「狛犬」、角を持たない像を「獅子」と呼び分けていました。角がある像を指す名称はどれでしょう?
日本に狛犬像が伝わった初期、角の有無で名称を区別していた。角付きが狛犬、角なしが獅子であり一対で配置された。中世に角が省略されていくと双方をまとめて狛犬と呼ぶ慣習が広まり、現在の総称となる。古式を残す春日大社や神護寺の木造像では吽形が角付きの狛犬、阿形が獅子という区別が残存し、鑑賞時の時代判定や意匠解読の手がかりとなる。角の有無は外来文化の受容過程を示す重要な要素でもある。
Q3 : 京都・西院春日神社に残る国指定重要文化財の石造狛犬は、日本に現存する最古級の石造例として知られます。この狛犬が制作されたと考えられている時代はどれ?
西院春日神社(京都市右京区)の石造狛犬は十三世紀前半、鎌倉時代前期の作とされる。木造が主流だった時代に耐候性を求め石材へ移行し始めた過渡期の遺構で、石に刻まれた渦巻き文様や力強い体躯は当時の仏師快慶系の彫法に通じる。最古級の石造例として屋外に狛犬を置く慣習が広がる契機となり、以後全国で石造狛犬が普及した。制作年代の確定には社伝や作風の比較研究が用いられ、日本の石造彫刻史を語る上で欠かせない資料となっている。
Q4 : 狛犬の台座に刻まれた玉や子獅子などの持ち物を総称して「持ち物狛犬」と呼びます。玉を前脚で押さえているモチーフが象徴するものは何?
玉取り狛犬が押さえる球体は如意宝珠に通じ、理想成就と完全円満な宇宙を象徴する。丸い形は欠ける所のない完全性を表し、願いが丸く収まるよう守護する意味が込められる。江戸期以降は玉をしっかり押さえる姿に災禍を封じ込めるニュアンスも加わり、商家や港町の神社で人気が高まった。子取りは子孫繁栄、巻物は学業成就を示すなど、持ち物によって祈願内容が変わるため、台座の細部に目を向けると信仰の具体的な願いが読み解ける。
Q5 : 江戸時代に流行した狛犬の形式「江戸尾立ち型」で、顔の特徴として最も顕著なのはどれか?
江戸尾立ち型は尾が高く立つ姿勢が名前の由来だが、顔面では眉と頬に刻まれる豆絞り状の渦巻き模様が目立つ。毛並みの立体感を強調し、疫病を絡め取る呪術的意味合いもあるとされる。細い目は京風、丸刈りは古式、横一文字の口は大和風に多い。江戸期の町石工は競って渦巻きを深く刻み、遠目にも装飾性が伝わるデザインを生んだ。眉の彫り方で産地や年代が推測できるため、東京都内の神社を巡ると同型でも微妙な地域差が観察できる。
Q6 : 屋外の石造狛犬に多用される「尾が渦を巻いて背中にかかる形」は、専門的に何と呼ばれる?
尾を大きく巻き上げて背や尻に乗せる形は「巻き尾」と呼ばれる。渦を巻く造形は動勢を強調し、魔を巻き込み退散させる象徴とも解される。平安期の木造は垂れ尾が多いが、屋外の石造では尾が折れにくくする実用上の理由から巻き尾が主流になった。立尾は真上に伸びる形式、髭尾は尾先が長く流れる形式で、江戸以降の特定地域に見られる。尾の形状を比較すると石工の流派や制作年代が推測でき、鑑賞の重要なポイントとなる。
Q7 : 狛犬の配置には例外もありますが、伊勢神宮外宮北御門前などに見られる左右逆配置は何と呼ばれる?
通常は参拝者から見て右が阿形、左が吽形だが、伊勢神宮外宮北御門前や下鴨神社河合社では左右が逆転する。この配列は「逆阿吽配置」と呼ばれ、宮中調度の古式や陰陽道の思想が影響したとする説がある。江戸後期には石工が独自性を示す目的で逆配置を採用する例も増えた。逆阿吽でも阿吽の対概念は維持され、左右を入れ替えることで特定の祭神の性格や方位信仰を強調する場合もある。鑑賞時に左右を確認すると神社固有の信仰背景が理解しやすい。
Q8 : 神社の狛犬には多様な石材が用いられますが、江戸時代中期以降、関東で最も一般的に使われた石材はどれ?
十八世紀以降、江戸近郊では加工しやすく耐候性もある安山岩系の「江戸砂岩」が狛犬の主要石材として普及した。浅草や神田の町神社に残る狛犬の多くが江戸砂岩製で、風化すると灰褐色になるのが特徴。花崗岩は西日本で主流、大谷石は栃木周辺に限定され、備前石は岡山地方の石灯籠に多い。石材の選択は輸送コストや石工技術と直結し、素材を見れば経済圏や流通網が読み取れる。素材観察は狛犬鑑賞に欠かせない要素である。
Q9 : 一般的な神社で参道正面から狛犬を見たとき、口を開いた「阿形」が置かれているのはどちら側か?
狛犬は一対で宇宙の始まりと終わりを示す阿吽を表し、口を開く阿形は「阿」の音を担う。参拝者が正面から見ると右に置かれるのが全国的な標準で、左には口を閉じた吽形が座る。右側の阿形は外へ向かう息、威嚇、発生の力を示し、左側の吽形は吸う息、静穏、終息を示す。例外として古社や寺院で逆配置が見られることもあるが、両像で結界を成す意図は共通している。阿吽の配置を覚えると、鑑賞の際に左右の違いをより深く味わえる。
Q10 : 二匹一対の狛犬は五十音の最初と最後を象徴する音から「阿吽」と呼ばれます。口を閉じた側の正式名称は次のうちどれ?
「阿吽」はサンスクリット語のaとhūṃに由来し、はじまりと終わり、息の出入りを指す。狛犬では口を開いた像が阿形、閉じた像が吽形と呼ばれ、寺社の楼門や仁王像などにも応用される。吽形は閉口ゆえに静けさや内向きの守護を担い、阿形は外へ威圧する役割を担う。二体で魔を寄せ付けずに結界を完成させる考え方が平安期以降に定着し、現在も社寺建築の基本意匠として脈々と受け継がれている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は狛犬鑑賞クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は狛犬鑑賞クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。