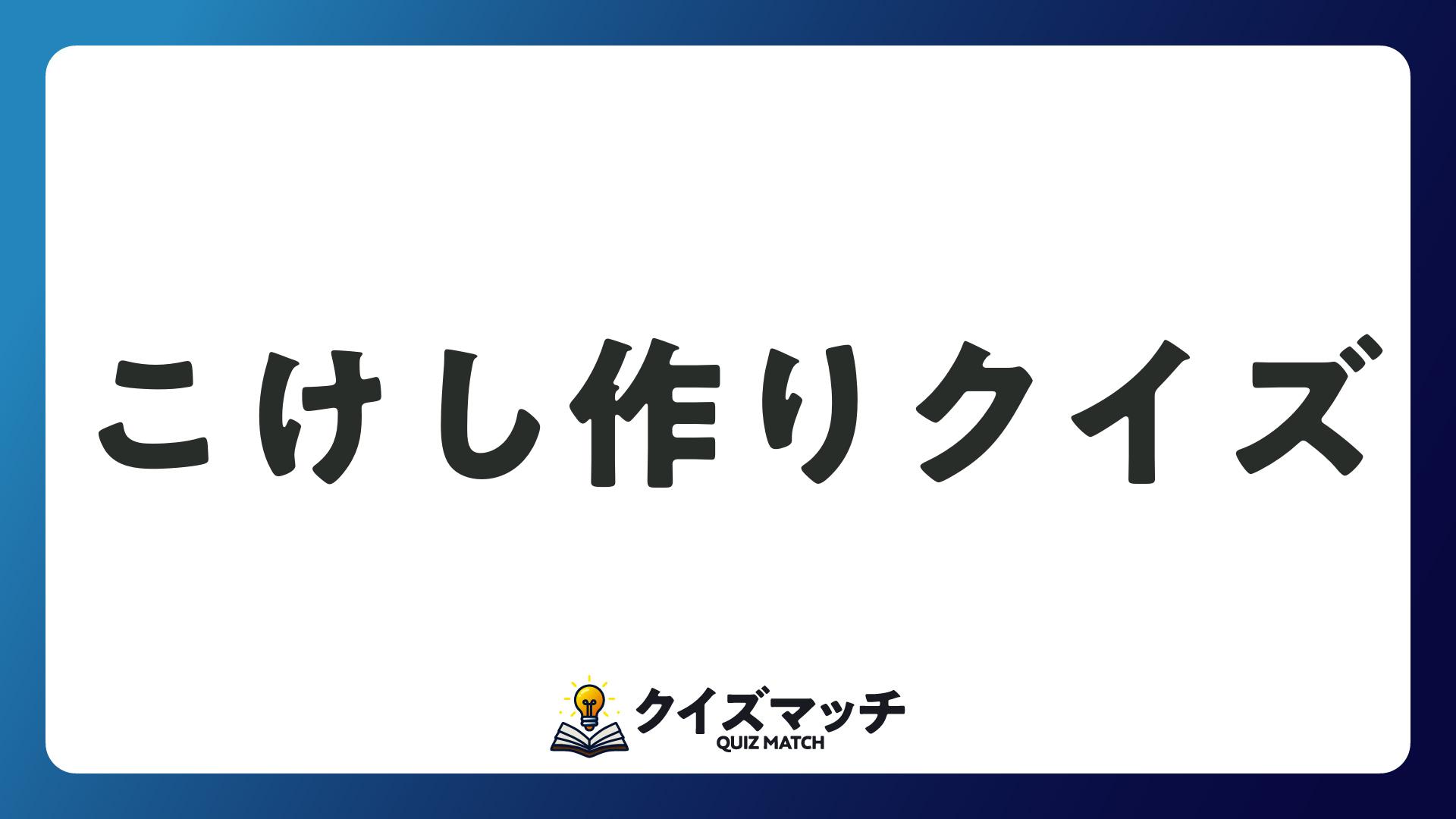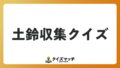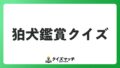東北地方の温泉街を中心に発展してきた伝統こけし。その歴史と製作工程、細やかな技術が注目を集めています。こけしを作る上で欠かせない材料、工程、道具についての知識を深めるべく、10問のクイズをご用意しました。木材の選定、色付けの秘訣、装飾の技法など、こけし作りの奥深さに迫っていきます。伝統と革新の両立を追求する現代の職人たちの技を、クイズを通して探ってみましょう。
Q1 : こけしの目や口など細線を描く際に主に使われる筆で、狸毛やイタチ毛を細くまとめた書画用のものを何というか?
面相筆は日本画の微細な顔料線描に使われる筆で、毛先が極めて鋭く弾力があり、こけしの目・眉・髪線など一発勝負の細線を滑らかに引くのに適している。刷毛は広い面を塗る道具で細部は引きづらく、スプレーガンやエアブラシは霧状塗装で線が滲むため伝統的工程には用いない。面相筆を使う際は木地を軽く湿らせて毛先が滑りやすくし、筆圧を変えて表情の強弱を付けるなど高い技術が求められる。人の息づかいが伝わる表情はこけしの価値を左右するため、この道具選びは極めて重要である。古作では墨汁と紅花顔料を面相筆で併用し、経年で墨が沈んで柔らかい雰囲気になるのも魅力とされる。
Q2 : 胴や頭にロクロ上で描かれる同心円状の細い赤や黒の線を総称して何と呼ぶか?
ろくろ線は回転する木地に筆や染料を当てて円状の帯を描く伝統的な装飾法で、鳴子系や弥治郎系など多くの系統で見られる。回転を利用するため線幅が揃い、単調にならないよう太細を交互にしたり、途中で筆を跳ね上げて点描を入れるなど職人の個性が現れる。単に装飾というだけでなく、視覚的に胴のくびれを強調し木目の荒れを隠す実用面もある。この線の美しさは回転速度と筆圧のバランスで決まり、修業初期から最も時間を費やす基本技術とされる。とばり模様や七宝文は別工芸の技法、錦絵は板絵の呼称でこけし特有ではない。
Q3 : 伝統こけしの十一系統が主に分布する六県以外の府県はどれか?
伝統こけしは東北地方の温泉地を中心に青森・秋田・岩手・宮城・山形・福島の六県で発展し、現在もその範囲内で十一系統に分類されている。新潟県は隣接して木地玩具の産地があるものの、系統としては含まれず、近年は土産物用の創作こけしが少量作られる程度で伝統継承の体系は無い。したがってこの問いでは新潟県が正解となる。他の三県はいずれも古くから工人が多く、系統名では津軽系(青森)、鳴子系(宮城)、肘折系(山形)などが有名である。地域と温泉文化が密接に関わる点もこけしの歴史的特色である。
Q4 : 江戸後期以来、胴の花模様や髪飾りの赤色に用いられた天然顔料として最も一般的なものはどれか?
山形県最上地域などで産出した紅花は染色用の高価な顔料として広く流通し、こけし職人も少量を練って赤絵具として使った。紅花の色素はサフラワーレッドで透明感のある黄味がかった赤が特徴。木地に滲み込みやすく、経年でやや褪色するが柔らかい風合いが残るため古作の鑑賞ポイントともなる。弁柄は鉄錆系で色調が暗く、辰砂は鉱物顔料で高価すぎ、合成アクリルは戦後に普及したため伝統的とは言えない。現在でも伝統工人は紅花顔料を自製する場合があり、その際はアルカリ抽出と酸性沈殿を繰り返して濃度を調整する。
Q5 : 電力が普及する以前から使われ、足で踏板を蹴って回転を与えるこけし用旋盤の名称はどれか?
蹴りろくろは床に据えた軸と滑車を芯棒でつなぎ、職人が片足でペダルを上下させて回転させる伝統的な旋盤である。回転数は踏み方により自由に変えられ、木肌を見ながら削り速度を即座に調整できるため、細かなくびれが多いこけし作りに向く。電動ろくろは効率的だが微妙な速度制御が難しく、スピンドルろくろやCNCろくろは主に工業製品向け。蹴りろくろのリズムは熟練を要し、音と手元の振動で材の状態を判断する伝統技術の象徴とされる。また座業のため上半身が安定し、長時間の作業でも刃先がぶれにくい利点がある。
Q6 : 頭部と胴部を別々に挽いた後、互いに差し込んで固定する際に用いられる日本古来の木工技法はどれか?
こけしでは胴の上端に雇いほぞを立て、頭側に対応するほぞ穴を掘り、接合用の膠や米糊を薄く塗って差し込むほぞ継ぎが用いられる。木目方向を合わせることで水分変化による割れを抑え、また回転軸が一致するため見た目も美しく仕上がる。矧ぎ合わせは板物の幅接ぎ、釘打ちやビス止めは金属を介するため木が割れやすく伝統こけしには用いない。ほぞ継ぎは強度と美観を兼ね備え、後世の修理で頭部を外して補修できる利点もある。接着硬化後に再度ロクロにかけて段差を消し、継ぎ目を感じさせないのも職人の腕の見せ所である。
Q7 : 伝統的に仕上げ段階で布に取り、摩擦熱で表面に光沢と防水性を付与する天然材料はどれか?
木蝋磨きはミツバチの巣から精製した蝋を柔らかい布に含ませ、ロクロで回転させながら木地に押し当てて熱で溶かし込む方法で、手触りが滑らかで自然な艶が得られる。化学塗膜がないため木の呼吸を阻害せず、紅花顔料の発色も活かす点が評価される。ウレタンニスやラッカーは硬い皮膜を形成し光沢は強いが、伝統的風合いが失われることと修理が難しい点が敬遠される。柿渋は防虫効果はあるが色味が濃く、こけし本来の白木らしさを損なうため一般的ではない。木蝋は温度で硬度が変わるため、季節ごとの配合を工夫する職人もいる。
Q8 : 次のうち、十一系統に数えられる伝統こけしの系統名はどれか?
土湯系こけしは福島市の土湯温泉を中心に発展した系統で、やや頭部が大きく左右に広がる前髪と菊花模様の胴が特徴とされる。十一系統にはほかに弥治郎系や蔵王高湯系などが含まれるが、白石・会津・仙台は歴史的に木地玩具を産したものの、現在は系統名としては正式に認定されていない。土湯系は江戸末期の工人佐久間吉郎右衛門の流れを汲み、戦後も多くの名工が輩出されたことからコレクター人気が高い。胴模様に重ね菊やねじり菊が描かれる点も鑑賞上のポイントである。
Q9 : こけしの材料として最も一般的に使われ、白く緻密でロクロ加工後の絵付け発色が良いことから職人に好まれる樹種はどれか?
ミズキは東北地方に多く自生し、木質が均質で比重も適度なため、ロクロ加工で削っても刃物あとが出にくく絵具の乗りが良い。乾燥時の割れや狂いも比較的少なく、細い胴や首の部分を削り出すこけし作りに向いている。さらに樹皮をはいだ時点でも白太部分が広く木取りがしやすい点も利点で、鳴子や遠刈田など主要系統で最も使用率が高い。スギは軽くて柔らかいが木目が粗く、ケヤキは硬すぎ、ヒノキは油分が多く発色が鈍るなど、いずれもこけしの絵付けや仕上げには課題が残る。こうした理由から伝統工人の多くがミズキを第一選択としてきた。
Q10 : 荒挽き後に数カ月から一年程度行う「寝かせ」と呼ばれる工程の主目的として正しいものはどれか?
荒挽きで大まかな形を取った直後の木材は内部に多量の水分を含み、この状態で仕上げ加工や絵付けを行うと乾燥過程で収縮し亀裂やゆがみが生じやすい。そこで通気の良い蔵で半年から一年ほど寝かせ、含水率を15%前後まで下げることで寸法が落ち着く。結果として仕上げ削りで刃物が暴れず、塗料の吸い込みも均一になり美しいこけしになる。特に胴体と頭を別材で作る場合、双方が同じ含水率でないと後に緩みや割れが起こるため、この工程は欠かせない。艶出しや燻煙処理は補助的に行う職人もいるが主目的ではない。
まとめ
いかがでしたか? 今回はこけし作りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はこけし作りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。