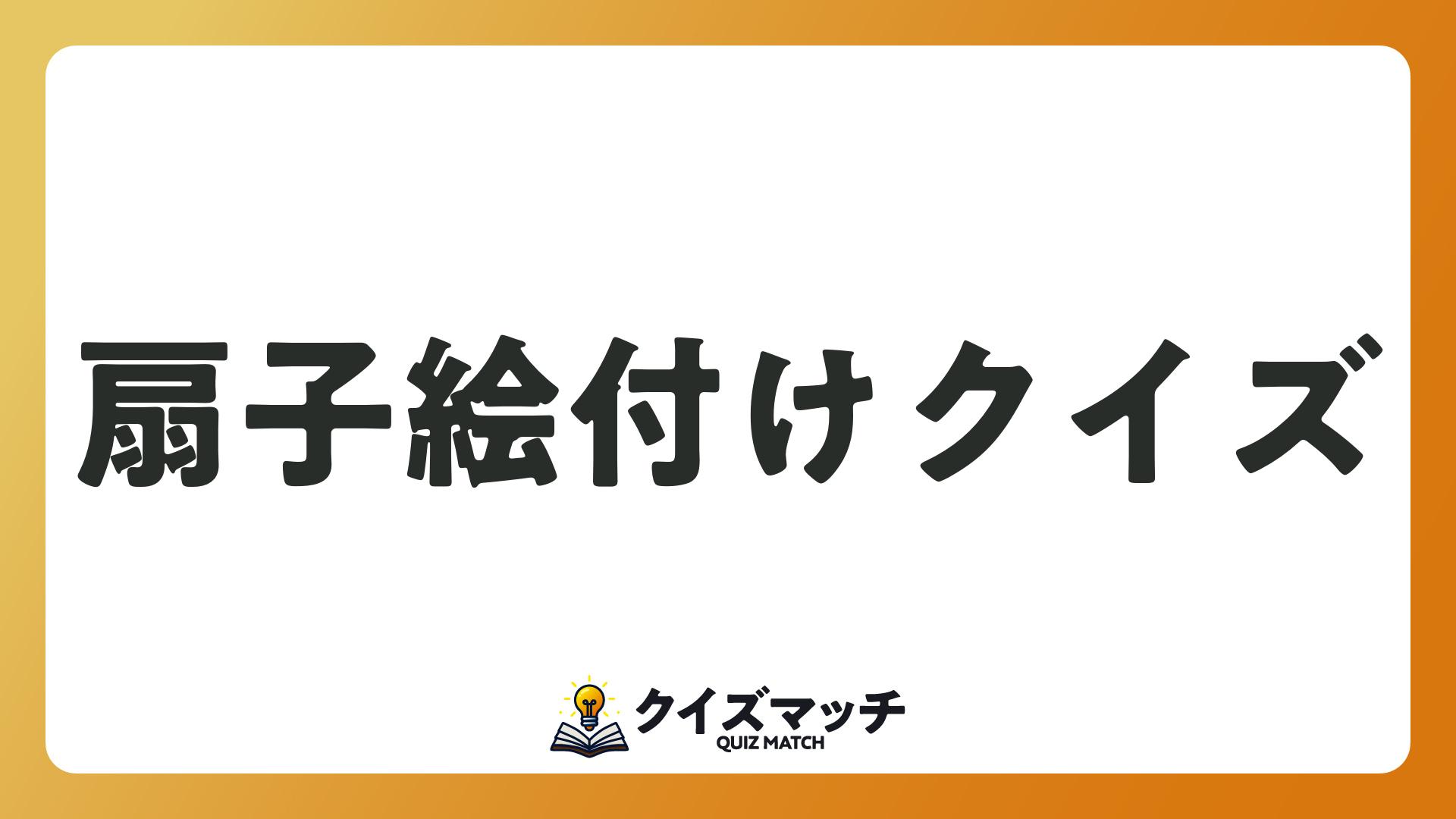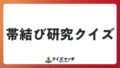扇子絵付けは、日本の伝統的工芸品の中でも特に高い技術を要する分野です。美しい絵付けのために丁寧に選ばれた和紙や岩絵具、そして熟練の職人技が集結します。本記事では、この扇子絵付けについて知識を深めていただけるよう、10問のクイズをご用意しました。扇子の素材や技法、歴史的な背景など、さまざまな側面から日本の繊細な美意識を感じ取っていただければ幸いです。
Q1 : 絹張りの扇面に直接絵具を置くと滲みが出やすいため、最初に施される滲み止め処理を何と呼ぶでしょう。
ドーサ引きは膠液に明礬を溶いた溶液を絹や和紙の表面に塗布し、タンパク質と金属イオンの結合で薄い皮膜を形成して毛細管現象を抑える技法である。これにより岩絵具や墨が布地内部へ浸透せず、発色が安定し細部描写も可能になる。柿渋は防水・防虫目的で色が付き、カシュー下地は漆器用、シーラーは洋画材であるため扇子絵付けには一般に用いられない。
Q2 : 江戸時代から続く京都の夏祭りで、山鉾の曳き手や見物客が自作や奉納された扇子を手に涼を取る光景が定番となっているものはどれでしょう。
祇園祭は八坂神社の祭礼として平安時代に起源を持ち、特に7月17日の山鉾巡行では豪華な懸装品とともに扇子が欠かせない季節の小道具となる。京友禅や金箔押しを施した奉納扇子が山鉾から授与されることも多く、観客はそれを仰ぎながら巡行を見守る。扇面には祭礼にちなんだ草花や家紋が描かれ、絵付け技術の粋が凝縮される。ねぶた祭や神田祭でも扇子は使われるが京都ほど意匠文化が発達していない。雪まつりは冬季で用途が異なる。
Q3 : 扇子の骨を束ねる要の部分に差し込まれ、全ての骨を回転させて開閉を可能にする金属ピンは何と呼ばれるでしょう。
要は扇子の生命線とも呼ばれる中心軸で、真鍮や鉄を小さな丸棒状に加工し、各骨に開けた穴へ貫通させてカシメて固定する。これにより骨が一点で回転し、扇の開閉が滑らかになる。要の頭には飾り鋲や紐を通す穴を設ける場合もあり、絵付けを施した地紙を支える骨格として重要。骨先は骨の反対端、要の緒は下げ紐、要串は竹串状の仮止め具であり金属ピンそのものを指す語としては誤り。
Q4 : 岩絵具として使われる瑠璃、群青、緑青などの顔料は、主にどのような原料を粉砕して作られるでしょう。
岩絵具は天然鉱石を粉砕・水簸し、粒度ごとに分級した顔料である。瑠璃はラピスラズリ、群青は藍銅鉱や青金石、緑青は孔雀石を素材とし、不純物を除き比重沈降させて粒度を整えることで発色と粒立ちを調整する。この粒子が光を乱反射し、扇子の小さな面積でも深みある色を生む。植物や昆虫由来の色素は染料で水溶性が高く、紙面では定着が弱い。化学合成顔料は近代以降に普及し伝統的岩絵具とは区別される。
Q5 : 扇子絵付けの仕上げで行う「シワ伸ばし」と呼ばれる工程は、どのような工具を用いて裏から軽く叩き、塗装による紙の縮みを平滑にする作業でしょうか。
打ち刷毛は短く硬めに揃えた豚毛などを束ねた刷毛で、紙の裏面を均一に叩くことで繊維をほぐし、絵具乾燥時に生じた微細な収縮シワを取る道具である。熱を使わないため顔料や金箔を傷めず、骨組にも余分な負荷を与えない。叩くリズムと力加減で紙がほどよく広がり、最終的に扇を開閉した際の波打ちを防止できる。焼きごてやアイロンは熱で絵具を変質させる恐れがあり、毛筆の軸は面が狭く効率が悪い。
Q6 : 高級京扇子の絵付け用地紙として古くから用いられ、光沢と強靭さを併せ持つことで知られる和紙はどれでしょう。
雁皮紙はジンチョウゲ科の低木である雁皮の靭皮繊維を漉いた和紙で、繊維が極めて細く平滑なため発色が鮮やかで細線も滲みにくい。強度が高く折り目に割れが生じにくいので扇子の頻繁な開閉に耐え、しかも表面にほのかな光沢が生じるため金泥や岩絵具が冴える。楮紙も一般的に使われるが繊維が太めで凹凸が出やすく、写実性や細密描写を重視する場合は雁皮紙が上位とされる。洋綿紙やライスペーパーは吸湿性が高過ぎるうえ強度が不足し、長期使用には向かない点で劣る。
Q7 : 扇子の骨と地紙を貼り合わせる際、古来日本画で使われる膠を溶いて作る接着剤が用いられます。この伝統的な接着剤として正しいものはどれでしょう。
膠は牛や鹿の皮・骨を煮出して得たゼラチンを乾燥させ、使用時に温水で溶かした天然接着剤である。乾燥すると堅牢だが加熱水で再溶解できる可逆性があり、修理や貼り直しが必要になる扇子工芸には最適。澱粉糊を加えて粘度を調節すれば骨への食い付きが増し、乾燥後も紙の可動性を適度に残す。化学系接着剤は固着力が強すぎて紙が割れやすく、しかも紫外線で黄変する恐れがあるため伝統的な作り手は敬遠する。
Q8 : 扇面に金箔や金粉を散らして煌びやかな模様を作る技法として、扇子絵付けで最も一般的に用いられるものはどれでしょう。
砂子は金や銀の薄板を細かく挽いて作った粉を「砂子筒」や小さな袋からまき散らし、接着層(膠や漆)の上に付着させる装飾技法である。紙や絹の扇面に施す場合、接着剤が薄いため重量負担が少なく、開閉の動きでも剥がれにくい長所がある。蒔絵は漆器に限定されることが多く紙面では難しい。箔押しは全面を覆う場合に用いるが部分的な散らし模様には砂子の方が自由度が高い。友禅は染色技法であり直接金粉を撒く工程は含まない。
Q9 : 琳派の代表的画家で、金地に扇面を散らした屏風などを多く制作し、扇子絵付けの意匠にも大きな影響を与えた人物は誰でしょう。
酒井抱一は幕末期の大名出身画家で、光琳百回忌を機に琳派の継承を志し、金地に扇面を貼り込んだ「扇面散屏風」や「夏秋草図屏風」を制作した。抱一の作品は扇面そのものを画面構成の要素として扱い、花鳥や季節の意匠を自在に組み合わせた点で後世の扇子絵付けに大きな影響を与えた。光琳や宗達も琳派の巨匠だが扇面を主題化した例は抱一ほど多くない。若冲は個性的な写生画で知られるが扇面画の遺作は限られる。
Q10 : 扇面に墨や顔料を引き、湿らせた刷毛で境目をぼかして美しいグラデーションを作る日本画の基本技法はどれでしょう。
ぼかしは濃い絵具を置いた直後に水分を含ませた刷毛で境界をなで、色を中間色へと滑らかに変化させる技法である。扇子は紙が折り畳まれるため硬い色面があると折条で割れが目立ちやすいが、ぼかしを使えば境界が柔らかく紙の動きに追随しやすい。たらし込みは濡れた面に別色を落とし滲ませる方法でぼかしとは工程が異なる。すり込みは絵具を擦り付けて色を入れる技法、飛白は刷毛目を残す描法であり、求めるグラデーション目的とは違う。
まとめ
いかがでしたか? 今回は扇子絵付けクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は扇子絵付けクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。