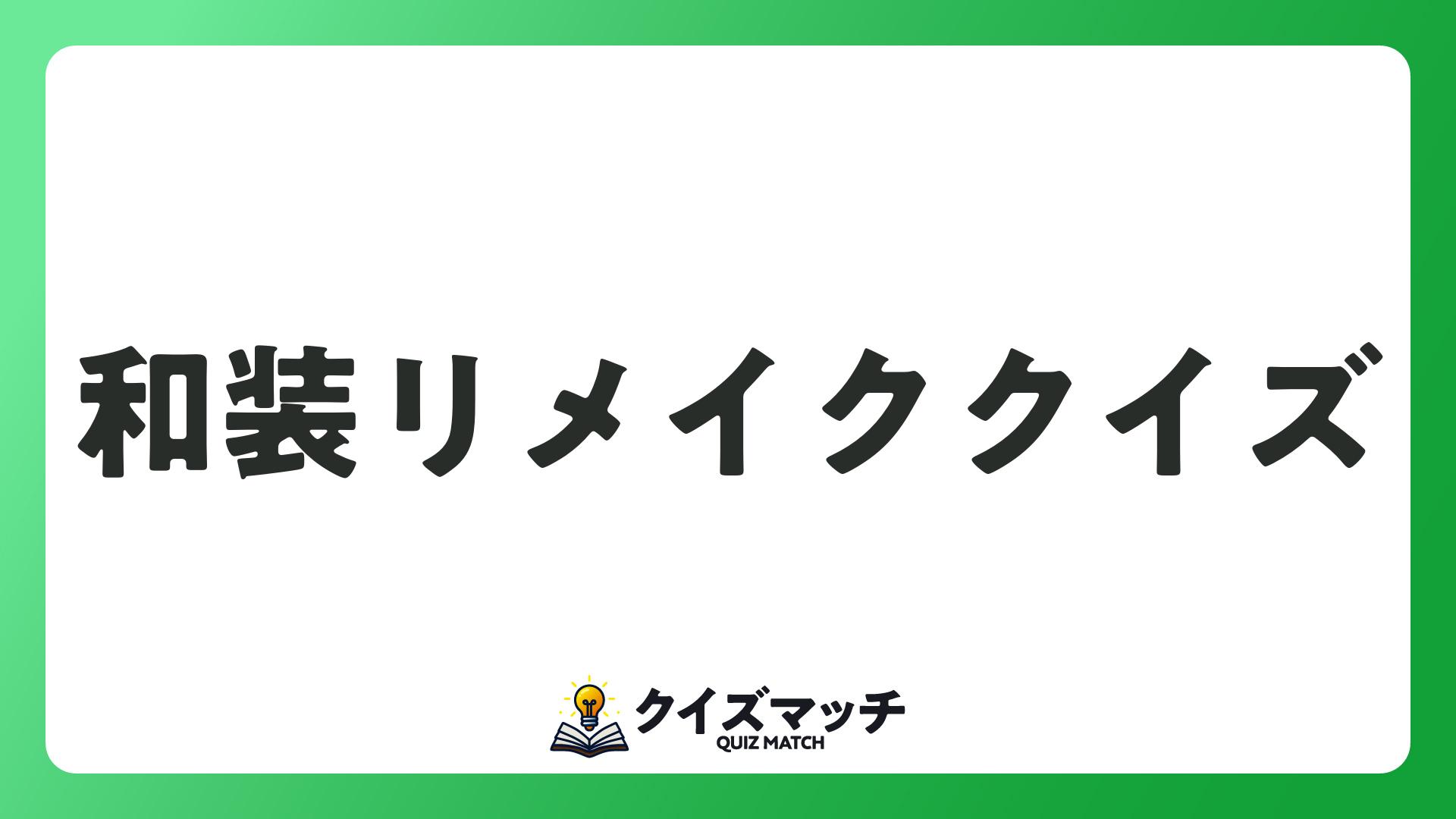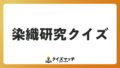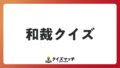和装リメイック作りに挑戦したい方必見!
着物や帯などの和装アイテムは、素材や柄、シルエットが洋服とは大きく異なるため、一見リメイクするのは難しそうに見えます。しかし、適切な下準備と手順さえ押さえれば、手作業でも素敵な洋服や小物に生まれ変わらせることができるのをご存知ですか?
本記事では、和装リメイクの基本から応用まで、10問のクイズを通してわかりやすく解説します。着物や帯の生地を活かした洋装化のコツや、小物づくりのテクニックなど、初心者から上級者まで幅広い層に役立つ情報をお届けします。
和装ファンの方は必見、これから始めたい方も必読の内容となっています。
Q1 : 振袖の絵羽模様を活かし、裏地を最小限にして仕立てられる洋装として人気が高いのはどれ?
振袖の大きな絵羽模様を洋服化する際には、ドレスよりもロングガウンコートが最適とされる。前を開けて羽織るデザインなので柄合わせの制約が少なく、裏打ちを省いても表地の華やかさがそのまま見える。袖幅も和装のまま活かせるため、解き洗い後に一直線に縫い合わせればシルエットが決まり、体形変化にも対応しやすい。ボレロやワンピースは柄を切り刻む必要があり、パンツは布幅が不足する。
Q2 : 帯の端布を使って初心者でも作りやすく、厚みを生かせる小物はどれ?
帯地は経糸に金糸や絹糸を高密度で打ち込んでおり、厚手で型崩れしにくいので、小さながま口ポーチに向いている。口金に合わせて裁断し、芯を入れなくても自立することが多く、初心者でも成功率が高い。バンダナやニット帽のような柔軟性が求められるアイテムには適さず、レースリボンは素材の性質が異なるため帯地では重くなりすぎる。子ども向けの工作教材としても人気が高い。
Q3 : ウール着物をマフラーにリメイクする際、布端のほつれ止めに最も多用される手縫いのかがり方はどれ?
ウール着物を解いてマフラーに仕立てる場合、布端を千鳥がけでかがる方法が一般的だ。千鳥がけはジグザグに針を進めるため、厚手のウールでも糸が食い込みにくく伸縮を妨げず、洗濯時のほつれを防ぐ。返し縫いは直線縫いなので端が波打ちやすく、たてまつりは折り返し布が必要、しつけ縫いは仮止めに過ぎない。見た目にも装飾性があり、手縫いでも短時間で仕上げられる点が評価されている。
Q4 : 羽織を前開きベストに仕立てる際、元の意匠を活かして衿飾り兼留め具として最もよく残される部分はどれ?
羽織をベストにリメイクする際は、もともとの羽織紐と衿を一体で残すと、簡単に前開きのデザインポイントになる。羽織紐の結びをそのままブローチ風に使えば留め具を追加する必要がなく、衿の折返しが顔回りを華やかに演出する。裄下や褄下は解いて脇や裾のパーツに回されるのが一般的で、袖口だけを装飾として残すと肩線が崩れやすい。リメイク初心者にも工程が少なく人気が高い手法である。
Q5 : 絹の着物を家庭で染め直す場合、安全に発色良く染まる方法として推奨されるのはどれ?
シルクの古着物を家庭で染め直す場合、酸性染料を使った常温または低温染めが推奨される。酸性染料はタンパク質繊維である絹と親和性が高く、色移りが少なく発色も鮮やかに仕上がる。インディゴやコーヒー染めはセルロース繊維向けで定着力が弱く、タイダイは高温とゴム締めによるムラが生じやすい。専門家も家庭染めでは酸性染料を勧めている。
Q6 : 羽裏の大胆な絵柄を生かして壁掛けにする際、布を切らずに全体を見せやすい展示方法はどれ?
羽裏は多彩な図案が一枚絵のように描かれているため、解いて平らにし、上辺に棒通し用の袋縫いを施してタペストリー仕立てにすると全柄を損なわずに展示できる。パネルストレッチは木枠に固定する際に端が折れ、ライトボックスは透過光で劣化が進む恐れがある。シュリンクフレームは縮み加工が前提の技法で絹地には不向き。棒通しなら折り跡も最小限で取り外しも簡単、保存性に優れる。
Q7 : ポリエステル着物を洋服にリメイク後、縫い代をアイロンで割る際の推奨温度帯はどれ?
ポリエステルの着物を洋服に作り替えたあと縫い代をアイロンで割る際は、化繊対応の140〜160℃設定にし、必ず当て布をするのが安全とされる。低温では折り癖がつきにくく、高温では繊維が溶融しテカリや収縮が生じる。中温域なら形状記憶性が活き、蒸気を併用するとさらに仕上がりが良い。ポリエステルは綿より耐熱性が低いため、180℃以上の高温は専門業者でも避けるのが通例である。
Q8 : 古い着物をいったん縫い目をほどいて反物に戻し、水洗いして寸法を整える和装リメイクの準備工程は何と呼ばれる?
着物をリメイクするときは、まず元の縫い目を完全にほどいて反物幅のパネル状に戻し、長年の汚れや糊を落とすため水で丁寧に洗い、陰干しして伸子で幅出しする。こうした一連の作業をまとめて解き洗いと呼び、この工程を省くと布目がねじれたりカビが再発したりするため、プロの仕立て屋でも必ず行う基本手順とされている。
Q9 : 帯をテーブルランナーにリメイクする場合、幅と長さ、硬さの点で最も扱いやすい帯の種類はどれ?
名古屋帯は幅約30センチ、長さ3メートル強とテーブルランナーにほぼ適切な長さで、芯が入っていて張りがあり、絵柄が太鼓部分に集中しているため真ん中に柄を見せやすい。丸帯や袋帯は厚みがありすぎ縫いにくく、半幅帯や兵児帯は幅が足りず芯がないので平坦に広がりやすい。したがってインテリア用途には名古屋帯が最も扱いやすいとされる。
Q10 : 解いた着物をワンピースに仕立てる前に縮みを防ぐ目的で行う下準備として最も適切なのはどれ?
水通しは、木綿や麻だけでなく絹を家庭で洗濯可能なカジュアル服に転用するときにも応用される下準備で、あらかじめ水に浸して布を縮ませ、のり分を落としてから陰干しし、その後アイロンで地のしを行う。これを怠ると完成後のワンピースが洗濯のたびに縮んだり斜行したりするリスクが高まる。地入れや防虫処理は別目的、刺し子は装飾であり縮み防止には直接役立たない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は和装リメイククイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は和装リメイククイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。