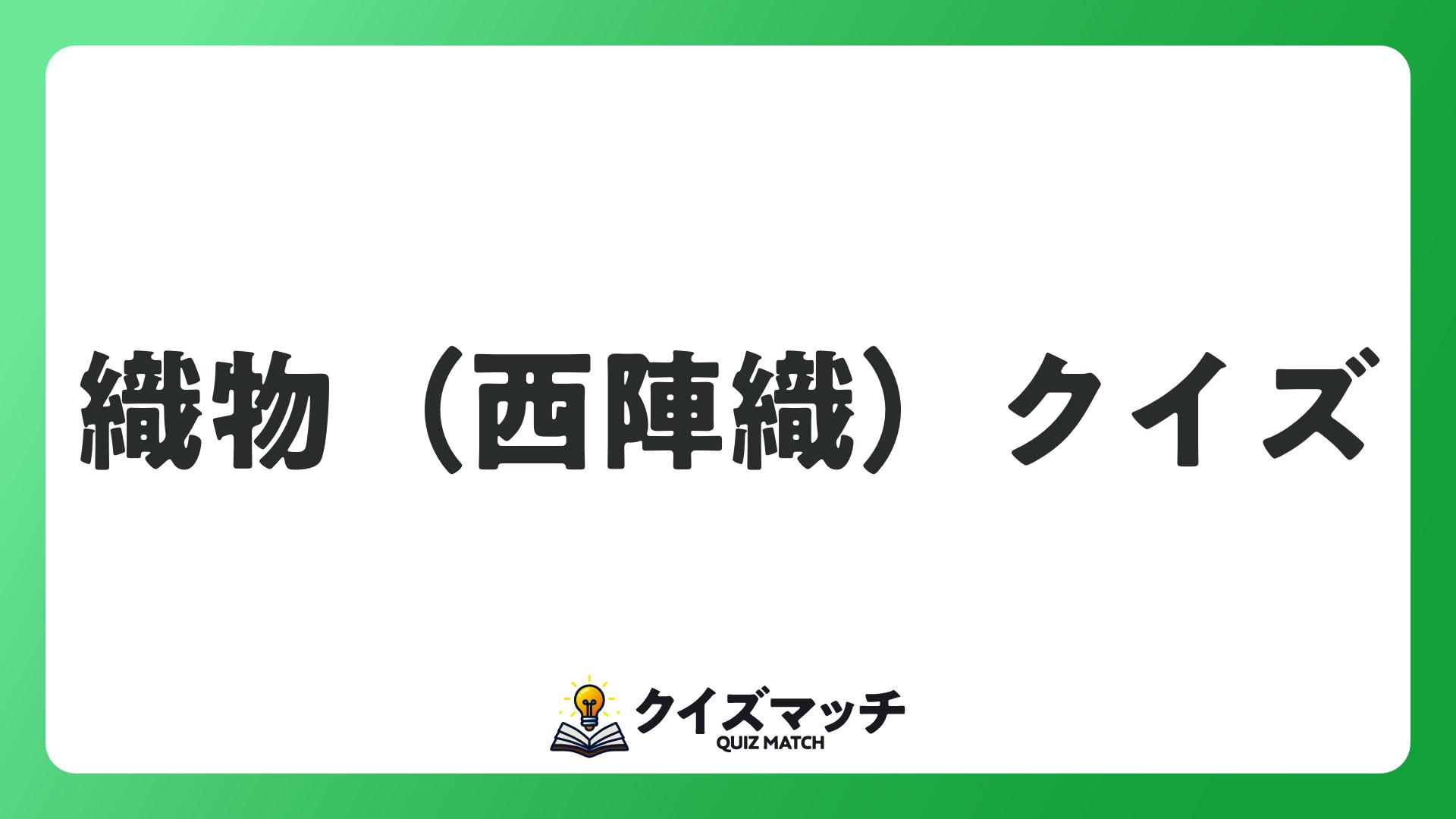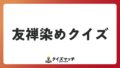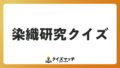西陣織は京都市上京区を中心に発展してきた伝統的な織物で、その豊かな色彩と精緻な意匠は世界的に知られています。複雑な文様を可能にする織機技術の進化や、先染めによる染色の工夫など、西陣の職人たちが培ってきた高度な技術が、この織物の魅力を引き出してきました。本クイズでは、西陣織の歴史や特徴、そして織物文化についての理解を深めていただけるはずです。西陣織の魅力を感じながら、10問のクイズに挑戦してみてください。
Q1 : 西陣織の特色である、糸を染めてから織る方法を何と呼ぶか?
西陣織は糸の段階で染色を行う先染めを原則とし、色が糸の芯まで浸透するため摩耗や汗に強く発色が長持ちする。複雑な経緯配列による経錦・緯錦の鮮やかな文様も先染めだからこそ実現できる。後染めは反物を織り上げてから染める技法で京友禅などが代表、捺染はプリント技法、空引き染めは絣糸の一種であり、西陣の基本は先染めである点が重要である。
Q2 : 西陣織が経済産業大臣の伝統的工芸品に指定された西暦は?
西陣織は1976年(昭和51年)2月26日に伝統的工芸品産業の振興に関する法律に基づく指定を受けた。指定には歴史的継承性、手工業的工程、産地集積などの要件があり、西陣織は600年以上の歴史と分業体制、手作業主体の12工程を満たしていることが評価された。1984年は京友禅、1992年は丹後ちりめん、1965年は法律制定前であり、西陣織の正式な指定年は1976年である。
Q3 : 複数色の緯糸を杼ごとに切り替えて文様を織り出す西陣織の代表的技法は?
緯錦は複数の色緯糸を文様部分だけに通すことで絵画的な柄を表現できる技法で、経糸で図柄を出す経錦と対になる。裏表で配色が反転し、百色以上の緯糸を整理した棚から職匠が杼を選び、一打ちごとに替えることで細密な絵柄を作る。絣織やつづれ織は構造や目的が異なり、緯錦こそ多彩な色彩表現を可能にする西陣独自の技法として知られる。
Q4 : 西陣織の多彩な文様を可能にした、19世紀にフランスから伝来したパンチカード式装置は?
ジャカード装置は1801年にジョゼフ・マリー・ジャカールが考案したもので、穴を開けた厚紙を読み取って経糸の上げ下げを自動制御できる。西陣では明治初期に導入され、高機だけでは不可能だった複雑文様の量産を実現した。現在は電子化が進むが原理は同じで、西陣織の意匠自由度を飛躍的に高める基幹技術となっている。ドビーやレピア、エアジェットは別方式の織機である。
Q5 : 唐草の系譜に属し、西陣織で格調高い帯柄として親しまれる文様は?
立涌は二本一組の曲線が湧き上がる水蒸気を表した有職文様で、平安期から装束に用いられてきた。西陣では経錦や綴織など各種技法で立涌を織り出し、格式ある束帯や帯地に多用される。青海波は波形、名物裂は茶道具裂全般、有職文様は総称であり、唐草の流れをくむ代表的柄として立涌が選ばれる。華麗さと縁起の良さから現代の帯でも人気が高い。
Q6 : 応仁の乱終結後に西陣の名が生まれたが、その終結年は?
応仁の乱は1467年に始まり、11年に及ぶ京の戦乱の末、1477年に終結した。戦火で散った織師たちが西軍の陣跡に戻り再興したことから「西陣」と呼ばれるようになる。1493年は明応の政変、1467年は開戦年、1501年は乱後の年代であり、1477年こそ再興の契機となった年であるため、西陣織の歴史を語る上で重要な節目となる。
Q7 : 西陣織の帯種で最も格式が高く第一礼装に用いられるものは?
袋帯は幅約31センチ、長さ4メートル以上の二重構造で裏まで同じ組織が続くため格調が高く、留袖や振袖など正礼装に合わせられる。西陣では金銀糸や引箔を贅沢に使い豪華な意匠を施した袋帯が人気で、婚礼用としても定番となっている。名古屋帯は準礼装から普段用、半幅帯・兵児帯はカジュアル向けであるため、礼装で最上位に位置づけられるのは袋帯である。
Q8 : 和紙に金箔を貼って細く裁断し糸状にする、西陣で金糸を作る伝統技法は?
引箔は和紙や絹紙に金・銀などの箔を貼り、数ミリ幅に裁断して糸に撚り合わせたりそのまま緯糸として織り込む技法で、西陣織の帯や能装束に欠かせない。薄い箔を紙が支えることで折れにくく、光沢が均一に現れる。箔押しは紙や革への圧着、こがね切は刀剣研磨、砂子は粉を撒く装飾技法であり、金糸づくりの本流は引箔であることを覚えておくと鑑賞が深まる。
Q9 : デジタルデータで経糸の開口を制御する、西陣織の最新織機技術は?
電子ジャカード制御は従来の厚紙カードを用いず、パソコンで作成した図案データを直接織機に送って経糸の上げ下げを行う方式。パンチカードの作製・保管が不要となり、デザイン変更も瞬時に可能なため、西陣では少量多品種のオーダーに対応しやすくなった。手投杼や踏木制御は手作業主体、シャットルレスドビーは経糸開口の仕組みが異なり、電子ジャカードこそ最新主流である。
Q10 : 西陣織が主に生産されている京都市の区はどこか?
京都市上京区の西陣地域は、平安時代から織物の町として発展してきたが、特に応仁の乱後、西軍が陣を張った西陣の地名がそのままブランド名となった。大宮通から堀川通、今出川通から北大路通に挟まれた一帯に織元や染屋、糸屋など関連業者が密集しており、今でも機音が聞こえる。したがって、伏見区や山科区ではなく上京区が主産地であることを覚えておくと、西陣織見学のときに迷わない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は織物(西陣織)クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は織物(西陣織)クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。