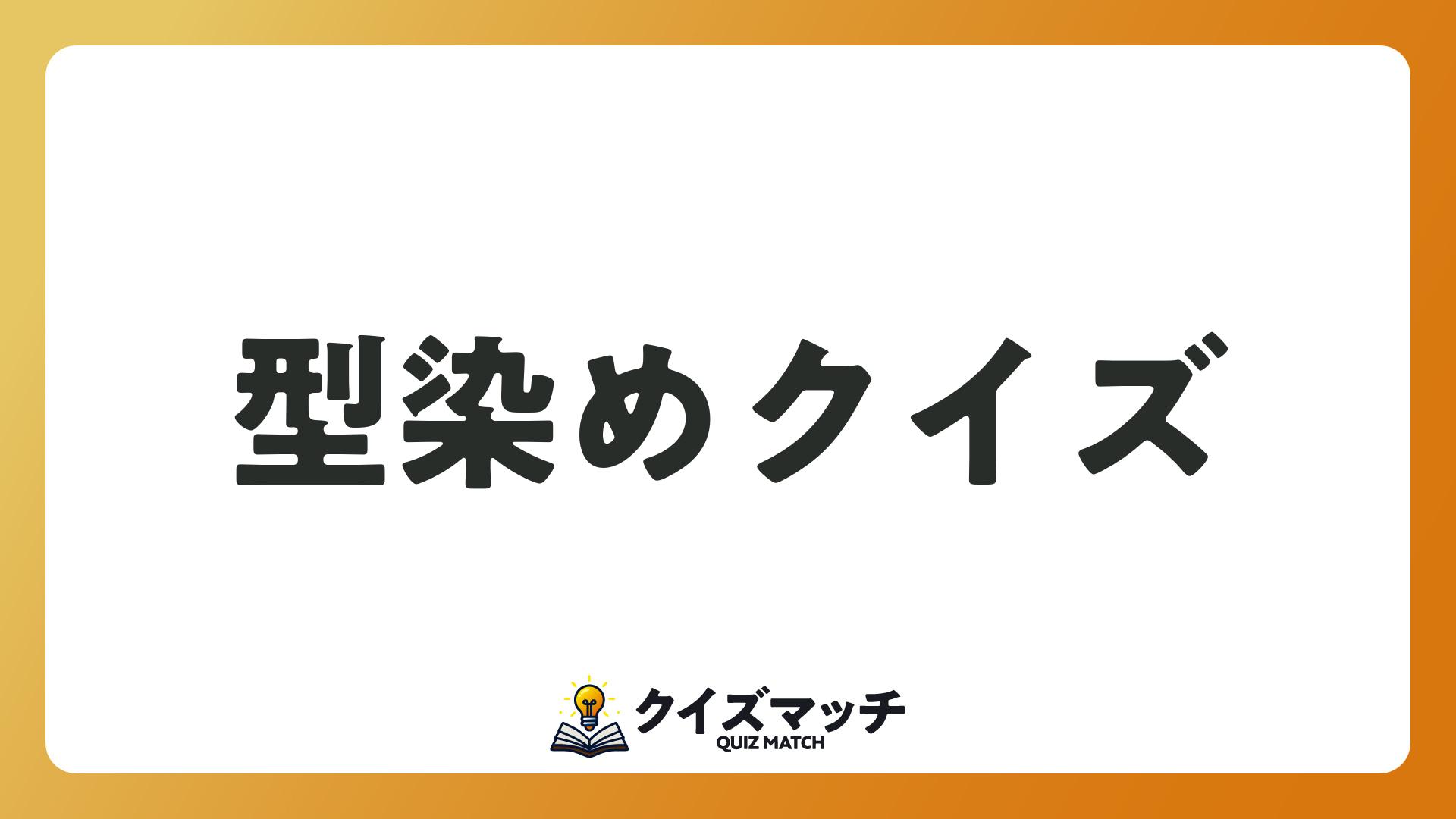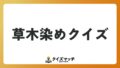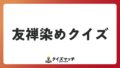型染めは、古代から伝わる日本の伝統的染色技術の一つで、型紙を使って複雑な模様を染め分ける手法です。型染めには、細やかな柄の再現性や染料の堅牢度など、他の染色技法には見られない特長があります。本記事では、型染めの歴史や技術、さらに型染めに関するクイズを10問ご紹介します。型染めの魅力と奥深さを感じていただける内容となっておりますので、是非ご一読ください。
Q1 : 染色が終わった後、布地に残った防染糊を取り除く最も一般的な工程は?
型染めでは染色と蒸しを終えた後、布を流水にさらしながら手で揉み、乾燥していた米糊をふやかして完全に落とす「水元」工程を行う。糊は水に入ると膨潤し繊維から剥離するため、洗いながら軽く叩き揉むことで布の白場が鮮明に現れる。冷風乾燥や紫外線照射は糊を除去する働きがなく、酸化剤浸漬は洗堯が必要なプリント処理で用いられるだけで型染めには一般的でない。水洗い後の湯のしで布目を整え完成となる。
Q2 : 伊勢型紙の素地として柿渋で貼り合わせる紙の主原料は何か?
伊勢型紙は三枚の薄い楮紙を柿渋で貼り合わせ、天日で乾燥させた強靭な紙を用いる。楮繊維は長く絡み合うため耐久性に優れ、刃物で細密に彫刻しても破れにくい。柿渋はタンニンが繊維間を硬化させ防水性を与える。洋紙やプラスチックでは刃通りや染料の吸放出特性が異なり適さない。こうした手漉き和紙の技術が型紙産地鈴鹿の伝統を支えてきた。
Q3 : 藍染以外の型染めで、江戸時代から赤色を得るために最も一般的に用いられてきた植物染料はどれ?
茜はアカネ科の多年草で日本では古くから根を煮出し赤色系統の染料として利用された。型染めで防染糊を置いた布を茜浴に浸すと、糊が防染された部分は白く残り、それ以外が温かみのある紅色に染まる。江戸期の武士の襦袢や庶民の小紋にも茜染は頻繁に登場し、耐光性や洗濯堅牢度も比較的高い。ログウッドは黒紫を、コチニールは虫由来の赤を、マリーゴールドは黄を得るが、茜ほど汎用的ではなかった。
Q4 : 小紋や浴衣の量産により型染めが庶民の間に広く普及し、産地が全国に拡大した最盛期はいつか?
型染めは奈良期に技法が伝わったとされるが、本格的に庶民文化へ浸透したのは江戸中期である。参勤交代で藩主が江戸に赴く際の贈答需要や、奢侈禁止令により豪華な刺繍が制限されたことから、細密な小紋を染め分けられる型染めが重宝された。商都大阪や江戸深川の問屋が伊勢型紙を買い付け、木綿浴衣や手拭が大量に出回った。これにより染屋が各地に生まれ、技術革新が進んで多彩な意匠が開発された。
Q5 : 防染糊を置き、染料を引き染めした後におこなう「蒸し」の主な目的は何か?
蒸気で布を一定時間蒸すと温度と湿度により染料分子が繊維深部へ拡散し、酸化還元や媒染反応が均一に進むため色が冴え、堅牢度が高まる。藍のような浸染型でも藍建て後に蒸すことでムラが整うことがある。布を柔らかくするのは湯のし、型紙は既に外しており蒸しでは扱わない。糊を硬化させる目的で加熱することはなく、むしろ後工程の水洗で糊を除去するため蒸しで糊を柔らかく保つ必要がある。
Q6 : 伊勢型紙の産地として国の伝統的工芸品指定を受け、型紙職人が集中している地域はどこ?
伊勢型紙は古くから伊勢国河芸郡白子(現三重県鈴鹿市白子地区)で作られ、伊勢商人の行商を通じ全国の染屋へ供給された。江戸幕府の御用達として発展し、明治以降も白子の職人は銅箔張りや道具彫など高度な技を継承してきた。京都や金沢にも型友禅の型紙を扱う職人はいるが、伊勢型紙の名称と伝統工芸品指定は鈴鹿市が対象である。久留米は絣が有名で型紙の産地ではない。
Q7 : 型染めと手描友禅との最大の技術的な違いは何か?
どちらも防染糊で柄部分を伏せて染める技法だが、型染めは彫刻した型紙を布に密着させてヘラで糊を刷り込み、同じ柄を反復できる。一方、京友禅などの手描友禅は筒と呼ばれる細い紙管に糊を入れて職人が直接布に線を描き、一点ごとに意匠が異なる。染料自体は共通のものも多く、素材にも決まりはない。したがって、糊を型で置くか手描きかが最も本質的な相違点である。
Q8 : 1956年に「型絵染」で人間国宝(重要無形文化財保持者)に認定された工芸家は誰?
芹沢銈介は沖縄の紅型に影響を受け、型染めに独自の図案と色彩を取り入れた「型絵染」を確立した。1956年に型絵染で国の重要無形文化財保持者となり、いわゆる人間国宝として評価された。富本憲吉は色絵磁器、棟方志功は版画、十五代酒井田柿右衛門は磁器の名工であり、型染めの保持者ではない。芹沢の作品は掛け軸や暖簾、絵本など多岐にわたり、民藝運動の中心的人物として国際的にも知られる。
Q9 : 型染めで糊を型紙の上から布地に押し込む際に用いられる三角形の木製または樹脂製の道具は何と呼ばれる?
型紙を置いた布の上に米糊をのせ、手前から奥へ均一に押しのばす際に使うのが「へら」または「しごきへら」である。先端がわずかに丸く加工された硬い板状の道具で、糊を型の切り口へ確実に押し込みつつ表面を平滑に仕上げることができる。刷毛は引染めで色を塗る道具、竹筒は友禅の糸目置き、ローラーは近代的なプリントで使用される。へらの材質には朴やメラミン樹脂が用いられ、磨耗を防ぐため職人は頻繁に研ぎ直す。
Q10 : 防染糊の主原料としてもっとも伝統的に用いられるものはどれ?
型染めに用いる防染糊は、蒸した糯米粉に米糠を混ぜて発酵させ、石灰を加えて練る「米糊」が基本である。デンプン質が乾燥後に繊維へ密着し染料をはじくため精緻な模様を保てる。石灰は腐敗防止と粘性調整の役割を担い、発酵過程で糊は滑らかになり型の細部まで行き渡る。この配合は室町期の文献にも見られ、現在も職人は同様のレシピを守っている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は型染めクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は型染めクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。