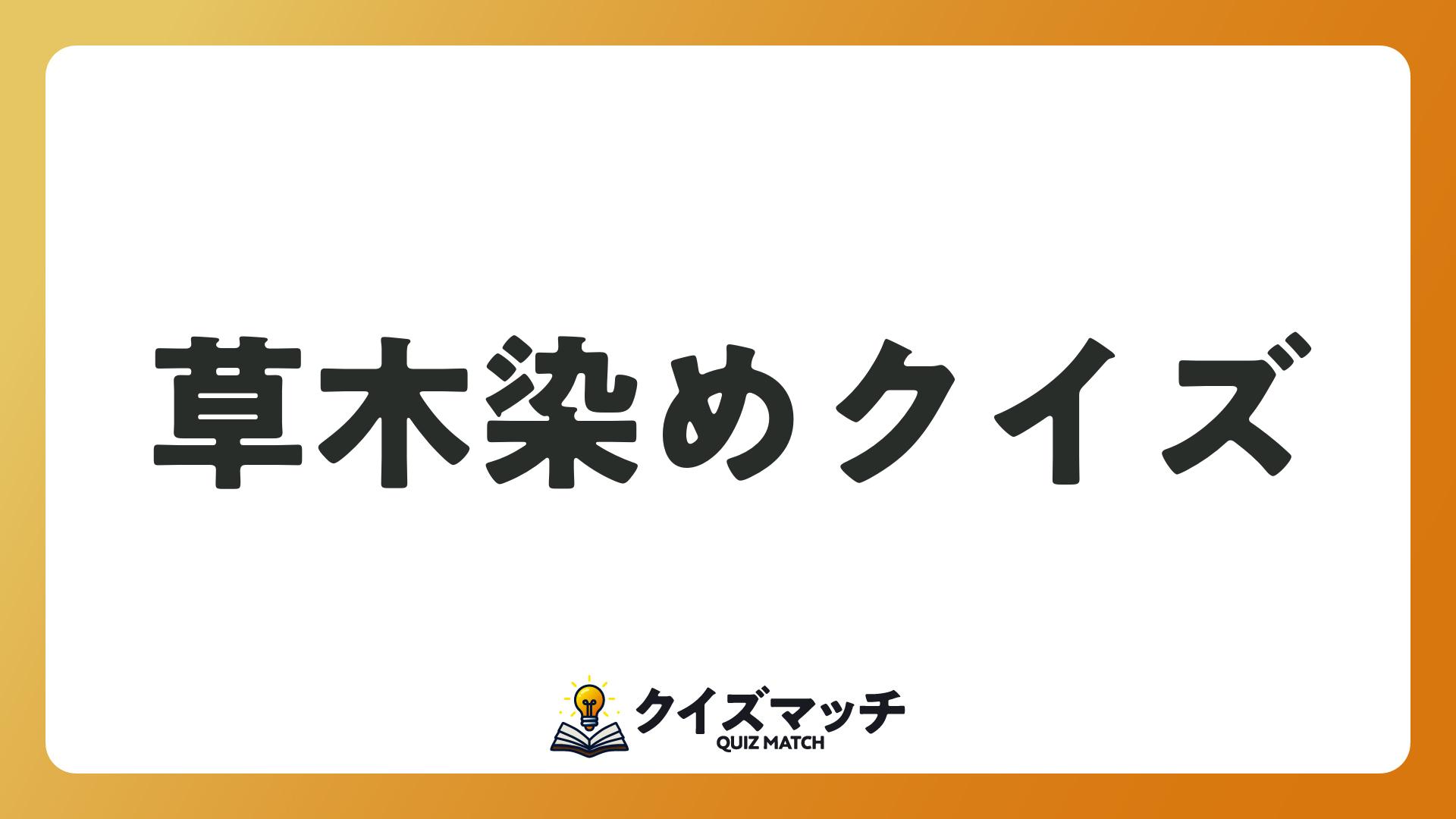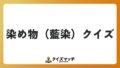草木染めは、自然の植物由来の色素を利用して布や衣料を染める伝統技術です。その奥深い世界を探るクイズを10問ご用意しました。藍染めから五倍子の黒染め、ウコンの防虫性まで、日本の染色史を彩る素材や技法の秘密に迫ります。自然と共生する染色の知識と技を通して、私たちの暮らしに根付く植物の恵みを再発見する機会となれば幸いです。
Q1 : 黒染めの材料として知られる『五倍子』は、どの樹木に寄生したヌカカの仲間が作る虫瘤(虫こぶ)を乾燥したものか?
五倍子はヌルデの若枝にヌルデシロアブラムシが寄生して形成する虫こぶを乾燥したもので、タンニン含有量が非常に高い。水抽出液を布に吸着させた後、鉄媒染を加えると深い黒色が定着するため、平安期以降武具や礼装の黒染めに欠かせない素材となった。ウルシやクヌギの虫こぶにもタンニンはあるが含有量や利用実績は低い。ブナの虫こぶは染料としてはほとんど用いられていない。
Q2 : インディゴを多く含み、日本の藍染で最も一般的に栽培されるタデ科一年草はどれ?
インディゴ色素を得られる植物は数十種あるが、日本の伝統藍染で主力となるのはタデ科のリュウキュウアイ(Persicaria tinctoria)である。江戸時代には阿波藩などで大規模に栽培され、葉を発酵させたすくもが全国へ出荷された。リュウキュウアイは短期間で生育し葉量も多く、インディゴ含有量も安定するため国内気候に最適だった。ホソバタイセイはヨーロッパ原産、ボウシバナはツユクサ科で短期の青汁染め、コマツナギはマメ科で含有量が少なく主流ではない。
Q3 : 鉄くぎを利用して作る伝統的な黒系媒染液『おはぐろ』は、主にどのような材料の組み合わせで作られる?
おはぐろは酢や酒粕などの酢酸性液に古釘や鉄片を浸し、数週間かけて鉄イオンを酢酸鉄として抽出した溶液である。タンニンと結合させることで墨のように深い黒が得られるため、五倍子や栗の渋皮などタンニン源と併用して黒染めを行う。化学的には酢酸第二鉄溶液で繊維中のタンニンを酸化錯体として黒変させる。灰汁と銅線は銅媒染、蜂蜜とアルミでは媒染液を生成できず、酒と石灰はアルカリ調整目的で黒媒染とは異なる。
Q4 : ウコン(ターメリック)の染液で染めた布が古来から僧衣や虫干し袋に選ばれてきた主な理由はどれ?
ウコンに含まれるクルクミンは黄色色素であると同時に昆虫忌避作用を示すことが知られている。ウコン染めの布はシバンムシやコイガなど貯蔵品害虫を遠ざける効果があり、経典袋や僧衣の保護目的に重宝された。酸性媒染と組み合わせることで色あせにも比較的強くなるため、長期保管する裂地にも適用。耐火性や防水性は得られず、紫外線吸収能もわずかなため主理由とはならない。
Q5 : 刈安やコブナグサを黄染めに用いる際、鮮やかな黄を出すために最も一般的に行われる媒染法はどれ?
イネ科の刈安やコブナグサに含まれるフラボノイド色素はアルミニウムイオンと錯体を形成すると安定して鮮やかな黄色に発色する。そのため抽出後にミョウバン溶液でアルミ媒染を行うのが定番である。鉄媒染にすると暗緑色、銅媒染ではくすんだ黄褐色へ変わり、クロム媒染も黄色になるが毒性が高く伝統的にはほとんど使われなかった。安全性と発色性の両面でアルミ媒染が最も広く採用されている。
Q6 : 木灰を水に浸して作るアルカリ性溶液で、草木染めのpH調整や洗浄に用いられる伝統材料は何と呼ばれる?
草木染めでは染料抽出や藍建てなどで弱アルカリ環境が必要になる場面が多く、その際に使われるのが木灰を水に溶出させた灰汁である。灰汁には炭酸カリウムや炭酸ナトリウムが含まれ、天然由来で繊維を傷めにくく、前処理や後洗いにも利用できる。カシやクヌギを燃やした木灰が好まれ、濾過して得た上澄み液を使う。苛性ソーダは強アルカリで危険、苦汁は塩化マグネシウム、山漆は樹脂であり、灰汁とは別物である。
Q7 : 紫根染めに用いられるムラサキ科植物 Lithospermum erythrorhizon の根は、日本で一般に何と呼ばれてきた?
ムラサキ(紫草)の根にはシコニン類が豊富に含まれ、乾燥品は日本で紫根と呼ばれる。奈良・平安期には高貴な位階を象徴する紫衣の染料として重宝され、延喜式など古文書にも記載がある。抽出にはアルコールや油が必要で、アルミ媒染で赤紫、鉄媒染で濃紫と幅広い表情を示す。退色しやすいがその希少性と鮮やかさから門外不出の技法とされた。阿仙薬はアカシア属樹皮、竜胆はリンドウ科の根、黄耆はマメ科の根でいずれも紫染めには使われない。
Q8 : 藍染めで鮮やかな青色を得るため、日本で伝統的に藍葉を発酵させて作る原料は何と呼ばれる?
藍染めは植物に含まれるインディゴ前駆体を微生物発酵により還元型インディゴへ変換し、布に付着させて酸化させることで発色させる。その際、タデアイの葉を乾燥後に適度な水分と温度で数か月かけて発酵させた固形物が必須で、これを日本ではすくもと呼ぶ。すくもには還元菌が豊富に含まれ、木灰汁などのアルカリと合わせて藍建てを行う。味噌や酒粕は食用発酵食品、米ぬかは発酵促進に混ぜる補助材で主原料名ではない。
Q9 : 媒染剤として最も広く使われるミョウバンの主成分は次のうちどれ?
草木染めでは水溶性の色素を繊維へ定着させるため金属イオンを含む媒染剤が必要となる。ミョウバンは古来世界各地で利用される代表的な媒染剤で、化学式はKAl(SO4)2·12H2O、名称は硫酸アルミニウムカリウムである。アルミニウムイオンは繊維と色素の双方と結合しやすく発色も鮮やかで扱いやすい。一方、塩化鉄や硫酸銅は黒や深緑を得るための鉄・銅媒染、酢酸亜鉛は灰色系に用いられるがミョウバンそのものではない。
Q10 : クルミの果皮を煮出して染めた場合、一般的に得られる色調はどれ?
クルミ(オニグルミやペカンなど)の外果皮にはタンニンとユグロン系色素が多く含まれ、これを煮出して媒染すると黄褐色から濃い茶色に発色する。古来、武具の革紐や木綿の生活布を日焼け風に染めるのに多用され、鉄媒染で黒茶、アルミ媒染で温かみのある茶と変化を付けられる。タンニンが主成分のため耐光性も比較的高い。赤紫や濃青みの色素は含まれず、黄緑は他植物由来であるため誤りとなる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は草木染めクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は草木染めクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。