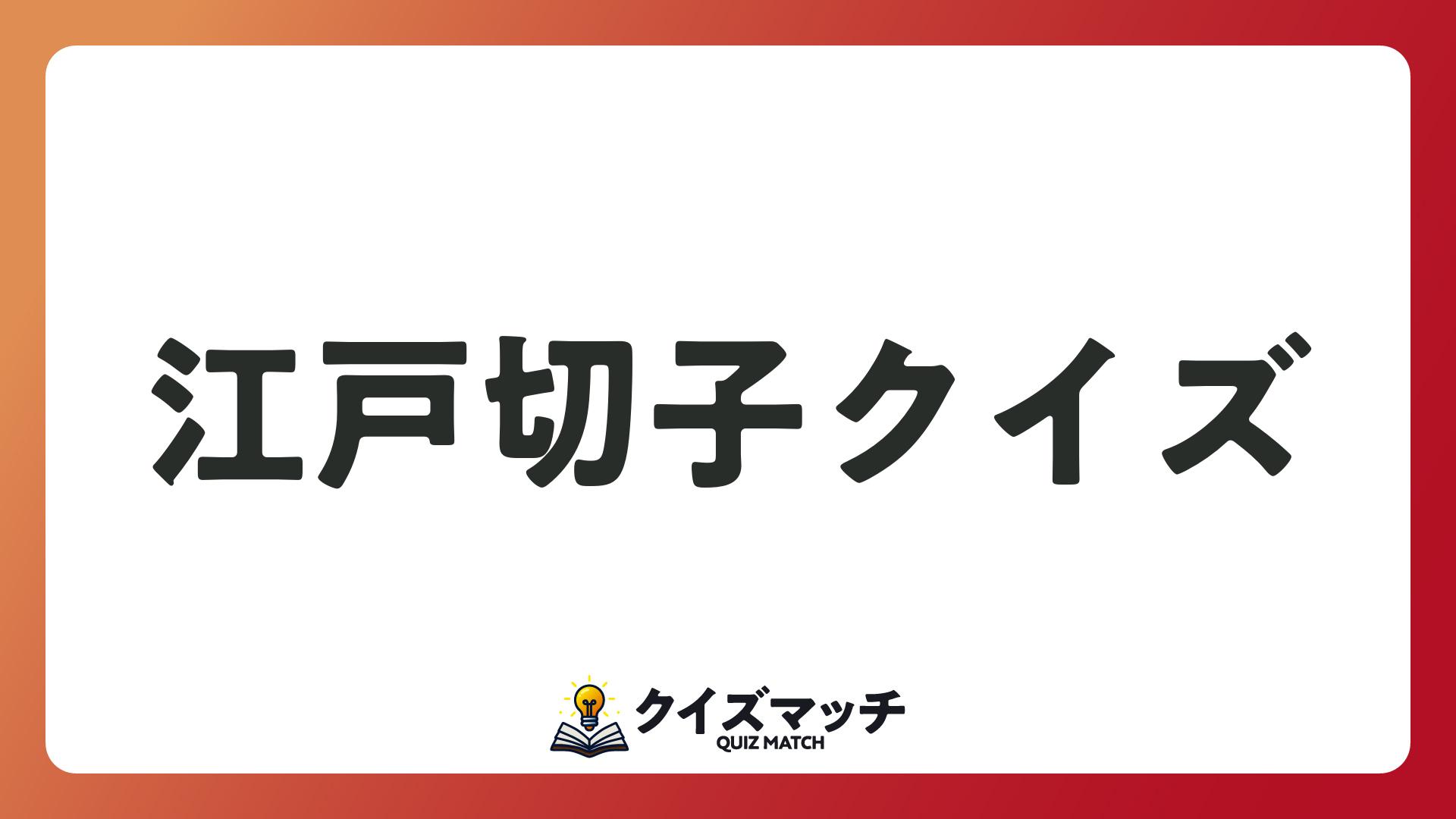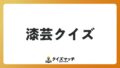江戸時代から続く日本伝統工芸の代表、江戸切子。その魅力と歴史を10問のクイズでたっぷりとお楽しみください。江戸切子の起源や代表的な文様、技法、材料など、職人の高い技術と美意識が詰まった世界をご紹介します。江戸切子文化の知られざる側面にも迫り、いつしか切子の魅力に引き込まれていくはずです。最後まで楽しい学びの時間をお過ごしください。
Q1 : 透明度を高める最終研磨で用いられ、白い粉末を水で溶いてバフに塗布することから『白粉』とも呼ばれる現代江戸切子の研磨材は?
最終仕上げの艶出しに使われるのが酸化セリウム(CeO₂)。粒径が0.3〜1ミクロンと極めて細かく、ガラス表面をわずかに化学的に溶解しながら機械的にも磨くため、微細な傷や曇りを消し透明感が格段に向上する。少量の水で練った懸濁液をフェルトバフに含ませ、温度管理をしつつ数分磨くと、カット面はまるで鏡のような光沢を帯びる。無鉛クリスタルなど化学組成を問わず効果が高く、職人の熟練度で艶の持続性までも左右される重要工程である。
Q2 : 江戸切子協同組合(東京カットグラス工業協同組合)の本部が置かれている東京都の区はどこ?
東京カットグラス工業協同組合は昭和54年設立の産地団体で、現在の事務局は江東区亀戸に所在する。江東区は江戸時代に砂町でガラス原料の砂が採れ、明治以降は工場用地も多かったため切子職人や研磨機メーカーが集積した地域である。同区では小名木川の水運を利用して原料や製品を運んだ歴史もあり、今でも工房見学や体験教室の多くがここで行われる。産地を代表する大田区蒲田や台東区浅草橋と並び、江東区は江戸切子ネットワークの中核的な位置を占める。
Q3 : 伝統工芸士の資格を江戸切子分野で取得するために必要とされる実務経験年数の目安は?
経済産業大臣が認定する伝統工芸士制度では、各産地の組合が技能審査を行い推薦する。その受験資格として江戸切子の場合は原則『12年以上』の実務経験が条件となる。長期間にわたり荒摺りから艶出しまで一貫して担当し、高度な技術と材料知識、さらには後進指導能力まで身につけていることが求められる。試験では実技でグラス1個を丸1日で完成させるほか、座学で歴史・材料学・安全衛生を問う筆記も行われるため、12年は単なる年数でなく総合力の裏付けとして機能している。
Q4 : 『菊繋ぎ』文様を構成する放射線は通常何度刻みで引かれる16分割の組み合わせが基本となっているか?
菊繋ぎは二段の放射線と同心円を重ね、菊花が連続するように見せる技巧的な文様である。一般的には円周を16等分する22.5度刻みの線を上下に配し、さらに角度をずらした二段目を重ねることで花弁が密に並ぶ。角度が異なると花弁の幅や光の反射が崩れるため、職人は割り出し盤の目盛りや墨打ちで正確に位置決めを行う。江戸切子は幾何学の正確性が美しさを左右する典型例で、22.5度という細かな分割は中上級者の技術指標ともされる。
Q5 : 近年環境負荷低減の観点から江戸切子で採用が進む、鉛を含まず高い屈折率と輝きを併せ持つ素材はどれ?
従来、高い光沢と重量感を持つ鉛クリスタルガラスが切子の主流であったが、鉛溶出や廃棄時の環境影響が問題視されるようになった。そこで開発されたのが酸化チタンや酸化ジルコニウム等で屈折率を高めた『無鉛クリスタルガラス』である。鉛を含まないため比重はやや軽いが、透明性と音色は従来品に遜色なく、海外輸出時の規制にも対応できる。江戸切子の工房では硬度が高い素材特性を活かし、細かなカットでも欠けにくい利点を生かした製品展開が広がっている。
Q6 : 江戸切子の起源とされる人物として知られる江戸後期の硝子商は誰?
加賀屋久兵衛は天保5年(1834年)頃、江戸大伝馬町で舶来ガラスに金剛砂を当てて模様を刻む方法を試みた人物と伝えられる。彼の試作が評判を呼び、以後職人が技術を改良しながら江戸の町に切子文化が根付いた。藩主や武家が愛玩したほか、明治期には輸出品にも発展する基盤となり、「江戸切子」の名はここから始まったといわれる。
Q7 : 江戸切子が経済産業大臣指定伝統的工芸品に加えられた年はいつ?
伝統的工芸品の指定は厳格な審査を経て行われる。江戸切子は平成14年(2002年)7月、全国で192番目の品目として正式に指定を受けた。これにより産地表示や技術継承のための支援、伝統工芸士の認定制度の適用など多くのメリットが生まれた。指定の裏には、職人団体による統一基準の策定や後継者育成計画の提出など長年の努力があり、江戸切子の品質と名称が法律的にも保護されるようになった。
Q8 : 交差する線が竹籠の編み目を思わせることから名付けられた江戸切子の代表文様は?
籠目文様は縦横斜めに走る直線カットが六芒星状に交わり、まるで竹籠の網代のように見えることから名付けられた。光が複雑に反射するため輝きが強く、底面や側面を一周させると見る角度で網目が浮かぶのが特徴。型紙で作る染織や建築の欄間にも用いられてきた幾何学模様で、魔除けの意味を込める習俗もある。切子職人は直線の深さと幅を均一に揃え、美しい幾何学を正確に刻む高い技量を求められる。
Q9 : 色付きの被せガラスの表面を削り地の透明ガラスを露出させて文様を浮かび上がらせる江戸切子の技法を何と呼ぶ?
江戸切子では無色透明の生地に薄く色ガラスを被せた素材を使い、カットで表層を彫り取って地色と色層の対比を生む技法を「色被せ」という。その歴史は明治期にイギリスのカメオガラス技術を取り入れたことで本格化し、赤被せ・藍被せなど多彩な色種が誕生した。色層はわずか1〜2ミリしかないため、深く彫りすぎると地が露出しすぎ、浅いと模様が曖昧になる。職人は旋盤の回転数と刃当ての圧力を絶妙に制御し、色と透明の境界を滑らかに仕上げている。
Q10 : 江戸切子で模様の輪郭を荒く削り出す際、金属円盤に工業用ダイヤを電着させた工具は何と呼ばれる?
現在の江戸切子工房では、荒摺り工程でステンレスや銅の円盤にダイヤモンド砥粒を固定した『ダイヤモンドホイール』が主流となっている。従来の金剛砂より切削力が高く、ガラスを早く正確に削れるため作業効率が向上し、熱変形や欠けのリスクも抑えられる。職人はホイールの粒度を数段階変えながら深さや幅を決定し、その後に細かい砥粒の石掛け、木掛け、バフ掛けで研磨と艶出しを行う。ホイールの回転音や火花は現代工房の象徴とも言える光景である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は江戸切子クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は江戸切子クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。