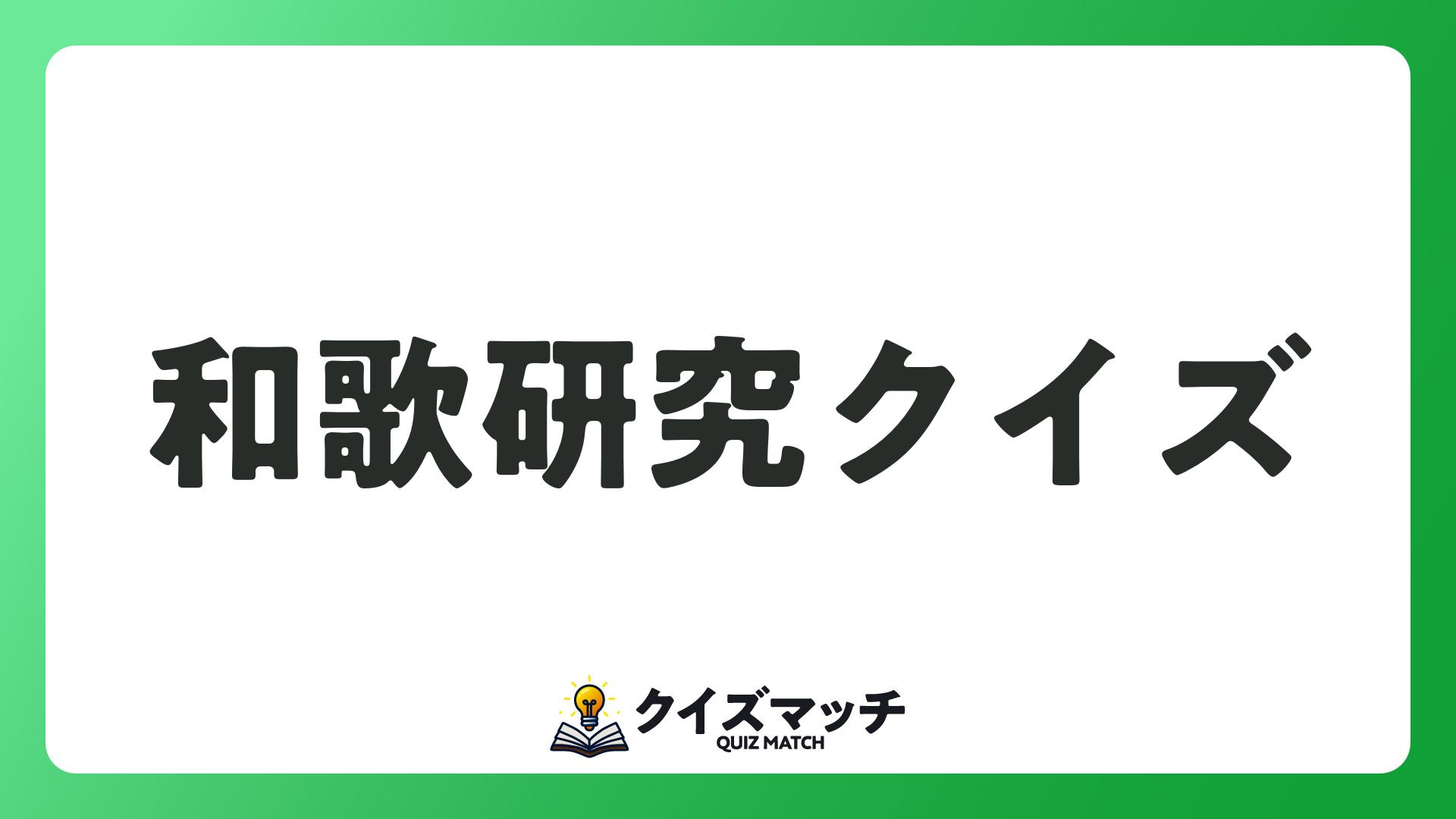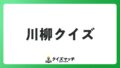和歌は日本の文化的遺産として、古今にわたり根強い人気を保ち続けてきた。その歴史と詠み手たちの足跡には、豊かな知的・情緒的魅力が宿っている。本記事では、『古今和歌集』から『新古今和歌集』に至る「八代集」を中心に、和歌研究の奥深さに迫るべく、10の多角的な小クイズを用意した。和歌に親しむ人も、これから触れ始める人も、日本文化の粋を感じ取ることができるはずである。奮ってご挑戦ください。
Q1 : 藤原定家が撰した歌論書として正しいものはどれか。
『近代秀歌』は藤原定家が鎌倉前期にまとめた優れた歌を選集した歌論的秘本で、自身の選出理由を簡潔な評で示し、後世の歌道に大きな影響を与えた。『無名抄』は鴨長明の歌論、宮廷歌会についての随想集、『毎月抄』は後鳥羽院の講書会記録で定家の編ではない。『袋草紙』は藤原清輔が古筆の来歴を記した書物で、歌論ではなく書誌学的資料である。従って定家の著になるのは選択肢1のみである。
Q2 : 私家集『山家集』を編んだ歌人は誰か。
『山家集』は平安末から鎌倉初期にかけて活躍した僧侶歌人西行(俗名佐藤義清)の歌を自撰・他撰併せて収めた私家集である。西行は出家して諸国を遍歴し、自然と心情を清澄な歌に結晶させた。源実朝は鎌倉幕府将軍で『金槐和歌集』を遺し、慈円は『拾玉集』、能因法師は『能因集』を持つが『山家集』には直接関与していない。よって選択肢2が正答となる。
Q3 : 『三十六歌仙』に名を連ねるが、『百人一首』には歌が採られていない人物は次のうち誰か。
藤原公任が撰んだ『三十六歌仙』は平安初期から中期の優れた歌人を列挙している。一方『百人一首』は鎌倉期に藤原定家が選んだ百首で、歴史的・人物的な配分が異なる。業平・小町・貫之はいずれも百人一首に代表歌が採られているのに対し、坂上是則のみは百人一首に登場しない。彼は『後撰和歌集』などに秀歌を残すが定家の選歌対象からは外れたため、選択肢3が正答となる。
Q4 : 「春過ぎて 夏来にけらし 白妙の 衣ほすてふ 天の香具山」を詠んだ作者は誰か。
上掲の歌は『万葉集』巻一に収められた天武天皇七年頃の御製とされ、作者は持統天皇(天智天皇の娘・天武天皇の皇后)。春から夏に移る季節感を、天の香具山に干される衣の白さと結びつけることで鮮やかに提示した名歌である。柿本人麻呂や山部赤人は同集を代表する歌聖だが作者ではなく、額田王は同じく宮廷歌人で「あかねさす 紫野行き…」の歌が著名。したがって選択肢4が正解となる。
Q5 : 『和漢朗詠集』を撰んだ人物は誰か。
『和漢朗詠集』は平安中期の貴族藤原公任が、漢詩と和歌を朗詠の便に供する目的で編纂した秀選集で、上巻を春夏秋冬・羈旅、下巻を離別・羇旅など題ごとに配置する。公任は音律を重視し、和歌と漢詩を並置する試みで後世の声楽や詩歌観に大きい影響を及ぼした。源俊頼は『金葉集』撰者、藤原俊成は定家の父で『千載集』撰者、紀長谷雄は漢詩人であり本集の編者ではない。
Q6 : 歌枕として名高い「吉野」は、和歌の中で主にどの季節を象徴する景物として詠まれるか。
吉野は奈良県南部、大和川上流に位置する山峡で、古来桜の名所として知られる。和歌では吉野山の桜を中心に雪と見まがう花の景を詠嘆する例が多く、春の題材として定着している。『古今和歌集』の紀友則の歌や後鳥羽院の吉野行幸歌など、桜花と春景を結び付けた作例が著名である。冬の雪や秋の紅葉も題材になるが頻度は少なく、夏景との結びつきも希薄であるため、伝統的には春の象徴が最も妥当とされる。
Q7 : 『古今和歌集』の仮名序を書いた人物は誰か。
仮名序は『古今和歌集』の国文学的意義や和歌の理念を平仮名で述べた序文で、成立当時から文学史上重要視されている。撰者の一人である紀貫之が、漢文の真名序を書いた紀淑望とは別に、日本語で平易に序の精神を語った。紀友則は共同撰者だが真名序や仮名序を書いたとする記録はなく、在原業平は六歌仙の歌人、藤原定家は後世の歌人で『古今』成立より三世紀ほど後の人物であるため誤りである。
Q8 : 『新古今和歌集』の撰者に含まれない人物は誰か。
『新古今和歌集』は後鳥羽院の院宣を受け、藤原定家・家隆・有家・良経・源通具・藤房・寂蓮らが選定に参加したとされる。鎌倉幕府三代将軍であり歌人としても名高い源実朝は、この勅撰集には歌を収められた側であって撰者ではない。定家は中心的撰者、家隆も同じ歌壇の代表、寂蓮は西行の流れを汲む僧侶歌人で撰者に連なる。よって選択肢2のみが非撰者として正答となる。
Q9 : 同音異義を利用し、単語を掛け合わせて二重の意味をもたせる和歌の技法はどれか。
掛詞は、同じ発音を持つ二語を重ねて一句に織り込み、聞き手に二重の意味を想起させる技巧で、平安和歌で盛んに用いられた。たとえば紀貫之の「あまのはら ふりさけ見れば 春日なる」は「ふり」と「降り」「経り」を掛けている。枕詞は特定の語にだけ掛かる修飾的定型語、序詞は比喩的な語句を連ねて本題を導く序段、本歌取りは先行歌を引用し響かせる技法で、同音異義そのものではない。
Q10 : 次の勅撰和歌集のうち、いわゆる八代集(初代『古今』から第八代『新古今』まで)に含まれないものはどれか。
八代集とは『古今』『後撰』『拾遺』『後拾遺』『金葉』『詞花』『千載』『新古今』の八つの勅撰集を指す呼称で、院政期以降の歌学で重要視された。選択肢1の『詞花』は第六代、2の『後拾遺』は第四代、3の『千載』は第七代に該当し八代集に含まれる。一方『新勅撰和歌集』は鎌倉後期に亀山上皇の院宣で撰進された集で、第十三番目の勅撰集にあたり八代集よりはるか後の世紀の編纂であるため、これのみが該当しない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は和歌研究クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は和歌研究クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。