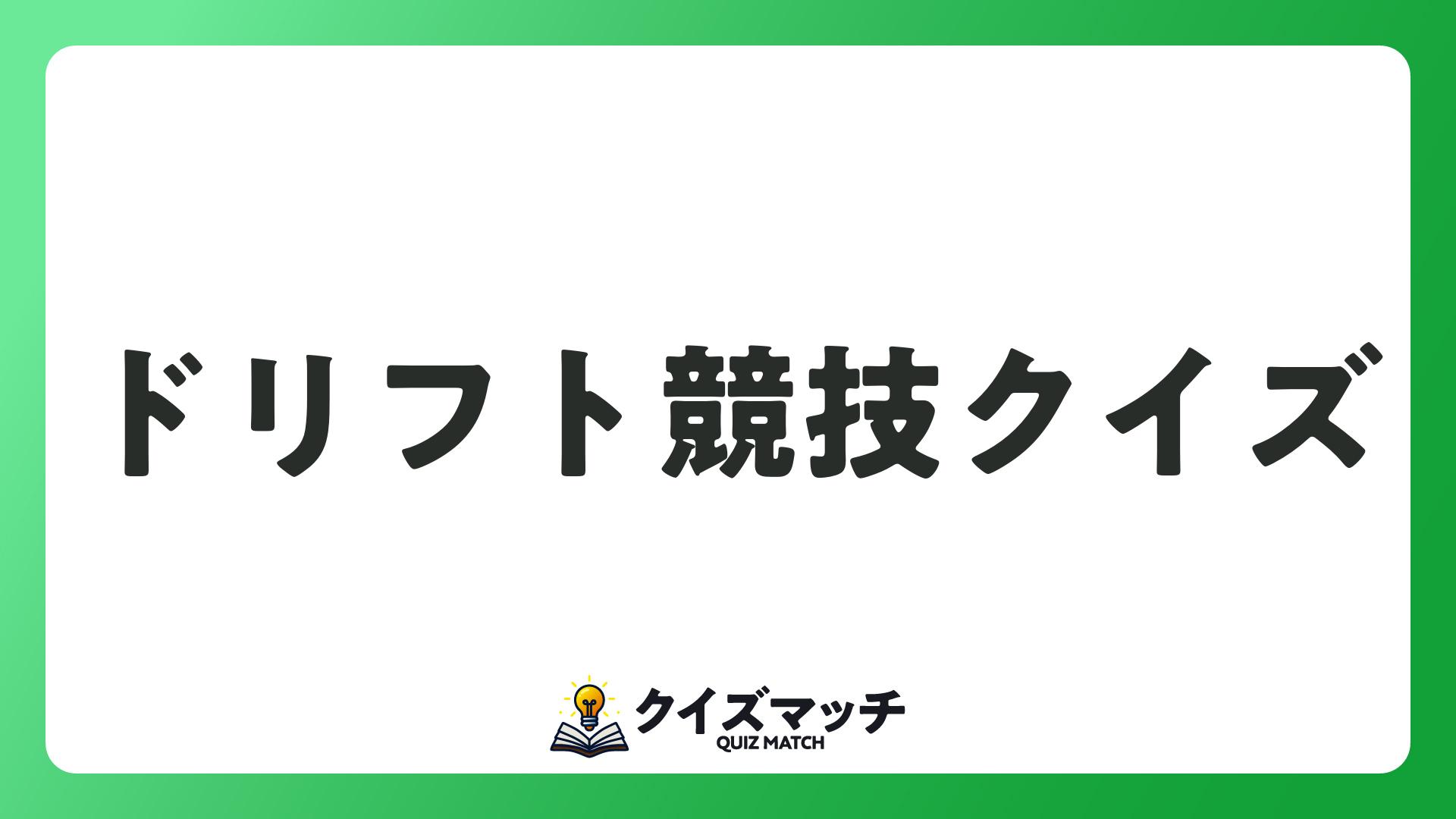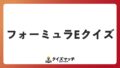ドリフト競技のルーツからトップシーンまでを網羅した10問のクイズ
ドリフトは1980年代の峠道を舞台に生まれ育った日本発のモータースポーツ。この記事では、ドリフト競技の歴史とルール、そして世界を牽引するトップドライバーたちについて、ドリフトファンなら知っておきたい知識をクイズ形式でお届けします。土屋圭市らパイオニアの活躍から、現代のD1グランプリや国際大会の動向まで、ドリフト文化の醍醐味を存分に楽しめる内容となっています。ドリフトの魅力を存分に味わえる一本です。
Q1 : 追走で観客を沸かせる技で、後輪バンパーを壁に軽く接触させながらラインを取る行為は通称何と呼ばれるか? スライドバンプ キッス・ザ・ウォール ウォールライド テールタップ
キッス・ザ・ウォールは車体後部をミリ単位で壁にタッチさせつつ大角度を保つ高度なテクニックで、壁までの距離感覚と車速管理が求められる。接触時間が短く衝撃が小さければ加点対象になり得るが、強く当てすぎるとバンパー破損やサスペンショントラブルにつながり減点やリタイアのリスクが高い。観客には迫力ある映像効果を提供できるため、トップドライバーは決勝の見せ場として狙うことが多い。
Q2 : D1GPの追走トーナメントで採用される方式で、リードとチェイスを互いに入れ替えて走る計2本の走行で勝敗を決める形式を何というか? 単発一発勝負方式 予選ポイント加算方式 3本連続走行方式 先攻後攻入れ替え2ラン方式
D1GPの追走はリード車が正確なラインを示し、チェイス車が限界まで接近して追従する様子を公平に評価するため、必ず2本のランで先攻後攻を交代する方式を採用している。各ラン終了ごとに審査員が優劣を判定し、合計ポイントまたは多数決で勝敗を決定。同点時はワンモアタイムで再戦する。進入速度、角度、追従距離、ゾーントレースなど複合要素が採点され、スタート位置有利の偏りを排除しつつ攻防の妙を引き出している。
Q3 : ドリフトの初動で行うクラッチ蹴り(クラッチキック)の主な目的は何か? 車速を落とすため アクセル開度を減らすため 駆動力を一瞬途切れさせ再度繋げることで後輪を滑らせるため タイヤ温度を下げるため
クラッチ蹴りはコーナー進入時にクラッチを瞬時に切り、エンジン回転を高めたのち急激にクラッチをつなぐことで駆動力を急増させ、後輪のグリップを破綻させるテクニック。低速域やグリップの高い路面で有効で、サイドブレーキより短時間で姿勢変化を作れる。蹴り過ぎればスピン、弱ければ角度不足となるため、踏力やタイミングが極めて重要。競技では速度維持と大角度を両立したいシーンで多用される。
Q4 : 2019年に富士スピードウェイで行われたFIA Intercontinental Drifting Cupで総合優勝を飾ったロシア出身ドライバーは誰か? ジョージー・チフチャン 斎藤太吾 マイケル・ロッカーフェラー 横井昌志
2019年のFIAインターコンチネンタルドリフティングカップは世界各国のトップドライバーが招待され、富士スピードウェイの特設コースで競われた。最終的にロシアのGeorgy Gocha Chivchyanが安定したライン取りと大角度を維持しつつ高い速度を保つ走りで決勝を制し、総合優勝を獲得。トヨタGT86をベースに1000馬力級にチューンしたマシンを巧みに操り、川畑真人ら強豪を下した。ロシア勢としてFIA公認大会初制覇となり、国際ドリフト界に大きなインパクトを与えた。
Q5 : ドリフト競技でDrift Kingの異名を持ち、D1GP設立にも携わった人物は誰か? 土屋圭市 織戸学 田中毅 井上尚志
土屋圭市は1980年代にAE86型トレノで峠やサーキットを舞台に意図的なオーバーステアを駆使した速い走りを披露し、メディアが彼をDrift Kingと呼んだことから愛称が定着した。OPTIONビデオやベストモータリングでドリフトのノウハウを解説し、後年はD1グランプリの創設メンバーとして競技ドリフトのルール作りや審査基準確立に尽力。現在も世界各地のイベントで審査員やインストラクターを務め、日本発祥のドリフト文化を国際的モータースポーツへ押し上げた中心人物と評価されている。
Q6 : 日本国内で始まったD1グランプリ(D1GP)の初年度シーズンが開催されたのは何年か? 1998年 2000年 2001年 2003年
D1グランプリはチューニング誌OPTIONを中心としたスタッフと土屋圭市らが主導し、従来のデモラン的イベントを正式な競技に昇華させる目的で発足。2000年末に告知され、翌2001年に第1戦エビスサーキットを皮切りにシリーズ戦がスタートした。初年度は全5戦で構成され、熊久保信重や谷口信輝が活躍。現在では国際ラウンドを含む大規模シリーズへ発展したため、2001年は黎明期を象徴する重要な年としてファンの間で語り継がれる。
Q7 : Formula Drift USAの公式採点で使用されない項目はどれか? 角度(アングル) ライン スピード タイヤ温度
Formula Drift USAではリード車のライン、リア滑り角度の大きさと安定度を測るアングル、ゾーン通過速度をセンサーで測定するスピードの三つが主審査項目となる。タイヤ表面温度は安全管理としてピットで測定する場合はあるが、採点配点の対象ではない。そのため決勝で高得点を得るには角度とラインを両立させつつ速度を落とさない走りが求められ、タイヤ温度はあくまで裏方的な管理項目にとどまっている。
Q8 : 後輪を駆動しやすく操舵輪と駆動輪が分かれるため、D1GP車両として事実上必須とされている駆動方式はどれか? FF FR RR MR
D1GPの車両規定では四輪駆動からの改造も認められるが、実際の競技では前輪操舵・後輪駆動を示すFRレイアウトが圧倒的多数を占める。FRはカウンターステアを取りやすく、スロットル操作でリアを滑らせたまま角度調整を行うのに適しているためだ。FFは駆動輪が前輪のため大きなアングル維持が難しく、RRやMRは荷重移動がシビアで扱いづらい。結果としてトップカテゴリーで勝負するチームはほぼ全てFRを選択し、車体剛性やサスセッティングで差別化を図っている。
Q9 : 2022年シーズンのD1グランプリシリーズチャンピオンに輝いたドライバーは誰か? 川畑真人 斎藤太吾 横井昌志 今村陽一
2022年のD1GPは開幕戦鈴鹿ツインから最終戦オートポリスまで全8戦で争われ、Team RE雨宮からGR86を駆る横井昌志が2勝を含む安定したポイント獲得でシリーズを制覇した。横井は2019年以来2度目のタイトルで、シーズン途中にJZX100から新型GR86へスイッチしながらも高い順応力を示した。追走でのプレッシャーに強く、壁寄せと大角度を両立。最終戦ではライバルの川畑真人を抑え、年間ランキングトップを確定させた。
Q10 : D1GPの車両レギュレーションにおいて、加速向上を目的としたN2O噴射装置(ナイトラス)の扱いはどう定められているか? 使用は禁止されている 排気量に応じて制限付きで許可 完全に自由に使用できる シリーズによって異なる
D1GPテクニカルレギュレーションではエンジン出力の急激な上昇が車体コントロールやタイヤ負荷に与える影響を考慮し、N2Oや亜酸化窒素を用いた化学的過給装置の装着と使用を全面禁止としている。ターボやスーパーチャージャーは認可されるが、ナイトラスはボンベ搭載自体が違反。これによりチームは機械過給とエンジンチューン、タイヤ選択でバランスを取る必要があり、安全性と公平性を確保している。
まとめ
いかがでしたか? 今回はドリフト競技クイズをお送りしました。
今回はドリフト競技クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!