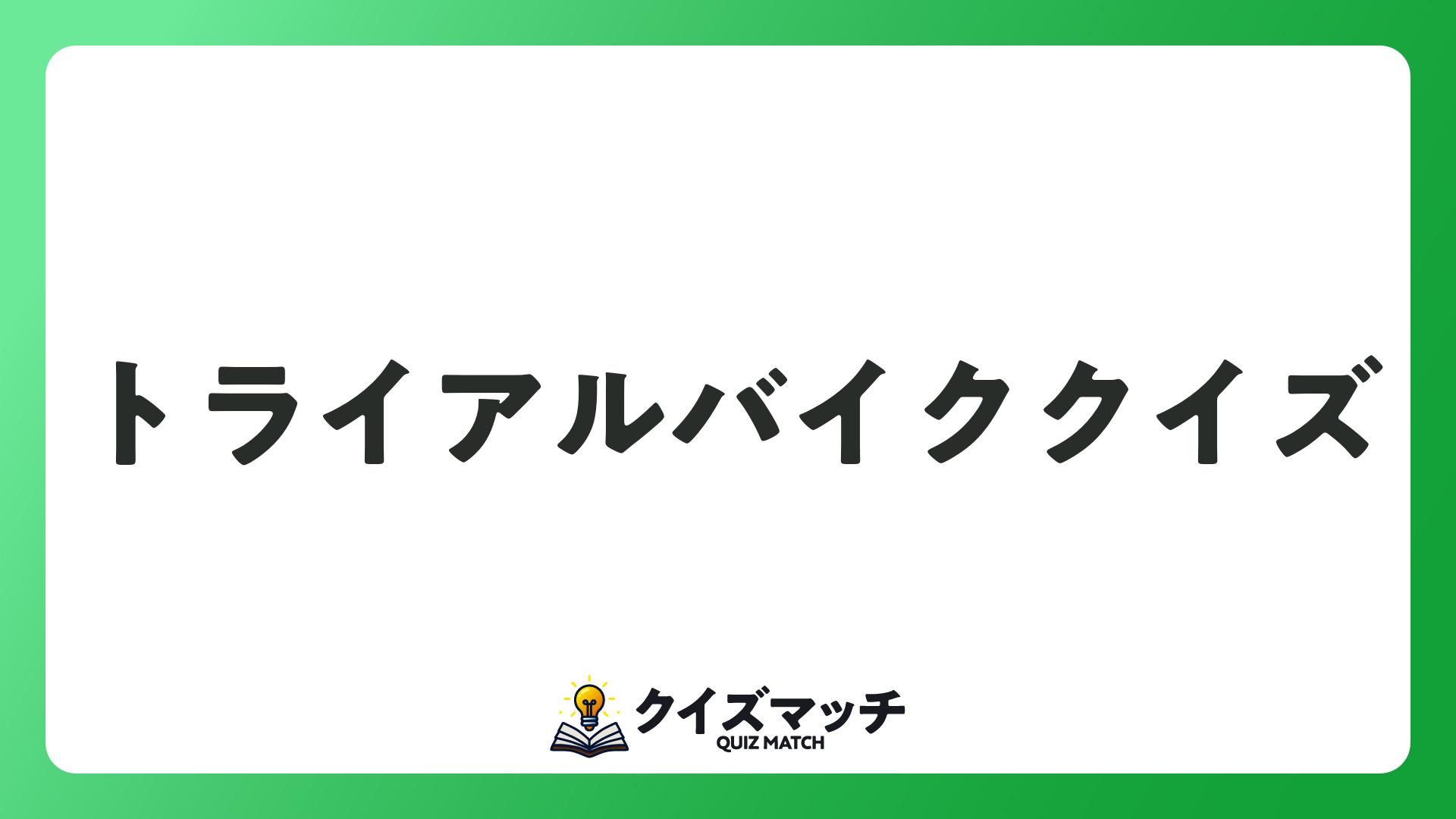トライアルバイクは、その場でバランスを取りながら静止する基本テクニックが欠かせません。スタンディングと呼ばれるこのテクニックは、重心移動、視線、ハンドルとブレーキの操作を調和させる必要があり、習得には時間を要しますが、トライアルライダーにとって必須のスキルです。この記事では、トライアルバイクに関する10問のクイズを用意しました。クイズの内容は、スタンディングのテクニック、世界選手権の記録保持者、クラッチ操作の方法、競技用バイクの特徴、日本人選手の活躍など、トライアルバイクの知識を深めるのに役立つ内容となっています。トライアルバイクファンの方はもちろん、これから始めたいと考えている方にも、このクイズを通じて、より深い理解が得られると思います。
Q1 : FIMトライアル競技の採点で、セクションを足つきなしでクリアした場合に与えられる減点は? 5点 2点 0点 3点
トライアルは減点方式で行われ、5点はセクション不通過や転倒など重大ミス、3点は3回以上の足つき、2点は2回の足つき、1点は1回の足つきに相当する。足を着かずに通過すれば減点は0点、これを俗にクリーンと呼ぶ。最終的な成績は各セクションの減点を合算し、総合計が少ないライダーが上位となる。したがって0点の積み重ねが勝負に直結し、トップカテゴリーでは1ラップ全クリーンが勝敗を分けることも珍しくない。
Q2 : FIMトライアル世界選手権(TrialGP)で2019年までに屋外タイトルを13連覇し、史上最多記録を持つライダーは? ダグ・ランプキン トニー・ボウ アダム・ラガ 藤波貴久
スペイン出身のトニー・ボウは2007年に初戴冠して以来、2023年現在まで屋外世界選手権を一度も取りこぼさずに連覇し続け、同時に屋内シリーズのX-Trialでも無敗を誇る。身体の柔軟さと独創的なステップワーク、電子制御を駆使したホンダ・モンテッサCota4RTでの圧倒的なダイナミックライディングが特徴で、従来の常識を覆すビッグステップ攻略を披露し競技の技術水準を大きく引き上げたと評価されている。
Q3 : クラッチ操作を素早く行いながらハンドルグリップを確実に保持するため、トライアルライダーが一般に推奨されるクラッチレバーの指の本数は? 4本指 2本指 1本指 3本指
レバーを1本指だけで引けば残りの指でグリップを強く握ったまま細かな体重移動ができ、赤土や濡れた岩など滑りやすい状況でも車体を安定させられる。2本以上で握ると握力は増すものの把持面積が減って腕上がりを誘発しやすく、ステアケースの弾き出し時などにバーを押さえ切れず転倒するリスクが増す。現行マスターシリンダーは軽いタッチで作動するため1本指でも十分な油圧が得られ、世界選手権ライダーのほとんどがこの方法を採用している。
Q4 : 競技用トライアルバイクに通常装備されておらず、短距離移動時を除いて使用しない部品はどれ? フロントフェンダー ラジエーター ハンドルバー シート
セクションでは立ち乗りが基本であり、跳躍時には車体と体が大きく動くため座面があると足やパンツを引っ掛けやすく危険が増す。さらに低いシルエットを確保して軽量化する目的もあるため、メーカーはあえてシートを設けずフレーム上側を樹脂カバーで覆うだけに留めている。短い移動区間ではそのカバー部分に腰を当てて座ることもあるが、正式には着座部として設計されていない。オンロードモデルとは真逆の発想がトライアルの特色と言える。
Q5 : 2004年、日本人ライダー藤波貴久がホンダ・モンテッサで獲得し、日本唯一の快挙となっているタイトルは? トライアル世界選手権アウトドア年間チャンピオン モトクロス世界選手権MX2チャンピオン ダカールラリー総合優勝 AMAスーパークロスチャンピオン
藤波貴久は10代で世界参戦を開始し、長年ランキング上位を維持しながらもタイトルに手が届かない時期が続いたが、2004年にダグ・ランプキンとの接戦を制してついに年間王者となった。アジア出身選手としては史上初の世界チャンピオンであり、日本国内トライアル人気を押し上げた立役者でもある。その後も2021年の引退まで連続出場記録を更新し続け、トップ10入りを22シーズン連続で達成するなど高い安定感を示した。
Q6 : 路面追従性を高めるため、トライアルバイクの前後タイヤは非常に低圧で使用される。競技前にセットされる空気圧として一般的な値は? 0.3〜0.4MPa(約3〜4bar) 0.04〜0.06MPa(約0.4〜0.6bar) 0.8〜1.0MPa(約8〜10bar) 1.2〜1.4MPa(約12〜14bar)
0.04〜0.06MPaは他の二輪分野と比べ圧倒的に低く、タイヤが岩の輪郭に沿って変形することでグリップ力を最大化できる。加えて空転を抑えサスペンションのような吸収機能も期待できるため、低速でのバランス保持やステアケースの登坂に有利となる。ただし空気が少なすぎるとビード落ちやリム打ちの危険があるため、外気温やセクションの硬さに合わせて0.04MPa付近から微調整するのが定石である。
Q7 : FIMが主催する屋内トライアル世界選手権は、現在どの名称で呼ばれている? TrialGP Indoor Trial World Cup Arena X-Trial ArenaTrialGP
1993年に開始されたインドアシリーズは当初「Indoor Trial World Championship」と呼ばれていたが、ブランド刷新に伴い2008年から「FIM X-Trial World Championship」に改称された。セクションは人工障害物で構成され、スピーディーな演出と観客との距離の近さが特徴。屋外のTrialGPとはポイント制度を共有せず独立シリーズとなっているが、両方を戦うトップライダーも多い。近年は映像配信の充実で国際的な注目度がさらに高まっている。
Q8 : 国別対抗戦であるトライアル・デ・ナシオン(Trial des Nations)の男子ワールドクラスにおいて、1チームがエントリーできるライダー数は? 2名 4名 5名 3名
トライアル・デ・ナシオンはFIMが運営する団体戦で、男子ワールドクラスでは各国代表を3名に限定している。採点は各セクションで最も悪いスコアをカットする方式を採るため、3名編成が戦術面で理にかなうとされる。過去には4名体制だった時期もあるが、2002年以降は機動力と大会運営の効率を重視して現行の3名制に落ち着いた。スペインが連覇を続ける一方、イギリスや日本などが表彰台争いに加わる激戦が毎年繰り広げられている。
Q9 : 後輪の弾性を使ってフロントを高く持ち上げ、段差上に前輪を先置きする基本ステップは何と呼ばれる? フロントアップ バニーホップ スプラット エンデューロクロス
フロントアップはリアサスペンションの沈み込みと同時に体を後方へ引き、反発する瞬間にクラッチをつなぎ加速することで後輪を弾ませてフロントを跳ね上げる技術で、多くの障害物攻略の基礎となる。段差の角に前輪を当てて荷重を抜けば続くリアの引き上げもスムーズになり、車体が寝ず直立に近い姿勢を保てるためクリーン通過の確率が高まる。失敗して前転しないよう視線とスロットル開度のタイミングが重要で、初級者は丸太やタイヤで練習するのが一般的。
Q10 : トライアルバイクで、その場でバランスを取りながら静止する基本テクニックを何と呼ぶ? スタンディング ホッピング ウイリー ジャッキング
スタンディングは車体をほぼ一点に保ったままライダーの体重移動と前後サスペンションの微細な伸縮でバランスを取り続ける技術で、地形確認や次の動作への準備に欠かせない。足を着かずに停止できれば減点を防げるため、世界トップライダーほど静止時間が長い。重心移動、視線、ハンドルとブレーキの僅かな操作を調和させる必要があり習得には時間を要するが、全レベルの練習メニューの出発点とされる。
まとめ
いかがでしたか? 今回はトライアルバイククイズをお送りしました。
今回はトライアルバイククイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!