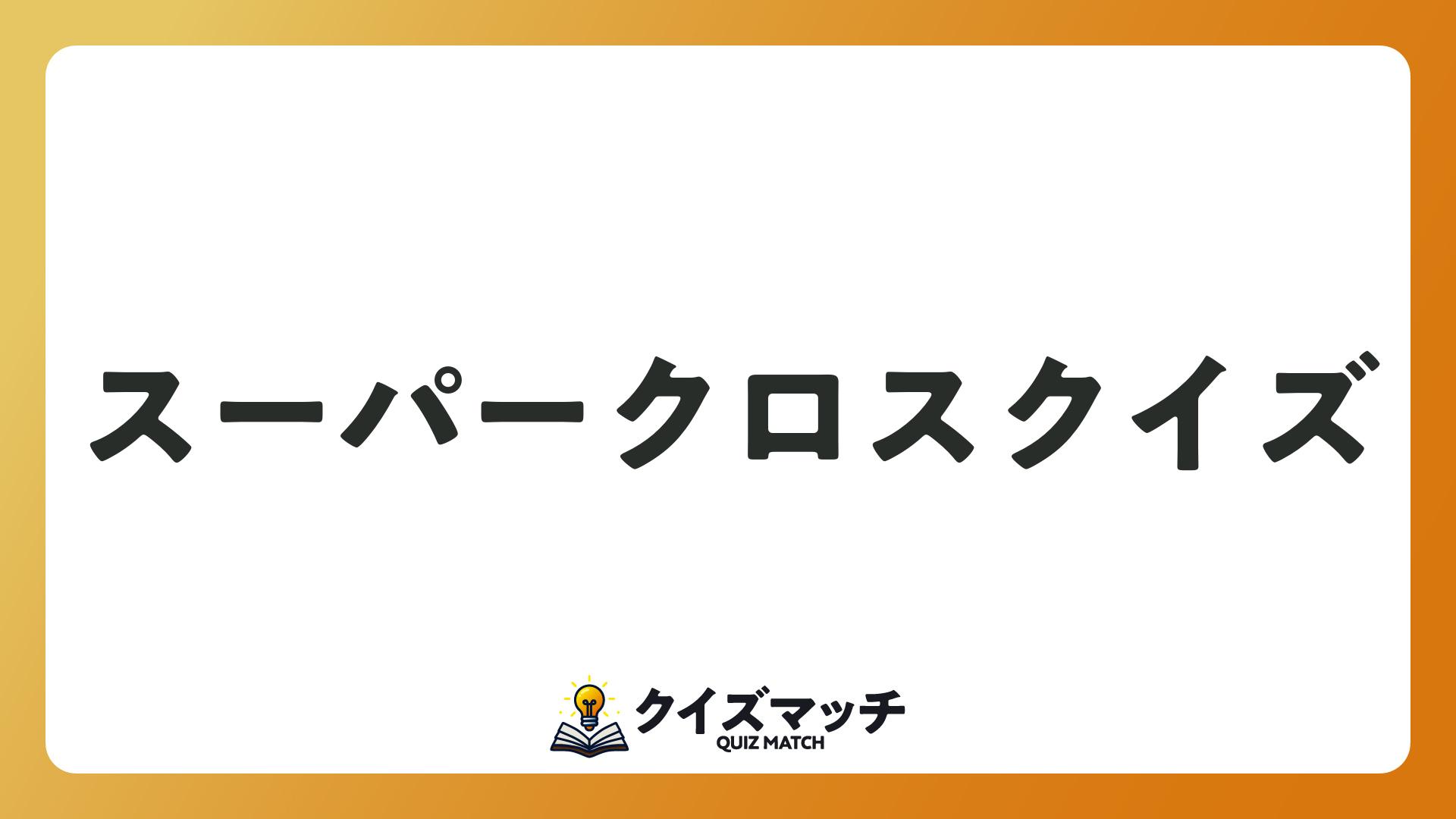スーパークロスクイズ – 歴史、科学、地理など多彩なジャンルから出題される難問に挑戦!
第一次世界大戦の引き金となった事件の舞台はどこか? イタリア料理カルボナーラに欠かせない伝統的なチーズとは? 量子力学の基礎を支える重要定数はどれか? 常温常圧で液体の元素はどれ?など、興味深い問題が満載。この機会にあなたの知識をテストしてみよう。歴史、科学、地理など、様々なジャンルの知識が問われる10問の超クロスオーバークイズをお楽しみください。
Q1 : 南アメリカ大陸に位置し、標高6961mで大陸最高峰とされる山はどれか? フィッツロイ チンボラソ アコンカグア ウアイナポトシ
アコンカグアはアルゼンチン西部、アンデス山脈のメンドーサ州にそびえ、海抜6961mで南アメリカおよび南半球の最高峰として知られる。山体は火山ではなく隆起によって形成されたが、周囲には氷河や雪原が広がり、南緯32度台という緯度の割に厳しい高山気候を示す。エベレストをはじめとする七大陸最高峰の一つとして多くの登山家に挑戦され、技術的難易度は高くないものの、高所順応や風雪への対策が必須となる。他の選択肢のフィッツロイ(3405m)やチンボラソ(6263m)、ウアイナポトシ(6088m)はいずれもアコンカグアより低い。
Q2 : 表面積で世界最大の淡水湖とされるのはどれか? ビクトリア湖 バイカル湖 タンガニーカ湖 スペリオル湖
淡水湖の面積ランキングでは、北米五大湖の一つスペリオル湖が約8万2000平方キロメートルで首位に立つ。水量ではシベリアのバイカル湖が圧倒的だが、面積に限ればスペリオル湖が世界最大となる。ビクトリア湖はアフリカ最大の湖として有名だが約6万9000平方キロメートルで2位、タンガニーカ湖は約3万2000平方キロメートルでさらに小さい。スペリオル湖はカナダとアメリカ合衆国にまたがり、巨大な淡水資源として生態系や気候にも大きな影響を与えている。
Q3 : クロロフィルが光合成で最も強く吸収する可視光の色はどれか? 赤色 緑色 黄色 赤外線
植物の葉緑体に含まれるクロロフィル a や b は赤色域(波長約660nm付近)と青紫域(約430nm付近)の光を強く吸収し、緑色域(約550nm付近)は反射・透過が優勢であるため葉は緑に見える。光合成では吸収した光エネルギーが電子励起を通じて化学エネルギーに変換され、最終的に炭酸同化反応につながる。黄色光や赤外線はクロロフィルの主吸収帯ではなく効率が低い。赤色光は系統 II の光化学反応中心で特に重要で、フィトクロムなど光形態形成にも影響を与える。
Q4 : 国際単位系 SI で磁束密度の単位として定義され、発明家ニコラ・テスラの名が冠されたものはどれか? アンペア テスラ ガウス ウェーバ
SI単位のテスラ(記号 T)は、1平方メートルあたり1ウェーバの磁束密度と定義される。名称は交流電流や無線技術で功績を残したセルビア系米国人発明家ニコラ・テスラにちなむ。アンペアは電流、ガウスはCGS単位系で用いられる磁束密度(1ガウス=10^-4テスラ)、ウェーバは磁束を表す単位であり、磁束密度とは区別される。磁場の強度評価にテスラが使われるのはMRI装置や加速器の磁石などで、現代の科学技術に深く関わる重要な単位である。
Q5 : 第一次世界大戦の引き金となったオーストリア皇太子フランツ・フェルディナンド夫妻が暗殺された都市はどこか? サラエボ ベオグラード プラハ ウィーン
1914年6月28日、ボスニア・ヘルツェゴビナの州都サラエボでセルビア系青年ガブリロ・プリンツィプが皇太子夫妻を射殺した事件が起きた。オーストリア=ハンガリー帝国はセルビアを強く非難し、同盟関係が絡み合っていた欧州列強が総動員体制に入り、第一次世界大戦が勃発する。場所がサラエボであったことは歴史の教科書でも象徴的に語られ、バルカン半島の民族問題の複雑さを示す事例として頻繁に引き合いに出される。
Q6 : イタリア料理カルボナーラで、伝統的に用いられる硬質チーズはどれか? パルミジャーノ・レッジャーノ ペコリーノ・ロマーノ ゴルゴンゾーラ リコッタ
カルボナーラの本場ローマでは羊乳から作られる塩味の強いペコリーノ・ロマーノをすりおろして使うのが古典的なレシピとされる。パルミジャーノ・レッジャーノも近年は世界的に普及しているため代用されることが多いが、伝統を重んじるイタリアの料理本や保護指定レシピではペコリーノが推奨されている。ゴルゴンゾーラやリコッタは種類の異なるチーズであり、カルボナーラの独特のコクや塩気、乳脂肪の粘度を再現するには適さないとされる。
Q7 : 物理学で用いられる定数 h が表すものはどれか? ボルツマン定数 アボガドロ定数 プランク定数 気体定数
小文字 h は量子力学の基礎を築いたマックス・プランクが導入したプランク定数を指し、値は約6.62607015×10^-34 J·s。光子や電子などの粒子が持つエネルギーと振動数の比例関係 E=hν を示す重要な役割を果たす。ボルツマン定数 k は統計力学、アボガドロ定数 N_A は物質量の尺度、気体定数 R は理想気体の状態方程式に現れる定数であり、いずれも h とは異なる概念である。プランク定数は近年、キログラムの再定義でも基本定数として利用され、計量標準の根幹を支えている。
Q8 : 常温常圧で液体として存在する元素はどれか? フッ素 ヨウ素 硫黄 臭素
地球上の元素の多くは常温常圧で固体か気体だが、例外的に水銀と臭素だけが液体で存在する。臭素はハロゲン元素で原子番号35、赤褐色で揮発性が高く、有毒な刺激臭を持つことからギリシア語の悪臭 bromos に由来した名が付いた。フッ素は淡黄気体、ヨウ素は昇華しやすい固体、硫黄は黄色い固体であり、いずれも室温で液体にはならない。臭素の液体性は分子間力と原子量のバランスによる融点・沸点の狭間に位置することが原因で、化学実験や工業用途で注意が必要な物質である。
Q9 : 日本で世界最古の木造建築群としてユネスコ世界遺産にも登録されている寺院はどこか? 法隆寺 東大寺 清水寺 鹿苑寺(金閣寺)
奈良県斑鳩町にある法隆寺は7世紀に聖徳太子ゆかりの寺として創建され、金堂や五重塔など飛鳥時代の建築が現存する。1993年には法隆寺地域の仏教建造物として日本初のユネスコ世界遺産に登録された。伽藍は火災に遭ったとの説もあるが、研究の結果、現存部分には7世紀後半の材が確認されており、現存する世界最古の木造建築群と評価されている。東大寺は8世紀、清水寺は平安時代、金閣寺は室町時代の建築で、いずれも法隆寺より後世のものになる。
Q10 : 日本国憲法第9条が定めている内容として代表的なものはどれか? 国民の生存権の保障 戦争の放棄 教育を受ける権利 法の下の平等
日本国憲法第9条は前文と並んで日本国の平和主義を象徴する条文であり、1項で国権の発動たる戦争と武力による威嚇・武力行使を永久に放棄すると宣言し、2項で陸海空軍その他の戦力および交戦権を保持しないと定めている。生存権は第25条、教育を受ける権利は第26条、法の下の平等は第14条に規定されており、第9条と混同しやすいが条文上の位置は異なる。戦争放棄条項は制定当初から国内外で注目され、自衛隊の位置付けなどを巡り憲法解釈が議論され続けている。
まとめ
いかがでしたか? 今回はスーパークロスクイズをお送りしました。
今回はスーパークロスクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!