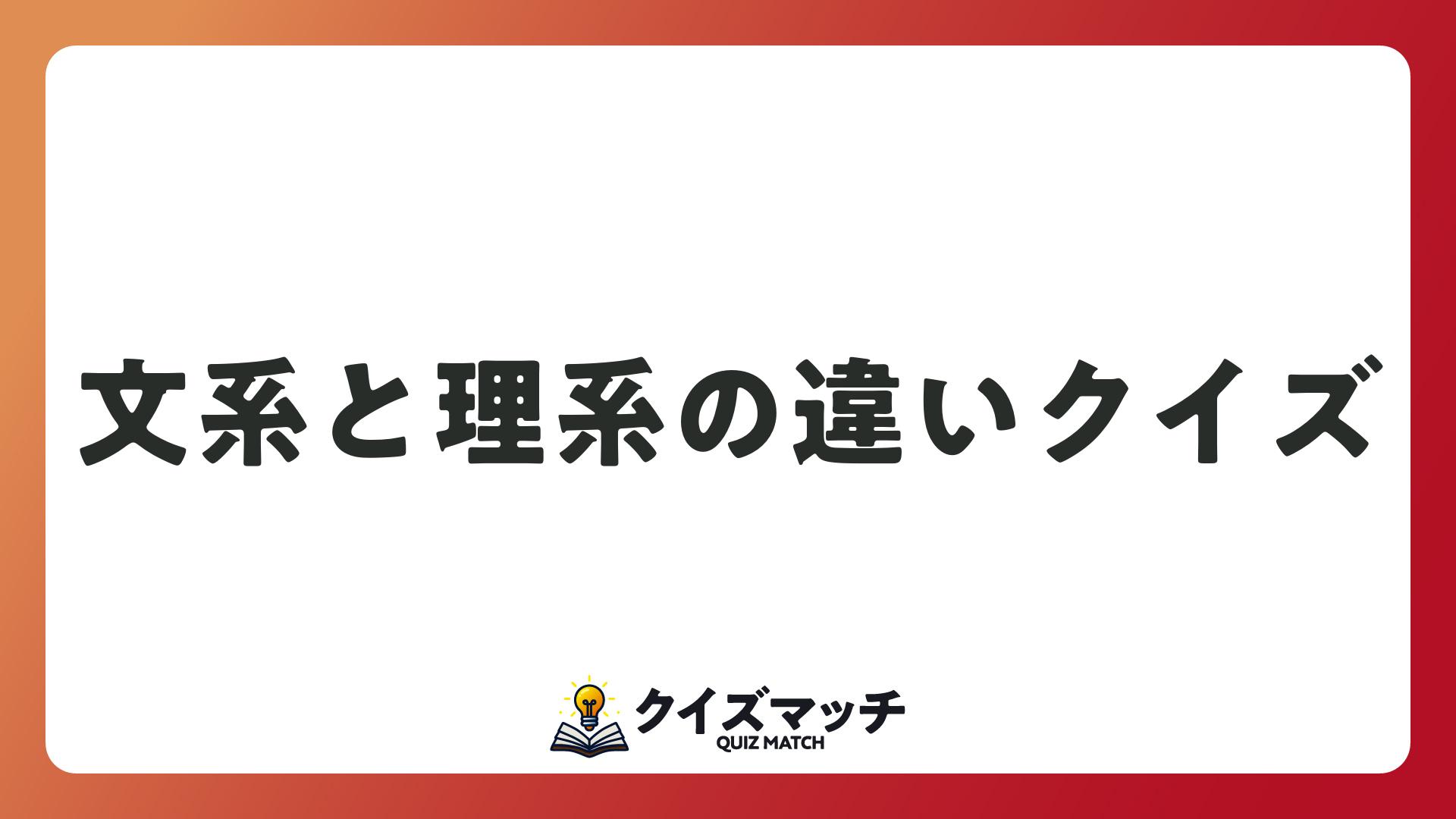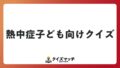文系と理系の違いを確認するクイズです。理系の数学や実験科学分野と、文系の解釈学や実証研究分野の特徴を問う10問のクイズを用意しました。大学の入試科目や授業内容、学術論文の書式など、専門分野の違いが反映される事項を取り上げています。理系と文系の思考方法や研究スタイルの相違を理解し、自分の適性を考える一助となれば幸いです。
Q1 : 法令解釈や判例研究を中心とする典型的な学問分野はどれか?
法学研究では条文や判例、学説に基づく論理的整合性の検討が中心で、実験や数値計算はほとんど行われない。学術論文も事実の再現性よりも解釈の妥当性が焦点となる。これは自然法則の実証を重んじる理系とは対照的で、法令解釈や比較法研究は典型的な文系的手法である。したがって該当するのは理工系ではなく法学である。
Q2 : ピアソンの相関係数を計算するプログラムを自作させる授業が必修となることが多い学部はどれか?
情報工学系ではデータ構造やアルゴリズムを学び、統計処理も自分でコードを書くことで計算機の仕組みと数式の対応を理解させる教育が行われる。文学部日本文学科など文系では作品解釈や歴史的背景の把握が主で、相関計算を手動で行う授業は少ない。研究で統計を使う場合でも既製ソフトを利用することが多く、必修として自作プログラムを課すのは理系学部の特徴である。
Q3 : 古典語の原典読解が必須とされることが多い分野はどれか?
古典文学や古代史では原文のニュアンスが翻訳で失われることを避けるため、ギリシア語、ラテン語、古典中国語などの文法と語彙を細部まで学ぶ必要がある。古典語による一次史料の読解が研究の出発点であり、文系でもとりわけ人文学系で必須とされる。化学や土木工学といった理系では専門用語は英語中心で、古典語の習得が卒業要件となることはない。
Q4 : 大規模数値シミュレーションを研究の主軸とする典型例はどれか?
気象学は大気運動を支配する非線形偏微分方程式をスーパーコンピュータで数値的に解き、将来の状態を予測することが核心である。観測データを取り込んだ大規模シミュレーションは理系でも計算科学寄りの方法論であり、質的インタビューやテキスト分析を重視する社会学や法哲学とは大きく異なる。したがって大規模数値シミュレーションの代表例は気象学である。
Q5 : 学術雑誌の評価指標「インパクトファクター」が特に重視される分野はどれか?
インパクトファクターは自然科学系の学術雑誌の引用頻度を測る指標としてトムソン・ロイターが開発し、特に医学・生物学分野のトップジャーナル選定や研究評価に強い影響力を持つ。文学や歴史学の雑誌は引用形態が書籍中心で数年かけて評価が定まるためIFが算出されないことが多い。社会科学でも重視度は低めで、IF偏重と批判されるほど頼りにするのは医学・生物学系である。
Q6 : 多人数の共著論文を生む研究室文化が最初に発達した分野はどれか?
巨大実験装置を共有する物理学や化学の研究室では、教授がテーマ設定を行い大学院生やポスドクが実験と解析を分担し、結果を連名で論文にする体制が伝統的に確立している。フランス文学や政治思想史など個人執筆が中心の文系研究と対照的である。近年は人文社会分野でも共同研究が進むが、ラボ文化の原型は理系の物理学研究室に由来する。
Q7 : フィールドワークとして裁判記録や法令の一次史料を精読する作業が不可欠なのはどの分野?
歴史学研究では史料批判と呼ばれる手続きで一次史料の信頼性を検証し、その文脈を読み解くために現地公文書館でのフィールドワークや古文書の翻刻を行う。電気工学や有機化学の実験室作業とは方法も目的も異なり、研究成果は史料の新解釈として論文や著書にまとめられる。従って裁判記録や法令資料を直接読む作業が不可欠なのは歴史学である。
Q8 : 大学入試で「数学III」を必修として課す学部系統はどれか?
数学IIIは微分積分を含む高度な数学で、理学部や工学部などの理系学部では物理現象の解析や設計計算に不可欠とされる。一方、文系学部では論理的思考力を測る目的で数学I・A、場合によっては数学II・Bまでで足りるとされることが多く、数学IIIを必修とする例はほとんどない。入試科目の違いは大学のカリキュラムで必要となる専門基礎の差を反映している。
Q9 : 研究論文でIMRaD構成が最も標準化されている分野はどれか?
IMRaD構成は生物学、医学、物理学など自然科学系の国際誌で標準化された形式で、実験方法と結果を明確に分離し再現性を高めることを目指す。歴史学や哲学など文系では資料解釈や論証が中心で、序論・本論・結論の自由な構成が多い。従ってIMRaDを徹底して採用するのは理系、とりわけ物理学など実証実験型の分野である。
Q10 : ロナルド・フィッシャーが開発した分散分析(ANOVA)が最初に普及した領域はどれか?
分散分析は英国の統計学者ロナルド・フィッシャーがロザムステッド農業試験場で作物の収量比較を行う際に考案した手法で、複数要因が連続量に与える影響を解析できる。農学実験から生物学、医学へと広がったため、最初に普及したのは理系である農学分野である。文化人類学や文学批評がANOVAを常用するのは現在でもまれで、応用は限定的である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は文系と理系の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は文系と理系の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。