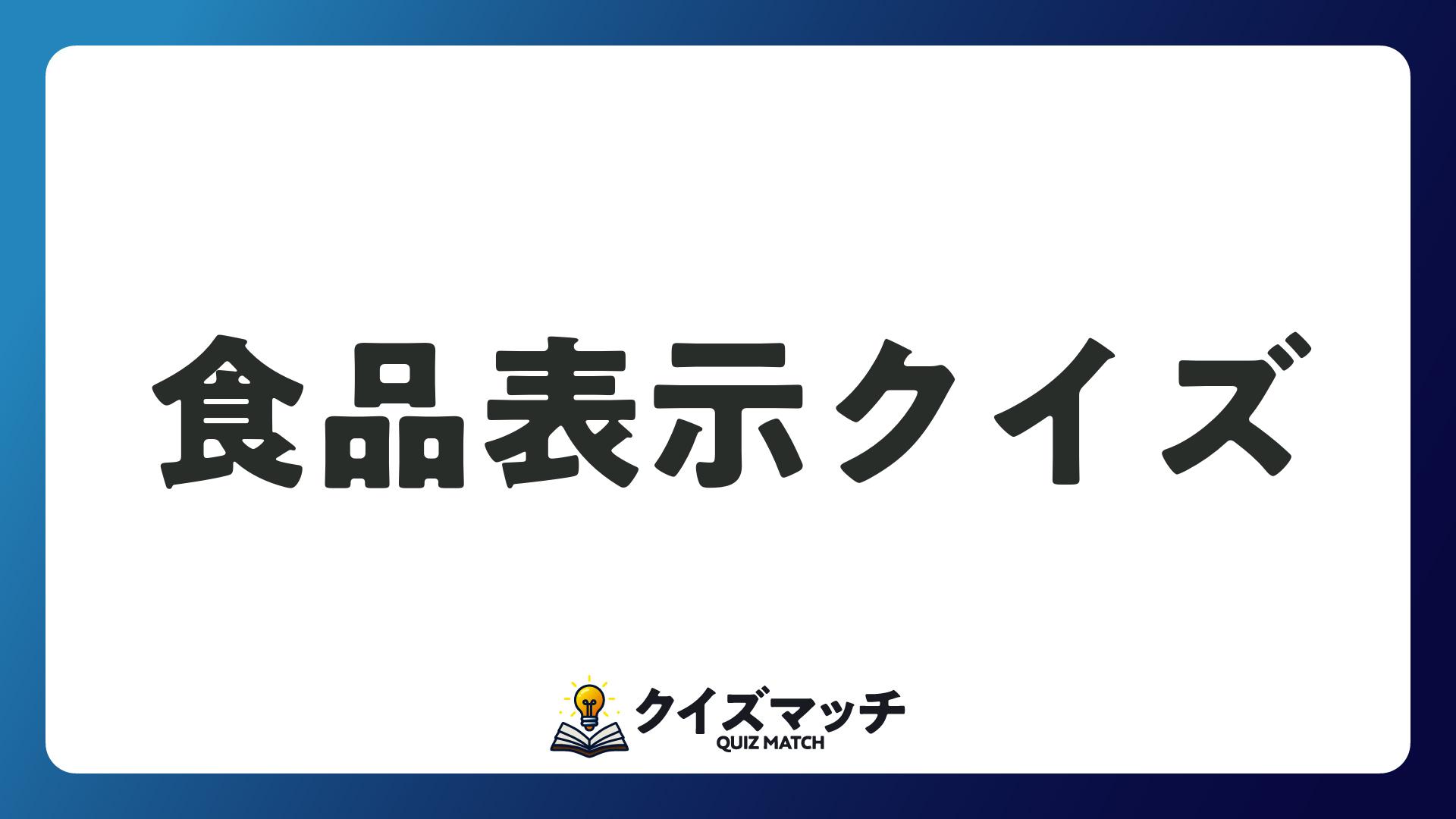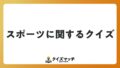食品表示に関する知識を深めましょう。今回のクイズでは、原材料の表示順序、産地表示、アレルギー表示、遺伝子組換え表示、期限表示、機能性表示、高たんぱく質表示、原料原産地表示、小さな容器包装での表示免除など、さまざまな食品表示の基準や義務についてチェックできます。食品表示に詳しくなれば、食品選びの際に役立つはずです。クイズを通して、自分の知識を確認し、理解を深めていきましょう。
Q1 : 遺伝子組換え農産物の義務表示における混入率の猶予基準(不検出とみなされる上限値)は何%か?
日本の遺伝子組換え表示制度では、主要原材料に意図せず混入した組換え体が重量比で5%以下であれば『遺伝子組換えでない』とみなせる猶予基準が設定されている。これは検査精度や流通段階での混入リスクを考慮した現実的な数値である。1%や3%では管理が難しく、10%では消費者保護の観点から緩すぎると判断された経緯があるため、現行法では5%が上限となる。
Q2 : 『要冷蔵』と表示された食品の保存温度として食品表示基準で定義されている範囲はどれか?
食品表示基準では要冷蔵品を0℃以上10℃以下で保存することと定義している。この温度帯は微生物の増殖を抑えつつ凍結を避けられるため、安全性と品質の両面で合理的である。-15℃以下は要冷凍の区分、1~5℃はチルドの目安、10~15℃は冷暗所程度を示すに過ぎず、いずれも法的定義の『要冷蔵』に当たらない。したがって0~10℃が正しい範囲となる。
Q3 : 品質が比較的劣化しやすく、日または時間で期限を示す必要がある期限表示はどれか?
食品表示基準では、製造からおおむね5日以内に品質が急速に低下し安全性に影響を及ぼす可能性のある食品には『消費期限』を付けるよう義務づけている。弁当や生菓子、サンドイッチなどが該当し、年月日あるいは時間で具体的に示す。『賞味期限』は長期保存が可能な食品に用いられ、期限を過ぎてもすぐに食べられなくなるわけではない。製造日や使用期限は期限表示の法的区分とは異なる。
Q4 : 機能性表示食品の届出において、科学的根拠として認められる方法はどれか?
機能性表示食品制度では、企業が消費者庁へ届け出る際に機能性に関する科学的根拠として①ヒトを対象にした臨床試験、または②既存論文を体系的に評価したシステマティックレビューの提出が義務づけられている。動物試験や未公開データは根拠として不十分で、公的サイト上で開示もできない。消費者アンケートは嗜好調査にすぎずエビデンスとして認められないため、選択肢3が正しい。
Q5 : 『高たんぱく』と表示するために必要なたんぱく質のエネルギー比基準として正しいものはどれか?
栄養成分強調表示で『高たんぱく質』を謳う場合、食品表示基準ではたんぱく質由来エネルギーが総エネルギーの20%以上である、または100g(ml)当たり10g以上含むという明確な数値基準が設けられている。5~15%では一般食品の範囲を超えず『高』と称することはできない。基準を満たさずに表示すると誇大表示とみなされ行政指導や回収の対象となるため、事業者は成分分析で20%以上を確認する必要がある。
Q6 : 2017年の改正により原料原産地表示が義務化された加工食品の範囲として正しいものはどれか?
平成29年の食品表示基準改正で、これまで任意だった多くの加工食品にも原料原産地表示が段階的に義務化され、業務用を除くほぼ全ての加工食品が対象となった。重量割合が最も高い原材料について国名や都道府県名などを表示する必要がある。ハムや米飯類だけに限定された制度ではなく、菓子や飲料も含む広範囲が対象であるため、メーカーは調達ロットごとに産地を特定し、適切な表示を行わなければならない。
Q7 : 栄養成分表示を省略できる『小さな容器包装』として定められている最大表示面積は次のうちどれか?
栄養成分表示は原則全ての加工食品に義務づけられているが、容器包装の最大表面積が30cm²以下しかない『小さな容器包装』では物理的制約を考慮し省略が認められる。30cm²を超える通常の缶や袋、アルコール飲料であっても基準を満たさない限り省略はできない。面積を測定せずに表示を省くと行政処分の対象となるため、事業者は実測値で可否を判断し、消費者に必要な栄養情報を提供する責任がある。
Q8 : 食品表示基準では、加工食品の原材料と添加物はどの順序で記載することが義務づけられているか?
食品表示基準では、原材料と添加物を区分せず、使用重量の多い順に一括して表示することが定められている。これにより消費者は含有量の多い原材料を容易に把握できる。カロリー順や五十音順では実際の配合割合と乖離し誤認を招く恐れがあるため認められない。旧制度で見られた添加物を先頭にまとめて列挙する方法も現行基準では不可であり、あくまで重量順で示す必要がある。
Q9 : 牛肉の個体包装製品の産地表示について、法律上正しい方法はどれか?
食肉の原産地は、出生地と肥育地が異なる場合でも累積飼養期間が最も長い場所を基準に決定する『最長飼養地』ルールが採用されている。単に「国産」と表記すると海外で一定期間飼育された牛も含まれる恐れがあり不十分である。出生地のみやと畜場所在地の表示では消費者が生産履歴を正確に把握できないため、法律は育成期間の長さを基にした表示を義務づけている。
Q10 : アレルギー表示が義務づけられている7品目に該当しないものはどれか?
食品表示法で義務化されている特定原材料はえび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生の7品目である。大豆は症例が多いものの、表示が推奨される『特定原材料に準ずる21品目』の一つであり義務表示ではない。えび・そば・卵は重篤な症状を起こす例が多いため必ず表示する必要がある。したがって大豆は7品目に含まれず、義務表示の対象外となる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は食品表示クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は食品表示クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。