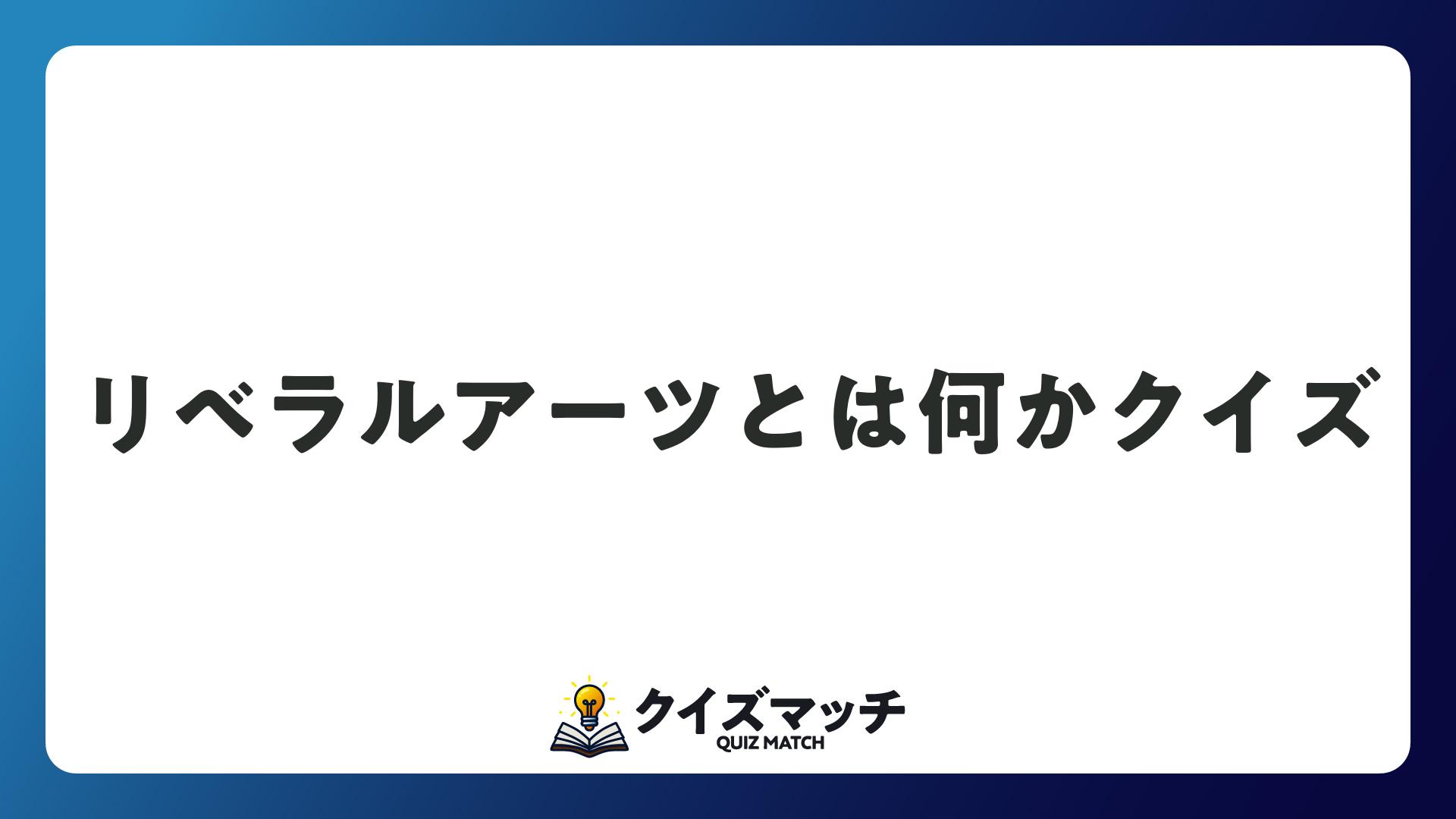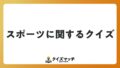リベラルアーツは、個人の自由や自治を基盤とする古代ギリシア・ローマの伝統から発展してきた教養教育の理念である。中世ヨーロッパではトリヴィウムとクアドリヴィウムに分類され、言語と論理、数と自然の探究を重視した。現代でも、専門教育だけでなく批判的思考力や異文化理解など、21世紀型スキルの育成にリベラルアーツ教育が注目されている。このクイズでは、このような歴史と概念を確認しながら、リベラルアーツの本質を問う。
Q1 : アメリカの『リベラルアーツ・カレッジ』の特徴として正しいものはどれか 少人数教育による幅広いリベラルアーツ教育を重視する 大規模な大学院研究に特化している 職業訓練にのみ絞ったカリキュラムを持つ スポーツアカデミーとしての色彩が最も強い
米国のリベラルアーツ・カレッジは学生数2000人前後の小規模学部教育機関が多く、専任教員との密接な対話型授業を通じて人文・社会・自然科学を横断的に学ばせることを理念とする。研究大学のように大学院教育を中心としたり、医療やビジネスなど職業資格取得に特化したりするわけではない。キャンパスライフでスポーツは推奨されるが目的ではない。したがって選択肢1が正しい。
Q2 : 『リベラルアーツ』七科を初めて系統的に整理し、学芸の女神物語として著したとされる5世紀頃の著作家は誰か プラトン マルティアヌス・カペラ トマス・アクィナス ルネ・デカルト
北アフリカ出身のラテン語作家マルティアヌス・カペラは『新婦フィロロギアと新郎メルクリウスの結婚について』という寓意書の中で七人の侍女として七自由学芸を擬人化し、後世の教育制度に大きな影響を与えた。そのリストが中世修道院や大学で採用されたことで、七科という枠組みが確立した。プラトンは古典期の哲学者、トマス・アクィナスは13世紀の神学者、デカルトは近世の哲学者であり該当しない。
Q3 : 伝統的リベラルアーツのクアドリヴィウムに含まれるものを次から選べ 哲学 法学 数学 外科学
クアドリヴィウムは算術(Arithmetic)、幾何(Geometry)、音楽(Musica)、天文学(Astronomia)の四学で、いずれも数をさまざまな角度から扱う点が共通する。数学は算術と幾何を総称する言い方としてここに含まれる。哲学や法学は古代以来重要だが七自由学芸には入らず、外科学のような医療技術はむしろ職業的実学である。したがって選択肢3が正解となる。
Q4 : 日本の戦後大学改革で『教養部』や『一般教育』の設置を促し、リベラルアーツ教育の導入を強く勧告した報告書を提出したのはどの機関か 文部省による明治期学制調査 大正デモクラシー期帝国議会 GHQによる『人間宣言』 アメリカ教育使節団報告書
1946年に来日したアメリカ教育使節団は、占領下の日本の教育制度を調査し、『Report of the United States Education Mission to Japan』を提出した。同報告書は専門学校的で縦割りだった旧制大学を改組し、一般教育課程を導入して幅広い教養を最初の2年間で学ばせる方式を提言した。この方針が新制大学の教養部創設やリベラルアーツ科目の拡充につながった。よって選択肢4が正解である。
Q5 : OECDなど国際機関が21世紀型スキルとしてリベラルアーツ教育に求める能力として最も重視されるものはどれか 特定職業に特化した技能習得 単一学問の深い専門性のみ 批判的思考力と異文化理解の育成 AIに全てを任せる能力
第四次産業革命が進む現代では、知識の陳腐化が速く、一つの職能技能だけでは長期的なキャリア形成が難しい。このためOECD国際学力調査や各国の大学改革では、複数分野を横断する知識を統合し、自ら問いを立て検証できる批判的思考力、異文化・異分野の協働を可能にするコミュニケーション力をリベラルアーツ教育で育むことを強調している。選択肢3がそれに該当する。
Q6 : 次の組み合わせのうち、リベラルアーツ七科と内容の対応として誤っているものはどれか Grammatica―言葉の構造を理解し表現する学問 Rhetorica―説得的な表現方法を学ぶ学問 Musica―音と数の比例関係を研究する学問 Logica―天体の運行法則を研究する学問
七自由学芸は言語を扱うトリヴィウム(Grammatica, Rhetorica, Dialectica/Logica)と数を扱うクアドリヴィウム(Arithmetica, Geometria, Musica, Astronomia)の計七科から成る。Logicaは推論や議論の妥当性を扱う学問であり、天体を研究するのはAstronomiaである。したがって選択肢4の対応だけが誤りで、他の三組は正しい対応関係となる。
Q7 : 古代ギリシア・ローマで「リベラルアーツ」が重視された理由として最も適切なのはどれか 自由市民が公共的議論や政治参加を行うための基礎能力を養う 主に奴隷の職業訓練を行うため 神官が秘儀を伝授するための学問 軍事戦術を専門的に学ぶため
古代の自由民はポリスやフォルムでの討論を通じて共同体を方向づける責任を負っていた。そのため、文法・修辞・論理など言語と論証の技法、数や音の理論を学ぶことが身分の証であり義務でもあった。これらは「自由人にふさわしい学芸」(artes liberales)と呼ばれ、肉体労働や兵士の訓練といった実用教育とは区別された。よって選択肢1が正しい。
Q8 : 中世ヨーロッパでリベラルアーツはトリヴィウムとクアドリヴィウムに分けられた。次のうちトリヴィウムに含まれないものはどれか 文法学 幾何学 修辞学 論理学
トリヴィウムは言語運用に関わる三学で、文法(Grammatica)、修辞(Rhetorica)、論理または弁証法(Dialectica)の総称である。一方、数の学であるクアドリヴィウムは算術、幾何、音楽、天文学の四学から構成された。幾何学はクアドリヴィウム側に属するため、トリヴィウムに含まれない選択肢2が正解である。
Q9 : クアドリヴィウムに含まれる学問のうち、天体の運行を観測し理論化するものは何か 音楽 文法学 天文学 修辞学
クアドリヴィウムは数の性質を四つの側面で探究する学問群で、算術が数そのもの、幾何が空間における数、音楽が時間における数、天文学が時空における数の応用と説明される。天球の運行や惑星の周期を計算し、宇宙の秩序を数理で理解しようとする天文学は典型的なクアドリヴィウム科目である。文法や修辞は言語学でありトリヴィウムに属する。したがって選択肢3が正解となる。
Q10 : リベラルアーツを日本語で表すとき、一般に使われる語として適切でないものはどれか 教養 自由学芸 リベラルアーツ 工学
日本ではリベラルアーツを「教養」「自由七科」「自由学芸」などと翻訳してきたほか、外来語のまま用いることも多い。一方、工学は近代以降に派生した実用的・職業的技術教育を指す専門分野であり、伝統的にリベラルアーツの枠外とみなされてきた。よって選択肢4の「工学」のみが不適切である。
まとめ
いかがでしたか? 今回はリベラルアーツとは何かクイズをお送りしました。
今回はリベラルアーツとは何かクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!