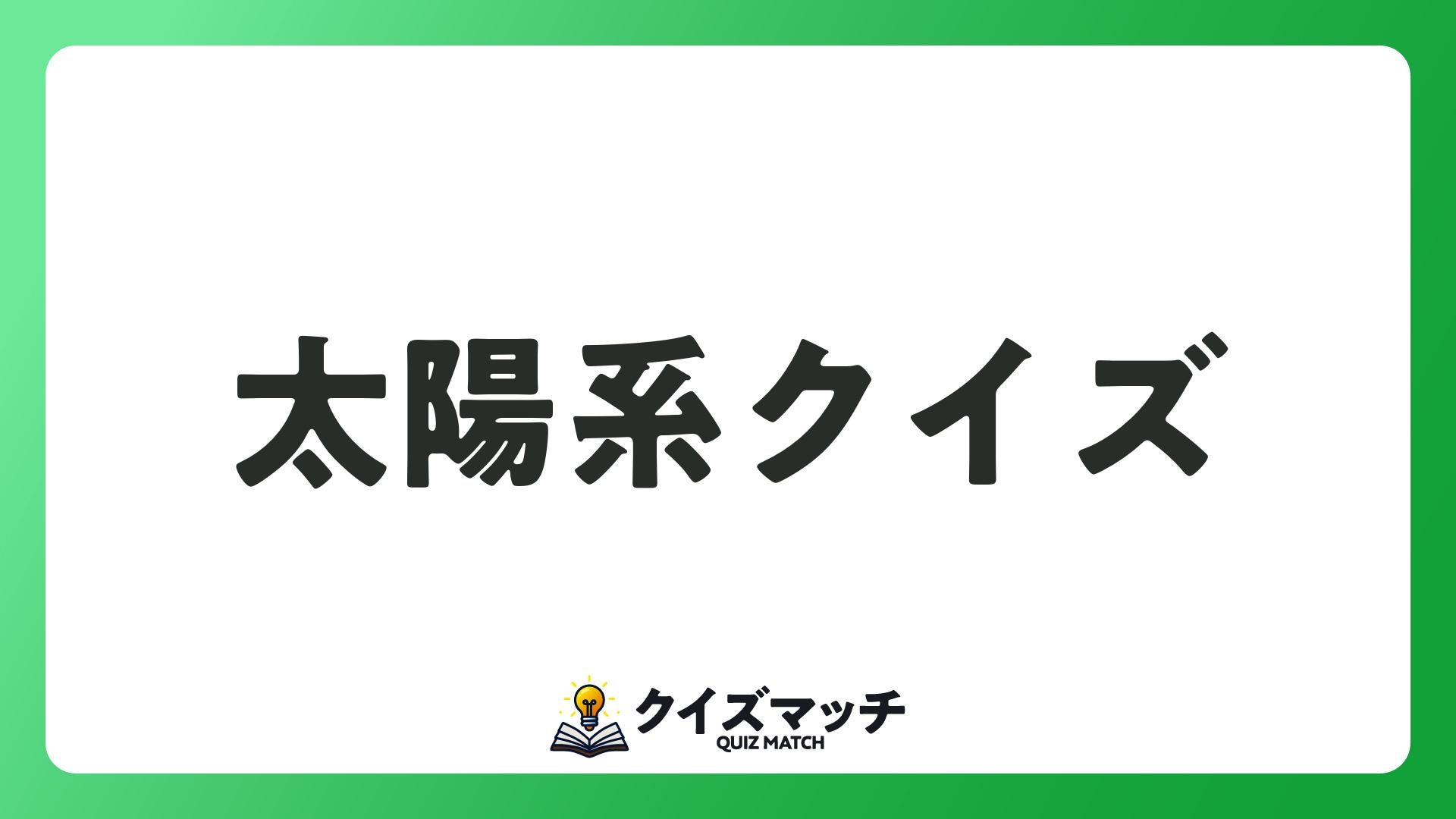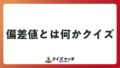太陽系の知識を深めるべく、10個の充実したクイズをお届けします。惑星の質量や大きさ、温度、周期といった基礎的なデータから、稀少な天体や特異な現象まで、多岐にわたる内容となっています。太陽系の概要を一通り理解できるよう、様々な角度からアプローチしています。クイズを通じて、私たちの住む宇宙に対する理解をさらに深めていただければ幸いです。
Q1 : ハレー彗星の公転周期はおよそ何年か?
ハレー彗星は周期約75~76年の短周期彗星で、古代から複数回にわたり記録された希少な肉眼彗星である。54年や65年では近日点通過が合致せず、150年以上なら長周期彗星に分類される。軌道は強い楕円で遠日点は冥王星軌道付近、近日点は地球軌道の内側まで達する。木星や土星の重力擾乱で周期は微調整されるが、紀元前から現代に至るまで70年台中盤で安定していることが歴史資料と天体力学計算で確認されている。次回の予想出現は2061年で、多数の探査機計画が検討されている。
Q2 : 自転軸が約98度傾いており横倒しで回転している惑星はどれか?
天王星は自転軸が公転面に対して約97.8度傾いており、ほぼ真横になった状態で自転している。金星は自転方向が逆だが軸の傾きは小さく、海王星は29度、水星は0.03度とさらに小さい。天王星の極端な傾斜は巨大衝突による説が有力で、84年の公転周期のうち半分近くを極夜もしくは白夜状態で過ごす。これに伴い大気循環や磁気圏は特異な挙動を示し、ボイジャー2号やハッブル宇宙望遠鏡の観測から季節変動の様子が徐々に明らかになっている。
Q3 : ボイジャー1号が最初にフライバイ観測を行った巨大惑星はどれか?
ボイジャー1号は1977年に打ち上げられ、重力アシストを利用するグランドツアー計画の第一歩として1979年3月に木星へ到達した。木星では大赤斑の詳細画像、イオの火山活動、エウロパの氷殻などを撮影し、惑星科学に革命をもたらした。その後土星系を1980年に通過しタイタンを探査したが、天王星と海王星には向かわずに太陽系外へ進んだ。木星でのフライバイは軌道変更と科学観測の双方で重要な意味を持ち、現在ボイジャー1号は恒星間空間を航行中である。
Q4 : 太陽風と地球磁気圏との相互作用で生じる発光現象はどれか?
オーロラは太陽風の荷電粒子が地球磁気圏に捕捉され、極域の上空で酸素や窒素を励起して発光する現象で、緑色や赤色のカーテン状の光として知られる。流星は宇宙塵が大気に突入して発光する別現象であり、日食や彩雲も太陽光の遮蔽や回折による光学現象で機構が異なる。磁気圏が強くない金星や火星では大規模なオーロラは見られず、地球独特の魅観光でもあるが、同時に磁気嵐時には通信障害や人工衛星への悪影響、送電網の誘導電流など社会インフラへ実害を及ぼすため、宇宙天気の監視対象となっている。
Q5 : 地球の質量に最も近い惑星はどれか?
金星の質量は地球の約0.815倍で、太陽系の岩石惑星の中では地球に最も近い数値となる。火星の質量は0.107倍、水星は0.055倍と大幅に小さい。海王星は氷巨惑星で約17倍とずっと大きい。質量だけでなく直径も地球と金星はほぼ同等で、かつて双子惑星と呼ばれたこともある。しかし金星の濃厚な二酸化炭素大気と強烈な温室効果により表面温度は約460℃に達し、地球とは対照的な灼熱の世界となっている点が重要である。
Q6 : 太陽系で最大の衛星はどれか?
太陽系で最大の衛星は木星の衛星ガニメデで、直径は約5262kmに達し水星よりも大きい。土星の衛星タイタンはほぼ同等で直径5150kmだが僅差で届かない。カリストは4820kmで3位、月は3474kmでさらに小さい。ガニメデは鉄でできた核と塩水の海を覆う氷殻を持つと考えられ、内部磁場を保有する唯一の衛星でもある。質量はタイタンよりやや小さいが体積が最大であるため、現在の定義では太陽系最大の衛星とされている。
Q7 : 太陽の光球面温度に最も近い値はどれか?
太陽の可視表面である光球の温度は平均約5800Kで、スペクトル型G2Vの基準ともなる。4000Kや5000Kでは赤色または橙色の恒星、7000Kでは白色のA型星に相当し太陽とは異なる。5800Kの黒体放射はピーク波長が約500nmで、緑付近にエネルギー最大値があるが全可視域にわたり放射するため白く見える。外層のコロナは100万Kを超えるが薄いため光度は低く、日食時にしか見えない。太陽の温度構造を理解することは太陽活動や地球環境への影響を評価するうえで不可欠である。
Q8 : 太陽系の惑星で公転周期が最も長いのはどれか?
海王星は太陽から平均約30天文単位離れており、ケプラーの第三法則で距離が大きいほど公転周期が長くなるため、8惑星中最長の約164.8年を要する。火星は1.88年、木星は11.86年、天王星でも84年にとどまる。1846年の発見以来まだ一周していないほど長い周期で、人類がその気象変動の全貌を観測するにはさらに数十年を要する。長い公転周期は太陽から受けるエネルギーが少ないことを意味し、大気や気象が他惑星と大きく異なる原因の一つとなっている。
Q9 : 2006年に冥王星が再分類された天体の種類は何か?
2006年の国際天文学連合総会で、惑星に求められる条件として軌道領域を支配していることが追加された。冥王星は同程度の外縁天体が多数存在するため条件を満たさず、準惑星へ再分類された。同時にケレスやエリスも準惑星に指定された。冥王星は直径約2376kmで月より小さいが、窒素やメタンの薄い大気と多様な地形を持つことがニューホライズンズ探査で判明し、依然として科学的価値は極めて高い。再分類は冥王星の地位を下げるものではなく、太陽系外縁の理解を深める契機となった。
Q10 : 太陽系最大の火山オリンポス山が存在する天体はどれか?
オリンポス山は火星のタルシス高地に位置するシールド火山で、高さ約22km、裾野の直径600km以上という規模は地球のエベレストの2.5倍を超える。月や水星にも古い火山跡はあるが、これほど巨大な山体は形成されていない。イオは現在も活発な火山活動を示すが、低重力と異なるマグマ性質により山の高さは抑えられる。火星ではプレート運動がほとんどなく、同じ場所から長期間マグマが供給されたこと、低重力で山体が崩壊しにくいことがオリンポス山を巨大化させた要因と考えられている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は太陽系クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は太陽系クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。