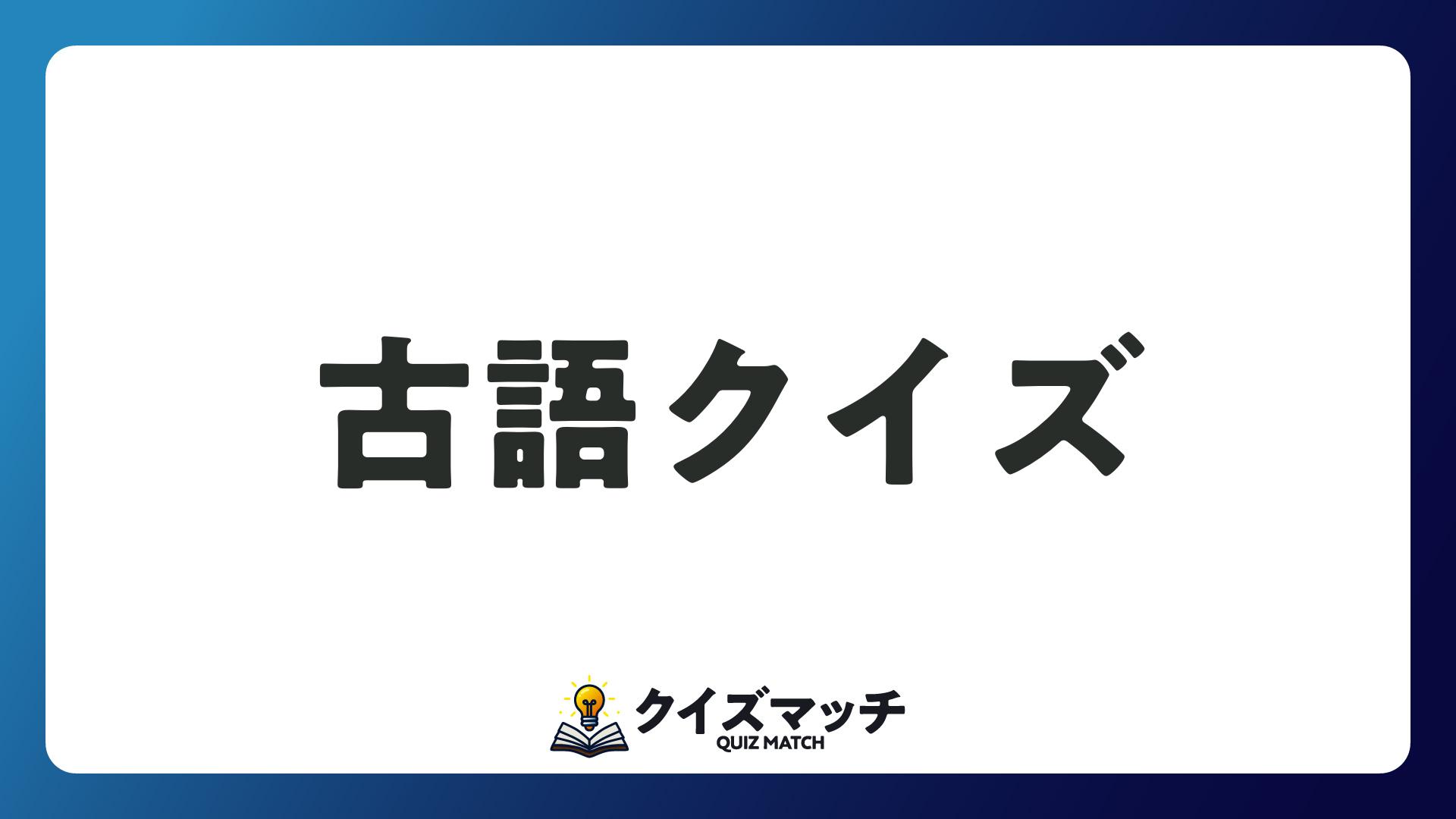古語に込められた美しい言葉の世界を味わってみませんか。平安時代の文学作品に数多く登場する古語には、深い知性と繊細な感性が宿っています。本記事では、あなたに10の古語クイズを用意しました。平安文化の精神性に触れながら、言葉の奥深さと変遷を探ってみましょう。古語の魅力に迷い込むかもしれませんが、思わず心奪われるはずです。さあ、古語の世界にいざなわれるがままに、その妙韻に身を委ねてみてください。
Q1 : 動詞「まどふ」の現代語訳として最も適切なものはどれか。
「まどふ」は四段活用の動詞で、原義は心や体が乱れて思うようにならないこと。そこから「途方に暮れる」「うろたえる」「迷う」「あわてふためく」などの意味で広く用いられる。『更級日記』の「いみじくまどひて泣きたまふ」では悲嘆のあまり取り乱す場面を表現し、単なる疑いではなく感情の混乱が強調されている。喜びや依存、誓約を示す語ではないため、選択肢4「迷う・うろたえる」がただ一つ正解となる。語幹から派生する「まどはす」(他動)との違いにも注意したい。
Q2 : 形容詞「やむごとなし」の語義として正しいものはどれか。
「やむごとなし」は「止(や)む事無し」が語源で、本来はやめることができないほど重要である意。転じて「格別だ」「高貴だ」「大切である」といった意味で用いられる。『源氏物語』では高位の人物を形容するのに頻出し、「やむごとなき際の人」(身分の高い人)のように尊貴さを示すキーワードとして機能する。現代語の「やむを得ない」と混同してしまうと意味を取り違えるため注意。したがって最も適切なのは選択肢1である。
Q3 : 形容動詞「つれづれなり」の意味として最も適切なものはどれか。
「つれづれなり」は平安から鎌倉期にかけて日記・随筆で多用された語で、①することがなく退屈だ、②物思いに沈みしんみりする、の2大義がある。『徒然草』という書名もこれに基づき、吉田兼好が暇を持て余しながら心に浮かぶことを書き綴った姿勢を示している。静けさ自体をいう語ではなく、騒がしさや激しさとも無関係であるため、所在なさや退屈を端的に表す選択肢3が正答。古典の心情表現を理解する上で欠かせないキーワードである。
Q4 : 動詞「はべり」の本来の敬語の種類として正しいものはどれか。
「はべり」はラ変動詞で、もとは身分の高い人のそばに「仕える」ことを意味し、その点で謙譲語(謙譲語Ⅰ)の性格を持つ。後に動詞の語尾的に用いられ、「〜でございます」「あります」と話し手が自分を低めつつ丁寧に述べる用法も派生したが、歴史的敬語区分では最初に覚えるのは謙譲語である。尊敬語は対象を高める語で用法が異なり、美化語や丁寧語とも分類が異なる。源氏物語「宮にさぶらひたまふ」などに見られるように、仕官・伺候の意味が原義となる。
Q5 : 形容詞「いみじ」を肯定的に用いた場合のもっとも適切な訳はどれか。
「いみじ」は語幹に「甚し」を持ち、程度のはなはだしさを示す形容詞で、文脈により良い意味にも悪い意味にもなる。肯定的な用法では「たいそうすばらしい」「この上なく立派だ」の意、否定的な用法では「ひどい」「おそろしい」と訳す。平安文学では感動詞的に「いみじ」とだけ挟み込み賞賛を示すこともしばしばある。今回の問題では肯定的な場合を指定しているので、程度の大きさと評価の高さを合わせ持つ選択肢4が正解となる。他の選択肢は意味域が異なる。
Q6 : 古語「いかで」の基本的な意味として正しいものはどれか。
「いかで」は平安期の文学作品に頻出する副詞で、主に疑問・反語の用法で「どうして」「どのように」、希求・願望の用法で「なんとかして」の意を示す。学校文法ではまず「どうして」という疑問語義を学ぶため、今回の設問ではそれを正答とした。『枕草子』「いかでこの世に長らへむ」では反語、『徒然草』「いかで月を見む」では願望と、文脈によって役割が変わる語であることにも留意したい。
Q7 : 形容詞「かしこし」の語義として最も適切なものはどれか。
「かしこし」は語幹に畏怖・敬意を含む形容詞で、原義は「恐ろしくすばらしい」。そこから派生して①畏れ多い、尊い、②すぐれている、③利口だ、④はなはだしいなど複数の訳があるが、もっとも一般的で初学者がまず覚えるのは「畏れ多い」である。『源氏物語』では帝や女御に対して「いと かしこし」と用い、対象の尊貴さを表す。現代語の「賢い」と混同しやすいため注意が必要だ。
Q8 : 古語「をかし」が表す感情にもっとも近い現代語訳はどれか。
『枕草子』の冒頭「春はあけぼの」に代表されるように、「をかし」は平安文学の美意識を象徴する語で、「趣があって心ひかれる」「おもしろい」「風情がある」という肯定的ニュアンスが中心である。中世以降に成立する「わび」「さび」とはまた異なり、軽やかで明るい感動を示すのが特徴。否定的な意味や悲哀の感情は含まないため、選択肢の中では一語でニュアンスを捉えている「趣がある・おもしろい」が最適となる。
Q9 : 助動詞「む」が終止形で文末に置かれた場合、もっとも基本的に表す意味はどれか。
助動詞「む(ん)」は未然形に接続し、文脈によって推量・意志・適当勧誘・婉曲・仮定など多義的に用いられるが、古文読解でまず押さえるべき中心義は「主語の未来を推量する」用法である。文末に置かれると主語が一人称以外でも「〜だろう」という推量が最も自然に立つため、本設問ではこれを正答とした。『竹取物語』「今はとて天の羽衣を着る時ぞ来む」など、終止形で未来を予測する例は多く、意志用法(主語が一人称)や婉曲用法(連体形)との識別が受験で頻出である。
Q10 : 形容詞「あさまし」の意味として正しいものはどれか。
「あさまし」は感情を強く揺さぶられる際に用いられ、現代語の「浅ましい」とは異なり平安期には「意外なことに驚き呆れる」「あまりにひどい」「嘆かわしい」といった驚愕のニュアンスを中心に持つ。たとえば『大鏡』では思いがけない出来事に対して「いみじうあさまし」と用い、予想を超える様子を描写する。選択肢の2はこの広い驚愕義を端的にまとめており、他の選択肢は語義と一致しない。現代語との意味のズレを確認しておくことが重要である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は古語クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は古語クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。