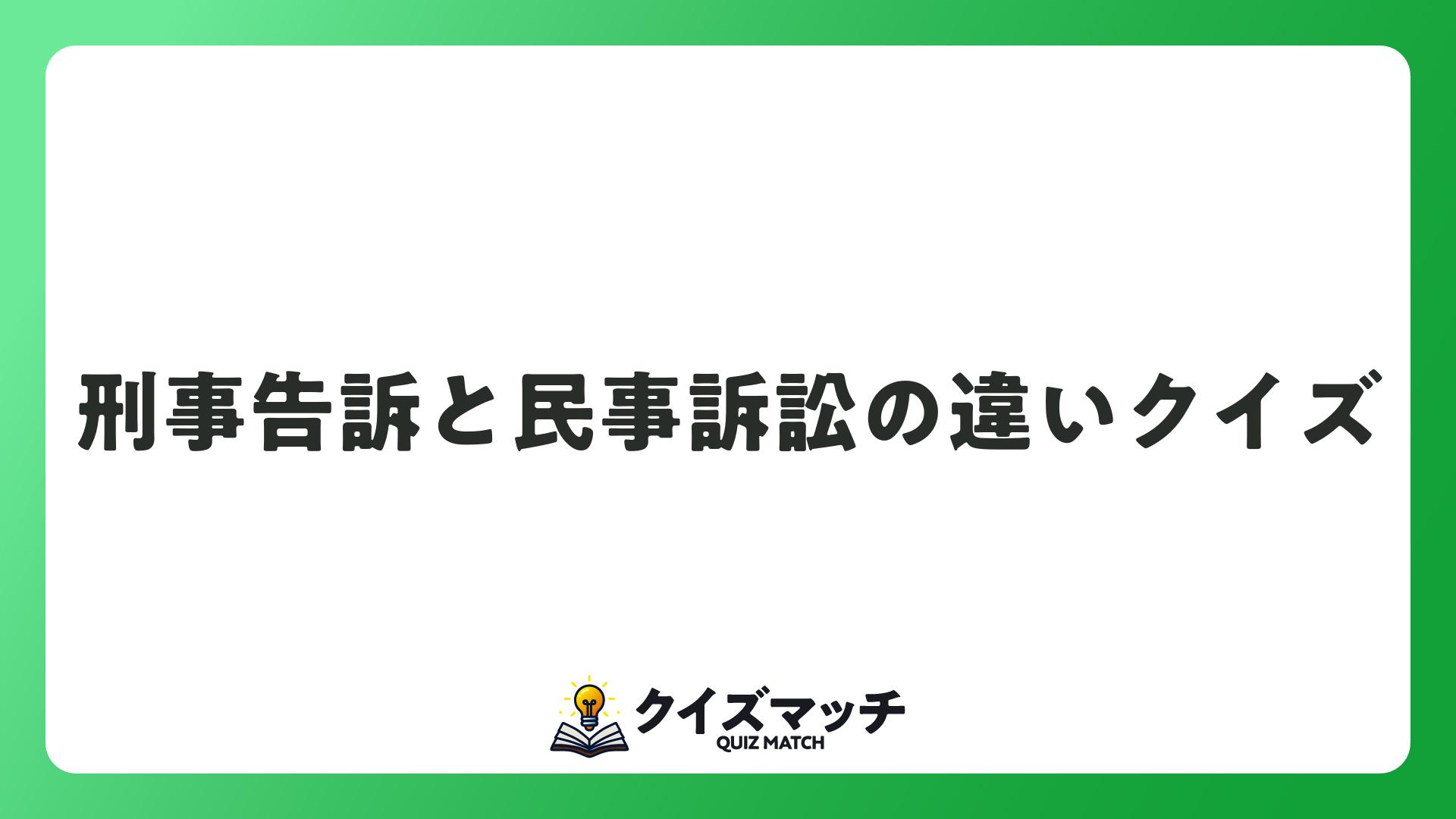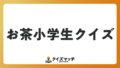刑事告訴と民事訴訟の違いを理解することは、法的紛争の解決を図る上で重要です。この記事では、10問のクイズを通して、両者の差異を詳しく学ぶことができます。刑事手続は公益性が強く、国家による犯罪の取り締まりを目的としています。一方、民事訴訟は私人間の経済的な権利関係の調整を主眼としています。このような根本的な違いが、証明度基準や時効期間、手続の進め方など、様々な点に反映されています。本クイズでは、これらの相違点を具体的に確認することができるでしょう。法律を正しく理解し、適切な紛争解決策を選択するためのヒントが得られるはずです。
Q1 : 民事訴訟で原告が請求を取り下げたり和解で終了させたりできる根拠となる原則はどれか
民事訴訟では当事者が訴えを起こし請求の範囲を定め和解や取下げによって訴訟の帰趨を決定できる。これを処分権主義と呼び、私人間の経済的紛争という性格から裁判所は当事者の意思に従って手続を終結させることができる。一方刑事手続では公益性が強く検察官は犯罪が認められても社会的事情を考慮して起訴猶予にするなど裁量があるが、起訴後に公判を取り消すことは例外で個人の意思だけでは手続を止めることができない。処分権主義は民事の特徴を鮮明に示す原則である。
Q2 : 訴額が140万円を超える損害賠償請求事件の第一審を管轄する裁判所はどれか
民事訴訟法では訴額140万円を超える請求は地方裁判所が第一審管轄となり140万円以下は簡易裁判所となる。地方裁判所には民事部と刑事部があるが損害賠償のような一般民事事件は民事部が担当する。家庭裁判所は家事事件や少年事件を扱い高等裁判所は控訴審を担う。したがって140万円を超える損害賠償訴訟の第一審として適切なのは地方裁判所である。この区分は事件の規模に応じた迅速かつ適切な審理を図るために設けられている。
Q3 : 告訴期間が存在する親告罪の具体例として正しいものはどれか
親族間の窃盗や業務上横領など一定の身分関係に基づく財産犯は刑法244条などにより親告罪と定められる。親告罪では被害者が犯人を知った日から6か月以内に告訴しなければ告訴権が消滅し国家は公訴を提起できない。殺人や放火は重大犯罪として非親告罪であり期間制限は設けられていない。詐欺も非親告罪である。よって告訴期間の例として典型的なのは親族間の窃盗でありこの点は民事請求に告訴期間という概念が無いことと対照的である。
Q4 : 民事判決が確定しても相手が任意に支払わない場合、原告が権利実現のために裁判所へ行うべき手続はどれか
民事判決が確定しても相手方が自発的に支払うとは限らないため勝訴した側は強制執行手続を利用して債務名義を基に相手の財産を差し押さえる必要がある。確定判決や和解調書は民事執行法上の債務名義となりこれに基づいて裁判所に差押えや競売を申し立てる。刑事判決のように国家が直ちに刑罰を科す仕組みとは異なり民事では当事者の申立てが不可欠である。再審請求や検察官への申立ては刑事の制度であり仮処分は暫定的保全措置である。
Q5 : 軽微事件で前科を付けずに手続を終結させる刑事処分として、民事訴訟の和解に機能が近いものはどれか
軽微事件で検察官が起訴せず将来の更生を促すために行う起訴猶予処分は民事訴訟における和解と同じく正式裁判に至らず手続を終結させる点で類似する。起訴猶予が決定すると前科は付かず刑罰は科されないが、再度の犯罪や社会的影響があれば後に起訴される可能性も残る。略式命令は有罪判決であり公判請求や強制起訴はむしろ手続を進める行為なので和解的要素はない。刑事と民事で終結の形態が異なることを押さえる必要がある。
Q6 : 刑事告訴を行うことができる主体として最も適切なのはどれか
刑事告訴とは犯罪事実を捜査機関に申告し処罰を求める意思表示であり刑事訴訟法230条以下で告訴権者が限定されている。被害者本人またはその法定代理人などが行えば正式な告訴として受理され警察や検察は捜査義務を負う。一方被疑者本人が自らを処罰してくれと言っても告訴は成立せず裁判所や銀行など第三者が行っても単なる参考情報で正式な告訴にはならない。したがって適法な告訴を行えるのは被害者側である。
Q7 : 民事訴訟における事実認定の証明度基準として一般的に用いられるものはどれか
民事訴訟は私人間の権利義務を調整する制度であり処罰を目的としないため証明度は刑事より緩やかである。裁判官が証拠を総合した結果真実である可能性が50パーセントをわずかに超えれば立証ありと扱うのが優越的蓋然性の原則である。刑事の合理的疑いを超える証明はほぼ確信が求められるため水準が大きく異なる。この差により刑事で無罪でも民事で損害賠償責任が認められる事例が現実に存在する。
Q8 : 不法行為に基づく損害賠償請求権について、行為時からの長期消滅時効期間として正しいものは何年か
不法行為に基づく損害賠償請求権の時効は改正民法724条で二本立てになっており被害者が損害と加害者を知った時から3年で消滅するのが短期消滅時効であるが長期の除斥期間として不法行為時から20年で権利は消滅する。したがって加害者を特定できず長期間経過した場合でも20年を経過するまでは訴えを起こす余地がある。刑事の公訴時効が成立しても民事で20年以内であれば損害賠償請求は可能という点が両制度の差異を示す。
Q9 : 被害者が加害者に金銭的補償を直接求めることを主目的とする手続はどれか
刑事告訴や検察審査会申立ては国家の刑罰権行使を促す手段であり被害者が直接金銭を得る場面は想定されていない。これに対し民事訴訟は私人間の紛争解決を目的とし訴訟物は損害賠償や契約履行など経済的請求が中心である。実際に勝訴判決が確定すると被害者は加害者の財産に強制執行を掛けて損害賠償金を回収できる。刑事にも被害者参加制度や損害賠償命令制度があるが例外的で本来の補償手段は民事である。
Q10 : 刑事事件が不起訴となった後、被害者が損害の回復を図るために通常選択する手段はどれか
検察官が不起訴と判断した場合国家は刑罰権を行使しないが被害者の損害が消えるわけではない。刑事とは独立して存在する損害賠償請求権を行使するためには民事訴訟を提起することが一般的な選択肢となる。民事の手続では被告に対し慰謝料や財産的損害の賠償を求めることができ刑事責任の有無とは別個に審理される。再度告訴をしても検察の判断が覆る保証はなく、陪審制度は日本に存在せず恩赦は刑罰軽減に過ぎないため損害回復には適さない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は刑事告訴と民事訴訟の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は刑事告訴と民事訴訟の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。