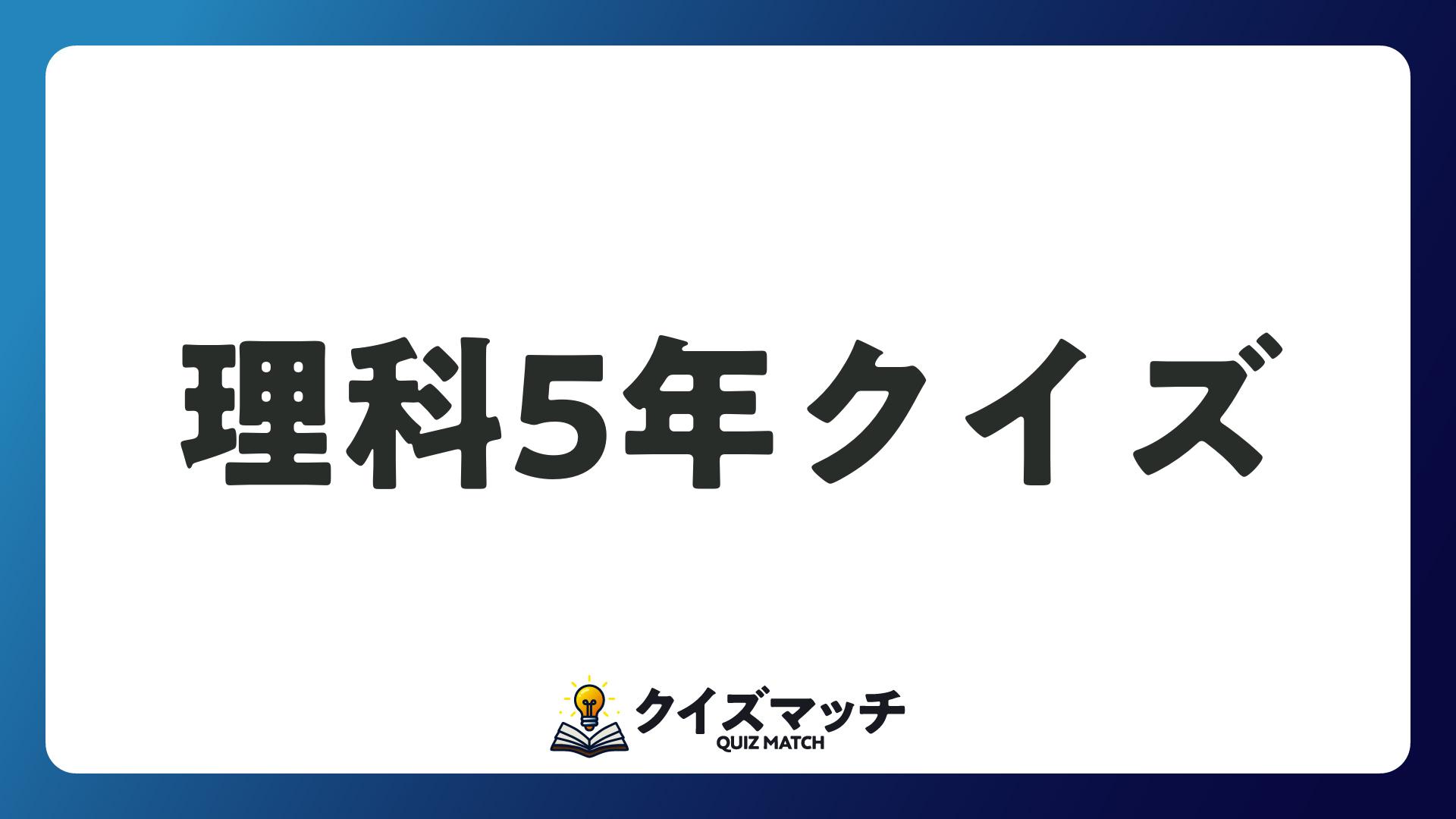理科5年生を対象とした10問の楽しい「理科5年クイズ」をお届けします。植物の受粉から地球の自転、電流の性質、磁石の性質、水の状態変化、水循環、月の見え方、生態系の仕組みなど、小学校5年生で学習する様々な理科分野の基礎知識を確認できるクイズばかりです。楽しみながら理科の面白さや不思議さを再発見してみてください。思わぬ発見があるかもしれません。さあ、さっそくクイズにチャレンジしましょう!
Q1 : 月が地球と太陽の間に入り一直線に並んだときに見える月の形はどれ?
月の公転により地球から見える月の明るい側面の割合が変化し、これを月相と呼ぶ。月が地球と太陽の間に来ると月の昼側は地球と反対側を向き、私たちには暗い夜側だけが向くためほとんど見えない。この状態が新月である。満月は逆に地球が月と太陽の間に位置し月全体が明るく見える。半月は上弦や下弦と呼ばれる直角配置のとき、皆既月食は満月時に地球の影が月を覆う現象で新月とは別である。
Q2 : 森林の食物連鎖で一次消費者に分類される生き物はどれ?
一次消費者は植物が光合成で作った有機物を直接食べる草食動物や草食性昆虫で、食物連鎖において生産者の次に位置する。森林ではシカやウサギ、カブトムシの幼虫などが該当し、彼らが蓄えたエネルギーは上位の肉食動物へ受け渡される。キツネやオオカミは肉食の二次以降の消費者、トンボの成虫も小昆虫を捕食するため同様に上位段階である。一次消費者が減少すると連鎖全体のエネルギー供給が不足し生態系の安定が損なわれる。
Q3 : 水溶液の酸性・中性・アルカリ性を簡単に調べるために小学校でよく使われる指示薬はどれ?
BTB溶液は酸性で黄色、中性で緑、アルカリ性で青と三段階にはっきり色が変わる万能型の指示薬で、理科実験で水溶液の性質を直感的に判定できる。紙のリトマス試験紙より色の変化幅が広く、弱酸や弱アルカリの差も確認しやすい。食塩と砂糖は無色の固体で指示薬の働きを持たず、強アルカリ性の水酸化ナトリウムは調べる対象そのもので危険が伴う。BTB溶液なら安全に酸性度を観察できる。
Q4 : 地球が1日に1回自転することで起こる現象はどれ?
地球は自転軸を傾けたまま西から東へ約24時間で1回転しているため、同じ地点が太陽側と夜側を順に向き昼と夜が定期的に交替する。四季の変化は公転と地軸傾斜の組み合わせ、月の満ち欠けは月の公転周期、流星群は宇宙の塵が大気に突入する現象で自転とは直接関係しない。自転が止まれば昼夜の周期も失われることから、自転がもたらす影響の大きさが分かる。
Q5 : 豆電球をより明るく点灯させる方法として最も適切なのはどれ?
豆電球の明るさは回路を流れる電流と電圧に左右される。乾電池を直列に接続すると電圧が足し合わされ高くなるので電流が増え、フィラメント温度が上がり光が強くなる。並列接続は電圧を変えず容量だけを増やすので明るさにはほとんど影響しない。導線を長くしたり抵抗器を入れると回路抵抗が大きくなり電流が減少するため逆に暗くなる。これらの違いを実験で確かめると電気の性質が理解しやすい。
Q6 : 日本の北半球中緯度地域で南中時の太陽が見える方角はどれ?
北半球では太陽は東から昇り南側の空を通って西に沈む。南中とは太陽が一日のうちで最も高い位置に来る瞬間を指し、この時方位は必ず真南になる。夏至の日は南中高度が一年で最も高く影が短いが、方位が南であることは季節にかかわらず変わらない。北半球で南中時に北の空に太陽が見えることはなく、東や西は日の出・日の入りの方角である。南半球では逆に北側を通るので比較すると理解が深まる。
Q7 : 磁石の極に関する性質として正しいものはどれ?
磁石にはN極とS極の二つの極があり、同じ極同士を近づけると反発し合い、異なる極同士では引き合う。この現象は磁力線がNからSへ向かって連続していることに起因し、異極間では磁力線がつながり力が互いを引き寄せる方向に働く。地球も巨大な磁石でN極は地理的には北を指す。実験で棒磁石を切ると必ず両端にNとSが現れ、単独の極だけを作れないこともこの性質を裏付ける。
Q8 : 水が沸騰しているとき、加えられた熱エネルギーは主に何に使われる?
水は100度に達すると一定圧力下では温度がほぼ変わらず沸騰が続く。外部から与えられる熱は分子間の結合を断ち切り液体を気体に変える潜熱として吸収されるため温度が上がらない。これを気化熱あるいは蒸発熱と呼ぶ。もし熱が温度上昇に使われるなら100度を超えてしまうが実際にはそうならない。質量や凝固とは関係せず、やかんの蓋を持ち上げる蒸気の勢いも潜熱が分子運動に変わった結果である。
Q9 : 水循環で海から蒸発した水蒸気が冷やされ雲になる過程を何という?
空気中の水蒸気は上空で気温が下がると飽和水蒸気量を超え余分な水分が微小な塵に付着して液体の水滴に変わる。この気体から液体へ戻る現象を凝縮という。細かな水滴が多数集まると雲が形成され、さらに成長すると雨粒や雪片になり降水をもたらす。蒸発は液体から気体への逆の過程、凝固は液体が固体になること、蒸散は植物が葉から水蒸気を放出する作用であり雲の形成とは区別される。水循環はこれらの過程が連続して起こることで成り立つ。
Q10 : 植物の花粉がめしべの先につくことを何という?
受粉は花粉が昆虫や風などによって運ばれ、めしべの柱頭に付着する現象で、植物の有性生殖の第一段階である。このあと花粉管が胚珠へ伸び精細胞と卵細胞が受精し種子形成が始まる。受粉が起こらなければ受精も果実形成も起こらず個体が次世代を残すことができない。光合成や蒸散は葉で行われる生命維持活動、発芽は種子の発育開始であり、花の生殖とは役割が異なる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は理科5年クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は理科5年クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。