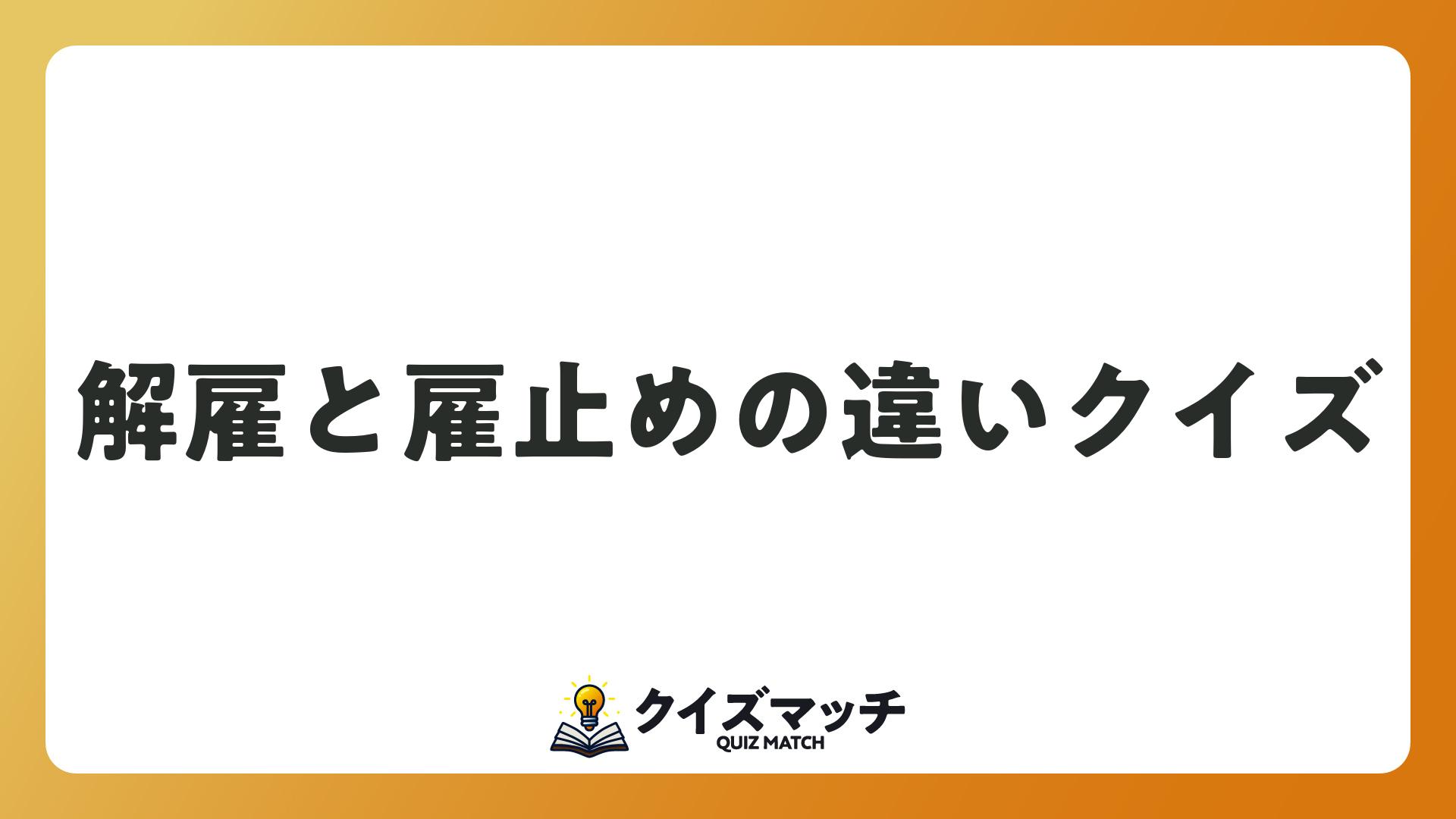解雇と雇止めの違いを知ろう
期間の定めのある労働契約を終了させる際、「解雇」と「雇止め」は大きな違いがあります。この2つについて理解を深めるため、10問のクイズに挑戦してみましょう。期間満了時の更新拒否や解雇の正当性など、雇用終了をめぐる法律上のポイントを確認できます。労働者としての権利を理解し、会社との関係を適切に管理するヒントが得られるはずです。あなたの知識を試してみてください。
Q1 : 期間雇用社員が通算5年を超えて働き、会社が更新を拒否した場合、労働契約法18条によって労働者が申し出るとどうなるか?
労契法18条は、同一使用者との間で有期労働契約が通算5年を超えて反復更新された労働者が、期間満了時に申し出れば無期労働契約へ転換できる権利を定める。よって5年超勤務者に対し会社が雇止めを行おうとしても、労働者が転換申込権を行使すれば無期転換が成立し、原則として雇止めはできなくなる。転換後に終了させるには解雇としての客観的合理性が必要となる。
Q2 : 雇止めで『合理的な更新期待』の有無を判断する際、最も関連性が低い要素はどれか?
雇止めが有効かどうかを判断する際、更新期待の有無が最大の鍵となる。過去の更新回数が多い、会社から更新を前提とする説明がある、就業規則で更新基準が曖昧などは期待形成を裏づける事情である。また勤務態度や能力は合理性の有無を評価する重要要素となる。一方、労働者の家計や生活状況は私人の事情であり法的判断要素とはならず、雇止めの可否を直接左右しない。
Q3 : 解雇が裁判で無効と判断された場合、労働者が一般に請求できる救済として正しいものはどれか?
解雇が無効と判断されると、法律上は労働関係が継続していたとみなされるため、労働者は地位確認と賃金支払い(バックペイ)を請求できる。会社が予告手当を支払っただけでは無効解雇の瑕疵は治癒せず、失業給付の上乗せや離職票の形式的交付は根本的な救済にはならない。雇止めの場合は原則として賃金継続請求は認められない点との違いを理解しておく必要がある。
Q4 : 契約期間満了直前に会社と労働者が更新に合意し継続就労した場合、労働関係の法的状態として正しいものはどれか?
契約期間満了前に会社と労働者が更新に合意し、満了日以降も働き続けた場合は、その時点で新たな労働契約が成立する。合意内容により期間の定めがある場合も無期契約になる場合もあり、解雇や雇止めといった終了行為は発生していない。したがって直前まで更新の可否が未定でも、合意が成立すれば法的には通常の契約継続となり、解雇予告手当の支払い義務なども生じない。
Q5 : 解雇の手続として法律で義務付けられているものはどれか?
労基法20条は、期間の定めのない労働契約や期間途中で契約を打ち切る場合(解雇)について、会社は少なくとも30日前に予告するか、平均賃金30日分以上の解雇予告手当を支払う義務を課している。一方、契約期間が満了して自然に終了する雇止めには同条の適用はなく、予告義務自体は存在しない。ただし雇止めでも合理性や手続的配慮が求められる点は留意が必要。
Q6 : 期間の定めのある労働契約の労働者に対し、会社が契約期間中に一方的に就労を拒否した場合、一般に何に該当するか?
期間の定めのある契約労働者といえども、契約期間中に企業が一方的に労務の受領を拒み、就労させない場合は契約期間途中の打切りであり、これは雇止めではなく解雇に該当する。したがって労基法20条の予告義務や解雇権濫用法理(労契法16条)の適用対象となり、会社は客観的合理性・社会的相当性を立証できなければ無効となる。
Q7 : 労働契約法19条の主旨として正しいものはどれか?
労契法19条は、反復更新等によって期間満了後も雇用継続への合理的期待が認められる場合に、雇止めを解雇に準じて制限する趣旨を持つ。同条は①過去の更新状況、②契約更新基準、③会社の言動等を総合考慮し、更新拒否に客観的合理性・社会的相当性が無ければ無効とする。すべての雇止めを一律に禁止する規定でも、無期転換を強制する規定でもない点が特徴となる。
Q8 : 雇止めにおける『更新の期待』が争点となった代表的最高裁判例はどれか?
最高裁昭和49年7月22日東芝柳町工場事件は、期間契約者に対する更新拒否が争われた代表例で、従前の反復更新や会社側の言動により合理的更新期待が形成されていれば、雇止めにも解雇権濫用法理が類推適用されると判示した。この判例がその後の雇止め法理の礎となり、労契法19条の立法過程にも影響を与えた。よって雇止めを論ずる際、同事件は避けて通れない。
Q9 : 解雇と雇止めの主要な違いとして正しいものはどれか?
解雇は期間の途中で企業が契約を一方的に終了させる行為であり、期間の定めのない契約でも定めのある契約でも起こり得る。一方、雇止めはあくまで期間の定めのある契約が満了した時点で次期契約を更新しない決定を指す。したがって両者は終了時点が異なり、適用される法律条文や手続義務も異なる。予告義務は解雇のみ、期間満了到来は雇止めの前提となる。
Q10 : 雇止めの通知期限として法令で明示的に定められているものはどれか?
雇止めに関しては、労基法20条のような法定予告期間は存在せず、満了前にいつ通知するかについて明確な規定はない。ただし行政通達や判例上、少なくとも次の契約を検討できるだけの相当期間前に説明・通知することが望ましいとされ、職業安定法や労働局指針でも配慮義務が示されている。法定義務でないことと、実務上求められる配慮を区別して理解する必要がある。
まとめ
いかがでしたか? 今回は解雇と雇止めの違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は解雇と雇止めの違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。