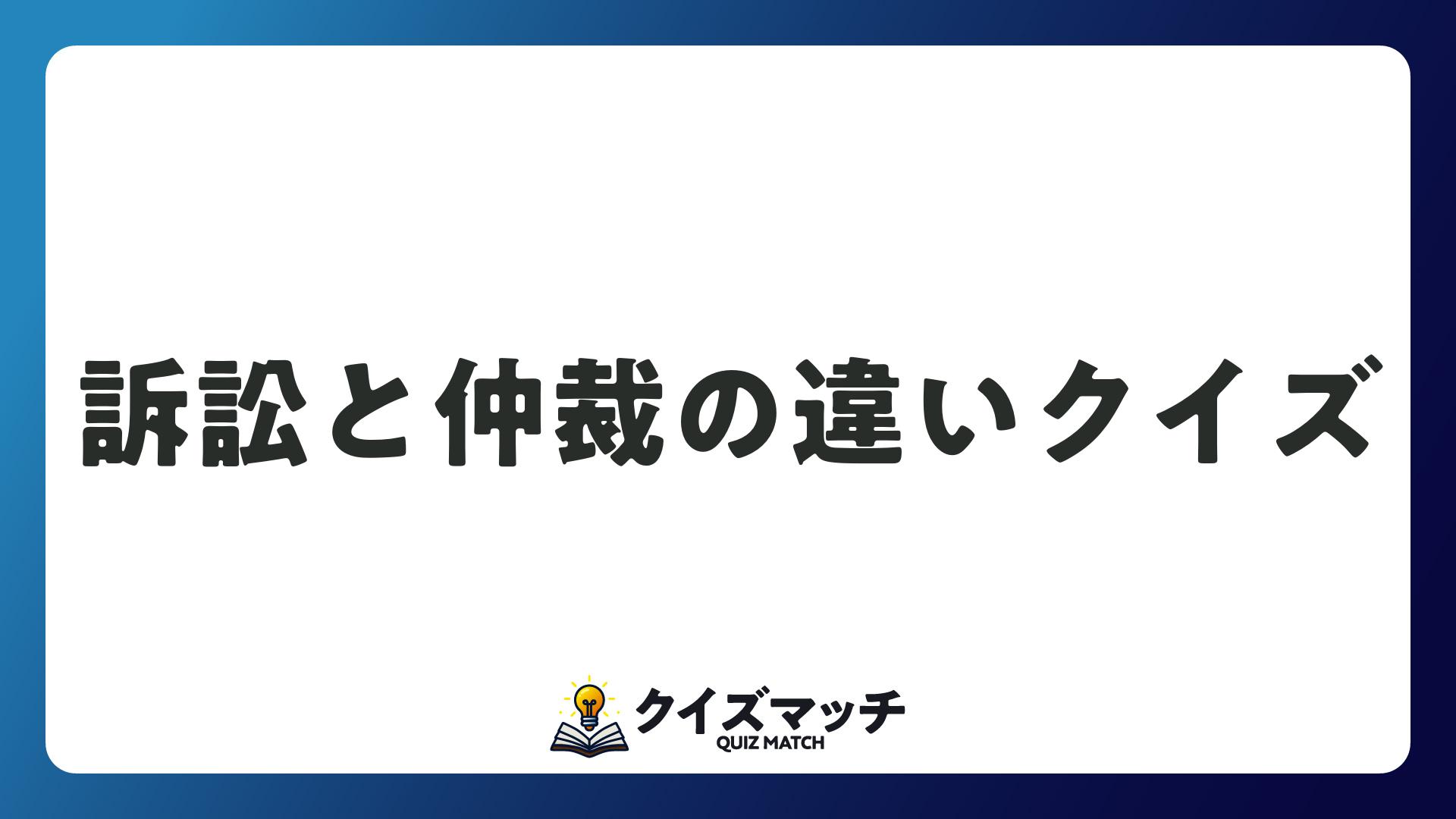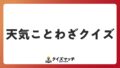訴訟と仲裁の違いを知る上で重要なポイントを 10 問の クイズにまとめました。仲裁の利点や特徴、手続の違い、コストなど、実務上の重要論点を網羅しています。仲裁には訴訟とは異なる独自の法理や規則が適用されるため、紛争解決手段を選択する際の判断材料となれば幸いです。国際取引や投資協定など、越境的な法的紛争に直面した際の参考としてご活用ください。
Q1 : 国際的な商事紛争で仲裁地(シート)をロンドンに定めた場合、手続に適用される準拠法として最も影響力が大きいのはどれか?
仲裁地法は座の法とも呼ばれ、手続面で仲裁を支配する。ロンドンを選ぶと1996年英国仲裁法が適用され、証拠開示の幅、裁判所の介入、判断取消しの範囲など手続の骨格を定める。契約準拠法は実体関係を規律するが手続には直接適用されない。被告所在地や機関所在地の法は通常補充的作用にとどまる。適切な仲裁地選択は公正性、執行性、裁判所支援の度合いなどを左右するため、国際紛争戦略において極めて重要である。
Q2 : 投資条約仲裁(ISDS)と商事仲裁を比較した際の顕著な相違点として正しいものはどれか?
投資仲裁は国家による収用、差別的規制、公正衡平待遇違反など国家措置の国際法違反を審査し、ICSID条約又はUNCITRAL規則に基づいて行われる。商事仲裁は通常民間主体間の契約紛争を扱い国家は当事者とならない。ICSID判断は条約により加盟国で判決同様に自動執行され、UNCITRAL投資仲裁判断もニューヨーク条約で執行可能であるため執行不可説は誤り。管理機関もケースごとに異なる。よって選択肢3が正しい。
Q3 : アメリカ連邦仲裁法(FAA)に基づく仲裁合意の強制に関する説明として正しいものはどれか?
連邦最高裁はサウスランド判決等でFAAは州裁判所にも適用されると判示し、州法が仲裁合意を差別的に無効化する場合はプリエンプションにより排除される。これにより消費者契約や雇用契約における仲裁条項も一般契約法上の瑕疵がない限り強制的に執行される。FAAは第1章が国内仲裁、第2章・第3章が国際仲裁を規律し幅広く適用される。セクション10の取消理由は限定的で、判断内容の単なる不合理性だけでは取消しは認められない。
Q4 : 訴訟と比べた場合の仲裁手続の非公開性について正しい説明はどれか?
多くの国際仲裁規則では手続や証拠、審問、最終判断の公開義務を設けておらず、機関が年次報告で概要を記載する程度で実名や詳細は伏せられる。訴訟は公開裁判の原則により判決書や期日情報が閲覧可能で、報道されることも多い。企業秘密やレピュテーションリスクを避けたい当事者にとって非公開性は大きな魅力となるが、投資仲裁など公益性が高い分野では透明性を求める動きも生じている。
Q5 : 訴訟における控訴・上告制度と仲裁判断の取消し制度の関係として正しいものはどれか?
仲裁判断は最終的かつ拘束力を持ち、通常は控訴制度が存在しない。唯一の救済は仲裁地裁判所への取消請求だが、審査範囲は仲裁合意の不存在、適正手続違反、公序違反など限定列挙された事由に限られる。事実認定や法律解釈の妥当性は審査対象外で、訴訟での控訴や上告のように内容面を争うことはできない。これにより迅速確定性が確保される一方、誤判是正機会が限られるという議論もある。
Q6 : 日本法上、裁判所が訴訟係属中に仲裁合意を理由として訴訟を却下又は中止する手段を定めた条文はどれか?
仲裁法第14条は、当事者間に有効な仲裁合意が存在するのに訴訟が提起された場合、被告が適切な時期に抗弁すれば裁判所は訴訟を却下または手続を停止しなければならないと定める。これはUNCITRALモデル法第8条を受けており、仲裁合意の優越性を担保するための制度である。民訴法第3条の6は国際裁判管轄規定にすぎず、仲裁を理由とする却下を直接規定していない。よって正解は仲裁法14条である。
Q7 : 訴訟と仲裁における裁判官・仲裁人の選任方法の比較として正しい記述はどれか?
訴訟では裁判官は国家公務員で、事件配点は裁判所内部の抽選等で決まり当事者が関与できない。一方国際仲裁では各当事者が一名ずつ仲裁人を指名し、三人目を両仲裁人か機関が選ぶのが一般的で、当事者は技術や業界に精通した専門家、望ましい国籍、言語能力を考慮できる。仲裁人は弁護士資格必須ではなく学者や元裁判官など多様で柔軟性が大きい。これが仲裁の専門性や当事者支配の高さの要因となる。
Q8 : 仲裁合意を含む契約が破棄された場合、その仲裁合意の効力は通常どうなるか?
国際仲裁法理で確立した分離性原則により、仲裁条項は主契約とは独立した合意とみなされる。したがって主契約が詐欺や解除などで無効になった場合でも、仲裁合意自体は存続し仲裁人が管轄権を持つ。さらにコンピテンス・コンピテンス原則により、仲裁人自身が仲裁合意の有効性を判断でき、裁判所の事前介入を最小化する。これらの原則はUNCITRALモデル法や各国仲裁法に明示され、紛争解決の確実性と効率性を高めている。
Q9 : 訴訟と仲裁のコスト構造の違いに関する説明のうち正しいものはどれか?
仲裁手続では裁判所利用料が不要である反面、複数の仲裁人への時間課金報酬、機関管理料、審問会場費、録音・逐語記録、専門証人費用などが上乗せされる。特に少額紛争では固定費比率が高く、訴訟より総額が大きくなる場合が多い。敗訴側全面負担義務は存在せず、規則は勝敗度合いや訴訟態度を考慮して按分を定める。逆に高額かつ技術的に複雑な案件では仲裁の方が迅速で結果的にコスト効率が良い場合もあり、単純に安い高いとは判断できない。
Q10 : 国際仲裁の最大の利点の一つとされる仲裁判断の執行に関する特徴はどれか?
ニューヨーク条約は170か国以上が加盟し外国仲裁判断の承認・執行を原則義務付けているため、仲裁判断は加盟国の裁判所で簡易な手続で強制執行できる。一方訴訟判決は外国で強制執行するには相互主義などの複雑な再審査を経る必要がある場合が多い。ゆえに国境を越えた取引では仲裁が選ばれやすい。条約の恩恵は当事者の国籍や同意の有無に左右されず条約要件を満たせば自動的に及ぶ。