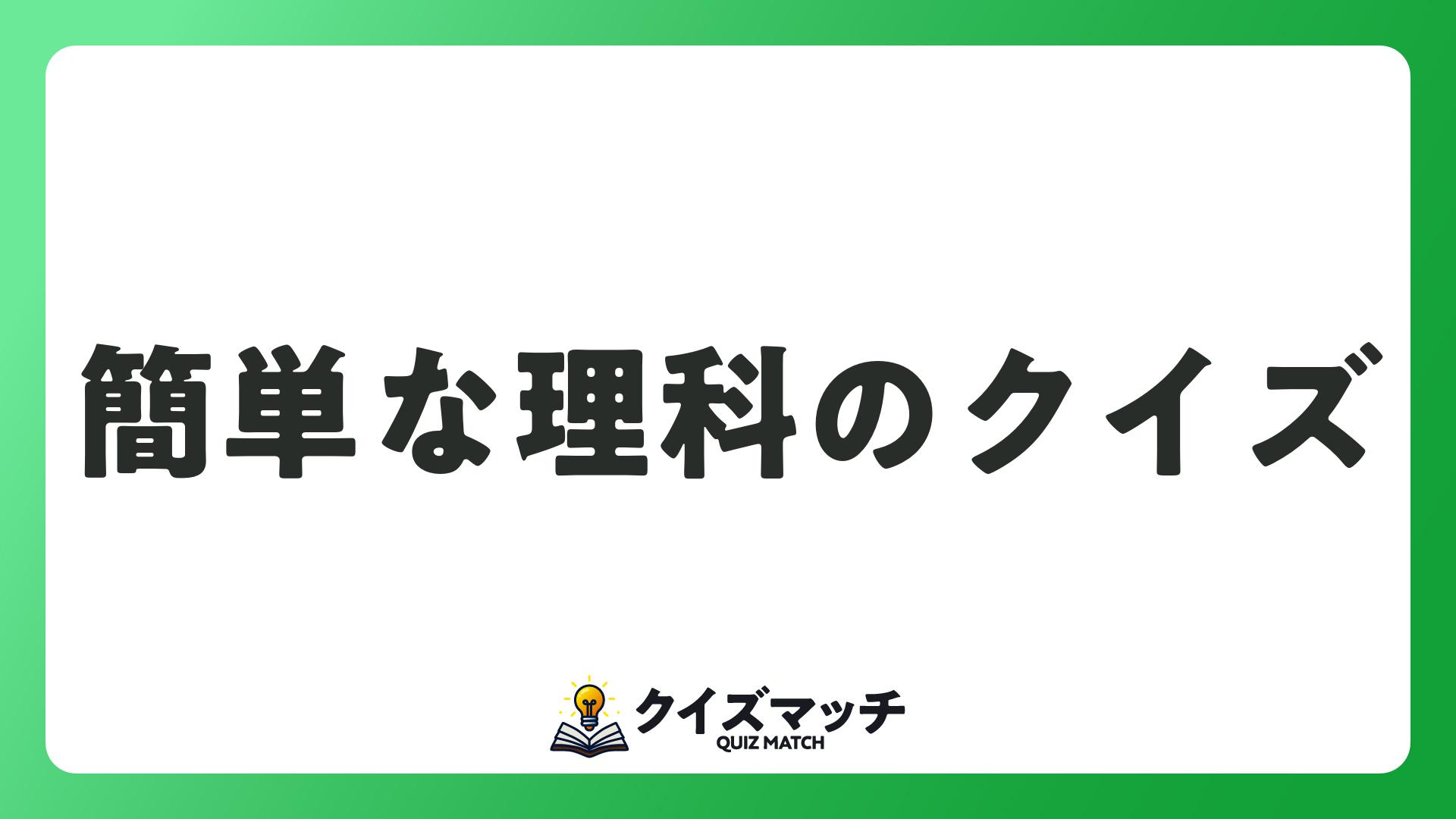「理科のクイズ王になろう!」日頃の理科の知識を試してみよう。簡単な10問で構成された本クイズは、空気の速さや鉱物の硬さ、植物の光合成、地球の自転など、身近な自然現象に関する基礎知識を問うものです。回答を選ぶ際は、科学的な原理と法則を踏まえた上で、最も適切なものを選んでみてください。楽しみながら、あなたの理科力を磨いていきましょう。
Q1 : ABO式血液型でO型の赤血球表面に存在しない抗原はどれか?
ABO式血液型は赤血球表面の糖鎖抗原の有無で分類される。H抗原という基本構造にN-アセチルガラクトサミンが付加されるとA抗原、ガラクトースが付加されるとB抗原になる。O型は遺伝的に転移酵素が不活性で両糖が付加されないため、H抗原のままでA抗原もB抗原も持たない。結果としてO型の血漿には抗A抗体と抗B抗体の両方が存在し、輸血適合で独自の振る舞いを示す。したがって赤血球表面に存在しないのはAとB両方であり、選択肢3が正解である。
Q2 : 次のうち典型的なイオン結合性化合物ではないものはどれか?
イオン結合は陽イオンと陰イオンが静電的に引き合い、格子状に配列した結晶を作る結合形式である。食塩NaClはNa⁺とCl⁻、KBrはK⁺とBr⁻から成り典型的。CaCO₃も多原子イオンCO₃²⁻を含むが、Ca²⁺とイオン結合しているため分類上イオン結晶である。一方NH₃(アンモニア)は窒素と水素が共有電子対を共有する共有結合性分子で、固体でも分子間力で構造を保持する分子結晶に過ぎずイオン格子は形成しない。したがってイオン結合性でないものはNH3が正解である。
Q3 : 水が4 ℃付近で密度が最大になる現象を何という?
多くの液体は温度が下がるほど密度が大きくなるが、水は0 ℃付近で逆に密度が減少し氷になるとさらに体積が膨張する。ところが4 ℃前後で最も密になり、その後加熱すると再び膨張するという特異な振る舞いを示す。この現象を水の密度異常という。原因は水素結合によるクラスター構造の再配列で、湖や海では表面が凍っても4 ℃の水が沈み底層を保温するため生物が冬季に生存できる。表面張力、毛細管現象、蒸発潜熱はいずれも水の性質だが密度変化とは別の現象である。
Q4 : 月の満ち欠けの周期である約29.5日を何と呼ぶか?
月は地球を約27.3日で一周するが、この27.3日は背景の恒星を基準にした恒星月である。私たちが夜空で観察する新月→満月→新月の周期は太陽との位置関係が再現するまでの時間で、平均29.53日。この周期を朔望月(さくぼうげつ)という。カレンダーの旧暦や潮の干満計算の基礎にもなる重要な値である。会合周期は複数の惑星や天体の見かけ配置が再現するまでの期間を示す用語、隠蔽月は古い暦概念で一般に用いられない。従って正解は朔望月である。
Q5 : 電池の両端に生じる起電力(電圧)を直接測定する器具として最も適切なのは?
ボルテメーター(一般にはボルトメーターと呼称)は内部抵抗が非常に大きく設計されており、回路に並列に接続してもほとんど電流を流さずに電位差を測定できるため、電池の起電力を正確に読み取るのに適している。アンメーターは電流計で内部抵抗を極小にし直列接続するので用途が異なる。オシロスコープは時間変化を可視化する装置で電圧測定も可能だが操作が複雑で基礎機器とは言い難い。ガルバノメーターは微小電流計で補助回路なしに電圧測定はできない。よって正解はボルテメーターである。
Q6 : DNAに含まれない塩基は次のうちどれか?
DNA(デオキシリボ核酸)の塩基はアデニン(A)、チミン(T)、グアニン(G)、シトシン(C)の4種類。一方、RNA(リボ核酸)ではチミンの代わりにウラシル(U)が使われる。ウラシルはピリミジン環にメチル基を持たない点でチミンと異なる。細胞はDNA合成時にウラシルが入り込むと修復酵素で排除するほど厳密に区別している。アデニン・グアニン・シトシンはいずれもDNAとRNAの双方に存在。したがってDNAに含まれない塩基はウラシルである。
Q7 : 地球の自転により運動する物体に働く見かけの力で、北半球では進行方向右向きに曲げるものは?
回転している地球を基準に運動を観測すると、慣性系との相違から見かけの力が現れる。その一つがコリオリ力で、物体の速度ベクトルと地球自転の角速度ベクトルの外積に比例し、北半球で右、南半球で左に偏向させる。気象ではこれが原因で貿易風や台風の渦が特定方向へ曲がる。遠心力も見かけの力だが方向は常に赤道外向きで、偏向効果とは異なる。摩擦力は接触面で生じる実在の力、万有引力は質量間の引力で自転には無関係。従って正解はコリオリ力である。
Q8 : クロロフィル(葉緑素)が可視光の中で最も吸収しにくい色は?
光合成色素クロロフィルaとbはそれぞれ青紫域(約430 nm)と赤域(約660 nm)に強い吸収ピークを持ち、そこで受け取った光エネルギーを化学エネルギーへと変換している。緑域(約500〜570 nm)は吸収が弱く、多くが反射または透過されるため植物の葉が人間の目には緑色に見える。紫域や青域、赤域は吸収が比較的強いので選択肢としては不適切。以上よりクロロフィルが最も吸収しにくい色は緑であり、問題の正解は「緑」となる。
Q9 : 天然物質の中でモース硬度が最も高いものは何か?
モース硬度は鉱物の傷つきにくさを1から10で示した指標で、10が最も硬い。ダイヤモンドは純粋な炭素が立体的に共有結合した結晶で硬度10を示し、実験室で合成された立方晶窒化ホウ素などを除けば天然物質中で最硬である。ルビーはコランダム(酸化アルミニウム)の赤色変種で硬度9、コランダム自体も9と高いがダイヤモンドに次ぐ。グラファイトは同じ炭素でも層状構造で層間の結合が弱く、鉛筆芯の材料になるほど柔らかい。したがって正解はダイヤモンドである。
Q10 : 空気中での音の速さは普通およそいくらか?
音速は気温に比例してわずかに増加するが、0 ℃で約331 m/s、20 ℃で約343 m/sである。中学校や高校の計算問題では15 ℃前後の代表値として330 m/s前後を採用するのが一般的で、これを覚えておくと問題での近似値計算に便利である。430 m/sを超える速さは水中や高温の気体の値であり、常温の空気では該当しない。逆に極低温ではさらに遅くなるため、選択肢の中で最も妥当なのは約330 m/sである。
まとめ
いかがでしたか? 今回は簡単な理科のクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は簡単な理科のクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。