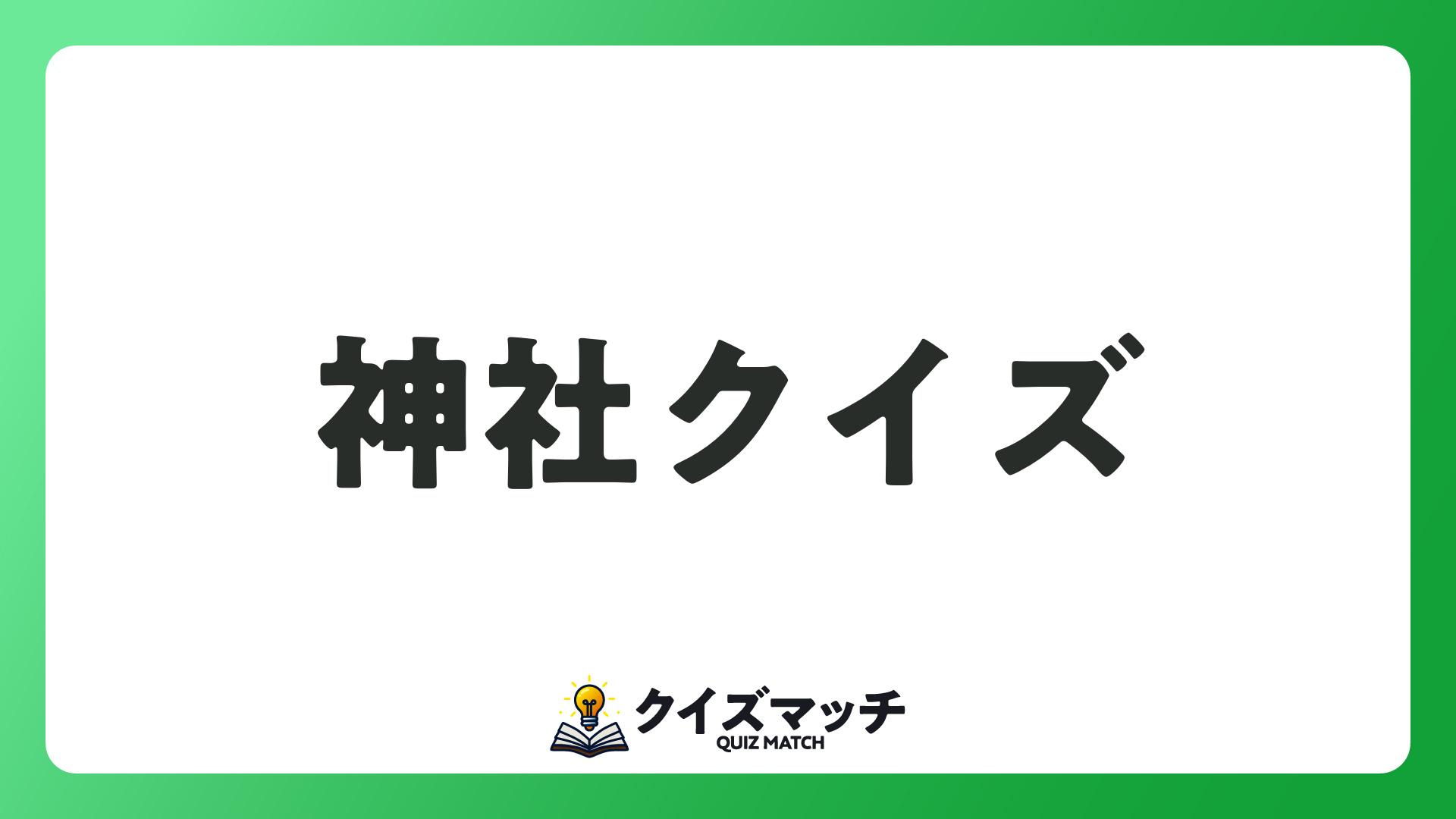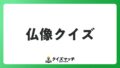日本には約8万社の神社が存在し、その中でも特に多いのが稲荷神社系や八幡神社系といった神社です。全国各地の神社には、歴史や建築、祭礼など、さまざまな魅力が詰まっています。今回のクイズでは、そんな神社の知識をお楽しみいただけます。神社の起源や特徴、祭事の由来など、日本の伝統文化に触れる内容となっています。神社に詳しくなくても気軽に挑戦できるよう、初心者にも優しい構成になっています。ぜひ、神社の世界をお楽しみください。
Q1 : 神社でよく見る「御朱印」は本来どんな意味があったのでしょうか?
御朱印はもともと納経(写経を納める)の証明書の役割が起源です。お寺や神社で写経を奉納した際に押してもらう印が始まりとされています。現代では参拝記念としていただくことが多いものの、その歴史的背景には信仰心の証明や功徳積みの意味があります。
Q2 : 神道の神々を祀る社殿の建築様式の一つで、屋根の両端に見える「千木(ちぎ)」の向きによって何がわかるとされる?
千木の切り口が水平なら女性神、垂直なら男性神を祀るとされる伝承があります。たとえば伊勢神宮の内宮(天照大御神)は千木が水平(女性神)、外宮(豊受大神宮)は垂直(男性神)です。ただし、全ての神社がこの規則に従うわけではありませんが、伝統的な目安のひとつです。
Q3 : 神社にある「狛犬」は左右で何と何の一対が基本となっているでしょう?
神社の入口などに置かれる狛犬は、口を開いた「阿形(あぎょう)」と、口を閉じた「吽形(うんぎょう)」が一対となっています。阿吽の呼吸のように、始まり(阿)と終わり(吽)、つまり宇宙や生命の始終を意味しています。獅子と虎などの組合せはありません。
Q4 : 鳥居について、もっとも代表的な型である「明神鳥居」は何に由来するといわれていますか?
明神鳥居は、笠木と島木という2本の横木が載り角度があるのが特徴です。その形は日本に古くからある、神域と人間界を分かつ原始的な門柱が起源であるとされます。伊勢神宮形式(神明鳥居)は明神鳥居とは形が異なります。仏教建築は直接関係していません。
Q5 : 神社の神職(しんしょく)で、神主の補佐役を主に務める女性の職名は何でしょう?
神職の補佐として神事や祭事で奉仕する女性は『巫女』です。白衣に緋袴の姿が特徴で、舞を奉納したり、御守り授与やお神楽の際に活躍します。斎女は古代宮廷や伊勢神宮の特別な役職です。禰宜は男性も含む神職で、社家は世襲神職の家系を指します。
Q6 : 出雲大社の特長的な巨大な注連縄(しめなわ)が下がる場所はどこでしょう?
出雲大社の象徴的な巨大しめ縄は、大社の東側にある「神楽殿」にかかっています。このしめ縄は長さ13.5m、重さ5トン以上にもなり、縁結びの神社として知られる出雲大社を象徴しています。本殿ではなく神楽殿で見られるので注意が必要です。
Q7 : 京都の「八坂神社」で毎年7月に行われる大きなお祭りの名前はどれでしょう?
八坂神社の祇園祭は、日本三大祭りのひとつで、毎年7月に京都市内を中心に盛大に開催されます。豪華な山鉾巡行や様々な神事が行われ、全国から多くの観光客が訪れます。祇園祭は疫病退散を祈る神事に始まり、1000年以上にわたり受け継がれています。
Q8 : 伊勢神宮で祀られている主祭神は誰でしょう?
伊勢神宮の主祭神は天照大御神(あまてらすおおみかみ)です。天照大御神は日本神話の中で太陽神とされ、皇室の祖先神でもあります。伊勢神宮は内宮と外宮から成り、特に内宮に天照大御神が祀られています。日本人にとって特別な信仰の対象です。
Q9 : 初詣で多くの参拝客が訪れることで有名な「明治神宮」はどの都道府県にあるでしょう?
明治神宮は東京都渋谷区に鎮座する神社で、日本を代表する初詣スポットです。毎年、三が日には300万人以上の参拝者が訪れ、日本で最も参拝者が多い神社として有名です。明治天皇と昭憲皇太后を祀っており、都心であるにも関わらず広大な杜(もり)が広がっています。
Q10 : 日本全国に約8万社あるといわれる神社の中で最も多い系統は次のうちどれでしょう?
全国の神社で最も多いのは稲荷神社系です。特に稲荷神社は総本社の伏見稲荷大社(京都)を中心に約3万社あるといわれています。商売繁盛や五穀豊穣を祈る神として全国的に信仰されており、鳥居が数多く連なることで知られています。なお、八幡神社も多いですが、総数では稲荷神社が勝ります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は神社クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は神社クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。