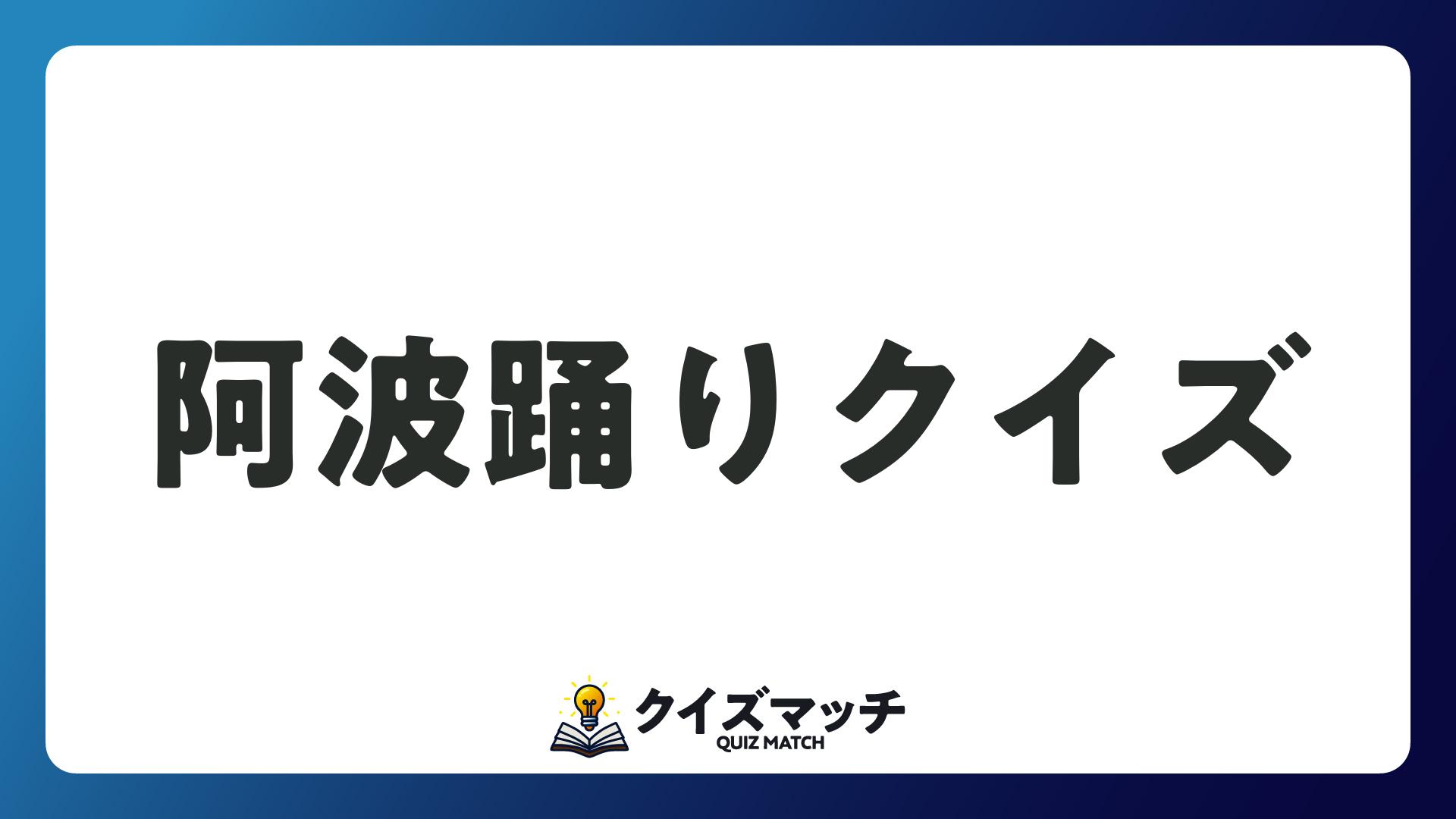徳島県に伝わる伝統的な夏祭り「阿波踊り」。その歴史や特徴を知る機会はなかなかありませんが、今回のクイズはまさにその「阿波踊り」について深く掘り下げていきます。徳島の夏の風物詩を題材とした10問の内容をお楽しみください。阿波踊りの発祥地や衣装、音楽、掛け声など、さまざまな側面からクイズが用意されています。阿波踊りの魅力に迫る貴重な機会となるでしょう。
Q1 : 阿波踊りの由来とされる伝説について正しいものはどれ?
阿波踊りが始まった由来には諸説ありますが、最も有名なのは「蜂須賀家政が徳島城の完成を祝い、城下の人々に酒を振る舞った際に自然発生的に踊りが始まった」という説です。以降、お盆の時期に踊られるようになり、今の阿波踊りに発展しました。
Q2 : 阿波踊りを踊る際の掛け声『ヤットサー』はどのような意味で使われますか?
『ヤットサー』は阿波踊りの代表的な掛け声であり、踊り手の気合いを込めたり、観客と一体となって盛り上がるためのフレーズです。「いざ踊れ!」や「さあ盛り上がろう!」という意味合いがこめられています。踊りの最中に何度も叫ばれます。
Q3 : 阿波踊りで使われる「鳴り物」に含まれないものはどれ?
阿波踊りの「鳴り物」とは、踊りのリズムや雰囲気を演出する音楽隊のこと。使用されるのは太鼓、三味線、鉦、篠笛などの日本伝統楽器です。ギターは阿波踊りの伝統楽器には含まれません。
Q4 : 徳島市阿波踊りに参加する踊り手グループを何と呼びますか?
阿波踊りの踊り手グループは「連(れん)」と呼ばれます。ひとつの連は数名から数百名で構成され、衣装や踊りのスタイル、楽器の構成に特色があります。有名な「娯茶平連」など伝統的な連も多く、観光客も参加できる「にわか連」などもあります。
Q5 : 阿波踊りの最大の特徴である踊りの型で“男踊り”に当てはまるのは?
男踊りは低い姿勢で膝をしっかり曲げ、力強く跳ねるような動きが特徴です。手にはうちわや扇子、提灯などを持つ場合もありますが、基本は元気に躍動感を持たせる踊りです。一方、女踊りはしなやかで優美な動きが基本となります。
Q6 : 阿波踊りのリズムを支える伝統的な楽器はどれ?
阿波踊りは太鼓(締め太鼓、鉦太鼓)、三味線、篠笛、鐘(かね)など様々な和楽器を用いて独特のリズムを刻みます。これらの楽器が一体となり、テンポよく陽気な雰囲気を作り出しています。楽器演奏者を「鳴り物」と呼んで踊りとともにパレードします。
Q7 : 阿波踊りで女性がよく着る衣装はどれ?
女性の踊り手(女踊り)は「浴衣に編み笠」という衣装が定番です。浴衣は鮮やかな色合いに帯を締め、顔を隠すように大きな編み笠(花笠、菅笠など)をかぶり、優雅でしなやかな動きを特徴としています。男性は着流しや法被姿が多いです。
Q8 : 阿波踊りの開催期間はいつが一般的でしょうか?
徳島市の阿波踊りは、毎年8月12日から15日の4日間にわたって開催されます。この時期はお盆にあたり、多くの人が里帰りするタイミングでもあります。他県で独自に開催する場合もありますが、最も本格的かつ有名なのは8月中旬の徳島市阿波踊りです。
Q9 : 阿波踊りの掛け声『踊る阿呆に見る阿呆…』このあとに続く言葉はどれ?
阿波踊りの有名なかけ声に「踊る阿呆に見る阿呆、同じ阿呆なら踊らにゃ損損」というものがあります。踊る人と見る人、どちらも阿呆(阿呆:おバカ)のようだが、どうせなら踊って楽しもう、という意味です。親しみやすさとおおらかさが魅力です。
Q10 : 阿波踊りの発祥地はどこですか?
阿波踊りは日本の代表的な盆踊りの一つで、その発祥は現在の徳島県(旧阿波国)とされています。阿波踊りは徳島市を中心に、毎年8月になると盛大に開催され、国内外から多くの観光客が訪れます。他の県でも阿波踊りイベントがありますが、発祥地でありメイン会場は徳島県です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は阿波踊りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は阿波踊りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。