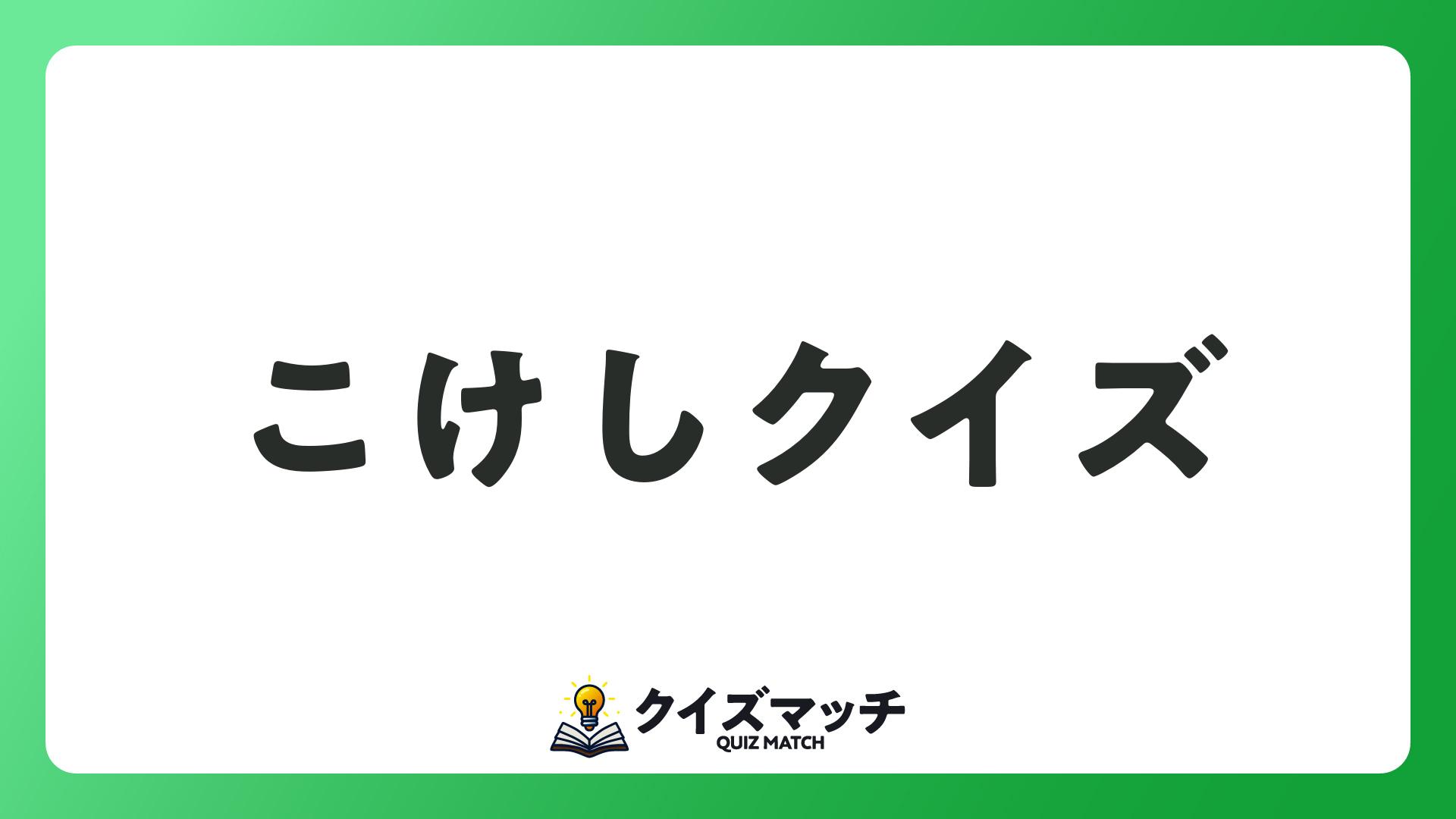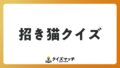こけしは日本の伝統的な木製玩具で、特に東北地方で作られています。その中でも、宮城県の鳴子温泉周辺が発祥の地として広く知られています。19世紀初頭に温泉地で土産品として作られ始め、特徴的な形や模様から「鳴子こけし」として有名になりました。以後、東北各地の温泉地を中心にこけし作りが盛んになりました。今回のクイズでは、こけしの歴史や特徴、さまざまな地域の代表的なこけしについて、10問お楽しみいただけます。
Q1 : こけしはもともと何を目的として作られ始めた?
こけしはもともと東北地方の温泉地で、湯治に来た客が子供へのお土産や遊び道具として買い求めるために作られました。次第にその素朴な美しさから蒐集家によっても注目され、伝統工芸品として今に至っています。魔除けや食器、楽器とは関係ありません。
Q2 : こけしの全国コンクールが毎年開催されている都市は?
宮城県白石市は、日本全国のこけし職人や愛好家が集う「全国こけしコンクール」の開催地として知られています。このイベントは昭和31年(1956年)から続き、優れたこけし作りの技術や創造性が競われています。
Q3 : 「創作こけし」とはどんなこけしか?
「創作こけし」は伝統こけしとは異なり、昭和初期以降に現れた新しいスタイルのこけしです。伝統的な決まった形や模様にとらわれず、作家が自由な発想で表現したこけしで、現代アート的要素も多く含まれるため、コレクターにも人気です。
Q4 : こけしの背中や胴体によく描かれる模様は?
こけしの胴体には「ろくろ模様」と呼ばれる同心円状の線描きがよく用いられます。ろくろで木を回転させながら描くため均一な円になるのが特徴です。梅や桜の花の模様もたまに見られますが、基本となる模様はろくろ模様です。
Q5 : こけしの顔の特徴として当てはまるのはどれ?
伝統的なこけしの顔は、切れ長の目やほんのりとした口元、優しく穏やかな表情が多いのが特徴です。地域や制作者によって多少の差はありますが、憂いを帯びた静かな雰囲気が、こけしの魅力の一つです。笑い顔や怒った表情は一般的ではありません。
Q6 : こけしの頭と胴体を繋ぐ接合部で、鳴子こけし特有の音が鳴る理由は?
鳴子こけしは頭部と胴体を別々に作り、接合部をきつめにしているため、頭部を回すと木と木とがこすれ合い、「キュッキュッ」と独特の音がします。これが鳴子こけしの名の由来ともなっています。カラクリや塗料、鉄くぎなどは使われていません。
Q7 : 東北三大こけしのひとつに数えられるこけしはどれ?
東北三大こけしとは、鳴子こけし(宮城県)、土湯こけし(福島県)、遠刈田こけし(宮城県)の三つです。これらはその産地の温泉地名を冠し、それぞれ形や模様に特徴があります。鳴子こけしはとくに頭部と胴体の接合部に鳴る音がすることが有名です。
Q8 : こけしの伝統的な形では存在しないパーツはどれ?
伝統的なこけしは頭と胴体で構成されており、手や脚などのパーツはありません。頭と胴体が丸みを帯びてつながった特徴的なデザインで、シンプルな構造がこけしの大きな魅力です。顔や胴体には独特の模様や表情が描かれています。
Q9 : こけしに使用される木材として一般的なのはどれ?
こけしの材料は適度な硬さと加工のしやすさが求められています。一番よく使われるのはミズキ(ミズキ科)という木で、木目が細かく白くてやわらかく、彫りやすいのが特徴です。ほかにもエンジュやカツラなどが地域によって使われることもありますが、ミズキが主流です。
Q10 : こけしの発祥地として有名なのはどこ?
こけしは日本の伝統的な木製玩具で、特に東北地方で作られています。その中でも、宮城県の鳴子温泉周辺が発祥の地として広く知られています。19世紀初頭に温泉地で土産品として作られ始め、特徴的な形や模様から「鳴子こけし」として有名になりました。以後、東北各地の温泉地を中心にこけし作りが盛んになりました。
まとめ
いかがでしたか? 今回はこけしクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はこけしクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。