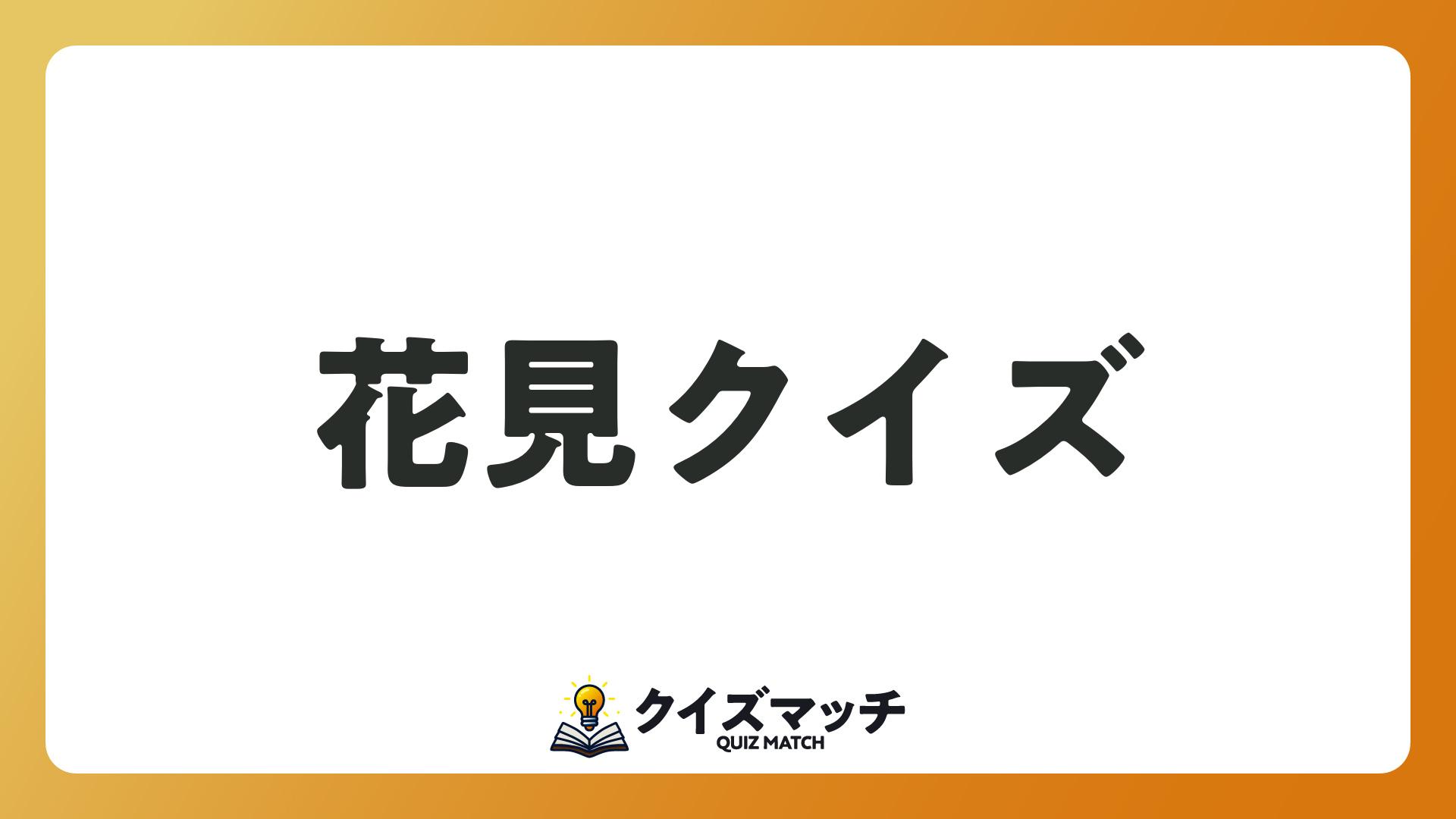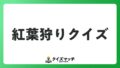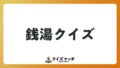日本人なら誰もが楽しみにしている春の恒例行事、花見。その歴史や風習、代表的な場所などについて、楽しいクイズ形式で学んでみましょう。平安時代から続く伝統行事の花見は、時代とともに庶民にも広がり、今では全国各地で賑わいを見せています。お団子や冷酒を楽しみながら、満開の桜の下で開かれる花見の楽しみ方を、このクイズで確認してみてください。
Q1 : お花見の宴会などでよく用いられるレジャーシートの色として一般的なものはどれでしょう?
日本の花見の風景でよく見かけるレジャーシートの色は「青」です。青いビニールシートは目立ちやすく広い場所にも敷きやすいため広く普及しました。ピンクや緑もありますが、最も多く使われているのは青色です。多くの人々がお花見の場所取りのため朝早くから青いシートを敷いて場所を確保しています。
Q2 : 花見の際、桜の枝を折ったり持ち帰ったりする行為が禁止されている理由はどれでしょう?
桜の枝を折ったり持ち帰ったりする行為は、公園などの場所で多くの場合禁止されています。これは、桜の木は非常に傷つきやすく、枝を折ることが木全体の健康を損なうからです。折られた部分から病気が入り枯れてしまうことも多いので、花見の際はマナーを守り、桜には手を触れないようにしましょう。
Q3 : 「花見酒」という言葉にぴったりの日本酒の飲み方として最も一般的なのはどれでしょう?
花見の季節(春)は比較的暖かくなるため、満開の桜の下でよく飲まれるのは「冷酒」です。屋外で爽やかな気分を味わいながら冷酒を楽しむのが一般的ですが、身体が冷える日には熱燗も飲まれます。とはいえ、花見酒=冷酒というイメージが強いです。
Q4 : 桜の咲き始めを告げる「開花宣言」を発表するのは、どの組織でしょう?
桜の開花宣言を発表するのは「気象庁」です。全国各地に標本木が設置されており、その木に5~6輪の花が咲いた時点で開花が宣言されます。気象庁はこの観測を基に全国の桜前線を発表しています。お花見の計画に役立てられるなど、毎年多くの人がこのニュースに注目しています。
Q5 : 江戸時代、庶民が花見に出かける際に人気だった移動手段は何でしょう?
江戸時代、庶民が花見に向かう際に特に人気だったのは「船」です。隅田川や大川などの川沿いに多くの桜が植えられ、川を船で行き来しながら花見を楽しみました。この「舟遊び花見」は江戸時代の風物詩となりました。徒歩での花見もありましたが、特別感のある船が人気でした。
Q6 : お花見に欠かせない伝統的な食べ物として有名なものはどれでしょう?
花見といえば「三色団子」が特に有名です。ピンク・白・緑の三色の団子は春の訪れや桜の開花を祝う意味も込められています。また、花見弁当と呼ばれる弁当も人気ですが、お団子は手軽さや見た目の華やかさから長年親しまれています。桜の下でお団子を食べるのは、日本人にとって春の風物詩のひとつです。
Q7 : 次の中で、京都の有名な花見スポットとして最も知られている場所はどこでしょう?
京都で有名な花見スポットといえば「円山公園」です。ここには巨大なシダレザクラがあり、夜桜のライトアップも人気です。広い公園内には数百本の桜が植えられ、例年多くの花見客で賑わいます。ほかにも嵐山や鴨川沿い、清水寺も有名なスポットですが、代表的スポットは円山公園です。
Q8 : 日本を代表するサクラの品種で、全国の花見に多く使われているものは何でしょう?
花見で最も多く植えられている桜は「ソメイヨシノ」です。江戸時代末期に染井村(現在の東京都豊島区)で生まれたこの品種は、一斉に咲きそろい見応えがあるため全国各地に広まりました。日本の桜の8割以上がソメイヨシノとされ、気象庁が開花宣言をする際もソメイヨシノを基準にしています。
Q9 : 花見が盛んに行われていた場所として有名な江戸時代の名所はどれでしょう?
江戸時代になると花見は庶民の間にも広がり、隅田川沿いなどが有名な花見の名所となりました。徳川吉宗が桜の木を植えさせた飛鳥山をはじめ、上野や隅田川沿いには多くの桜が植えられ、花見客で賑わいました。現在でも東京都内の花見スポットとして隅田川沿いは多くの人で賑わいます。
Q10 : 日本で花見が最初に行われたとされる時代はどれでしょう?
花見は日本の伝統的な行事で、桜の花を鑑賞しながら宴会などを楽しみます。日本で最初に記録された花見は平安時代に遡ります。嵯峨天皇の時代、宮中で桜を見る宴が開催され、以降、花見は貴族の間で広まりました。平安時代の文学や日記にも桜の描写が数多く見られ、これがやがて武士や庶民にも広がり現代の花見文化に繋がっています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は花見クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は花見クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。