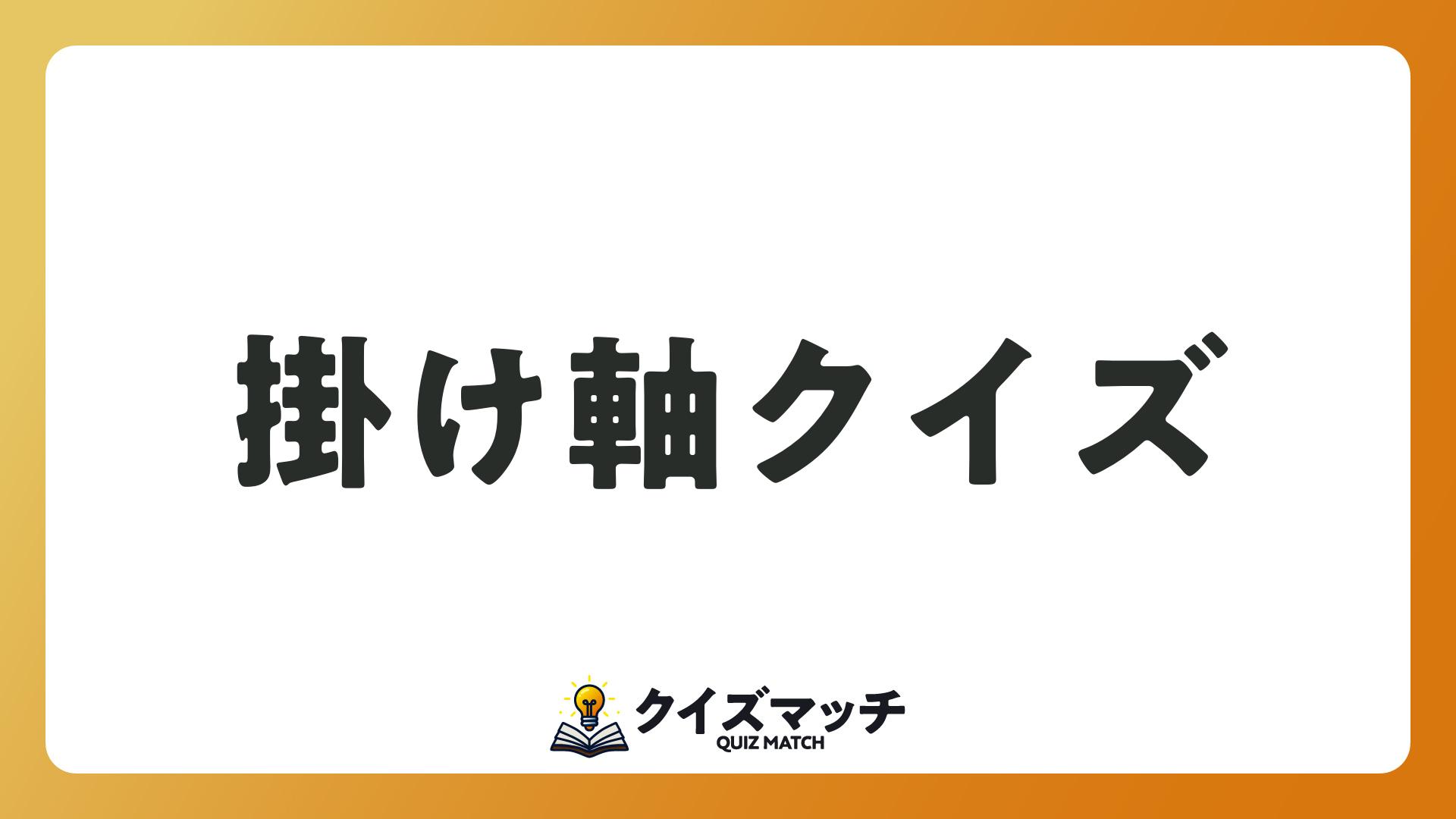掛け軸は日本の伝統的な装飾品の一つですが、その構造や材質、用途など、知らないことも多いのではないでしょうか。今回のクイズでは、掛け軸の基本的な知識を問う問題を10問ご用意しました。掛け軸の表装部品の名称から、保存方法、流派の特徴まで、幅広い内容をカバーしています。掛け軸の魅力を感じながら、ご自身の知識を確認してみてください。
Q1 : 江戸時代、掛け軸の需要が特に高まったのは何が普及したためか?
江戸時代には、商人や町人による「町人文化」の発展により、美術や書画への関心が高まりました。これに伴い、床の間に飾る掛け軸の需要も急増しました。武士や寺院文化にも掛け軸は使われていましたが、特に町人層の美的関心の高まりが背景にあります。
Q2 : 掛け軸で、壁面に固定するために付いている部品の名前は?
掛け軸の上端に付いている紐状の部分「掛緒(かけお)」は、壁面や床の間の掛け具に固定するために使います。軸先は下端左右の重し兼装飾部品、八双は上端の横木、風帯は飾り用の帯です。
Q3 : 掛け軸の表装で「一文字」とはどこの部分を指すか?
「一文字」とは、掛け軸の本紙と中廻し布の間の狭い金襴や裂で作られた装飾帯の部分を指します。この部分は主題となる画像や書の存在感を引き立て、装飾性も高いです。掛け軸の構成要素として重要な役割を果たします。
Q4 : 禅語などが書かれた掛け軸を特になんと呼ぶか?
「一行書軸」は、禅語や名言、歌句などが一行で墨書きされた掛け軸のことです。茶室や床の間によく掛けられ、簡潔な表現の中に深い意味が込められています。その他の用語は正式な名称として一般的ではありません。
Q5 : 掛け軸の保存方法として適切なものは?
掛け軸は和紙や絹などデリケートな素材で作られているため、湿気や直射日光に弱い特性があります。そのため、風通しのよい場所で保管するのが最適です。湿度が高いとカビや虫食い、直射日光は色あせの原因となります。床に直置きも傷みにつながります。
Q6 : 竹や松など、自然の主題を描いた掛け軸の流派で有名なのは?
「南画」は江戸時代から盛んになった、文人が好んだ中国的な山水画を中心とする流派です。自然を題材にした掛け軸が多く作られ、竹や松などの植物画も有名です。琳派や狩野派は装飾的要素の強い流派、大和絵は日本的な古典画の流れです。
Q7 : 茶道で使われる掛け軸のことを何というか?
茶道の席では「茶掛軸」と呼ばれる掛け軸が使われます。季節や茶会の趣旨に合わせた書や画が選ばれ、茶室の雰囲気を演出します。「花押軸」は署名のある軸のこと、「時雨軸」「高札軸」という正式な名称はありません。
Q8 : 広げた掛け軸を巻くための部品で、軸先が付いているものは?
掛け軸の下端には「軸木」という木の棒があり、その両端に「軸先」と呼ばれる装飾や重しの役割を持つ部品が付いています。これにより掛け軸をきれいに巻くことができ、保存や持ち運びにも便利です。八双は上端の木、風帯は装飾の帯、掛木は掛ける時の棒です。
Q9 : 掛け軸の本紙に使用される伝統的な素材はどれか?
掛け軸の本紙に最も多く使用されている伝統的な素材は「紙」です。和紙が特に好まれ、墨絵や書、彩色画が描かれます。なお、布(絹本)を使うこともありますが、ガラス、木材、プラスチックなど現代的な素材は伝統的な掛け軸にはほとんど使われません。
Q10 : 掛け軸の表装で、山と称される部分はどれか?
掛け軸は様々な部分から成り立っていますが、「山」と呼ばれるのは掛け軸の一番上の部分である「天」です。「一文字」は本紙と中廻しの間の金襴部分、「表装本紙」は主題が描かれている部分、「中廻し」は本紙の周囲の布で、上端が「山(天)」と呼ばれています。押絵や家紋の位置にも関わる部分です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は掛け軸クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は掛け軸クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。