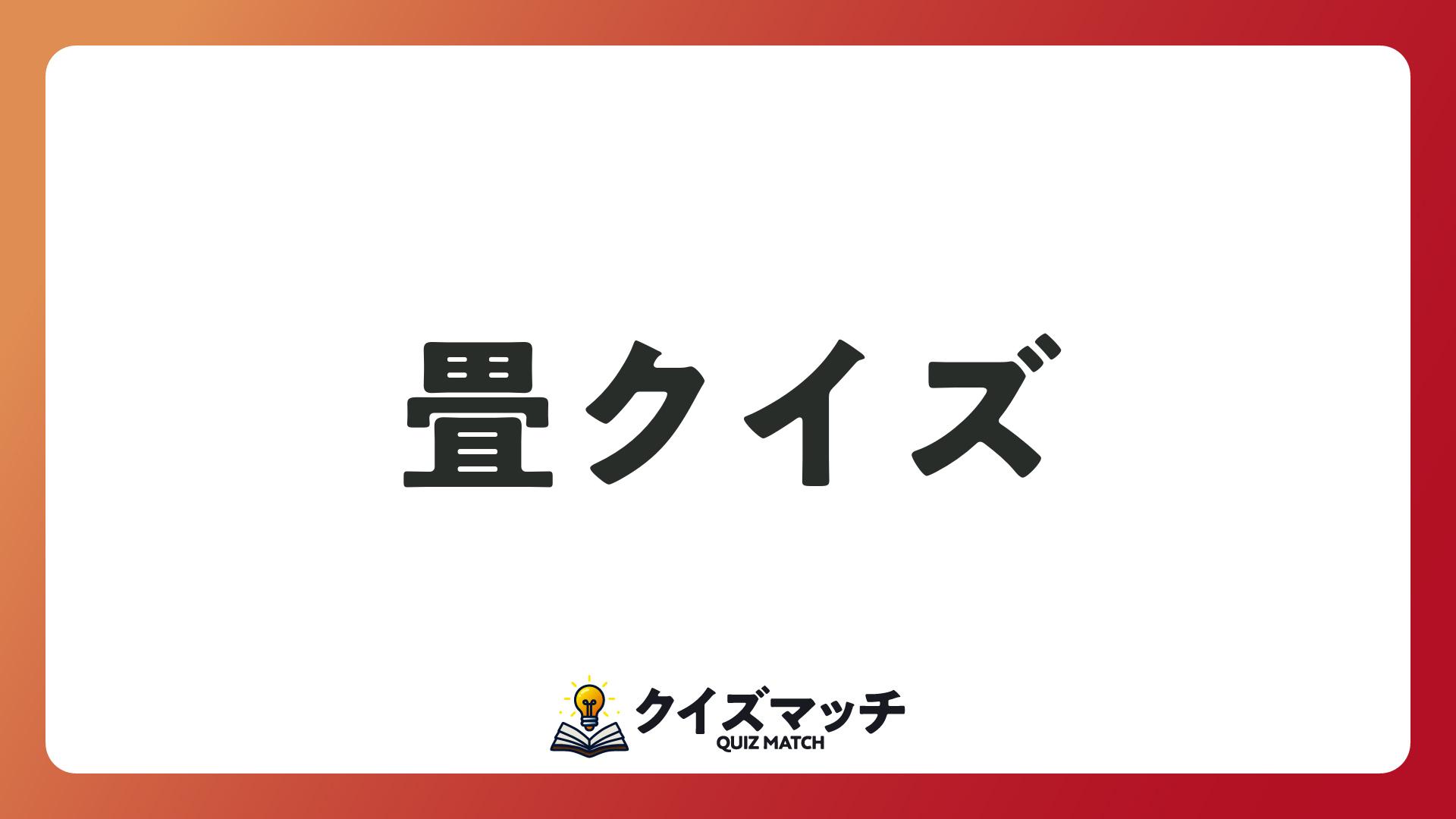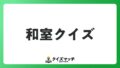日本の伝統的な座敷遊びの「畳クイズ」にチャレンジ! 畳は日本の生活と深く結びついており、その歴史や素材、特徴について、意外な事実がたくさんあります。畳の歴史から製造の仕組み、そして畳をめぐる習慣や言葉遊びまで、10問の豊富な内容でお楽しみください。畳への理解を深めながら、あなたの知識を試してみましょう。
Q1 : 熊本県が全国シェアの大部分を占めている畳表の原料は次のうちどれでしょう?
熊本県は日本の畳表に使われるイグサの生産日本一で、全国シェアの約97%以上を占めています。主に八代平野で生産されており、品質や量で他の地域を大きくリードしています。畳表用のイグサは、長くて傷の少ないものが高級品とされます。ワラは畳床、竹やリネンは畳表には用いられません。
Q2 : 畳の製作において、芯材(畳床)に使われてきた伝統的な素材は何?
畳床は元々、稲藁を何層にも重ねて圧縮し、紐でしっかりと縫い上げて作られていました。藁床は弾力性や吸湿性に優れています。近年では軽量化やコスト削減のため、インシュレーションボード、発泡スチロールなどの人工素材も用いられていますが、伝統的な畳床は稲藁が主流です。
Q3 : 畳の枚数の多い「大広間」のような部屋が多かった、主な時代はどれでしょう?
畳を敷き詰めた大広間が一般に見られるようになったのは江戸時代です。武家屋敷や寺社、大名屋敷などで、大規模な畳敷き空間が用いられるようになりました。それ以前は部屋の一部だけに畳を使用していたことが多かったです。
Q4 : 畳の表面が傷みやすい主な原因の一つは何でしょう?
畳は湿気を多く吸収する性質があるため、通気性の悪い場所ではカビが生えやすく、またカビが畳表を傷める原因となります。定期的な換気や乾燥剤の使用が重要です。直射日光も多少影響しますが、主な原因はやはり湿気とカビです。
Q5 : 日本建築において『床の間』に置かれる畳の名称は?
和室に設けられる『床の間』には、通常の畳より格式の高い『床畳(とこだたみ)』が敷かれます。床畳は材料や縁、寸法の取り方が周りの畳と異なり、特別な扱いを受けます。茶室や客間など、正式な和室では必ず見られる伝統です。
Q6 : 畳の歴史の始まりとして最も古い記録が残る時代はいつでしょう?
畳は飛鳥時代(7世紀ごろ)にはすでに日本で使用が始まっています。『正倉院文書』などに畳の記録が残っており、当時の畳は現在のような敷き詰め式ではなく、座具や寝具のように使われていました。江戸時代に入ると武家や町人にも一般化し、部屋全体に畳を敷くスタイルが浸透しました。
Q7 : 昔から『畳の目を数える』という表現が使われる理由は何でしょう?
『畳の目を数える』は、何もすることがなく、退屈している様子を表す日本語表現です。畳の縦横の目をじっと数えるしかやることがないほど暇、という比喩的な意味です。昔の家屋で畳が一般的だったことから、こうしたことわざが生まれました。他の選択肢は、実際の語源や用法とは異なります。
Q8 : 畳の縁に使われる布や素材の名称は何と言うでしょう?
畳の四辺のうち、長辺側に付いている布や化繊の装飾部分は『畳縁(たたみべり)』と呼ばれます。畳縁には様々な色や模様があり、格式や部屋の用途によって変化します。例えば、武家や寺院では家紋入りの畳縁が使われることもあります。畳縁は単に装飾的役割だけでなく、畳の角を保護する役割も兼ねています。
Q9 : 畳1枚の標準的な大きさである本間(京間)サイズは約何cm×何cmでしょう?
日本の畳には地域によっていくつかの寸法がありますが、最も大きいのが『本間(京間)』サイズで、約191cm×95.5cmです。他に、『江戸間(関東間)』や『中京間(名古屋間)』といったサイズもありますが、本間が伝統的な基準寸法とされています。家の広さを表す際に畳数が使われる理由でもあります。
Q10 : 日本の畳の表面に主に使用されている植物は何でしょう?
畳の表面(畳表)には主にイグサ(藺草)と呼ばれる植物が使われています。イグサは湿度を調整する性質があり、触り心地が良いため、古くから和室の床材として使われてきました。ワラは畳床の芯材に、竹や麻は畳縁やその他の用途で使われることがありますが、畳表自体はイグサが中心です。イグサの生産は主に熊本県が有名です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は畳クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は畳クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。