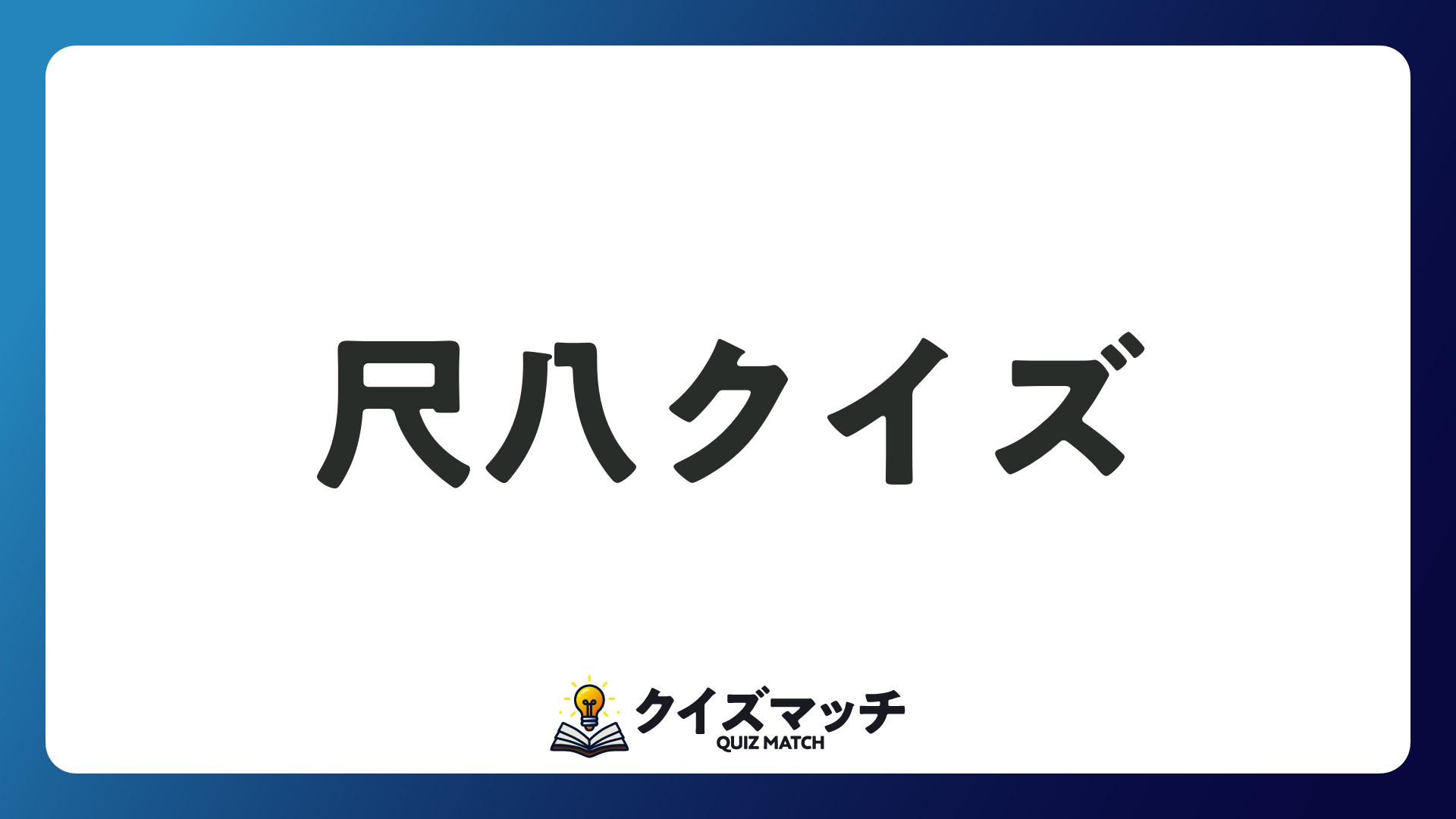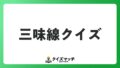尺八は日本の伝統的な縦笛で、主に竹を素材として作られています。歴史的・伝統的には竹製の尺八が一般的で、独特の音色や響きを持っています。標準的な長さは約54.5cmで、5つの指穴を持つのが特徴です。本曲と呼ばれる尺八独奏のジャンルが江戸時代に成立し、今日に受け継がれています。このように、尺八は日本の伝統音楽において重要な役割を果たしてきました。以下のクイズでは、そんな尺八についてさまざまな知識を問います。
Q1 : 尺八において、特定の音色やニュアンスをつけるために息のスピードや角度を調整して演奏する技法は何ですか?
「メリカリ」とは、尺八を演奏する際に管を口元に対して傾け(メリ:下げる、カリ:上げる)、息の角度やスピードを変えて音高・音色を自在に変化させる代表的な技法です。この奏法によって表現に深みや個性を付与できる特徴があります。
Q2 : 尺八において、音程を調整するために演奏中に指を半分開ける技法のことを何といいますか?
尺八で演奏するとき、指穴を半分だけ開けることで音程を微調整する技法は「半穴(はんあな)」です。音程を高低細かく調整する目的で使い、演奏技術としてとても重要です。微妙なニュアンスや異なる音階を演出するためによく使われます。
Q3 : 明治以降、尺八が学校教育などで生徒に教えられるために用いられた俗称はどれ?
「都山尺八」は明治時代以降に「都山流」により広く普及した種類です。指穴の配置や演奏法が体系化され、教育現場にも導入されました。都山流による尺八教育は始め、譜面も独自に開発され、普及活動が盛んに行われました。
Q4 : 尺八を吹く際に重要な吹き口の名称は何ですか?
尺八で音を出すために使う最も重要な部分は「歌口(うたぐち)」です。尺八の上端を斜めにカットし、鋭いエッジを設けてあります。奏者はそこに自分の唇を当て、息をコントロールして音を出します。不適切な吹奏では良い音が出にくいため、基本となる重要部位です。
Q5 : 尺八が伝統的に使われていないジャンルはどれですか?
尺八は歌舞伎音楽や現代音楽、さらにはクラシック音楽にも応用されていますが、「雅楽」には原則として使われません。雅楽は笙や篳篥、龍笛など独自の管楽器編成で演奏されますので、歴史的には尺八の出番はほとんどありません。
Q6 : 尺八の音楽ジャンルで、江戸時代に成立し、主に独奏曲として発展したものはどれですか?
「本曲(ほんきょく)」は、江戸時代に成立した尺八独奏のための伝統音楽ジャンルです。禅宗での精神修養目的や虚無僧の宗教儀式でも利用されました。旋律やリズムが即興性に富み、表現力豊かな楽曲が多い領域です。
Q7 : 現代尺八の標準的な指穴の数はいくつですか?
尺八の標準的な指穴の数は5つです。正面に4つ、背面に1つ(親指用)の穴が開けられています。場合によっては異なる数の穴を持つ尺八も作られていますが、日本の伝統尺八は5つの穴が標準仕様であり、これでさまざまな音階を演奏します。
Q8 : 尺八が最も広く使われていた歴史的な宗派は?
尺八はもともと普化宗(ふけしゅう)と呼ばれる禅宗の一派で「虚無僧(こむそう)」によって吹かれていました。虚無僧は尺八を吹いて托鉢し、修行の一環としていました。普化宗は江戸時代に広まり、その儀式音楽や禅の修行で尺八が重要な役割を果たしました。
Q9 : 尺八の標準的な長さ(名前の由来として一般的な長さ)は約何センチメートル?
尺八という名は尺貫法の「一尺八寸」に由来し、約54.5cm(1尺=約30.3cm、8寸=24.2cm)に相当します。これがもっとも一般的な長さで、標準管と呼ばれることが多いです。短いものや長いものもありますが、このサイズが日本の伝統尺八としてもっとも基本となります。
Q10 : 尺八はどのような素材で主に作られていますか?
尺八は主に竹を素材として作られる日本の伝統的な縦笛です。現在では木や合成樹脂を素材とした尺八も存在しますが、歴史的・伝統的には竹製がもっとも一般的であり、独特の音や響きを持っています。竹竹の節と根元を生かして製作され、これによって豊かな響きが得られるのが特徴とされています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は尺八クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は尺八クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。