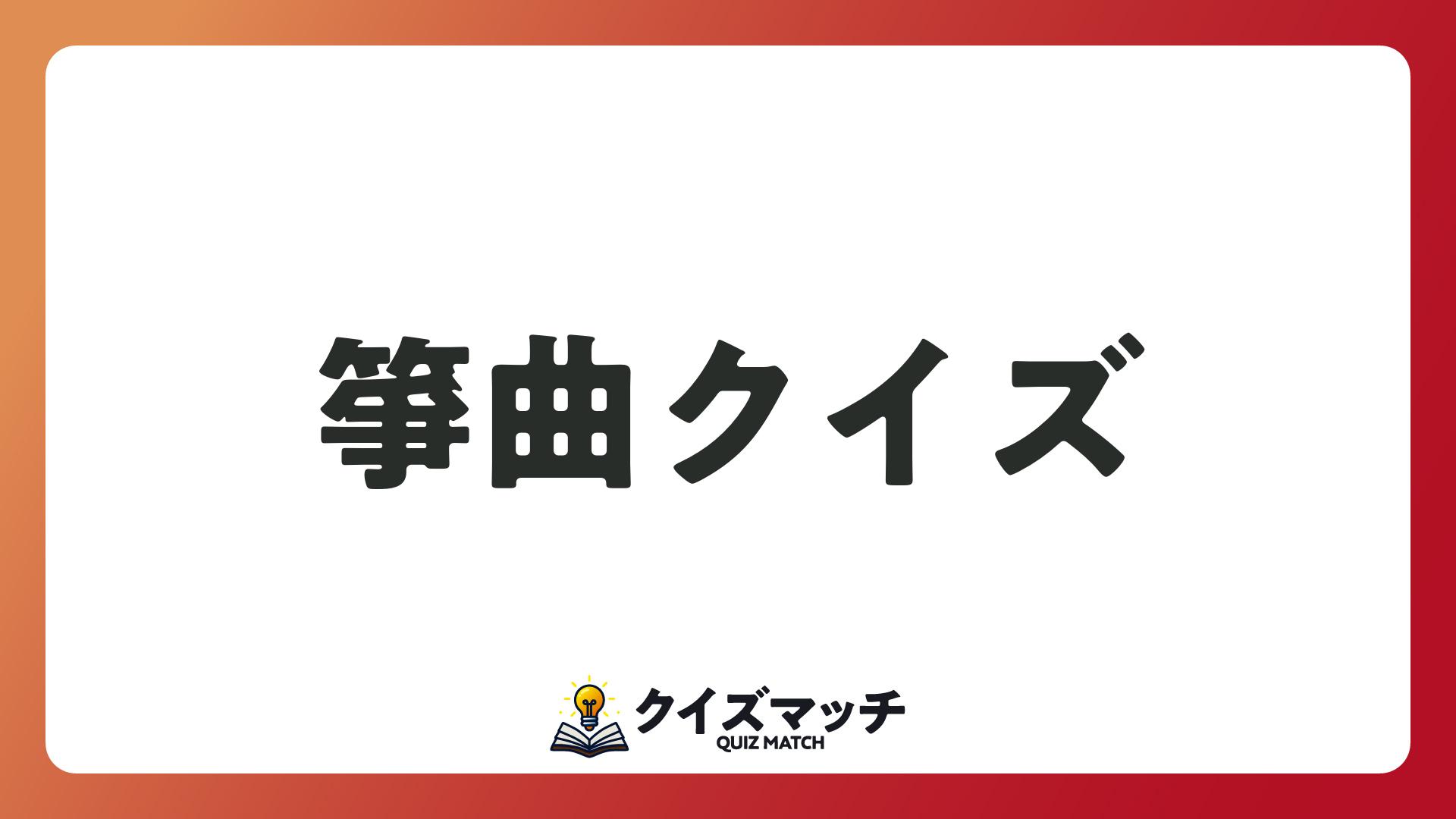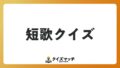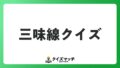箏曲に関する知識を問うクイズにチャレンジしてみましょう。箏は日本音楽の代表的な楽器の一つで、長い歴史と伝統を持ちます。その中で特に有名な作品や作曲家、演奏方法など、箏曲ならではの魅力を楽しみながら学んでいきましょう。全10問のクイズをお楽しみください。
Q1 : 箏の楽譜で使われる特有の表記方法はなにか?
箏の伝統的な楽譜は、カタカナで「イ」「ロ」「ハ」などと音名や指使いが表記されます。これは箏独自の記譜方法で、五線譜と異なり16世紀ごろから使われています。近年は五線譜も併用されますが、伝統ではカタカナ表記が主流です。
Q2 : 箏曲の「手事(てごと)」とは何を指す?
手事とは、歌の入らない器楽的な間奏部分のことです。箏曲や地歌では、歌パートの間に演奏される特徴的な器楽部分のことを指します。これにより、曲に起伏や変化が生まれ、聴き手を飽きさせない工夫がなされています。
Q3 : 江戸時代以降、箏曲の普及に最も影響を与えた流派はどれか?
江戸時代以降、箏曲の普及に最も大きな影響を与えたのは生田流(いくたりゅう)です。生田流は生田検校によって創設され、後の箏曲発展に大きく貢献しました。現在も多くの奏者が生田流として活動しています。
Q4 : 『みだれ』という箏曲の特徴はどれ?
『みだれ』は八橋検校により作曲されたとされ、通常の段物とは違い、段構成がゆるやかで形式にとらわれない自由なリズムが特徴です。これにより「乱れ」と呼ばれています。伝統的な箏曲の中でも特異な存在です。
Q5 : 箏曲で使われるツメ(爪)の正しい着ける場所はどこでしょう?
箏を演奏する際には、右手の親指、人差し指、中指にツメ(爪)をはめて絃を弾きます。左手は主に絃を押さえて音程や音色を変える役割を担います。伝統的な演奏法では右手三指のみのツメが標準です。
Q6 : 地唄箏曲の三絃箏合奏で最も多く使われる調弦法はどれでしょう?
平調子(ひらぢょうし)は、箏と三絃の合奏で最も基本となる調弦法です。特に地唄箏曲では、三絃と箏の調弦を共通にすることで一体感のある合奏が実現できます。他にも調弦法はありますが、平調子が基本となっています。
Q7 : 『千鳥の曲』を作曲した人物は誰でしょう?
『千鳥の曲』は、松浦検校(まつうらけんぎょう)によって作曲されました。松浦検校は19世紀初頭に活躍した作曲家で、箏や三絃による日本音楽の発展に貢献しました。この曲は、和歌をテーマにしており、情緒豊かな旋律が特徴です。
Q8 : 宮城道雄が作曲した、日本を代表する箏曲はどれでしょう?
宮城道雄(みやぎみちお)は20世紀前半を代表する作曲家で、広く知られている作品が『春の海』です。この曲は箏と尺八による現代的な楽曲で、元旦や新年を代表する音楽としても有名になりました。世界的にも日本の音楽を代表する名曲です。
Q9 : 箏の通常の絃の本数は次のうちどれでしょう?
現在日本で一般的に使われる箏(こと)は13本の絃を持っています。かつては7本や12本のものもありましたが、八橋検校の時代以降、13本が標準となりました。近現代では17絃や20絃などのバリエーションもありますが、基礎となるのは13本です。
Q10 : 箏曲の代表的な楽曲『六段の調』を作曲した人物は誰でしょう?
『六段の調』は箏曲の中でも非常に有名な作品で、八橋検校(やつはしけんぎょう)が江戸時代に作曲しました。八橋検校は近世箏曲の祖と称され、西洋音楽で言うところのバッハやモーツァルトのような存在です。彼の作曲した『六段の調』は、現在でも多くの箏奏者が演奏しています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は箏曲クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は箏曲クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。