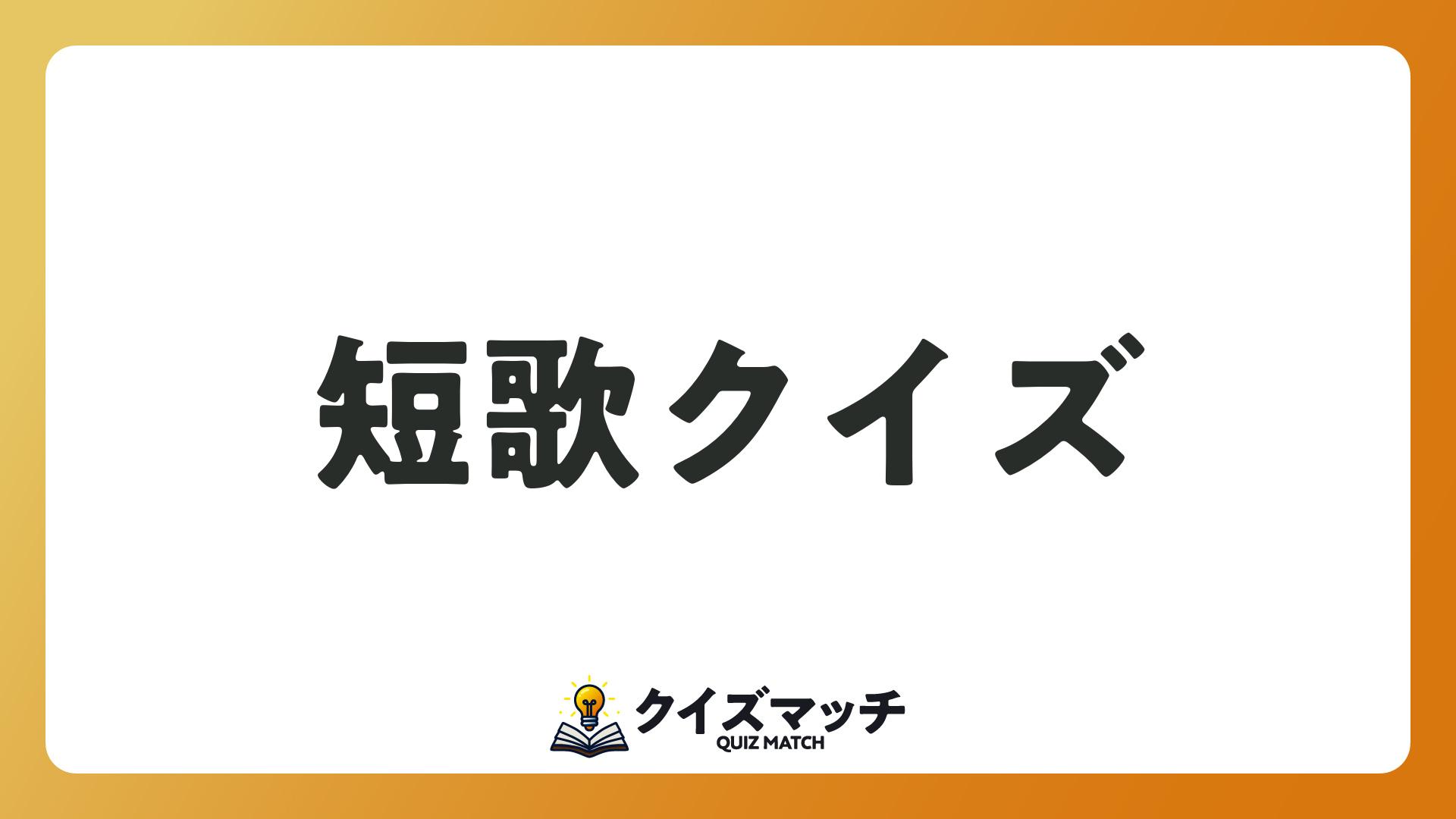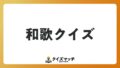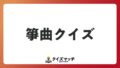【短歌クイズ】日本の和歌文化に触れてみよう
和歌は日本文化の根幹をなす重要なジャンルです。本記事では、様々な歴史の中で生み出された短歌の世界を10問のクイズを通して紹介します。平安時代から近代に至る作品の作者や内容、短歌の定型など、和歌の基礎知識を楽しみながら学んでいただけます。短歌の魅力に触れ、日本文学の深さを感じていただければ幸いです。クイズに挑戦して、日本の美しい和歌世界を探索してみましょう。
Q1 : 「不来方のお城の草に寝ころびて空に吸はれし十五の心」の歌人は誰?
この歌は石川啄木のものです。啄木は『一握の砂』などの歌集で、みずみずしい青春の感情や近代的な自己意識を切実に詠みました。この歌は、啄木の岩手県盛岡での少年時代の心象風景を表現しています。
Q2 : 「浅茅生の小野の篠原忍ぶれどあまりてなどか人の恋しき」の作者は?
この歌は式子内親王の作です。しとやかな抑制の美学を持つ恋歌で、恋ごころを篠の葉にたとえる繊細な表現が特徴的です。彼女は百人一首にも歌が採用されるなど、平安末期を代表する女流歌人として知られています。
Q3 : 『万葉集』に収録されている歌数はいくつ?
『万葉集』は現存する最古の和歌集で、約4500首の和歌が収録されています。天皇、公卿から庶民まで多彩な階層の歌が含まれており、日本の初期文学や社会・風俗を知る歴史資料としても重要です。
Q4 : 近代短歌運動を牽引し、歌誌『明星』を創刊した人物は?
明治時代、近代短歌の革新運動『新詩社』を率い、歌誌『明星』の創刊を行ったのは与謝野鉄幹です。彼のもとには多くの若い歌人(与謝野晶子、石川啄木ら)が集い、日本近代短歌の礎を築きました。
Q5 : 「田子の浦ゆ うち出でて見れば 真白にぞ 富士の高嶺に 雪は降りける」を詠んだ人物は誰?
この歌は山部赤人によるものです。田子の浦から望む富士山が雪で真っ白に染まっている情景を詠んでおり、日本の自然美の象徴的な歌とされています。彼は万葉集の代表的な歌人の一人です。
Q6 : 百人一首の中で唯一の女性天皇による歌の作者は?
百人一首に収められている唯一の女性天皇の歌は持統天皇のものです。彼女の「春過ぎて夏来にけらし白妙の衣ほすてふ天の香具山」は四季と清らかさを感じさせる名歌として親しまれています。
Q7 : 「君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手に 雪は降りつつ」の作者は誰?
この歌は光孝天皇によって詠まれました。春の野で若菜を摘む情景と、恋しい相手のためにつらい目にも耐えている作者の気持ちが込められています。百人一首の中でも有名な一首です。
Q8 : 短歌の定型として正しいものはどれ?
短歌は全部で31音、五・七・五・七・七の韻律が基本定型です。俳句は五・七・五ですが、短歌の場合はそれに七・七がつきます。万葉集から現代短歌までこの形式が守られています。
Q9 : 「ちはやぶる 神代も聞かず 龍田川 からくれなゐに 水くくるとは」を詠んだ歌人は誰?
この有名な短歌は在原業平が詠んだものです。百人一首にも取り上げられており、赤く染まった龍田川の流れの美しさと神秘を歌っています。業平の奔放な恋歌と並んで、日本古来の自然の美の感受性を見事に表現した一首です。
Q10 : 『古今和歌集』はどの時代に編纂されましたか?
『古今和歌集』は平安時代に編纂された最初の勅撰和歌集です。905年ごろ、醍醐天皇の命によって、紀貫之らによってまとめられました。奈良時代は万葉集、鎌倉時代・室町時代にはさまざまな勅撰集が編まれますが、『古今和歌集』が最初の勅撰和歌集として平安朝の文化を象徴しています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は短歌クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は短歌クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。