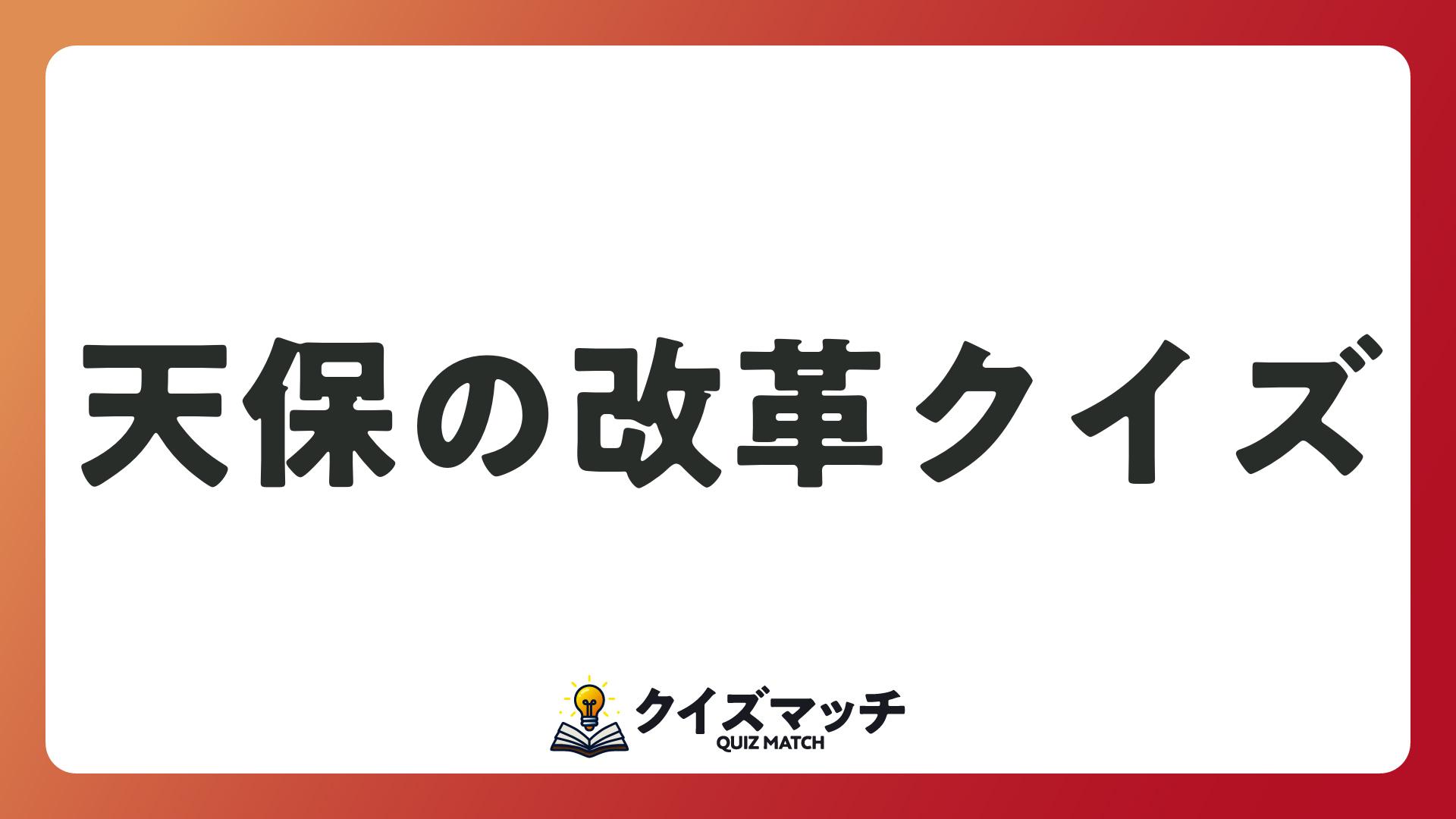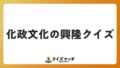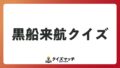天保の改革を知る上で重要な10問のクイズを用意しました。天保の改革は、江戸幕府が社会・経済の立て直しを目指して行った一連の政策改革です。これらの政策は、物価高騰の抑制や倹約の推進、農村の振興などを目指していましたが、様々な対立や問題を招きました。このクイズを通して、天保の改革の歴史的背景や内容、その評価について理解を深めていただければと思います。
Q1 : 天保の改革の評価として正しいものはどれでしょう?
天保の改革は様々な新政策を打ち出しましたが、思惑通りの社会安定には至らず、物価や財政の安定化は限定的でした。上知令への反発や商人・農民の不満も強く、結果的には一部効果のみで抜本的な成果にはならなかったと評価されています。
Q2 : 天保の改革で庶民に対し発布された農村帰還政策の正式名称はどれ?
天保の改革で出された農村帰還政策は「人返し令」です。江戸や大坂に流入した農民を元の村に戻すことで農村の人手不足や荒廃を食い止めようとしたものですが、都市の貧困や農村の疲弊は根本的に解決できませんでした。
Q3 : 天保の改革で取り締まり対象となったのはどのような娯楽でしたか?
天保の改革では、庶民の風紀を正すため芝居小屋や歌舞伎座の取締りが強化されました。遊里の廃止や移設も実施され、江戸の中村座、市村座、森田座も江戸市外の浅草へ移されました。これらの規制は庶民の娯楽文化に大きな影響を与えました。
Q4 : 天保の改革で、江戸幕府が復活させた大名領の直轄地化政策をなんという?
天保の改革では、江戸・大阪周辺の大名領や旗本領を幕府直轄地にする上知令(じょうちれい)が発令されました。これは幕府の財政再建をねらったものでしたが、大名・旗本の激しい反発を招き、短期間で廃止されています。
Q5 : 天保の改革で開設が命じられた公設市場の名前は何でしょう?
天保の改革で、米価の安定を目的として江戸・大坂に米会所の開設が命じられました。米会所は公設市場として米を統制し、物価の安定を図ろうとしたことが特徴です。しかし、思惑通りの成果は上がらず、逆に流通の停滞を招く一因ともなりました。
Q6 : 天保の改革期、幕府が対処しなければならなかった外国船の事件は何か?
天保の改革期には、1837年のモリソン号事件がありました。アメリカ船モリソン号が漂流民を送り届けようと来航しましたが、異国船打払令に従って砲撃で追い返されました。この事件は、幕府の対外政策と攘夷強化の象徴的出来事といえます。ロシア船来航やペリー来航は他時代の事件です。
Q7 : 天保の改革で施行された倹約政策に関する説明で正しいものはどれ?
天保の改革では倹約政策が徹底され、ぜいたくな生活を取り締まるため華美な衣服や贅沢品の使用が禁止されました。これにより身分や生活の見直しを促す狙いがありました。新田開発は他の時代にも行われていますが倹約政策とは直接関係しません。
Q8 : 天保の改革で発布された、江戸や大阪などへの農民の流入を制限した法令はどれ?
天保の改革では、江戸や大阪などの都市への農民の流出を止めるため、人返し令が発布されました。これにより農民は強制的に元の村に戻され、農村の人口減少による耕地の荒廃を防ごうとしました。ただし、実際には農民の生活苦が続き、根本的な解決には至りませんでした。
Q9 : 天保の改革で、物価の安定を目指して解散させられた業者の集団はどれですか?
天保の改革では、物価高騰を抑えるため株仲間の解散が命じられました。株仲間とは、商人たちが幕府の許可を得て営業を独占していた組織です。株仲間解散によって自由取引を促し、物価安定を図りましたが、流通の混乱が生じ、結果的に物資供給が滞るなどの問題を招きました。
Q10 : 天保の改革を主導した幕府の老中は誰ですか?
天保の改革を主導したのは水野忠邦です。天保の改革(1841~1843年)は、江戸幕府の社会・経済の立て直しを目指して行われました。松平定信は寛政の改革、阿部正弘は安政の改革を担当しており、徳川家斉は将軍です。水野忠邦は、農村復興や倹約令、株仲間の解散など、多岐にわたる政策を実施しました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は天保の改革クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は天保の改革クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。