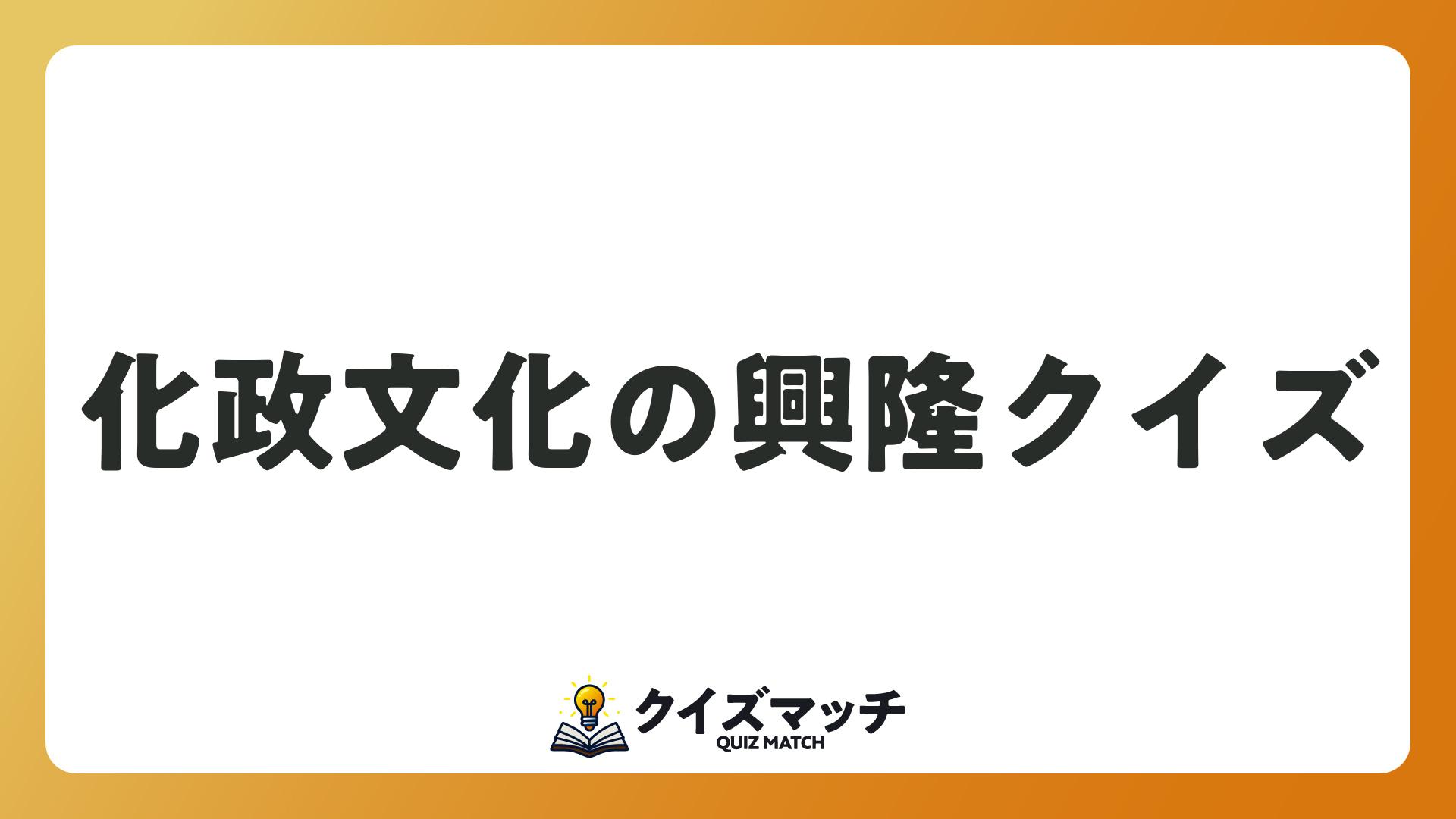化政文化の時代、町人文化が発展し、民間の文芸や娯楽が大きく花開きました。その中心的存在として、浮世絵師の葛飾北斎や人情本の代表作家・式亭三馬、そして歌舞伎の名優・市川団十郎など、様々な文化人が活躍しました。また、貸本屋の普及による識字率向上や、農民向け実用書の刊行など、出版文化の発展も見られました。本クイズでは、この化政文化の興隆に関する知識を問います。
Q1 : 化政文化の舞台である歌舞伎の発展に大きく寄与した役者は誰か?
市川団十郎は江戸歌舞伎を代表する名優で、多くの市川家の役者が団十郎の名を襲名しました。荒事を大成し、町人文化を象徴する存在となりました。他の選択肢も有名な歌舞伎役者ですが、化政文化を代表する存在として特に市川団十郎が重要です。
Q2 : 化政文化を支えた商人や町人が用いた尺貫法で、1丈は何尺か?
江戸時代に広く用いられた尺貫法では、1丈は10尺です。町人文化や商業、建築においてもこの単位系は欠かせず、取引や建築基準の標準となっていました。他の選択肢は誤りです。
Q3 : 江戸時代後期の化政文化を特徴づける町人学問のひとつである蘭学(洋学)について、最も関係の深い人物は誰か?
化政文化期には南蛮文化や蘭学(西洋の学問)が盛んになり、大槻玄沢は蘭学者として多くの弟子を育て、蘭学普及に尽力しました。杉田玄白も有名ですが時期はやや早く、本居宣長は国学者、伊能忠敬は地図作成者であり、蘭学の普及で中心的なのは大槻玄沢です。
Q4 : 化政文化期に栄えた農民向けの教訓書として有名なものはどれか?
『農業全書』(宮崎安貞著)は江戸時代の農民向けの指導書、実用書であり、農業技術から生活の知恵まで幅広く紹介されています。化政文化の時代には農業や生活文化の発展に伴い、こうした実用書や教訓書が普及しました。
Q5 : 化政文化の発達と関係の深い江戸の中心的な繁華街はどれか?
化政文化期には江戸の浅草が商業、娯楽、宗教の中心地となりました。特に浅草寺周辺は、多くの芝居小屋や寄席が並び、『粋』で知られる江戸町人文化の発信地でした。他の選択肢である江戸城下、赤坂、築地も有名な地域ですが、町人文化や娯楽の中心という点では浅草が際立ちます。
Q6 : 化政文化の時代、識字率向上や出版の発展に大きく貢献した、江戸の貸本業者は何と呼ばれていたか?
化政文化の時代には、貸本屋と呼ばれる業者が登場し、庶民にも広く本が読まれるようになりました。貸本屋は本を購入できない人々にも低料金で本を貸し出し、識字率や出版文化の発展に大きく寄与しました。他の選択肢は本の商売や出版の関連用語ですが、本を貸し出すことを主業とするのは貸本屋です。
Q7 : 大衆向けの読み物である『読本』を代表する作品『南総里見八犬伝』の作者は誰か?
『南総里見八犬伝』は、滝沢馬琴(曲亭馬琴)による長編読本です。これは化政文化の時代に大流行し、作者の馬琴は読本を代表する作家として広く知られています。曲亭馬琴は滝沢馬琴の別号ですが、一般的な表記は滝沢馬琴です。他の選択肢は読本や滑稽本の作家です。
Q8 : 次のうち、化政文化を代表する俳諧の流派はどれか?
化政文化期を代表する俳諧の流派は『化政派』と呼ばれます。松尾芭蕉や与謝蕪村は、それぞれ江戸前期・中期を代表する人物ですが、化政文化期には柄井川柳や松尾多勢子らによって町人の生活を詠む俳句、特に化政派が発展しました。流派の名称として正しいのは『化政派』です。
Q9 : 化政文化期に庶民の間で流行した、人情本の代表的作家は誰か?
人情本は化政文化を代表する庶民向けの文学で、主に人情・恋愛・江戸庶民の生活を題材としました。その代表的作家が式亭三馬で、『浮世風呂』などが有名です。井原西鶴(浮世草子)、上田秋成(怪談)、滝沢馬琴(読本)は同時代や前後の他ジャンルの作家です。
Q10 : 化政文化の時代に町人文化を代表する浮世絵師として活躍した人物は誰か?
化政文化の時代、町人文化が発展し、浮世絵が大衆の娯楽となりました。その中でも葛飾北斎は、『富嶽三十六景』などの作品で世界的にも有名な浮世絵師です。彼の作品は斬新な構図と豊かな色彩で、多くの人々に愛されました。他の人物は時代やジャンルが異なります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は化政文化の興隆クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は化政文化の興隆クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。