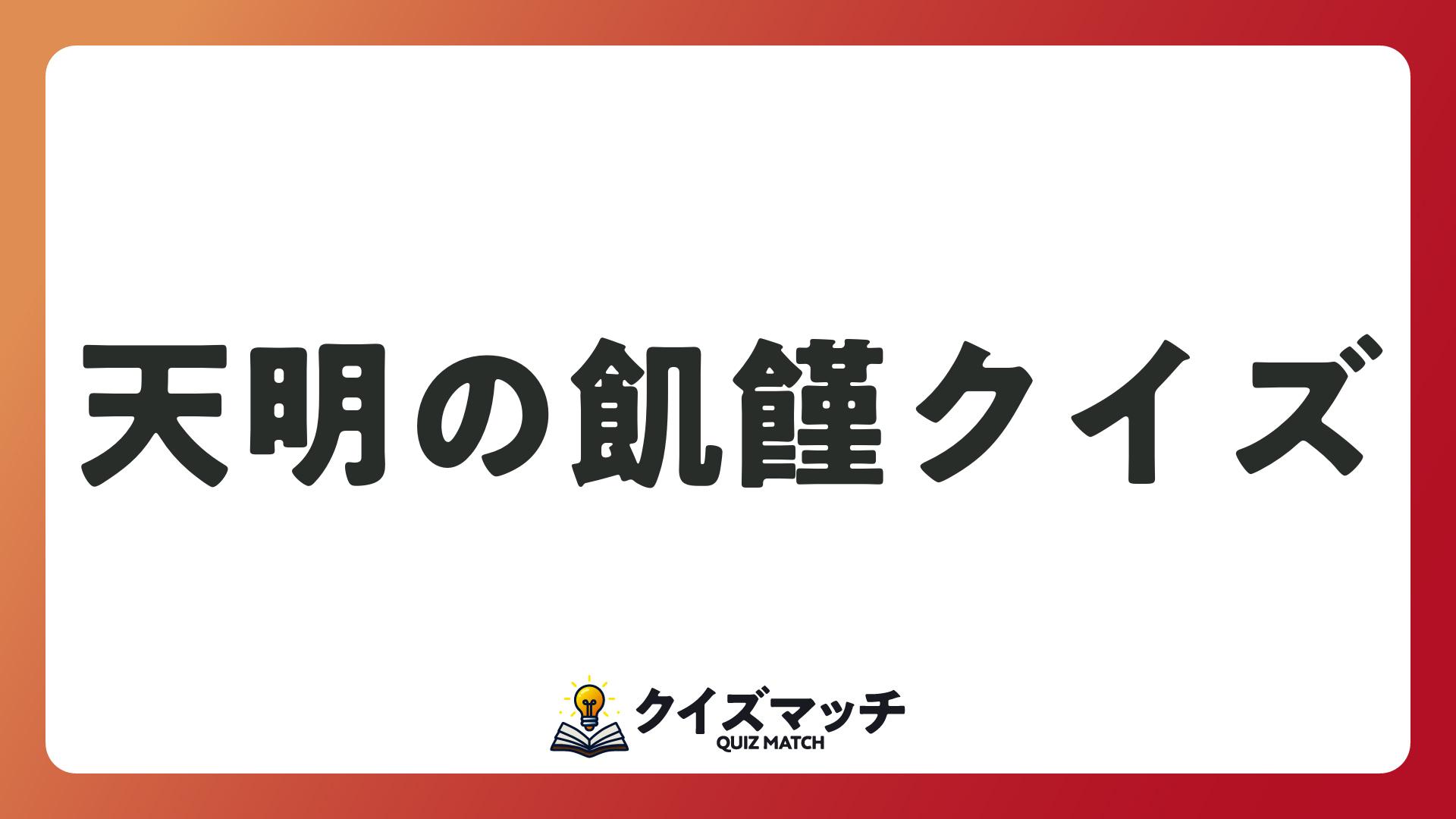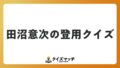天明の飢饉は江戸時代中期、1782年(天明2年)から1788年(天明8年)まで発生しました。日本の三大飢饉の一つで、東北地方などで特に被害が大きく、農民の大量餓死を招きました。この時代の飢饉の主因は、何度も繰り返された冷害や浅間山の大噴火による異常気象で、稲作を中心とした農作物の凶作をもたらしました。この飢饉の際には、東北地方を中心に大規模な打ちこわしなどの社会不安も発生し、全国で30万人以上の犠牲者が出たと推定されています。このような大飢饉を経験した江戸時代中期の状況について、10問のクイズにお答えいただきます。
Q1 : 天明の飢饉が終息した時、老中として改革を行い次の世を担った人物は?
天明の飢饉の後、社会不安が高まったため、老中・松平定信が寛政の改革を始めます。田沼意次は飢饉時の老中で、贈収賄などで失脚しました。松平定信は倹約や農村救済を進めました。
Q2 : 天明の飢饉で幕府が取った対策として正しいものは?
幕府は米の高騰を防ぐため米の価格統制を実施しました。新田開発の奨励や、大名の参勤交代中止などはこの時期の直接的対応策ではなく、寺社から米を取り上げることも一般的ではありませんでした。
Q3 : 天明の飢饉の際、食糧確保のために農民がとった手段として誤っているものはどれか?
食糧難の中で農民は木の皮や草まで食べ、また自給自足用の畑を増やしたり、備蓄を放出したりしましたが、大規模に耕地を捨てて都市へ移住する例は多くありません。むしろ土地にとどまり餓死者が増えました。
Q4 : 天明の飢饉による死者数はどのくらいと推定されていますか?
天明の飢饉による死者は全国で30万人以上とも推計されています。正確な人数は不明ですが、当時の記録では特に東北地方で甚大な被害となり、多くの餓死者が出ました。
Q5 : 天明の飢饉は、何という火山の噴火と関連が深いですか?
1783年の浅間山の大噴火は、天明の飢饉の冷害と並び、被害を一層拡大させた主要な要因です。大量の火山灰が降り積もり、農作物の生育が阻害され、大飢饉を招きました。桜島や雲仙岳ではありません。
Q6 : 天明の飢饉と関連して起きた一揆の中で最大規模とされるものは?
天明の飢饉の際、都市部を中心に『天明の打ちこわし』が多発しました。特に江戸では天明7年(1787年)、米の高騰や困窮民が商家や米問屋を襲撃する大打ちこわしが発生しました。
Q7 : 天明の飢饉時に被害が特に深刻だった地方はどこですか?
天明の飢饉では特に東北地方が甚大な被害を受け、津軽藩や南部藩などでは人口の三分の一が餓死したといわれます。寒冷な気候と相まって稲作の壊滅的な凶作が続きました。
Q8 : 天明の飢饉の時代、将軍であった人物は誰ですか?
天明の飢饉が起きた時代の将軍は、徳川家治(第10代将軍)です。家治の治世は1779年から1786年までで、その間に飢饉が発生しました。徳川家定と徳川家斉、吉宗は他時代の将軍です。
Q9 : 天明の飢饉の主な原因とされる気象現象は何ですか?
天明の飢饉の主因は、何度も繰り返された冷害です。特に浅間山の大噴火や、異常気象が続いて日本の広範囲で冷夏や日照不足が発生し、稲作を中心とした農作物の凶作をもたらしました。洪水や台風も農業被害の原因ですが、天明の飢饉の最大の特徴は冷害です。
Q10 : 天明の飢饉が発生したのは西暦何年から何年までですか?
天明の飢饉は江戸時代中期、1782年(天明2年)から1788年(天明8年)まで発生しました。日本の三大飢饉の一つで、東北地方などで特に被害が大きく、農民の大量餓死を招きました。他の選択肢は他の時代の年号であり、正しい期間は1782年~1788年です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は天明の飢饉クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は天明の飢饉クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。