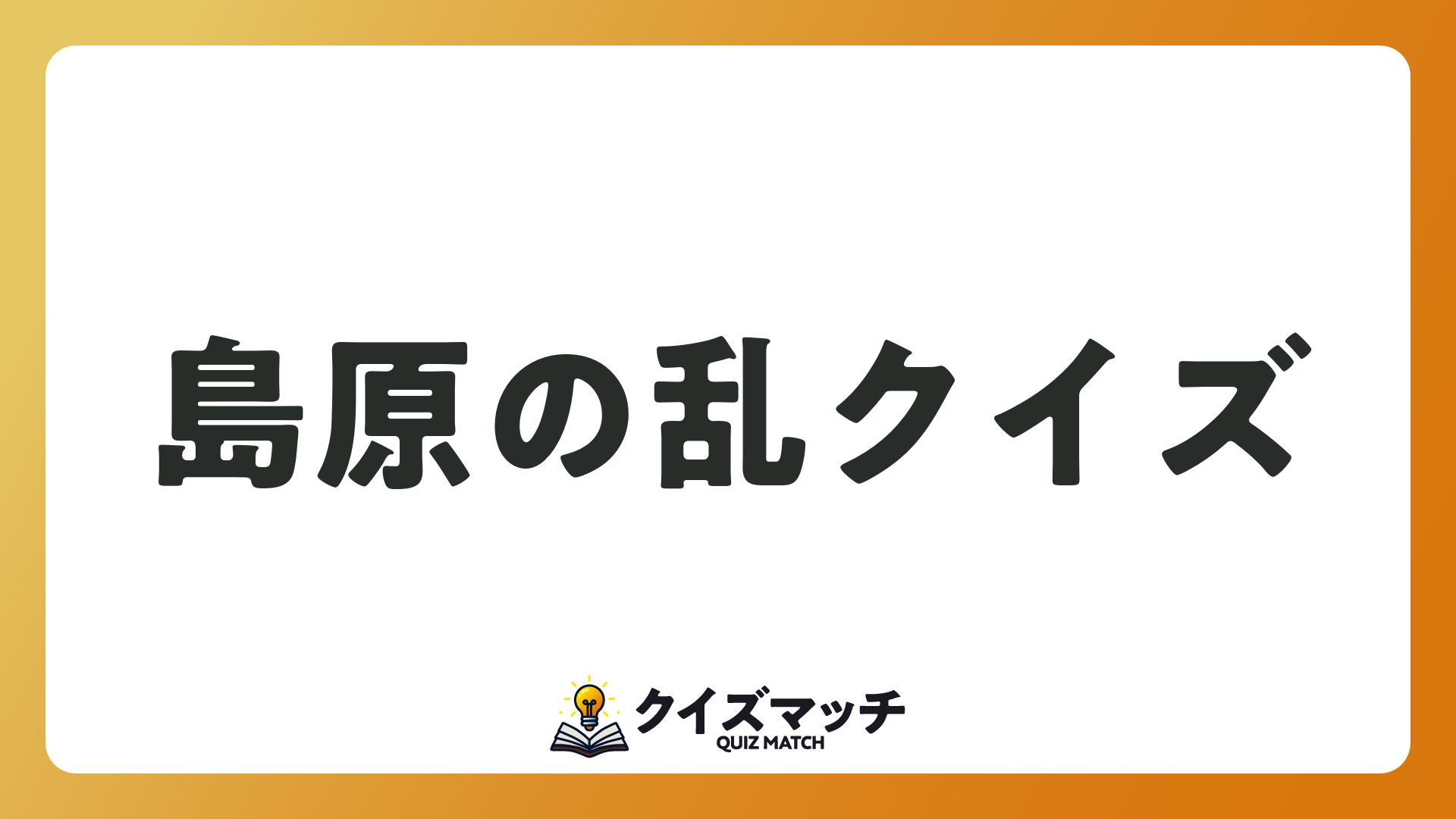島原の乱は、1637年に島原半島で発生した大規模な農民一揆です。過酷な年貢の重圧が直接の引き金となり、キリスト教弾圧もあいまって、天草四郎を中心とする農民や浪人、キリシタンらが一揆を起こしました。最終的には原城で壮絶な籠城戦を展開しましたが、幕府軍の包囲攻撃によって鎮圧されることとなりました。この一揆を契機に、幕府はさらなるキリスト教弾圧と鎖国政策の強化を進めていきます。島原の乱には、当時の日本社会の構造的な矛盾が凝縮されていたと言えるでしょう。
Q1 : 島原の乱に参加した反乱側兵力の総数として近いものはどれか?
島原・天草一揆の反乱側勢力は、2万〜3万人と推定されています。これは農民や浪人、キリシタン、女性や子供も含んだ人数です。彼らが原城に立てこもりました。これに対し、幕府からは12万前後の大軍が投入されています。乱の規模の大きさがわかる数字です。
Q2 : 島原の乱がきっかけとなり、江戸時代の宗教政策にどう影響を与えたか?
島原の乱の最大の帰結の一つは、幕府によるキリスト教の徹底的な禁止政策がさらに強化されたことです。乱の参加者の多くがキリシタンだったため、幕府は宣教師や信者の徹底的な摘発・迫害を進めることとなり、キリスト教の信仰は地下に潜伏するしかなくなりました。
Q3 : 島原の乱鎮圧の過程で幕府軍が外部からも雇った兵力はどこの国のものか?
幕府方は原城攻防戦の際に、オランダ商館から大砲の援助を受けました。雲仙からオランダ船が原城への砲撃を加え、幕府軍を支援しています。これも鎖国前夜である当時の独自事情をよく物語っており、乱の鎮圧に西洋の火器が実際に用いられたことが資料からも明らかです。
Q4 : 島原の乱で一揆勢力が募った信仰は何か?
島原の乱の大きな特徴の一つが、キリシタン(キリスト教信者)の参加です。江戸幕府によるキリスト教弾圧が進む中、信仰を守ろうとするキリシタンも蜂起しました。天草四郎もカリスマ的なキリスト教的指導者として活躍しています。
Q5 : 島原の乱の際、幕府の討伐軍を総指揮した武将は誰か?
幕府方の総大将を任されたのは松平信綱です。彼は乱の鎮圧で手腕をふるい、それによって大いに名を挙げました。信綱は冷静な指揮で包囲戦を展開し、徹底的な兵糧攻めの作戦をとりました。
Q6 : 島原の乱の後、幕府が特に強化した政策はどれか?
島原の乱の影響を受けて、幕府はキリスト教の徹底的な取り締まりとともに、海外との関係を厳格に管理する鎖国政策をより一層強化しました。ポルトガル船の来航も原則禁止となり、外国人流入やキリスト教伝来を防ぐことが狙いでした。
Q7 : 島原の乱が発生したのは何年か?
島原の乱は1637年(寛永14年)に勃発しました。一向一揆や他の暴動と区別する上で重要な年号です。12月に島原で乱が始まり、翌1638年2月の原城落城まで続きました。日本史上にも指折りの大規模な一揆であり、この年を覚えておくのは大切です。
Q8 : 天草四郎らが立て籠もった城の名前は何か?
島原の乱におけるクライマックスで、一揆軍が最後の拠点として篭城したのが原城です。原城は島原半島にある山城で、乱の最終局面では幕府軍による総攻撃の舞台となりました。城内では数万人規模の農民や浪人、キリシタンらが壮絶な籠城戦を展開しました。
Q9 : 島原の乱の指導者として知られる人物は誰か?
島原の乱の中心的なリーダーは、天草四郎時貞です。彼は若干16歳という若さでありながら、カリスマ性と宗教的権威をもって一揆軍を率いました。人々は彼を救世主とも見なして従い、乱の象徴的存在となりました。他の選択肢は関係する人物ですが、指導者として名を遺したのは天草四郎です。
Q10 : 島原の乱が発生した主な原因として最も適切なものはどれか?
島原の乱が発生した大きな要因は、過酷な年貢の取り立てなど、極度の租税の重圧を背景としています。天草や島原地方の農民は困窮し、一揆へと追い込まれました。もちろん、キリスト教の弾圧も一因ですが、第一に重い年貢が生活を圧迫したことが直接的な原因とされています。これが多くの農民や浪人、キリシタンの蜂起へと繋がりました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は島原の乱クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は島原の乱クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。