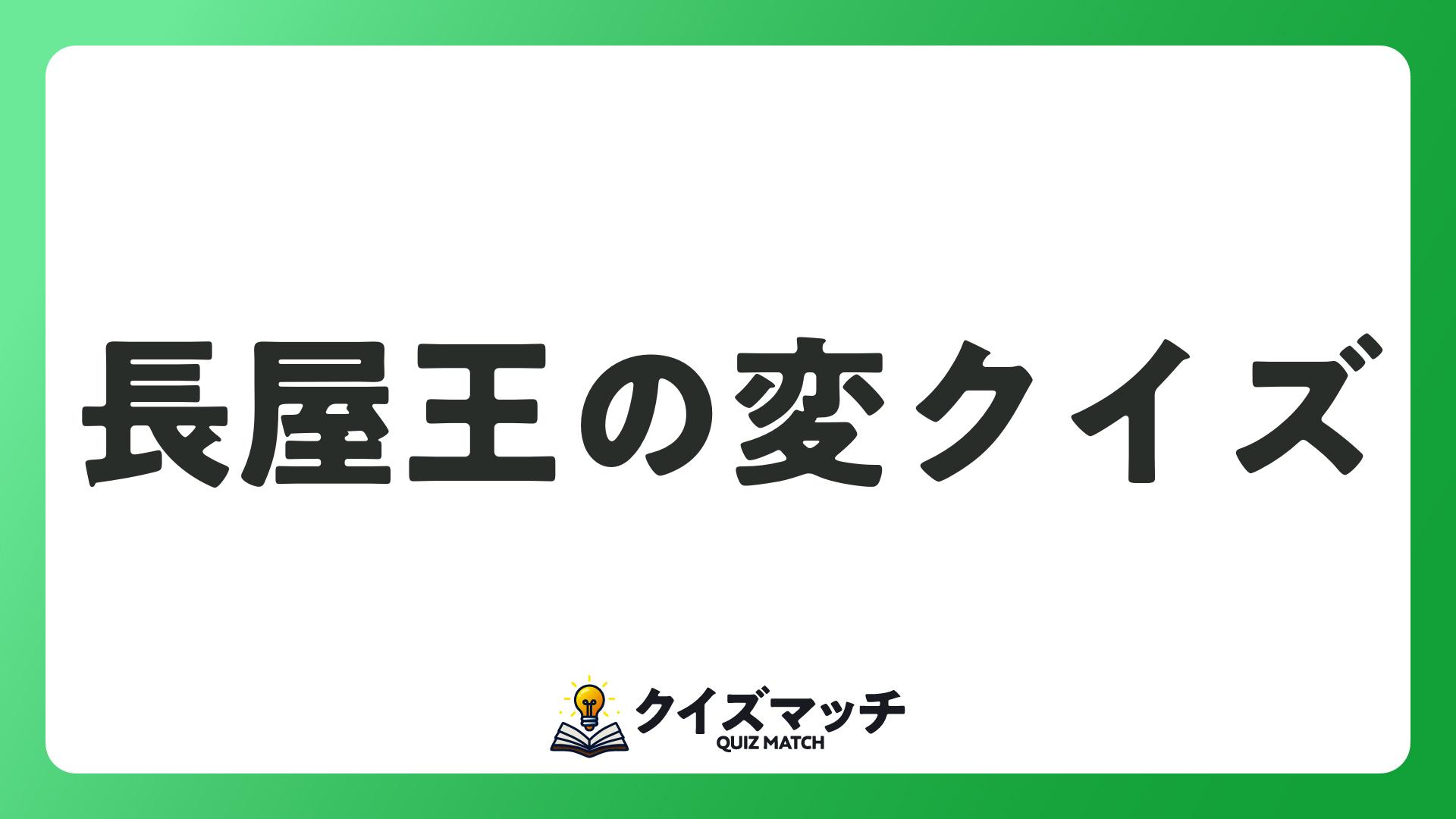長屋王の変は、奈良時代初期の政治事件として知られています。右大臣だった長屋王が藤原氏の策謀によって謀反の疑いをかけられ、自害に追い込まれた事件です。この一大事件を経て、藤原氏は権力を拡大し、奈良時代の政治構造に大きな影響を及ぼしました。この記事では、長屋王の変に関する10の興味深いクイズを通して、この重要な歴史的出来事について深く探っていきます。
Q1 : 長屋王の変がきっかけとなったと考えられる政策は?
長屋王の変の前年に藤原氏は墾田永年私財法の制定を行いました。これは土地私有を拡大させ、藤原氏のさらなる富と権力増大につながる重要な政策です。長屋王はこれに反対的であったともいわれ、事件の背景にもなっています。他の政策は時代や意味が異なります。
Q2 : 長屋王の変が描かれている歴史書は?
長屋王の変は、奈良時代から平安時代初期に編纂された『続日本紀』に詳しく記録されています。『日本書紀』『古事記』はより古い時代を扱い、『万葉集』は文学作品集ですので直接的な記述はありません。
Q3 : 長屋王の変をきっかけに広まった藤原氏への風説は?
長屋王の変後、「長屋王の祟り」が起こるという風説が社会に広まりました。実際に事件の後、藤原四兄弟が次々と病死したことから、怨霊信仰と藤原氏の恐怖が一層強まりました。これは疫病流行とも結びついて語られることがあります。
Q4 : 長屋王の変で自害した長屋王の称号は?
長屋王は事件当時、右大臣の職にあったことで知られています。右大臣とは唐風に整備された官僚機構の上位役職で、左大臣に次ぐナンバー2のポストです。事件によって、この高位官僚も排除されました。
Q5 : 長屋王の変の後、藤原氏が産出した天皇は?
長屋王の変の直後、藤原氏は聖武天皇の即位をより確固たるものにし、藤原氏の権力基盤を強めました。聖武天皇は大仏建立や奈良の都を象徴する天皇です。光仁天皇、孝謙天皇、桓武天皇は別の時代や系統になります。
Q6 : 長屋王の変後、とくに権力を握った藤原氏の兄弟の人数は?
長屋王の変後、藤原不比等の息子である藤原武智麻呂・房前・宇合・麻呂の四人(藤原四兄弟)が権力を掌握しました。彼らは南家、北家、式家、京家の祖となり、藤原氏の家系拡大の中心的な役割を担いました。
Q7 : 長屋王の変によって権力を強めた一族はどれか?
長屋王の変は藤原氏、とくに藤原四兄弟(不比等の子たち)による権力拡大の画期となりました。事件後、藤原氏は重要な官職を独占し、奈良時代の政治構造に強い影響を及ぼしました。源氏、平氏、物部氏とは時代や立場が異なります。
Q8 : 長屋王が自害した際、妻である吉備内親王は誰の娘か?
長屋王の妻・吉備内親王は文武天皇の皇女です。吉備内親王は高貴な皇室血統であったため、長屋王が政界で強い影響力を持った一因でもあります。この夫婦は子宝にも恵まれましたが、事件とともに運命をともにします。
Q9 : 長屋王の変の直接的な発端となったのは何か?
長屋王の変は「謀反の密告」が発端となりました。藤原氏は長屋王が謀反を企てていると密告し、朝廷にその疑いをさせました。その結果、長屋王邸が包囲され、彼とその家族が自害に追い込まれました。飢饉や大仏建立、戸籍改定は関連しません。
Q10 : 長屋王の変が起こった年はどれか?
長屋王の変は、奈良時代初期の729年に発生した政治事件です。当時右大臣だった長屋王は藤原氏の策謀により謀反の疑いをかけられ、自害に追い込まれました。この事件は藤原氏の権力拡大の大きな契機となりました。選択肢のうち、正しいのは「729年」です。他の選択肢は年代がずれています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は長屋王の変クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は長屋王の変クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。