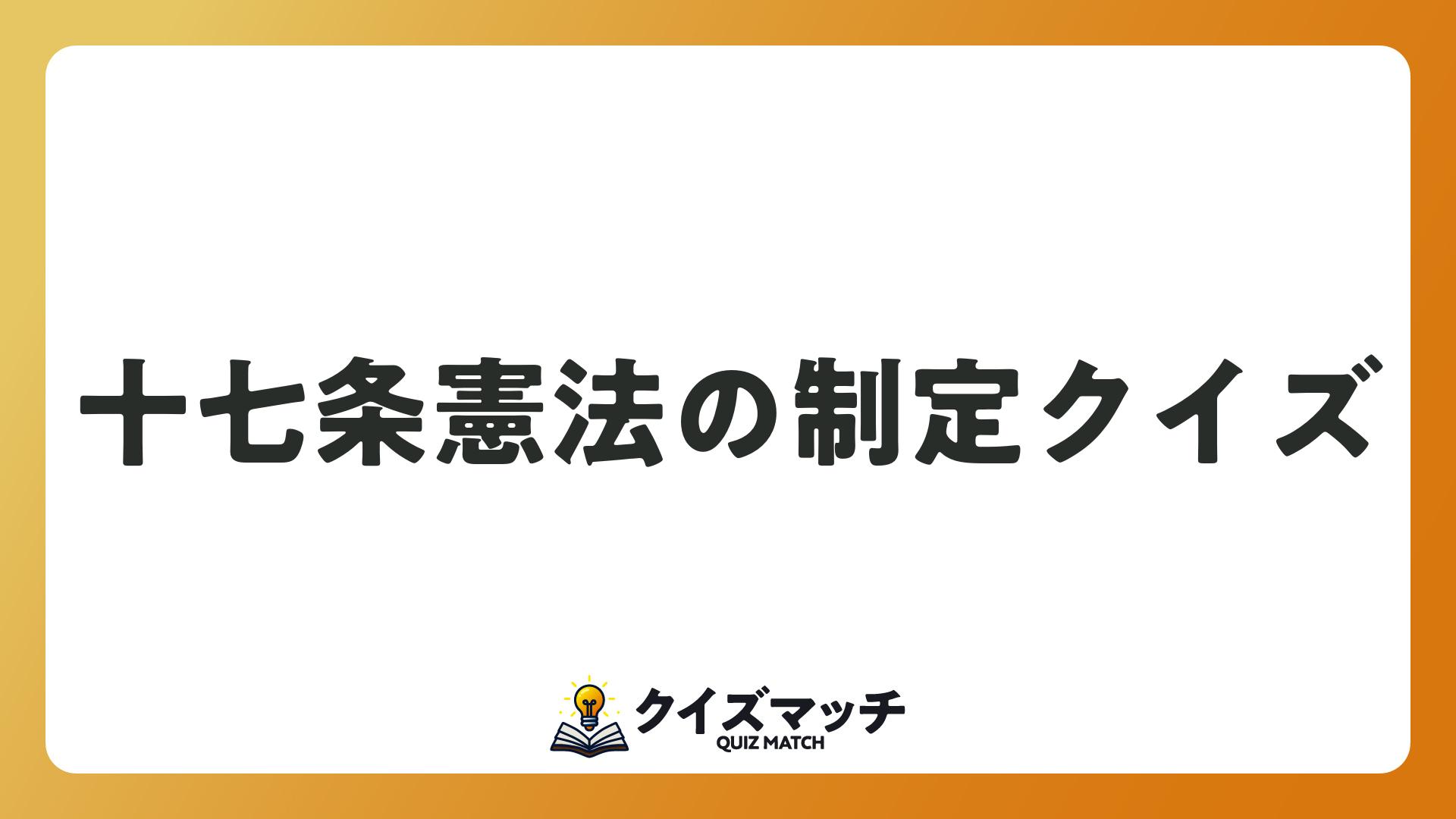聖徳太子が604年に制定した十七条憲法は、仏教と儒教の思想を基盤とした日本最古の憲法です。この憲法は役人の心構えや国家運営の指針を定めており、和を重んじる姿勢が特徴的です。十七条憲法は日本の律令国家体制の礎となった重要な法令で、その制定過程や内容について、クイズを通じて理解を深めていきます。
Q1 : この憲法の成立が日本史に与えた意義として正しいものはどれか?
十七条憲法は、律令国家体制の先駆けとなる法体系として大きな意義があります。後世の大化の改新や律令制の導入への道を開き、日本国家の政治構造の基礎を作ったと考えられています。武士や国会、鎖国とは直接関係がありません。
Q2 : 十七条憲法がまとめている条文の数はいくつか?
十七条憲法は、名前の通り全部で17の条文からなる法令です。役人としての心得や国家の運営方針について17項目に分けて規定されていました。
Q3 : 十七条憲法が示す社会の理想像に当てはまるものはどれか?
十七条憲法は「和をもって貴しと為す」に代表されるように、多様な意見を調和させて国を治める社会を理想としています。武力や権力支配、豪族の横暴などを抑え、公正な政治体制の確立を目指しました。
Q4 : 憲法の内容の中で、仏教の教えに従うよう説かれている条文はどれか?(条番号を聞く問題)
十七条憲法の第二条には「篤く三宝を敬うべし」とあり、三宝(仏・法・僧)を大切にするという仏教の考え方が盛り込まれています。これは仏教思想の影響を強く反映しています。
Q5 : 十七条憲法が制定された当時、日本の中央政府の最高権力者は誰だったか?
十七条憲法が制定された604年は、推古天皇が日本の中央政府の最高権力者でした。聖徳太子はその摂政として推古天皇を補佐しつつ、この憲法を制定しました。
Q6 : 十七条憲法で職務にあたる役人が従うべき心構えとして、強く求められているのはどれか?
十七条憲法は、役人(官人)は上に従い下を思いやること、つまり上下関係を保ちつつ全体の和を大切にすべきことを重視しています。私欲や命令無視、反逆などはむしろ戒められています。
Q7 : 十七条憲法第一条で特に重視された徳目はどれか?
十七条憲法第一条には「和をもって貴しと為す」という言葉が掲げられており、和(調和、協調性)が最も重要な徳目とされています。これは仏教の考え方にも通じ、日本社会の協調性の原点ともいわれます。
Q8 : 十七条憲法が制定された年代として正しいものはどれか?
十七条憲法は推古天皇12年(西暦604年)、つまり7世紀初頭に制定されました。日本が律令国家へと変化していく端緒となった出来事のひとつです。
Q9 : 十七条憲法の主な内容として、どの思想が強く反映されているか?
十七条憲法は、主に仏教と儒教の教えを取り入れて作られました。仏教思想に基づく和の精神を重視しつつ、儒学の忠と礼の精神を役人に求める内容となっています。道教やキリスト教の直接的な影響はほとんど見られません。
Q10 : 十七条憲法を制定したとされる人物は誰か?
十七条憲法は、604年に当時摂政であった聖徳太子が制定したとされています。聖徳太子は推古天皇の摂政として政治改革を推進し、仏教や儒教の教えを取り入れて官僚や役人の規範を規定しました。彼の名が憲法の制定と強く結び付けられているのが特徴です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は十七条憲法の制定クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は十七条憲法の制定クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。