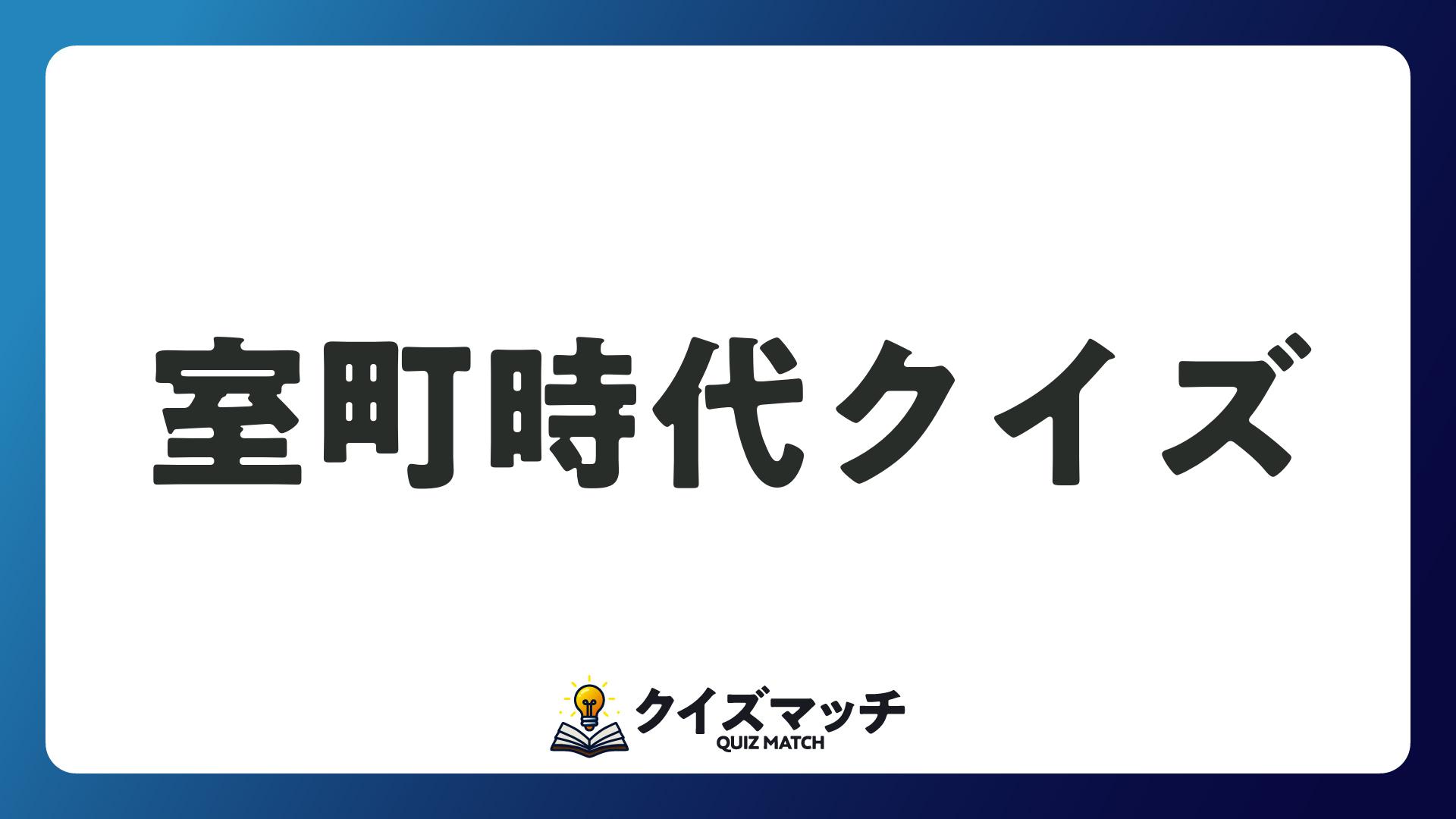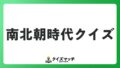室町時代は、足利氏による幕府支配が続いた約240年間の歴史です。この時代には、文化面では東山文化や銀閣寺の造営など、政治面では南北朝の統一や日明貿易の発展など、さまざまな出来事がありました。今回のクイズでは、こうした室町時代の重要な出来事や人物について、10問の問題を用意しています。室町時代の歴史を振り返りながら、当時の政治や文化について理解を深めていただければと思います。
Q1 : 戦国時代の契機となった応仁の乱の年は?
応仁の乱は1467年に始まり、室町幕府の支配力衰退や全国的な戦国時代の到来の契機となりました。長引く戦乱は社会秩序を混乱させ、武士たちが実力で領地を奪い合う戦国時代へとつながったと評されます。
Q2 : 日明貿易(勘合貿易)を本格的に行った将軍は誰ですか?
勘合貿易(日明貿易)を本格的に行ったのは三代将軍・足利義満です。明との正式な外交関係の樹立と貿易の制度化を進め、幕府の財政基盤を強化しました。勘合という割符を用いて、公式であることを証明しました。
Q3 : 室町時代に南北朝を統一した将軍は誰ですか?
南北朝時代の南朝・北朝が合一(明徳の和約)したのは1392年、第三代将軍・足利義満の時代でした。義満は勅使派遣や所領返還などで統一を実現させ、名実ともに幕府の権威を高めました。これにより室町時代は安定期に入りました。
Q4 : 室町時代、一乗谷を拠点とした大名は誰?
一乗谷(現・福井県)を本拠地にして繁栄した戦国大名は朝倉氏です。文明から戦国期にかけて、京都の文化を取り入れつつ、各地の文化人を保護したことで知られています。大内氏は周防・長門、細川氏は四国や山陰、伊達氏は東北地方です。
Q5 : 室町時代、銀閣寺(東山文化)を建立した将軍は?
銀閣寺(正式には慈照寺)は、八代将軍・足利義政が造営しました。東山文化の象徴として知られ、義政は自身の美学を反映させた庭園や建物を設計しました。一方、足利義満は金閣寺(鹿苑寺)を建立し、北山文化を築きました。
Q6 : 室町時代に制定された武家の法令はどれ?
室町時代初期、足利尊氏が発布した武家法令は『建武式目』です。これは建武政権の後、新しい政権の基準を示すために発布されました。御成敗式目と貞永式目は鎌倉幕府時代の法令で、分国法は戦国時代の守護大名の家法です。
Q7 : 応仁の乱で東軍の中心人物となったのは?
応仁の乱(1467年〜1477年)は、室町幕府の権力争いと守護大名の対立が激化した内戦で、東軍の総大将は細川勝元、西軍は山名宗全でした。一色義直や今川義元は異なる時代や地域の有力者です。細川勝元の東軍と山名宗全の西軍が10年以上戦い続け、日本全国に動乱が広がりました。
Q8 : 室町幕府の三管領家に含まれないのはどれ?
室町幕府の三管領家は細川氏・斯波氏・畠山氏です。これらは幕府の政務を統括した家柄で、将軍家を補佐する重職でした。山名氏は有力な守護大名であり、応仁の乱の西軍の中心でしたが、三管領家には含まれていません。
Q9 : 室町時代中期に起こった大規模な農民一揆はどれですか?
正長の土一揆は1428年に起きた日本最初の本格的な農民一揆として知られています。徳政令を求めて農民が蜂起しました。山城国一揆や加賀一向一揆も重要な一揆ですが、室町時代中期でかつ農民による全国的な一揆というと正長の土一揆です。享徳の乱は関東での合戦です。
Q10 : 室町幕府を開いた人物は誰ですか?
室町幕府を開いたのは足利尊氏です。鎌倉幕府滅亡後、新政権樹立を目指し、1338年に征夷大将軍となって京都に幕府を開きました。以後、約240年続きます。足利義満や義政も有名な将軍ですが、征夷大将軍として幕府を開いたという点では尊氏が正解です。義昭は15代将軍で、足利幕府最後の将軍にあたります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は室町時代クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は室町時代クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。