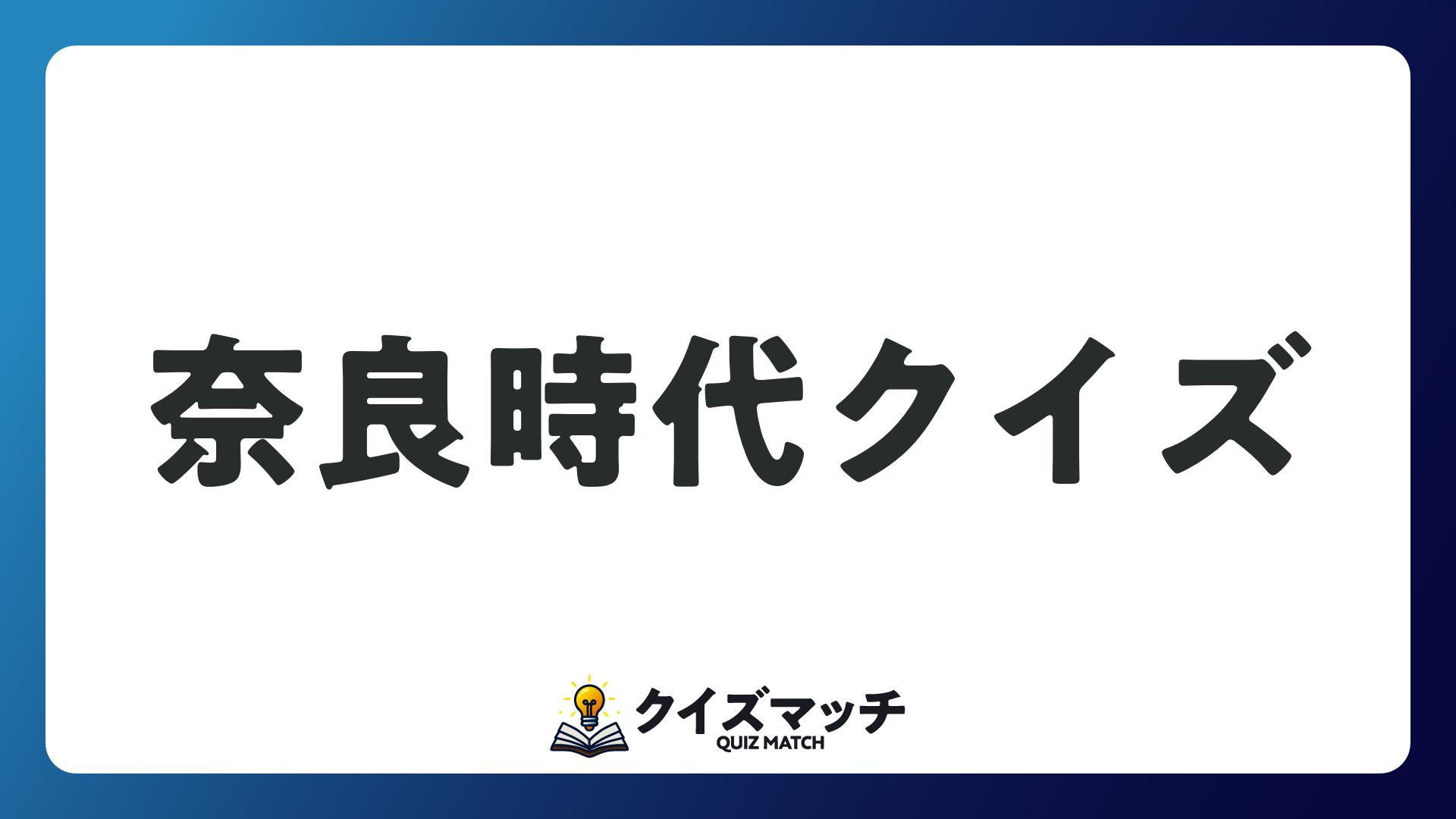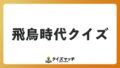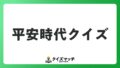奈良時代は日本が律令国家として確立し、仏教文化が花開いた重要な時代でした。この記事では、平城京の建都、正史の編纂、木造建築、大寺院の建立、歌人の活躍、土地制度、貨幣制度、地方行政、語彙集の成立など、奈良時代の様々な歴史的な出来事についての10問のクイズを用意しました。奈良時代の歴史に精通できるはずです。奈良時代の日本を理解する上で、このクイズに挑戦してみてはいかがでしょうか。
Q1 : 奈良時代に中国より伝来し、のちの国語辞典の源流となる語彙集はどれですか?
倭名類聚抄は、平安時代に編纂されましたが、その源流となる語彙集や仏典用語解説書が奈良時代の中国から伝わりました。中国の字書・語彙書の影響を強く受け、後世の国語辞典のモデルとなっています。特に漢語と和語の対照辞典としての先駆け的な意義がありました。
Q2 : 奈良時代の地方行政で、郡司を指導した役職を何といいますか?
国司は奈良時代の律令制度のもとで、中央から地方の国(現在の地方公共団体に近い)に派遣され、行政事務や郡司の監督・指導に当たりました。太政大臣・右大臣・大納言は中央官職で地方行政のトップではありません。国司は郡司と連携して国を治めました。
Q3 : 奈良時代の代表的な貨幣で、わが国最初の流通貨幣はどれですか?
和同開珎は708年に鋳造され、わが国最初の流通貨幣とされています。これが日本で本格的に流通した最初の貨幣制度の始まりです。富本銭も先行例として存在しましたが、流通規模や国家的な鋳造命令の点で和同開珎が一般的に最初の貨幣として認識されています。
Q4 : 奈良時代に仏教の普及・興隆に尽力し、鑑真を日本へ招いた人物は誰ですか?
行基は奈良時代の僧侶で、民衆教化や寺建立に尽力しました。また、晩年には東大寺の大仏建立に協力し、諸国の信者を集めるなど大きな影響力を持ちました。鑑真を実際に招いたのは唐招提寺創建に関わる複数の僧も含みますが、その中心的存在が行基です。
Q5 : 律令制のもと、庶民に支給された耕作地を何と呼びますか?
口分田とは、奈良時代の律令制で庶民に支給された耕作地のことです。6歳以上の男女に一律に与えられ、死去すると返還しなければなりませんでした。班田はその分配作業自体を指すこともあり、田荘や公田は別の性格があります。口分田の制度は現代農政とは異なり、土地私有が限定的でした。
Q6 : 奈良時代に天皇に仕え、『万葉集』にも多くの歌を残した歌人は誰ですか?
大伴家持は奈良時代を代表する歌人のひとりで、『万葉集』の編纂や多くの歌を残したことで知られます。他の歌人も有名ですが、家持は特に奈良時代後期の宮廷歌人として重要です。彼は『万葉集』の実質的なまとめ役と考えられています。
Q7 : 聖武天皇が建立を命じた、奈良時代を代表する大寺院はどれですか?
東大寺は聖武天皇が国分寺建立の詔を出し、大仏建立を命じたことで有名です。東大寺の大仏殿や大仏(盧舎那仏)は奈良時代日本仏教の象徴で、国と仏教を一体化させる政策の象徴でもありました。他の寺院も奈良時代に存在しますが、東大寺は特に国を代表する大寺院です。
Q8 : 奈良時代に建てられた世界最古の木造建築として有名なのはどこですか?
法隆寺の現存する建物は世界最古の木造建築として知られていますが、正確には飛鳥時代末期の建物も含まれます。奈良時代にも多くの寺院が建てられ、法隆寺はその代表としてユネスコ世界遺産にも登録されていますが、法隆寺の五重塔などは、他と比較しても極めて古い木造建築です。
Q9 : 奈良時代に編纂が始まった日本最初の正史は何ですか?
日本最初の勅撰正史は『日本書紀』ですが、奈良時代に編纂が始まった正史は『続日本紀』です。『古事記』は物語的な性格が強く、『風土記』は地方の地誌を記述したものです。続日本紀は奈良時代に始まり、歴史書として重要視されました。
Q10 : 奈良時代に都が置かれた都市はどこですか?
奈良時代では、710年に平城京(現在の奈良市)に都が置かれました。それ以前の飛鳥時代でも都が移されていましたが、奈良時代は平城京に恒久的な都が設けられ、約80年間続きました。京都は平安時代、大阪や福岡は奈良時代の都ではありません。
まとめ
いかがでしたか? 今回は奈良時代クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は奈良時代クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。