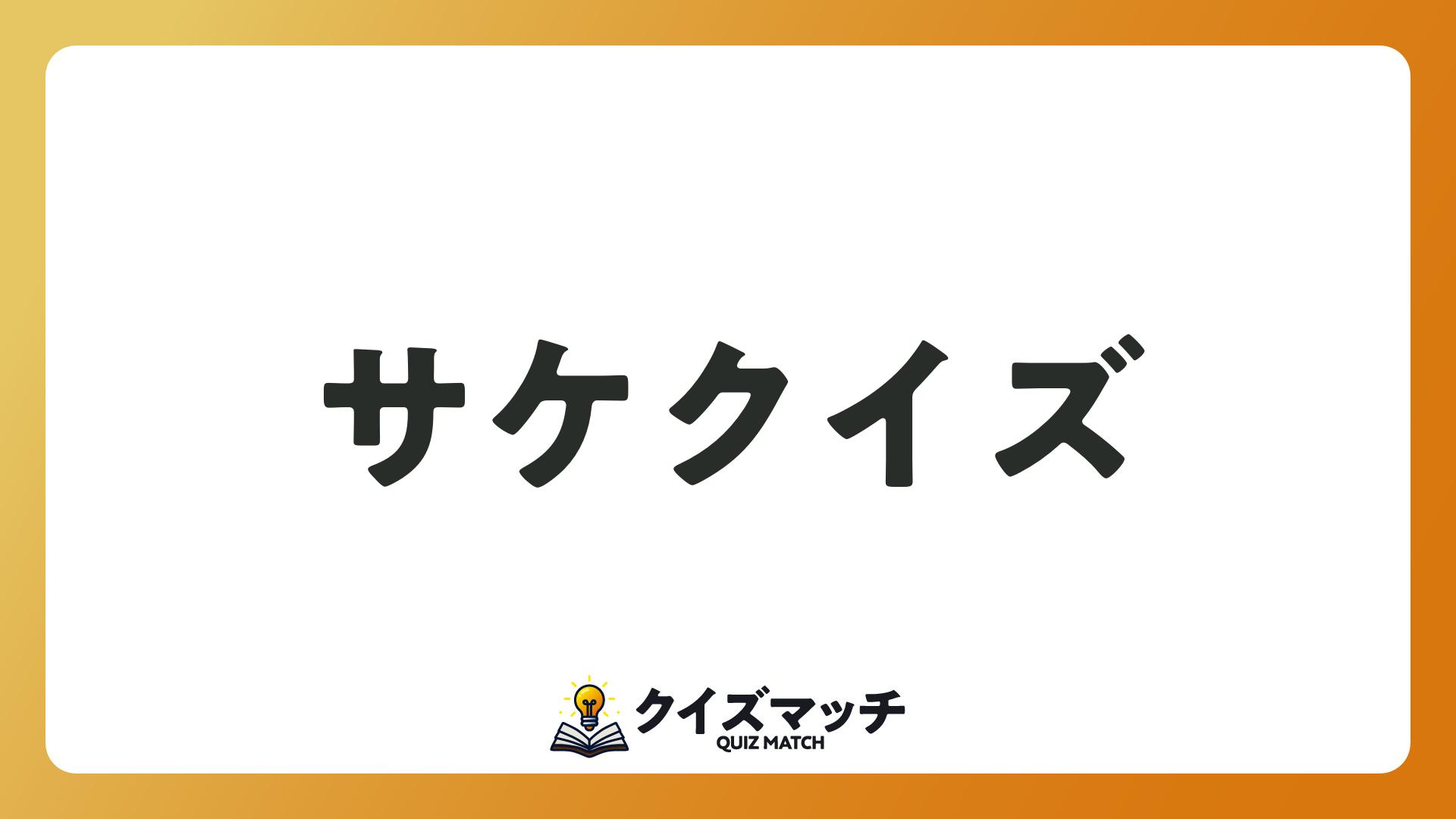サケの魅力に迫る10の問題! 海と川を行き来するサケの生態や、日本人になくてはならない存在であるサケについて、クイズで楽しく学べる一冊です。サケの産卵や生活史、さらには味や食べ方など、サケに関する知識が確実に深まります。サケ好きはもちろん、サケをもっと知りたい人にもおすすめの内容となっています。サケ博士を目指せるかもしれません。クイズにチャレンジしてみましょう!
Q1 : サケの仲間が淡水域から海水域に移動できる理由は?
サケが淡水と海水を行き来できるのは、成長段階で体の塩分調節機能(浸透圧調整能力)が変化するからです。淡水から海水、あるいはその逆へ移動する際に、エラや腎臓などの機能が環境に応じて適応し、体内の塩分や水分のバランスを保ちます。これを実現する生理的特性がサケの回遊を可能にしています。
Q2 : サケの産卵行動において、一般的に見られる特徴はどれ?
多くのサケは産卵行動を終えると生涯を終えます。産卵後の体力消耗や感染症により死亡する個体が大多数です。複数回産卵する種もいますが、日本で見られる多くのサケは「一生一度」の産卵です。川で産卵するため「湖のみ」は誤りです。
Q3 : サケと名前がつくが実際はサケ科ではない魚はどれ?
サケガシラはサケ科ではありません。サケガシラはリュウグウノツカイに近い深海魚で、和名に「サケ」と入りますが、サケやマスとは全く別の分類群に属します。一方、ヤマメ、アマゴ、サクラマスはいずれもサケ科の魚です。
Q4 : サケの寿命として正しいものはどれですか?
サケは種類によって若干異なりますが、一般的な寿命は約3~7年です。サケは孵化後に川や海を転々とし、数年後に成熟した後に生まれた川に戻り産卵します。産卵後に死亡する“一生一度”の生態を持つ種類が多いため、10年以上生きたり、複数回産卵するものはほとんどいません。
Q5 : サケの仲間で、日本の養殖産業で主に養殖されている種類はどれですか?
日本の養殖で主に生産されているサケはギンザケです。ギンザケは成長が早く、養殖に適しているため、1970年代以降国内で生産が増加しました。シロザケは天然が大半で、キングサーモンやベニザケも国内では養殖がほぼありません。ギンザケは特に養殖技術の発展によって安定供給が可能になっています。
Q6 : サケの仲間はどこの海域を主に回遊していますか?
サケの仲間は主に北太平洋を回遊しています。日本近海からアラスカ、ベーリング海にかけて広く分布しており、成長した後に生まれた川に戻る習性があります。北極海にも稀に進入することがありますが主な回遊海域ではありません。日本海も生息海域の一部ですが大部分が北太平洋です。
Q7 : サケのイクラはどの部位に由来しますか?
イクラは、サケの卵巣に由来する卵を加工した食品です。サケの成熟卵を取り出し塩漬けや醤油漬けに加工し、いわゆる「いくら」となります。精巣は筋子とは区別され、筋肉や肝臓はイクラの材料にはなりません。安価なものはトビウオやシシャモなどの卵が使われることもありますが、本来イクラはサケの卵です。
Q8 : サケの身が赤いのは主に何の成分によるものですか?
サケの身が赤いのは、アスタキサンチンというカロテノイド色素によるものです。サケはエビやカニなどを食べることで体内にアスタキサンチンを蓄積し、その色素が筋肉に沈着して赤い色になります。なお、他の候補であるリコピンやβカロテンは主に植物の色素であり、ヘモグロビンは魚肉の赤さとは関係ありません。
Q9 : 日本国内で最も多く漁獲されるサケの種類はどれでしょう?
日本で最も多く漁獲されるサケはシロザケ(Chum salmon)です。シロザケは「秋サケ」とも呼ばれ、日本近海や北太平洋を回遊し、成長後に日本の河川へ遡上します。日本のサケ漁業の中心となっており、食用やイクラの原材料などとして広く利用されています。他の種は国産の漁獲量が少ない、もしくは輸入が中心です。
Q10 : サケの成魚が川を遡上する主な理由は何ですか?
サケの成魚が川を遡上する主な理由は、繁殖のためです。海で成長したサケは生まれ故郷の川に戻り、産卵行動を行います。この行動は「母川回帰」と呼ばれ、サケ類特有の生態です。遡上の際には食事を摂らず、繁殖を終えた後には多くが死んでしまいます。餌を探す・休息・敵から逃れることが主目的ではありません。
まとめ
いかがでしたか? 今回はサケクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はサケクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。