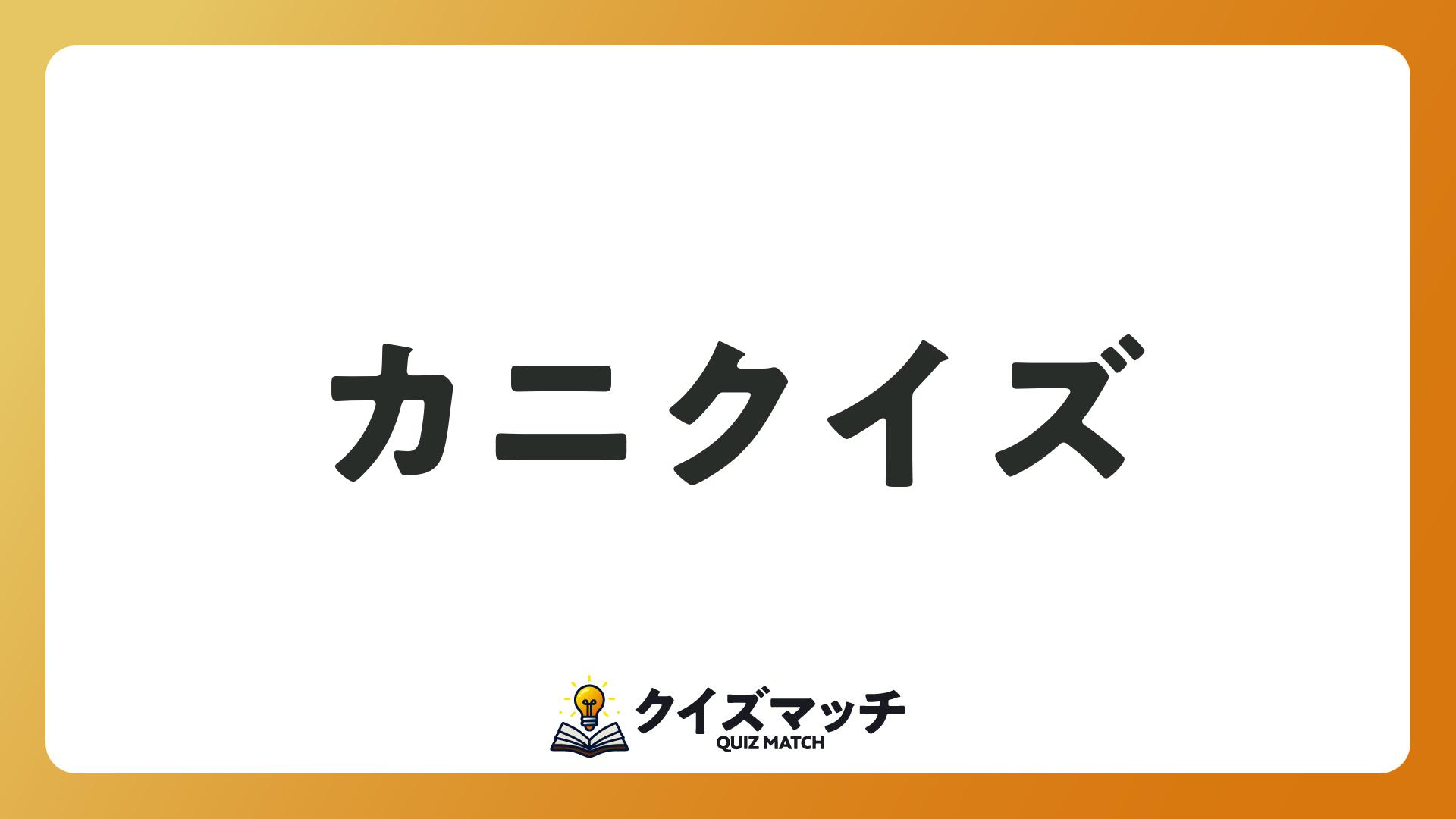カニクイズに挑戦!日本でよく食べられるカニの魅力を探ろう。ズワイガニ、タラバガニ、ワタリガニなど、様々なカニの種類とその特徴について、10問のクイズを用意しました。カニの英名や生態、習性、食べ方など、カニに関する豆知識が満載。カニ好きなあなたはどこまで正解できるでしょうか。クイズを通してカニの世界をもっと知り、新しい発見をしていきましょう。
Q1 : 主にカニの脱皮直後に起こる現象で、外敵から身を守るためにしばらくじっとする、この行動を何と呼ぶ?
カニの脱皮は「モールティング」と呼ばれます。脱皮直後は新しい殻が柔らかく、外敵に襲われやすいため、カニは岩陰や砂の中に隠れてしばらくじっとしています。これにより新しい殻が硬化し身の安全が保たれます。モールティングは成長や再生にも欠かせないサイクルです。
Q2 : 毛ガニに多く含まれ、内子とも呼ばれる部分はどこ?
毛ガニの「内子」とは、卵巣のことで、オレンジ色の濃厚な味が特徴です。多くの場合、メスの毛ガニから得られます。これに対して「カニミソ」は肝臓にあたる部分で、また別のうまみ成分です。それぞれ用途や味わいが異なりますが、どちらも毛ガニならではの珍味です。
Q3 : カニの脚が再生する現象をなんと呼ぶ?
カニなどの一部甲殻類は、事故や攻撃で脚を失った場合、その部分を再び作り出す能力を持っており、これを「再生」と呼びます。自切は自分で脚を切断する行動を指しますが、再生は失った部分の再生長そのものを指す用語です。数回の脱皮を伴って元の形に戻ります。
Q4 : 日本で養殖が行われていないカニはどれ?
タラバガニは冷たい海域に生息し、日本では天然物が流通するのみで養殖は行われていません。ワタリガニやズワイガニ、ケガニは規模の大小はありますが一部で養殖・蓄養が行われています。タラバガニの養殖は難易度が高いため、今もほぼ全量が天然です。
Q5 : カニが一度脱皮してから次の脱皮までの期間を何という?
カニは脱皮を繰り返して成長しますが、脱皮と脱皮の間のことを「間期」と呼びます。間期中は殻が硬まり、活動や摂食が活発になります。脱皮は生命維持や成長に欠かせず、幼体や若い個体ほど頻繁に脱皮しますが、成体になるとその回数も減っていきます。
Q6 : ズワイガニのオスとメス、一般に高値がつくのはどちら?
ズワイガニは、オスの方が脚が長く身が多いため市場価値が高い傾向があります。メスは卵やミソを持ち、味わい深いですが、身入りが少なくサイズも小さいため値段が控えめです。また、オスは「松葉ガニ」「越前ガニ」などブランド名でも知られています。
Q7 : 浜ゆでにして食べることが多い、日本海沿岸でよく知られるカニはどれ?
日本海沿岸で冬場によく獲れ、浜ゆでされて食べられる代表的なカニはズワイガニです。ズワイガニは冬の日本の味覚の代表格で、身がしっかりしていて甘みがあります。ケガニは北海道中心、ワタリガニは全国的に分布していますが主に別の調理法で食べられます。
Q8 : 北海道名産の「花咲ガニ」の主な水揚げ地域はどこ?
花咲ガニは北海道・根室地方を中心に水揚げされるカニです。花咲半島周辺のみで多く見られ、身がぎっしりと詰まった味わいが特徴です。花咲ガニは非常に希少で、また鮮度が命のため、道内でしかなかなか味わえない貴重なカニとされています。
Q9 : カニの体には脚(はさみも含む)が何本あるでしょう?
カニは十脚目に属しており、一般的に脚は全部で10本(はさみ脚2本+歩脚8本)あります。はさみを含まずに歩脚だけの場合は8本となりますが、全体では10本が正解です。他の甲殻類では脚の数が異なる種もいますが、カニと呼ばれる動物の基本的な特徴の一つです。
Q10 : 日本でよく食べられているカニ「ズワイガニ」の正式な英語名はどれ?
ズワイガニの正式な英語名は「Snow Crab」です。日本でも人気のズワイガニは、大西洋や北太平洋に多く生息し、「オピリオ」や「ベニズワイ」など複数の亜種があります。「King Crab」はタラバガニ、「Dungeness Crab」はアメリカ西海岸のダンジネスクラブ、「Blue Crab」はアメリカ東海岸で食べられるワタリガニの一種が該当します。
まとめ
いかがでしたか? 今回はカニクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はカニクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。